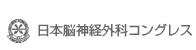パーキンソン病・本態性振戦・ジストニア症
パーキンソン病
パーキンソン病は①手足のふるえ(振戦)、②からだのこわばり(筋強剛または固縮)、 ③動作緩慢やからだの動かしにくさ(無動または寡動)、④前かがみ姿勢、すくみ足、突進歩行(姿勢反射障害)を特徴とします。また表情が乏しくなり(仮面様顔貌)、便秘や起立性低血圧などの自律神経症状、嗅覚の障害、行動の計画や実行ができない、物忘れがひどいなどの認知機能低下、うつ・不安、幻覚・妄想などの精神症状、不眠や日中の眠気などの睡眠障害もパーキンソン病の患者さんにみられる症状です。
脳には神経と神経の間の信号伝達をする「神経伝達物質」があり体をスムーズに動かすことができます。ドパミンはその神経伝達物質の一つで、脳深部の中脳にある黒質神経細胞で主に作られますが、パーキンソン病では黒質神経細胞が障害された結果、ドパミンが不足しているため、上記の様な運動症状が出現します。運動の症状以外にも、便秘や起立性低血圧などの自律神経症状や、精神症状、認知症状、睡眠障害をしばしば認めます。
治療は、薬物治療が第一です。不足しているドパミンを薬として補給するのがレボドパです。またドパミンの代用となるのがアゴニストとよばれるドパミン作働薬です。パーキンソン病ではこれらの薬がとてもよく効きます。最近ではその他の作用を持つ薬も多く使われるようになりました。当初はよく効いていたこれらの薬も、長く内服すると、次第に薬の効果時間が短縮し、一日に何回も薬を内服するようになります。薬が効いている時間はよく動けるのですが(オン)、薬が切れると体が固まり、動けなくなってしまいます(オフ)。これをウェアリングオフ現象といいます。さらに薬の量がふえるにつれて、体がクネクネと勝手に動いてしまうジスキネジアという不随意運動も出現してきます。ウェアリングオフやジスキネジアは薬の副作用なので、これらが症状として出現してくると、薬による調整は難しくなります。そうなると、外科手術治療を検討します。目安は1日に5回以上のレボドパ製剤の内服、2時間以上のウェアリングオフ、また1時間以上のひどいジスキネジアです。
外科手術は、脳の深部のごく一部を凝固する(熱で焼き固める)方法や、脳の深部に電極(細い電線)を留置し全胸部や腹部の皮下に植え込んだ刺激装置とつなぎ微弱な電気で刺激する脳深部刺激治療(DBS)があります。それぞれの症状や手術の目的に応じて、凝固や刺激の部位が異なります。手術は定位脳手術という方法を用いて正確に行うことができます。近年の画像診断技術や手術技術の発達や、刺激機器の向上により、正しい適応で行えば、手術の有効性は高くまた比較的安全であると考えられています。最近では超音波による破壊術(切らない治療)であるMRガイド下集束超音波治療(FUS)が保険適用となっています。
本態性振戦
手の震えが生じる本態性振戦の原因は不明ですが、家族歴のあることがしばしば認められます。パーキンソン病の様な体の動かしにくさはありません。40歳ぐらいから発症し加齢とともにひどくなることが多いです。β遮断薬という高血圧にも使われる薬が効果を示す場合があります。薬の効果がない場合は外科治療を考慮します。パーキンソン病と同様に、DBSや凝固術、ガンマナイフ治療が行われます。多くの場合は著効します。またFUSによる破壊術も有効です。
ジストニア症
ジストニア症とは、自分の意思とは関係なく、筋肉が収縮したり、硬くなったりする病気です。収縮する筋肉は患者さんごとに限られ、同じような動きや姿勢になります。何か動作をしようとした時に筋肉が収縮しすぎたり、働くべきでない筋肉が過剰に収縮したりするためにスムーズな動作ができないという症状が代表的です。また、勝手に手足が動いてしまい、目的の動作ができない、あるいはからだが変形して極端な姿勢異常となってしまうこともあります。全身の筋肉に異常を来す全身型、一つの上肢、または下肢のみに限局する局所型などいくつかのタイプがあります。また原因も、遺伝性のもの、脳炎などの後遺症、職業性のもの、原因不明のものと多彩です。ジストニアの発症のメカニズムは、はっきりわかっていません。ただ、大脳基底核の機能異常があることは確かなようです。薬による治療は、効果がないことが多く、その様な場合には手術が考慮されます。その中でも全身性の遺伝性ジストニアに対する淡蒼球内節の電気刺激療法の有効性がよく知られています。また、その他のジストニアでも様々な部位での凝固療法や電気刺激療法(DBS)が行われています。