波形・レポートの講評
2025年認定試験申請で提出された波形・レポートの講評
2025年認定試験が6月1日に実施されます。
認定試験の受験を申請するにあたり提出された波形・レポートを認定委員会にて審査致しました。この結果を講評として公開致します。
受験をされる方だけでなく、日ごろの診療においても参考としていただけますと幸甚です。
【脳波分野】
脳波波形の図、レポートともに経年的に質が高くなっており、講評が大いに参考となっていると考えられるため、引き続き前回2024年分を含む講評 を十分に参考とされたい。
脳波波形の図については、誘導(電極)の記載がないもの、導出法(モンタージュ)が2種以上ないものがあり、提出時には「脳波分野 波形・レポートチェックリスト」「脳波波形・所見のサンプル」を入念に確認されたい。また、解像度が良くないもの、表示が薄いものの提示があり、評価が困難となるため留意されたい。また、アーチファクトの混入が強いもの、鋭波(sharp wave)ではなく鋭一過波(sharp transients)のように見えるもの、全般性棘波でも非対称性の強いものの提示があり、評価に影響するため可能な限り典型的かつ最良の図を提示されたい。
レポートについては、所見欄には記載があるが、判定(解釈)欄に対応する記載のないものがあり、所見欄に記載のある所見は過不足なく判定(解釈)して記載されたい。また、左右の誤記、スペルミス、他誤字、脱字、重複等があり、提出時には入念に確認されたい。
脳波分野の受験、脳波波形の図、レポートの提出にあたり、「日本臨床神経生理学会編. モノグラフ臨床脳波を基礎から学ぶ人のために第2版. 診断と治療社. 2019」を参照されたい。
【筋電図・神経伝導分野】
筋電図/神経伝導分野の波形レポート審査を行いました。審査員より以下のようなコメントがありました。今後の診療にお役立ていただけることを期待します。
皮膚温について
神経伝導検査や反復神経刺激試験にとって温度管理は大変重要です。末梢神経伝導検査は、平常時の深部体温より5℃以上低く、外気温により大きな影響を受けやすい四肢末梢部の神経を評価します。温度の低下は神経伝導に様々な変化を起こします。よって、末梢神経伝導検査は四肢の温度管理の指標として、皮膚温を測定することが求められています。「どこ」で測定するか、は、成書にも記載がないものが多いのですが、EAN/PNSによるCIDPのガイドラインでは、手掌33℃以上、外果30℃以上と部位と温度を明記しており、これを参考に出来ます。
例年、提出レポートに上肢で36℃以上、あるいは下肢で35℃以上などと、非発熱下ではなかなかあり得ない数値が記載されているものがあります。非接触式体温計で皮膚温を測定することも多くなりましたが、非接触式体温計の体温測定モード(前額部の皮膚温から推定される舌下温を体温として表示するとされています)を用いている可能性が高いと思われます。通常非接触式体温計には表面温度測定モードが付属していますので、皮膚温の測定にはそちらを用いるべきです。
また、断りなしに低い温度で検査し続けるなど、皮膚温を「書いただけ」というような態度のレポートも認められます。皮膚温は適切な温度管理を行っていることを示すために求められているのであって、大切なのは温度を書くことではなく、温度管理です。もし、血流障害などにより温度管理が不十分にならざるを得なかった場合、その旨をレポートに記載すべきです。
潜時計測と基線
潜時の計測の間違いは、伝導速度の結果に影響します。このため潜時は正確に測定する必要があります。正確な潜時の計測には、基線が平坦でかつ安定していることが重要です。基線が安定していない場合は、電極の貼り付け不良などの原因が必ずあるはずです。検査を開始する前にきちんと条件を整える必要があります。基線が斜めになっていたり、ノイズが混入していたりする記録は雑な印象を与え、検査の信頼性に疑義を生じさせます。特に専門医・専門技術師受験のレポート審査を受けるにあたって、このような波形は適しません。避けるべきです。
波形を記録すると筋電計が自動的に潜時を計測しますが、筋電計がつけたマーカーが本来の潜時とずれているということはしばしば経験されることです。検者はマーカーの位置が正しいか、その都度自分の目で確認する必要があります。立ち上がりが緩やかな波形では、より遅く潜時が計測される傾向がありますが、このような場合は筋電計のゲインを上げて(例えば5mV/divから1-2mV/divに変更する)、波形が立ち上がるポイントの正確な潜時を手動で計測し直す必要があります。
Fib/PSWについて
Fib/PSWの認識が正しくできていない申請者が散見されました。Fib/PSW認識の最重要ポイントは発火リズムで、完全にregularな発火であることが特徴です(一部irregularなfibrillation potential もありますが、これの認識はregularなfib/PSWをしっかりマスターしたあとの、高度の技能となります)。これが査読者にわかるように、十分な長さのあるラスターモードの記録を提出するようにして下さい。また波形が鈍っているのは多くの場合遠方の運動単位電位(MUP)です。Fibrillation potentialは必ずシャープです。
橈骨神経MCSについて
橈骨神経MCS(示指伸筋記録)の前腕刺激がうまくできていない人が目立ちます。前腕での橈骨神経(後骨間神経)の走行はやや深く、かつ示指伸筋など尺側の筋群への枝と、短母指伸筋などの橈側の筋群への枝が遠位では分かれるので、前者の部分刺激になると肘上刺激のCMAPより若干小さくなることが起こり得ます。ただこれを避けようと刺激を上げ過ぎると、前骨間神経に刺激がspreadして、方形回内筋のCMAPが大きく混入してきてしまいます。このように橈骨神経前腕部刺激はかなり難しいのは確かです。
また橈骨神経のErb点刺激を何も考えずにやっているらしい人が見られます。橈骨神経でErb点刺激を行うときには、collision法の施行が必須です。
伝導ブロックと時間的分散について
伝導ブロック所見と”異常な”時間的分散(excessive or abnormal temporal dispersion)とは、神経伝導検査において重要な判定項目です。伝導ブロック所見と異常な時間的分散は、ともに末梢神経中間部の脱髄の指標として認識されていますが、生理学的に起きている現象は異なることから、脱髄判定に用いられる各種の電気診断基準でもハッキリ区別されています。
一般的に伝導ブロック所見は、近位刺激CMAPの持続時間の延長なし(遠位の<30%)に、近位刺激CMAPの振幅または陰性頂点面積が減ずるもの(30%や50%などの基準がある)をそう判定します。一方近位刺激CMAPの持続時間が遠位刺激のそれに較べ30%以上延長するものは異常な時間的分散と判定されます。
伝導ブロックは、軸索は保たれたまま活動電位の伝導が遮断した状態です。これが運動神経で生じた場合は原則として筋力低下を生じます。実際の臨床では、伝導が保たれた線維の発火頻度を上昇させることで筋力を補おうとする代償が及ばない程度に伝導が遮断した線維の割合が増えると筋力が低下します。電気生理学的なCMAP振幅30%あるいは陰性頂点面積50%の低下といった基準は、十分に筋力低下を起こしうる数の線維が伝導出来ない状態を想定しています。
一方で、異常な時間的分散は、伝導の速い(正常な)線維と、伝導が遅くなった線維が混在している状態を示します。つまり、遅いながらも伝導しているので、脱力はなくても良いことになります。
両者はしばしば局所脱髄で生じ、混在することもありますが、伝導ブロックは脱髄急性期に、異常な時間的分散は再髄鞘化が起きている回復期に見られることが多い所見です。専門医は神経伝導検査波形の変化から、背景にある病態生理を推察する役割も担っています。両者を区別することは重要です。
伝導ブロック診断のpitfall
伝導ブロックの診断には様々なpitfallがあります。近位での刺激不足は基本的なもので、特に脱髄性ニューロパチーでは閾値上昇が見られるので、刺激不足に注意が必要です。この他、Martin-Gruber吻合(尺骨神経MCSで特に問題になりやすい)、刺激の波及(current spread, co-stimulation)などがあります。特に刺激の波及は様々なところで起こり得るので、電気診断の専門医はこれらを熟知していなければいけません。別項でも述べたように、橈骨神経MCSや正中神経MCSでのErb点刺激では、橈骨→正中、正中→尺骨の刺激の波及が問題となり、これらは必発なので、collision法の施行が必須です。また手根管症候群において手掌刺激で手関節刺激のものよりはるかに大きなCMAPが記録されて、伝導ブロックと診断している申請者がいましたが、正中神経MCSでの手掌刺激では尺骨神経への刺激波及が起こっていないことを証明するのは極めて困難で、十分な信頼度を持った判定はできません。感覚神経ではこのような問題がないので、手掌刺激と手関節刺激を比較することで伝導ブロックの存在の推測がある程度可能です。
外傷の電気診断
神経外傷の診断・予後判定には神経伝導検査、針筋電図などの電気生理学的手法が大変有用です。ただし、急性期の診断においては、受傷後の時間を考慮に入れることが必須です。Waller変性が神経根部から手足の末梢まで進展・完成するには2週間程度かかることは基本の知識となります。また、臨床症状と電気生理所見を対比させた上で解釈することも重要で、例えば感覚脱失がある部位のSNAPが(Waller変性が完成していると思われる時期以降も)出現するのは、neurapraxia(=伝導ブロック、予後は良い)でも見られますが、後根神経節より近位での完全損傷=引き抜き損傷でも見られる所見で、この場合は予後不良です。同一髄節でのCMAP消失、SNAP保持は後者を支持する所見となります。
【術中脳脊髄モニタリング分野】
術中脳脊髄モニタリングにおけるコントロールMEPとベースラインMEPについて
ベースラインMEPと記載すべきところをコントロールMEPと誤って記載されている波形レポートが散見されました。診断と治療社から出版されている術中脳脊髄モニタリングの指針(編集 日本臨床神経生理学会)に記載されていますが、ベースラインMEPは、侵襲的操作前に手術操作により影響を受ける可能性がある基準となるMEP波形と定義されます(p33〜34)。一方、コントロールMEPは、Tc-MEPモニタリング中に、対象筋となるMEP波形に変化があった場合、その変化が有意かどうか判定する際に参考とするモニタリング筋のMEP波形と定義されます(p34)。
Tc-MEP(経頭蓋電気刺激・運動誘発電位)モニタリングにおけるfacial MEPの刺激条件について
facial MEPを上下肢MEPと同じ条件で刺激してしまうと刺激アーチファクトと波形がオーバーラップして、皮質運動野が刺激された結果の波形なのか、顔面神経が末梢で刺激された波形なのかが区別できなくなります。顔面神経が末梢で刺激された波形はMEPのcontrolにはなりません。facialをcontrolとして用いるのであれば、facialに適した刺激条件で別に記録を行うべきです。
たとえば、①刺激のartifactがMEPと重ならないようにISIを1000Hz(1ms)に設定して記録する、②biphasic stimulationで記録する、③解析時間を10ms/divではなく3ms/divに設定して刺激のartifactとMEPを分離して確認できるようにする、などの対策が必要です。また、facial MEPがうまく記録できない場合は、僧帽筋MEPをコントロール波形として記録してもよいでしょう。
症例レポート波形用紙について
症例レポートの提出に際しては、日本臨床神経生理学会ホームページに掲載されている症例レポート用紙を使用して作成していただいています。申請者の中に旧い書式の症例レポート用紙を使用して提出している申請者が散見されました。症例レポート用紙の書式は毎年見直して更新していますので、最新の症例レポート用紙をダウンロードして症例レポートを作成するようにしてください。
2024年認定試験申請で提出された波形・レポートの講評
2024年認定試験が6月2日に実施されます。
認定試験の受験を申請するにあたり提出された波形・レポートを認定委員会にて審査致しました。この結果を講評として公開致します。
受験をされる方だけでなく、日ごろの診療においても参考としていただけますと幸甚です。
【脳波分野】
てんかん性放電(棘波・鋭波・棘徐波複合など)の定義
てんかん性放電すなわち棘波(spike)・鋭波(sharp wave)は通常後続徐波(afterslow/post-spike slow)を伴うものであり、伴わないものは鋭一過波(sharp transients)となりてんかんを示唆する所見とはならない。後続徐波を伴わず鋭一過波とすべき波形を棘波と判読しているレポートが散見された。みられる脳波波形がてんかん性放電の定義を満たすのか、あるいは満たさずに鋭一過波とすべきか、日々意識した脳波判読が望まれる。てんかん性放電の定義に関しては、最近の論文(Kural MA et al., Neurology. 2020;94:e2139-47. https://doi.org/10.1212/NE9.0000000000200073)などを参照されたい。また棘徐波複合(spike and wave complex)もてんかん性放電の一種であるが、棘波ないし鋭波が通常3つ以上連続する所見とされる。単発の棘波ないし鋭波に対して「棘徐波複合」と表記しているレポートもあった。脳波分野専門医・専門技術師を目指す場合、てんかん性放電(棘波・鋭波・棘徐波複合など)の定義についての確認が望まれる。
脳波所見と解釈の対応
てんかん性放電(突発性異常)がなく、徐波(非突発性異常)のみの脳波に対して、その徐波から示唆されるのは徐波がみられる部位の「局所機能異常」までであるが、「てんかんを示唆する」と解釈しているレポートがあった。また、例えば側頭部にてんかん性放電がみられる場合、「側頭部から出現する焦点発作」を示唆する脳波所見であるが、「(内側)側頭葉から出現する焦点発作」と解釈しているレポートがあった。頭皮上脳波の判読では、髄液を介して拡散する脳波を記録するため、「側頭部、前頭部」のように「葉」でなく「部」として記載することが望まれる。脳波判読能力の向上を目指す上で、脳波所見とそれに対応する解釈の対応を意識して、トレーニングいただきたい。
疑われる異常に対応する適切な表示モンタージュ
デジタル脳波の普及により、記録時とは異なる様々な表示モンタージュでの脳波判読が可能である。適切なモンタージュを選択することで、適切な診断しいては治療が可能であるが、不適切なモンタージュを選択することで診断を誤るリスクがある。全般性の脳波活動の評価には耳朶を基準とした単極誘導が良いが、average(AV)モンタージュで提示されているレポートもみられた。全般性の(広範な)脳波をAVモンタージュで表示するとあたかも局所性のようにみえ、誤った判読につながる。また側頭部の脳波活動の評価は双極誘導あるいはAVモンタージュが良いが、耳朶を基準とした単極誘導で表示することで全般性と誤った判読となっているものもあった。それぞれのモンタージュの利点・欠点を理解した上での適切な脳波判読が望まれる。
脳波の局在について
全般性の脳波活動を局在性、また逆に局在性のものを全般性、と判読しているレポートがあった。全般性の脳波活動は、通常前頭極部から少なくとも頭頂部にまで及ぶ両側性脳波活動とされる。局在性の脳波活動であれば双極誘導でのphase reversal(位相の反転)やAVモンタージュでの振幅から、その活動の局在・最大点を探す。上述の通り、判読に際しては複数のモンタージュを組み合わせて、全般性か、局在性であればどのような分布か(頭位マップをイメージあるいは実際に記載して)を論理的に考える必要がある。
※ 現在本学会ではHPにあるEラーニングコンテンツが充実しつつあり、特に「脳波判読の実際-正常脳波所見-」、「脳波判読の実際-てんかん性異常-」などは脳波判読を学ぶ上で非常に有用である。脳波分野専門医・専門技術師を目指す申請者にとってもこれらを用いた自己研鑽が推奨される。
【筋電図・神経伝導分野】
皮膚温について
神経伝導検査にとって温度管理は大変重要です。末梢神経伝導検査は、平常時の深部体温より5℃以上低く、外気温により大きな影響を受けやすい四肢末梢部の神経を評価します。温度の低下は神経伝導に様々な変化を起こします。よって、末梢神経伝導検査は四肢の温度管理の指標として、皮膚温を測定することが求められています。「どこ」で測定するか、は、成書にも記載がないものが多いのですが、EAN/PNSによるCIDPのガイドラインでは、手掌33℃以上、外果30℃以上と部位と温度を明記しており、これを参考に出来ます。例年、提出レポートに上肢で36℃以上、あるいは下肢で35℃以上などと、非発熱下ではなかなかあり得ない数値が記載されているものがあります。近年、非接触式体温計で皮膚温を測定することも多くなりましたが、非接触式体温計の体温測定モード(前額部の皮膚温から推定される舌下温を体温として表示するとされています)を用いている可能性が高いと思われます。通常非接触式体温計には表面温度測定モードが付属していますので、皮膚温の測定にはそちらを用いるべきです。また、皮膚温を「書けばよい」というような態度のレポートも認められます。皮膚温は適切な温度管理を行っていることを示すために求められているのであって、大切なのは温度を書くことではなく、温度管理です。もし、血流障害などにより温度管理が不十分にならざるを得なかった場合、その旨をレポートに記載すべきです。
被検筋の選択について
末梢神経伝導検査のルティン検査では、被検筋は定められおり、正常値もそれに従って作成されていると思います。しかし、例えば、下垂足に対する腓骨神経伝導検査では、振幅正常値の変動が大きいEDBだけでなく、脱力のある前脛骨筋を被検筋として追加検査を行うべきです。その他の神経の検査においても、可能な場合は被検筋として脱力がある筋を選んだ検査を追加した方が診断に結びつきやすいと考えられます。
感覚障害と神経伝導について
皮膚の感覚鈍麻は、皮膚の感覚情報が中枢に伝わっていない状態を示します。これが末梢神経由来である場合、感覚神経の伝導障害(軸索変性か伝導ブロックか)を示す所見です。病態が軸索変性であるときに、感覚鈍麻を示す神経において感覚神経活動電位が正常であることは後根神経節より近位の障害を示唆する所見です(伝導ブロックであれば「検査区間より近位」です)。一方で、「しびれ感」は、感覚過敏や異常な感覚神経発火、あるいは時には感覚の中枢性過感作状態を表す病態で、なんらかの感覚異常を示しているに過ぎません。感覚鈍麻の有無を述べずに「しびれと感覚神経活動電位正常」をもって、節前性障害と診断することはできません。そのような推測ができるのは、高度の感覚鈍麻ないし感覚脱失があるにも関わらず感覚神経活動電位が正常な場合だけで、その場合にも言えるのは、1)末梢神経軸索の近位部での伝導ブロック(Waller変性進行前の急性期を含む)、2)節前性障害(後根神経節より近位の神経根での障害)、3)中枢神経での障害、のいずれかであるということにとどまります。
下肢の神経伝導検査に関して
本年度試験におけるレポートには、下肢の伝導検査を求めていませんでしたが、次年度よりそれをレポートの要項に含めたいと思います。長さ依存性の末梢神経障害は下肢から始まるので、障害に対する感度は下肢の伝導検査が鋭敏です。レポートに下肢の伝導検査を含めない受験者が見られましたが、是非とも下肢の伝導検査を習得していただくようお願い致します。
針筋電図記録について
筋電図・神経伝導分野の専門医試験受験申し込み時のレポート提出に際し、「針筋電図においては、線維自発電位/陽性鋭波波形など客観的に判読可能な波形を少なくとも1例分付けるようにして下さい」とお願いしています。これは、試験において非常に基本的な波形判読問題の正答率が予想よりも低いことを鑑み、試験前に指定した波形を適切に判読出来ているか確認させていただく目的で行っています。針筋電図、とりわけ安静時活動ではリズムの評価が大切です。これがわかりやすいように、波形は「ラスター表示」、すなわち連続する複数スイープを上から順に並べた波形で提示していただくことが望まれます。
【術中脳脊髄モニタリング分野】
症例レポート作成時における出力波形
Tc-MEP(経頭蓋電気刺激・運動誘発電位)モニタリングの症例を提出する場合、導出筋を明記し、審査者がベースライン波形、MEP振幅低下時の波形がどれかわかるように明記してください。また、術前・術後または時系列で変化がわかるように提示してください。
波形が小さい、複数の波形がオーバーラップしている、などの理由で波形変化の確認が困難な症例レポートが散見されました。出力される波形が小さすぎないよう、複数の波形がオーバーラップしないように調整してから症例レポートを作成してください。
Tc-MEPの刺激条件の記載
提出されたレポートの中にMEPの刺激強度や刺激間隔の設定の確認が必要な症例が散見されました。本年度試験におけるレポートには、MEP刺激条件を詳細に記載することを求めていませんでしたが、次年度より「刺激強度、刺激間間隔、刺激頻度、連発回数」を記載していただくようレポートの要項に含めたいと思います。
Tc-MEPモニタリングにおける電気刺激強度の設定における注意点
脳外科領域ではTc-MEPモニタリングにおける電気刺激強度の設定は注意が必要です。刺激強度が強すぎる場合、モニタリングしたい部位(病変)よりも深部まで刺激が到達し、手術操作による障害が起こってもMEPが変化しない偽陰性を引き起こす危険性があります。
<刺激強度を設定する際の注意点について>
①刺激の効果を決める大きな要因は電流強度(mA)と刺激幅(msec)の積である電荷(μC)です。安全性と刺激効果の両方を高めるためには、電流強度と刺激幅を最適化することが重要です。経頭蓋刺激における刺激幅の推奨値は0.2msec$301C0.5msecとされていますが、麻酔による抑制が大きい運動誘発電位においては0.5msecが有用です。刺激幅を0.5msecにするとより低い電流強度でより安定した振幅の大きな運動誘発電位を記録することができます。
②強度設定は頭蓋内病変と脊椎脊髄病変を区別しておこなう必要があります。頭蓋内病変に対して強すぎる強度を用いると、モニタリングしたい部位(病変)よりも深部まで刺激が到達し、手術操作による障害が起こってもMEPが変化しない偽陰性を引き起こす危険性があります。その対策として、可能な限り弱い刺激強度でかつ安定した電位の誘発を意識する必要があります。具体的には電位を常に左右両側から同時記録し、刺激対側のみに誘発が限局する強度を目安とします。また、MEPの振幅が小さいと波形消失が起こりやすくなるので、500μV以上の電位でのモニタリングが望ましいと考えます。至適な刺激強度には大きな個人差があります。強度の検討は症例毎に実施してください。
Tc-MEPモニタリングの判定について
提出された症例レポートの中にモニタリングの判定の根拠が明確でないものが散見されました。モニタリングの判定は手術終了時のMEP振幅で判定しますが、アラームレベルの設定(アラームポイント)によってモニタリングの判定が変わります。所属施設によってアラームポイントが異なりますので、症例レポートにはアラームポイントを記載するようお願いします。
手術終了時のMEP振幅がアラームポイント以上であれば判定は ‘negative’ となり、術後麻痺が生じていれば False negative、術後麻痺が生じていなければ True negativeと判定します。一方、手術終了時のMEP振幅がアラームポイント未満であれば判定は ‘positive’ となり、術後麻痺が生じていれば True positive、術後麻痺が生じていなければ False positiveと判定します。また、True negativeと判定される症例で、手術中にMEP振幅がアラームポイントを超えて低下していた場合は<rescue症例>と判断しTrue negative (rescue)と判定します。





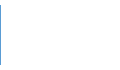
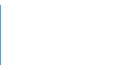
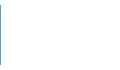
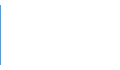
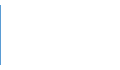
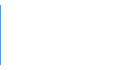
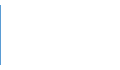
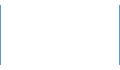
 学会作成ガイドライン・用語集
学会作成ガイドライン・用語集 会員ホームページ
会員ホームページ 会員 e-Learning
会員 e-Learning