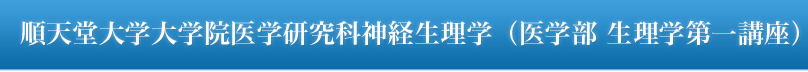活動報告
-
2012.8.26 須田
- ・第12回生理学若手サマースクールが8月8日、9日に開催されました。テーマ「脳の時間」について、中村先生(大阪大学)、喜多村先生(東京大学)、深井先生(理化学研)、西田先生(NTTコミュニケーションズ科学基礎研)に講義して頂きました。


-
2012.3.16 猿渡
- 2012年3月9日(金)に順天堂大学10号館8階803カンファレンスルームにて東京大学大学院総合文化研究科の寺尾将彦先生に「眼球運動時における非網膜的な視覚情報処理」との演題でご講演頂きました。
私たちは日常生活において頻繁に目を動かしています.寺尾先生は追跡眼球運動,急速眼球運動(サッカード)といった眼球運動時の視知覚を心理物理的手法で測定することにより、眼球運動に関わる皮質内信号が感覚処理にもたらしている変化を明らかにしてこられました。
ご講演では、一つ目には追跡眼球運動時の等輝度色運動の知覚の話を、二つ目には追跡眼球運動時における仮現運動での運動対応の話をされました。被験者に追跡眼球運動を行わせた場合と固視させた場合で、知覚測定の結果を比較すると、追跡眼球運動による知覚の変化を検出することが出来ます。私たちの脳内では、網膜より入力された刺激はまず網膜を中心とした座標系で処理され、処理が進むに連れて外界の座標系が再構成されていくことが知られていますが、追跡眼球運動により生じるこれらの知覚の変化は、脳内で外界の座標系が再構成された後に起こっていることを示唆する実験結果についてご紹介がなされました。
三つ目には,サッカードによって私たちの視空間が主観的に縮むという話でした。仮現運動での運動対応は近い刺激間で起こり易いとの性質を利用した独自の課題で、サッカード中の視覚がサッカードの方向に平行方向に空間的に縮んでいることを示す実験についてお話されました。
我々の視覚系では、外界を捉える処理が網膜の入力のみからの計算を越えて感覚器の動きの情報を加味したより能動的な処理が行われていることを明確に示され、視知覚の神経生理学的な機構を考えていく上でも大変興味深いものでした。
-
2012.2.1 宇賀
- ・日本テクノセンターで企業研究者向け講演会を行いました。視覚神経生理学の基礎と応用の話をしましたが、企業の方がどのような興味を持っているのかが分かり、大変勉強になりました。
- ・日本視覚学会2012年冬季大会に参加しました。質感研究が増えたのが印象的でした。個人的には「立体映像の知覚,視覚疲労とその医学的視点」のシンポジウムが勉強になりました。