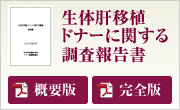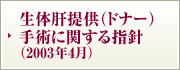2025年8月吉日
このたび大段秀樹先生の後任として、伝統ある日本肝移植学会の理事長を拝命しました。大変光栄に存じておりますとともに、諸先輩方が築かれてきた我が国の肝移植の歴史の重みをあらためて感じております。
私は1993年卒業ですが、当時、東京大学ではまだ肝移植は行われていませんでした。何を専門にするか絞り切れないまま、旧第二外科に入局した私は前期外勤を終えて、1996年に大学に戻ったときに初めて生体肝移植に触れ、以降後期外勤の2年を除き、ほぼ30年近く肝移植に関わり続けたことになります。この30年を振り返ると、肝移植は格段の進歩を遂げたと思います。手術手技や周術期管理の改善により、短期・長期成績は著明に向上し、今や1年生存率は90%を超えようとしています。保険適応の拡大もその結果です。また、膨大な経験・知識の蓄積により、あらゆる場面で合理的な簡略化・効率化がなされ、肝移植はかつてのような医局挙げての一大イベントではなく、単に消化器外科の中で“若干複雑で時間のかかる手術”の一つとなりつつあります。
一方で肝移植に関する課題は山積みです。脳死肝移植は安定して年間100例を超えるようになりましたが、まだまだ肝移植でしか救えない患者さんの数に見合っているとは言えません。さらに臓器提供が増えるよう、地道な啓蒙活動の継続が必要と思います。また、医療現場の体制も十分ではありません。働き方改革が進む中、外科医のみならず肝移植に携わるあらゆる職種のみなさんが楽しく持続的に働けるよう、業務の効率化・タスクシフト・タスクシェアなどの環境整備を進めていかねばなりません。欧米から大きく後れを取りましたが、機械灌流(恒温・低温ともに)などの技術の導入を迅速かつ確実に進め、ドナープールの拡大、成績の向上、働き方の改善につなげたいと考えています。
生体肝移植は脳死ドナーが十分数供給されれば、本来縮小に向かうべきと考えますが、いまだその気配はなく、今後も重要な役割を担い続けると思われます。胆管狭窄やsmall for size graftのような部分肝グラフトならではの問題点、生体ドナー手術の低侵襲化などさらに継続的に取り組むべきと思われます。また、日本の人口減少傾向を鑑みると、肝移植もある程度集約化が避けられないと思われますが、地域偏在が生じないよう、集約された施設に過度の負担にならないよう、バランスのとれた体制づくりを進める必要があります。このあたり個人や一施設で対応できることではないので、学会全体として意見調整した上で行政にも働きかけていくべきと考えています。
また、今まであまり取り組まれてこなかった課題として全人的・総合的な長期フォローアップを挙げたいと思います。アルコール性肝不全に対する移植後再飲酒、代謝性肝障害の再発など、技術的には成功した肝移植例でも多くの問題が生じています。これらの問題解決には外科医の努力だけではまったく対処不能であり、移植内科医をはじめとする精神科医やレシピエント移植コーディネーターらの協力が必須です。肝移植長期成績向上には多職種連携による総合的取り組みを進めるべきであり、本学会においても移植外科医以外の職種の方々のプレゼンスを高めるよう、努めたいと思っております。
以上、私が現時点で認識している課題とそれに対する方向性を挙げてみました。肝移植のさらなる発展・普及のため、今後とも努力してまいりますので、ご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。