HELICS活動概要と指針の解説
医療情報標準化推進協議会(HELICS協議会)は、2001年に設立され、標準化活動をしています。その活動は、 医療情報システムで扱う患者情報などを電子的に交換するための方法、コードや保存形式について、標準化団体間での 一貫性のある活動を実現するために、標準化の方針と内容について協議し、同時に、利用分野ごとに使用すべき標準規格を 推奨し、「指針」を定め、「医療情報標準化レポート」を提供しています。HELICS協議会が指針とした標準規格のなかから、 厚生労働省の保健医療情報標準化会議が審査して、厚労省標準規格が定められております。現在までに22の厚労省 標準規格があります。
それらは(1)マスターテーブル/コード:HOTコード、医科病名、歯科病名、臨床検査マスター、看護実践用語マスター、 歯式コード、口腔診査情報標準コード、(2)データ交換規格:臨床検査、放射線、処方、CDAに基づく退院時サマリー規約、 (3)電子診療情報/診療情報提供書、(4)放射線分野:PDI(CD媒体による画像情報連携)、DICOM (画像フォーマットなど)、JJ1017(画像検査コード)、REM(医療放射線被ばく管理)、(5)その他:SS-MIX2ストレージ、 処方・注射用法規格、MFER(波形フォーマット)、地域医療連携技術仕様、データ入力用書式の仕様(RFD)などです。
本チュートリアルでは、医療情報標準化推進協議会(HELICS)の活動概要を解説し、その後、「HELICS指針や厚労省標準 規格」の中から最近改訂された規格や新規に採用された規格として、(1)地域医療連携における情報連携基盤技術仕様 (XDS:cross-enterprise document sharingやXCA:cross-community accessなど)、(2)医療放射線被ばく監視統合 プロファイル(REM:Radiation Exposure Monitoring Integration Profile)、(3)歯科関連のコード(標準歯式コード仕様/ 口腔診査情報標準コード仕様)と(4)医用波形フォーマット(MFER: medical waveform format encoding rules)を 解説します。
第1部 医療情報標準化推進協議会(HELICS協議会)活動の概要 江本 豊 (HELICS協議会)
第2部 HELICS指針の解説
| 1) | 医用波形フォーマット(MFER: medical waveform format encoding rules) | 小林 聡 | (フクダ電子株式会社) |
| 2) | 地域医療連携における情報連携基盤技術仕様(XDS:cross-enterprise document sharingやXCA:cross-community accessなど) | 安藤 裕 | (日本IHE協会) |
| 3) | 医療放射線被ばく監視統合プロファイル(REM:Radiation Exposure Monitoring Integration Profile management) | 山中 誠一 | (日本IHE協会) |
| 4) | 歯科関連のコード(標準歯式コード仕様/口腔診査情報標準コード仕様) | 玉川 裕夫 | (日本歯科医師会) |
・発表資料は、「5.プログラム」からダウンロードできます。 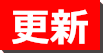
・チュートリアル参加費は無料です。(ただし参加するには連合大会の大会参加登録が必要です) ・事前申し込みは不要です。直接2号館1階・展示室211(C会場 )、もしくはWeb視聴でご参加ください。
・医療情報技師ポイント(1ポイント)がつきます。 * 2号館1階・展示室211(C会場 )で参加される方は、医療情報技師認定番号が分かるものをご持参ください。 (会場で医療情報技師ポイント申請書を記入していただきます)
* Web視聴で参加された方には、連合大会終了後にアンケートと医療情報技師ポイント申請フォームの URLをメールでお送りしますので、医療情報技師認定番号をフォームに登録して下さい。 └→ 【重要】URLはWeb-ex Eventsにログインする際に入力されたメールアドレスにお送りします。 誤ったメールアドレスでログインするとポイント申請ができませんのでご注意下さい。
* JAMI技師育成部会への技師ポイント申請は、HELICS事務局がまとめて行います。
・Web視聴の場合、医療情報技師ポイントの付与には60%(72分)以上の視聴が条件となります。 詳細はJAMI技師育成部会のページをご確認下さい。
