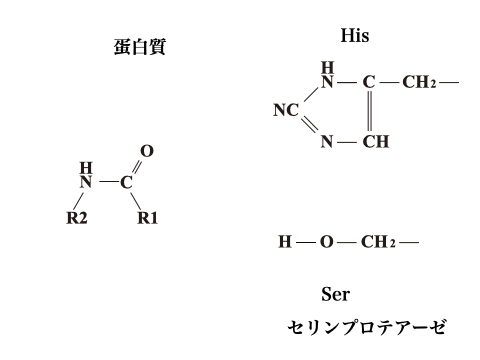セリンプロテアーゼは、図のGIFで示しているように、いくつかの段階を経て蛋白質を分解します。セルピンもセリンプロテアーゼによって切断されますが、その反応過程の中間状態で進行が止まります。アンチトロンビンの場合、「四面体中間体遷移状態」と呼ばれる状態で反応が止まり、その結果、トロンビンなどのセリンプロテアーゼと共有結合した1:1の複合体を形成します。トロンビンの場合はトロンビン- アンチトロンビン複合体(Thrombin-antithrombin complex; TAT)として、トロンビン産生の指標として使用されています。自身が切断されながらも(部分的ではありますが)、酵素活性を阻害するため、このような阻害様式を「自殺型酵素阻害」とも呼びます。
アンチトロンビンは流血中でもトロンビンなどの凝固因子を阻害しますが、その阻害速度はゆっくりとしたものです。これを「進行性阻害能」と呼びます。しかしアンチトロンビンにヘパリンが結合すると立体構造が変わり、その阻害速度は著しく促進されます。この意味でヘパリンはアンチトロンビンのアロステリック効果を及ぼすと考えられます。このようなヘパリンによって促進された阻害能を「ヘパリンコファクタ活性」と呼びます。日常診療で測定されているアンチトロンビン活性はこの「ヘパリンコファクタ活性」です。
全てのヘパリンがアロステリック効果を発揮するものではなく、ある特定の位置に硫酸基が配列したヘパリンのみがアンチトロンビンに結合し、その阻害能を促進します。またヘパリンのアンチトロンビンへのアロステリック効果はその分子量によってその性質が大きく異なります。アンチトロンビンに結合するためには5つの糖鎖があれば可能ではありますが、この場合、凝固第X因子に対するアロステリック効果は発揮されるものの、トロンビンに対する効果は認められません。これは凝固第X因子に対する阻害効果はアンチトロンビンの立体構造の変化のみで促進されますが、トロンビンに対する効果はアンチトロンビンの構造変化とともに、トロンビンが同一ヘパリン分子上に存在する必要があるためです。このためトロンビンに対してもアロステリック効果を発揮するためには10数残基の糖鎖が必要と考えられています。分子量が大きなヘパリンを含む「未分画ヘパリン」に比較して分子量が小さなヘパリンを多く含む「低分子ヘパリン」や「ヘパラン硫酸」がトロンビンに対するアロステリック効果に比較して、活性型凝固第X因子に対するアロステリック効果が高いのはこのためです。
先天的にアンチトロンビンの産生が低下もしくは塩基変異のために機能低下している場合があります。前者はアンチトロンビン欠損症、後者はアンチトロンビン異常症ですが、まとめてアンチトロンビン欠損症と呼ぶことが多いようです。変異の種類によって臨床症状、検査所見、治療介入の必要性など多少異なるます。詳細はアンチトロンビン欠損症を参照してください。
播種性血管内凝固症候群(Disseminated intravascular coagulation; DIC)の病態では血漿中のアンチトロンビンが低下する場合があり、このため血栓止血学会のDIC診断基準ではアンチトロンビン値が診断のための項目に含まれています。血栓止血学会のDIC診断基準は、実際に運用しようとするといろいろ問題がある診断基準ですが、アンチトロンビンが診断項目に採用されている点は特徴的でありこの点だけは評価できる点と考えられます。
DICの診断基準に採用されているとはいえ、凝固系の活性化に伴うトロンビンや活性型凝固第X因子の産生増加に伴いアンチトロンビンが消費性に低下することは通常起こりえません。これはトロンビンや活性型凝固第X因子の前駆体であるプロトロンビンや凝固第X因子の血中モル濃度から考えると明らかで、これらの因子のモル濃度はアンチトロンビンに比較して低く、凝固活性化のみではアンチトロンビンが低下するほどのトロンビン産生は惹起されません。これは著しい凝固活性化を伴うDICを合併する全骨髄性白血病などではアンチトロンビンの低下は軽度にとどまることに一致します。
一方敗血症をはじめとする炎症性の病態ではDICの病態を合併しなくても血漿中のアンチトロンビンの値が低下します。またアンチトロンビンの値が低下した症例ではさまざまな臓器障害を合併し、その予後は不良であることが知られております。DICも血液凝固系の臓器障害の一つとして捉えると、アンチトロンビンが低下したDICは予後が不良になることは理解できると思います。このためアンチトロンビンが低下した病態では予後の改善が認められることが重症感染症の一部の病態で報告されており、また炎症性疾患の臓器障害などの病態形成に重要な役割を果たしているサイトカインの産生をアンチトロンビンが制御する可能性も示されています。この意味ではアンチトロンビンは単に凝固系の制御因子をこえた、生体反応全体の重要な制御因子である可能性もあると考えられます。
アンチトロンビンはアミノ酸配列としては一種類ですが、糖鎖構造の違いでα-アンチトロンビンとβ-アンチトロンビンに分けられます。α-アンチトロンビンが血液中のアンチトロンビンの主な成分で、Asn 96、Asn 135、Asn 155及びAsn 192に糖鎖が存在していますが、β-アンチトロンビンはAsn 135の糖鎖が存在せずヘパリンへの結合能が上昇しています。
またアンチトロンビンは多くの場合、前述のように「四面体中間体遷移状態」でセリンプロテアーゼによる切断が止まりますが、時にこの段階で反応が止まらず、P1部位が切断された状態のアンチトロンビン(Cleaved antithrombin)が生成されます。P1部位の切断によって、アンチトロンビンの立体構造が変わりヘパリンに対する親和性は低下し、またプロテアーゼの阻害能も消失していますが、このようなCleaved antithrombinには血管新生抑制作用があることが報告されています。また活性中心を含む部位が立体構造変化を起こし、Cleaved antithrombinと同様の変化を起こしたLatent antithrombinと呼ばれる変異体やPrelatent antithrombinも存在し、同様に血管新生抑制作用が存在することが報告されています。
|