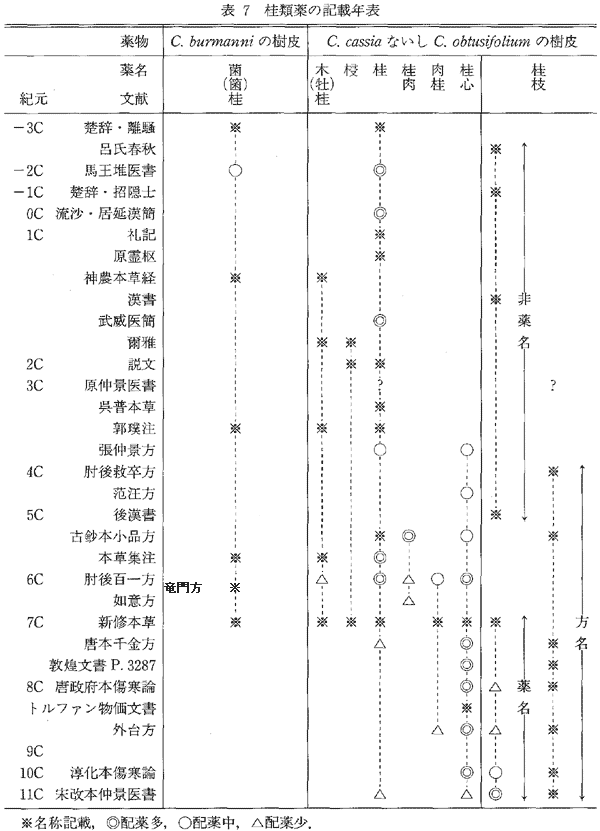←戻る
真柳誠「中国11世紀以前の桂類薬物と薬名-林億らは仲景医書の桂類薬名を桂枝に統一した」
『薬史学雑誌』30巻2号、96-115頁、1995
中国11世紀以前の桂類薬物と薬名
-林億らは仲景医書の桂類薬名を桂枝に統一した-*1
真柳 誠*2
The names of drugs in the cassia-bark family in China prior to the 11th century
- on the standardization as Guizhi(桂枝)by Lin Yi(林億)and other scholars of cassia-bark
family drug names appearing in the medical works written by Zhongjing(仲景)-*1
MAYANAGI Makoto*2
*1中国中医薬学会医古文研究会第8回中医文献及医古文学術研討会(1995年4月、中国・西安)にて発表。
*2北里研究所東洋医学総合研究所・医史学研究部
*2Department for the History of Medicine, Oriental Medicine Rsearch Centre of
the Kitasato Institute. 5-9-1, Shirokane, Minato-ku, Tokyo,108 Japan.
Summary
The Chinese medical classics Shanghan Lun(傷寒論), JinguiYaolue(金匱要略)and Jingui Yuhanjing(金匱玉函経)are regarded as having been written by Zhan Zhongjing(張仲景)in the early part of the third century A.D.. However all current editions of the three works are based on the northern Song(北宋)edition reviced by Lin Yi(林億)and other scholars that was first published in 1065 and 1066. Guizhi(桂枝)appears in prescriptions in all three books as an important medicine. Yet whereas in the Chinese Pharmacopoeia (C.P.)Guizhi is defined as the Cinnamomi Ramulus (the whole twig), in the Japanese Pharmacopoeia (J.P.) it is defined as the Cinnamomi Cortex (the bark). The reasons for this defference between China and Japan has not been studied before.
The author conducted a historical analysis of the terms and materials used for cinnamomic medicine in China from the third century B.C. to the year 1066. The following results were obtained.
(1) Until the Han(漢)period the drug name Gui(桂)was commonly used for products made from the bark (the cork from the bark being removed) of cinnamomic plant. Such products have been excavated from a tomb where they were interred in the second century B.C., and the drug name Guixin(桂心)was commonly used for them until the Tang(唐)perod.
(2) The terms Gui, Qin(梫), Mugui(牡桂), Mugui(木桂), Guirou(桂肉), Rougui(肉桂), Guixin, and Guizhifound in medical texts up to the tenth century were all used for the products made from the bark. The Tang government's pharmacopoeia of 659, the Xinxiu Bencao(新修本草),designates their material plant as either C. cassia or C. obtusifolium. This product primarily corresponds to Cinnamomi Cortex, being Keihi(桂皮)in J.P. or Rougui in C.P..
(3) The term Jungui(菌桂)was used from the third century B.C. for products in the shape of a bamboo pipe which were made from the bark of cinnamomic plant twig that had been repeatedly rolled up, and which were used as dietary foods or spices. The Xinxiu Bencao designates the material plant as C. burmanni,and the product corresponds to the cinnamon sticks now in use.
(4) As to use Guizhi as decoction, we can not deny the possibility that in theoriginal medical wroks of Zhongjing there was a prescription by the name of Guizhi Tang(桂枝湯). However, there are no examples of the drug name Guizhi until the sixth century, and most prescriptions of Zhongjing that were used around the Tang period employ Guixin or Gui. Because of this in some prescriptions there has arisen a contradiction in the terminology; for example in Guizhi Tang, Guizhi might be prescribed instead of Guixin. Further, there are also prescriptions named Guixin…Tang(桂心…湯). On the other hand, no evidence has been found that the whole twig of cinnamomic plant was used as a drug prior to theeleventh century. Consequently, this indicates an extremely small likelihood that in the time of Zhongjing the drug name Guizhi was employed, or that the whole cinnamomic twig was employed as a drug.
(5) In the Taiping Shenghuifang(太平聖恵方)which was published in the early part of northern Song period there is, among the prescriptions for Guizhi, an example drawn from the prescriptions of Zhongjing, of the use of a drug named Guizhi, which has the same meaning as Guixin. However, at the time Guixin was commonly used term.
(6) Since, when the Zhongjing medical works were edited and published by the northern Song government, there was a need to unify and standardize the drug names in the three works, the cinnamomic medicine names were standardized as "Guizhi with bark removed (Guizhi with the note that the cork is to beremoved)", which means the same as Guixin. By this method a contradiction between the drug name and prescription name was avoided. At the same time, prescription names of the kind Guixin…Tang were amended to Guizhi…Tang. Accordingly, the Guizhi in the editions of the Zhongjing medical works does not mean the whole twig Cinnamomi Ramulus but the bark Cinnamomi Cortex.
1 緒言
1-1 薬物の疑問-日本と中国の相違
後漢時代の張仲景は3世紀初に医書を編纂したと伝えられている。そして現在に伝わる仲景医書の全版本は、北宋政府校正医書局の林億らの校訂、いわゆる宋改を経て初めて1065年に刊行された『傷寒論』(以下『傷寒』)、同年に刊行された『金匱玉函経』(以下『玉函』)、翌1066年に刊行された『金匱要略』(以下『金匱』)に基づく1)。当3書には桂枝湯など桂枝を配剤した処方が多数あり、その桂枝に日本は『日本薬局方』(以下『局方』)が規定する桂皮2)、すなわちCinnamomum cassiaまたは同属植物の乾燥樹皮であるCinnmomic Cortexを用いる。
一方、C. cassiaの乾燥樹皮を『中華人民共和国薬典』(以下『薬典』)は肉桂と規定するが3)、現中国で肉桂を仲景医方の桂枝に用いることはない。中国は別に桂枝と呼ぶ薬物を仲景医方に用い、これを『薬典』はC. cassiaの乾燥した直径0.3-1.0cm の小枝全体であるCinnamomic Ramulusと規定し4)、桂枝尖という枝先の商品もある。しかし、『薬典』の桂枝に相当する薬物は『局方』にない。すると仲景医方の桂枝に樹皮を用いる日本と、小枝全体を用いる中国は本来いずれが正しいのだろうか。
1-2 薬名の疑問-仲景医書の記載不一致
仲景医書は桂枝以外の桂類薬名を例外的に記載する。たとえば『傷寒』発汗吐下後病篇の五苓散に桂心5)、『玉函』巻七の五苓散に桂6)が配剤される。また『金匱』痙湿暍病篇の葛根湯と痰飲咳嗽病篇の五苓散にも桂が配剤され、同書雑療法篇には薬味を記さないが桂湯という処方もある7)。あるいは『金匱』瘧病篇の白虎加「桂枝」湯に「桂」8)、『傷寒』『玉函』『金匱』の桂枝加「桂」湯に「桂枝」9)が配剤され、加味薬名と配薬名が一致しない。さらに『傷寒』『玉函』の桂枝去桂加茯苓白朮湯10)で桂枝湯から除去されるのはもちろん桂枝であり、方名の「去桂」と一致しない。
1-3 問題の所在と研究方法
仲景医書のこれら桂・桂心は桂枝と同一薬物なのか、それとも別物なのか。もし同一薬物なら、なぜ例外的に桂や桂心という薬名を記載するのか。もし別物なら、桂枝・桂・桂心はどこが相違するのか。すなわち問題は、仲景医書の桂枝が本来いかなる薬物で、桂・桂心といかなる関係にあるのかである。当問題が解決されるなら、桂枝の解釈が日本と中国で相違する是否も決着可能だろう。ただし現在の『傷寒』『玉函』『金匱』は印刷物となるまでの800年近い筆写伝承による変化が十分に予測され、この3書だけで名と物の歴史変遷を内包する当問題は正確に考察できない。そこで歴代の記載文献を批判しつつ、所載の仲景医方および関連文献や出土物などから総合的に検討することにした。
2 漢代までの桂
2-1 非医書の菌桂・桂・梫・木桂
前3世紀の『楚辞』離騒は菌桂や桂酒11)、漢代の『礼記』檀弓上は桂12)および『爾雅』は「梫、木桂」13)、2世紀初の『説文』は「梫、桂也」14)などを記載する。この『爾雅』と『説文』から判断すると、梫・木桂・桂は異名同物だったらしい。しかし形状記載はいずれもなく、後に3世紀の郭璞が『山海経』注に「衡山有菌桂、桂員(円)似竹」15)、また『爾雅』注に「今江東呼桂、厚皮者為木桂」13)と記すのみである。一方、桂枝の表現が前3世紀の『呂氏春秋』(『爾雅翼』所引)16)、前1世紀の『楚辞』招隠士、1世紀の『漢書』、5世紀の『後漢書』にある17)。あるいは「桂枝~」の用例が多数みいだされるが18)、いずれも薬名ではない。
2-2 出土した中国古代の桂皮と現存する中国中世の桂心
前168年に埋葬された馬王堆1号漢墓の副葬品から、医療目的らしい7植物の香薬とともにC. chekiangenseの樹皮小片が出土し、調査報告書はこれを桂皮という19)。注目すべきは、コルク層が除去されていた点である。これは王侯貴族の副葬品なので、当時としては上等な加工品だったろう。なお出土品に小枝全体の桂類はない。
奈良時代の日本では唐から輸入した桂心等の薬物を、孝謙天皇が756年に東大寺に献上した。現存する当時の献上目録「種々薬帳」に桂心の名で記載され、その桂心が現在も正倉院に保管されている。実物を調査した結果、C. cassiaないしC. obtusifoliumに基づく大小さまざまな板状~半管状~管状の樹皮で、みなコルク層が除去されていた20)。天皇の献上物なので当然これも上等品である。小枝全体の桂類は現存せず、当時の献上記録・使用記録にも桂枝の薬名はない。
以上より中国では、紀元前から桂類薬の上等品にコルク層を除去した樹皮を使用し、それを中世では桂心と呼んでいたことが分かる。
2-3 出土医書の桂・菌桂
馬王堆3号漢墓の出土医書(前168年以前)には薬名として、『五十二病方』に桂9回・美桂1回・菌桂1回、『養生方』に桂3回・菌桂3回、『雑療方』に桂4回の記載があるが、桂枝など他の桂類薬名は一切ない21)。また前1世紀~後1世紀頃の『流沙墜簡』と『居延漢簡』の医方簡には桂のみ各2回22)、1世紀頃の武威出土医書には桂のみ12回の記載がある23)。
当頻度から漢代までの一般的名称は主に桂、ついで菌桂だったと推定できる。桂・菌桂の具体的相違は不明だが、薬名に桂枝は使用されていなかった可能性が高い。
2-4 『霊枢』(『太素』『甲乙経』)の桂
『霊枢』には薬名として寿夭剛柔篇に桂心、経筋篇に桂の記載がある24)。ところが両者の対応文を、『太素』25)『甲乙経』26)はともに桂と記す。上述した漢代までの非医書や出土文献にも桂心はなかった。すると後漢代頃の原『霊枢』の桂が、後代の伝承過程で寿夭剛柔篇のみ桂心に改められたと推定できる。
当変化は、漢代の桂が後代に桂心と理解された可能性も示唆する。なおこの3書および同系医書の『素問』にも桂枝の薬名は一切ない。
2-5 小結①
(1) 漢代までの薬名では桂、ついで菌桂が一般的だった。また一般的ではなかったが、梫・木桂は桂の異名だったらしい。
(2)当時の上等薬物はコルク層を除去した樹皮、つまり後の桂心である。漢代までの桂は後に桂心と理解された痕跡があるので、当時の桂には樹皮のコルク層除去品もあっただろう。
(3) 桂類小枝の実物は未発見であり、諸記録からしても桂枝の表現は当時まだ薬名に使用されていなかった可能性が高い。
3 漢~唐代本草書の桂類
漢代までの記録・出土品だけでは名と物の関係が不明瞭で、桂と菌桂の相違も分からなかった。他方、陶弘景の『本草集注』(500年頃、以下『集注』)によれば、朱字経文の『神農本草経』(1-2世紀、以下『本経』)で牡桂・菌桂が、3-4世紀頃の墨字経文(以下、仮に『別録』)で桂が本草の正条品に収載された。『本経』や『別録』は各形状をあまり記載しないが、のち唐代までの本草書は比較的詳細に観察している。そこで各記載を検討し、唐以前の桂類薬と基原植物および現市場品との関連を考察してみた。
3-1 桂27)・牡桂28)と桂枝
桂は『別録』で本草正条品に収載されたが、本草での初出は3世紀初の『呉普本草』29)だろう。しかし『呉普本草』も『別録』も形状は記さない。陶弘景は桂条に注して「以半巻多脂者、単名桂、入薬最多」という。形状が半巻ならば当然樹皮である。しかし、いま中国で桂枝とする径1cm以下の小枝から「半巻多脂」の樹皮を採取するのは現実的に不可能だろう。当時の桂はある程度太い枝ないし幹の樹皮に相違ない。また「入薬最多」というので、桂は陶弘景の6世紀前後にも一般的桂類薬だったと分かる。
一方、牡桂は『本経』が初出であるが、『別録』ともに形状や植物を記述しない。陶弘景の牡桂注で初めて「状似桂而扁広」といい、樹皮と分かる。さらに『新修本草』(659年、以下『新修』)、および『蜀本草』(938-964年)を介して『嘉祐本草』(1061年)に転引された『新修図経』(659年)は唐政府の編纂で、産出地から実際の情報を収集している30)。それゆえ形状や植物にも詳しく、唐代までの記録では信頼性がもっとも高い。この要旨は以下のように整理できる。
a.梫・木桂・牡桂・桂について
『新修』牡桂条注:梫、木桂、…牡桂即今木桂及単名桂者是也。
b.肉桂・桂枝と桂心について
『新修』桂条注:牡桂嫩枝皮、名為肉桂、亦云桂枝。
『新修』牡桂条注:小枝皮肉多半巻、…一名肉桂、一名桂枝、一名桂心。
『新修図経』牡桂条注:其嫩枝皮半巻多紫肉、…謂之桂枝、又名肉桂、削去上皮(コルク層)、名曰桂心、薬中以此為善。
c.牡桂・木桂について
『新修』桂条注:其老者、名牡桂、亦名木桂。
『新修』牡桂条注:大枝皮…如木、肉少味薄、不及小枝皮。
『新修図経』牡桂条注:其厚皮者、名曰木桂。
d.牡桂植物の葉長について
『新修』桂条注:牡桂葉、長尺許。
『新修』牡桂条注:此桂花子、与菌桂同、惟葉倍長。
『新修図経』牡桂条注:葉狭、長於菌桂葉一二倍。
まずdの「牡桂葉、長尺許(牡桂葉は1尺ほどになる)」から牡桂植物を同定してみたい。唐代の1尺は大制で約30cm、小制で約25cmに換算される31)。中国に自生するクスノキ属薬用桂類種で葉が最長はC. obtusifoliumで約10-22cm、次はC. cassiaで約8-17cmである32)。両種以外はより短葉の種しかなく、牡桂植物はこの2種に限定できよう。現在の日本市場の大多数は中国から輸入されるC. cassiaの樹皮で、商品名を集散地から広南桂皮や東興桂皮と一般にいい、『薬典』の肉桂や『局方』の桂皮に該当する。他方、C. obtusifoliumの樹皮を日本でベトナム桂皮といい、桂皮の上等品とされるが、ほとんど中国市場にない。したがって唐政府が規定した牡桂(桂)植物は主にC. cassiaで、一部にはC. obtusifoliumもあっただろうと判断できる。
bでは若枝の半巻状で多肉な皮を肉桂や桂枝といい、コルク層除去品を桂心という。この形状に相当する中国の現市場品は33)、径約3cm前後の枝や幹の樹皮とされる桂通や官桂で、『薬典』の肉桂や『局方』の桂皮に用いられる。またcでは大枝の厚い皮を木桂と規定する。この形状は径約8-10cm以上の幹の樹皮とされる現市場品の企辺桂や板桂に相当し33)、やはり『薬典』の肉桂や『局方』の桂皮に用いられる。したがって『新修』の桂枝とは現在の肉桂・桂皮の別名であり、径約1cm以下の小枝全体を薬物とする現在の桂枝は『新修』の規定にない。
ところで『新修』は牡桂と桂を同一品と判断するのに、なぜ別々の条文に記すのか。これは『別録』が34)、桂の条文を牡桂とも菌桂とも別に記したことに起因する。それで陶弘景の『集注』は牡桂を「状似桂而扁広」というが、『別録』を踏襲して両者を一緒にしなかった。『新修』の桂条注も桂と牡桂は同一と断定して「剰出単桂条、陶為深誤也」というが、分類だけは『別録』『集注』に従った。そして当分類は宋代まで踏襲されたので、後々混乱が深まっていったといえる。
3-2 菌桂35)
菌桂は本草に『本経』から収載されたが、形状記述はない。『別録』で初めて「無骨、正円如竹」と記され、これは前述の『山海経』郭璞注にいう「菌桂、桂員(円)似竹」ともおよそ合致する。ちなみに仁和寺本『新修』は菌桂でなく、箘桂と記す36)。この箘には竹の意味があり菌と通じるので37)、菌桂(箘桂)とは竹筒状桂類薬の意味で呼ばれた名称だろう。『集注』の菌桂条で弘景は「正円如竹者、惟嫩枝破巻成円、猶依桂用、非真菌桂也」「三重者良、則明非今桂矣、必当別是一物」と注し、菌桂と桂はまったく別物と考えている。一方、『新修』菌桂条の注は「大枝小枝皮倶菌、然大枝皮不能重巻、味極淡薄、不入薬用」という。すると7世紀までの菌桂は桂(牡桂)と別植物で、その小枝の樹皮は重なり巻くが、大枝の樹皮は味が淡薄で重なり巻かず使用不可だったらしい。
他方、『新修図経』注は牡桂の葉が「長於菌桂葉一二倍」といっていた28)。現在の中国に自生する薬用桂類種で、葉の長さが牡桂すなわちC. cassiaやC. obtusifoliumの1/2~1/3なのは 6-10cmのC. burmanniしかない38)。すると『新修』の7世紀以前の菌桂はC. burmanniの小枝の皮だった可能性が予測されよう。ところで現在スパイスとして使用されているシナモンスティックの大部分は、C. zeylanicumのセイロンニッケイとC. burmanniのジャワニッケイに基づく39)。製法は株から新出した若枝の皮を剥ぎ、コルク層を削り落として重ね巻き40)、紙巻きタバコほどの太さになっている。その形状はまさしく竹筒状で、唐代までの菌桂の文献記載と一致する。このシナモンスティックは辛味が弱くて甘味が強い食用で、辛味・甘味ともに強い薬用のC.cassiaの樹皮とは相当に違う。菌桂もシナモンスティック同様、香辛料だったのだろうか。
本草の経文を見ると、桂条の『別録』と牡桂条の『本経』『別録』はいずれも治療効果に具体的病状を挙げる。ところが菌桂は『本経』に「主百病、養精神、和顔色、為諸薬先聘通使、久服軽身不老、面生光華、媚好常如童子」、と一般的な健康増進効果しか記されない。『別録』は菌桂の効果すら一切記載しない。すると菌桂は治療用ではなく、健康増進を目的とした香辛料だったに相違ない。『本経』上薬の秦椒が食用で、下薬の蜀椒が薬用という同様例もある。馬王堆医書以降、菌桂を配剤した処方が医方書にみえないのも当理由からであろう。一方、C. zeylanicumの葉長は15-20cmで40)、『新修』がいう菌桂の葉長と合致しない。以上より、菌桂はC. burmanniに基づき、シナモンスティックと同様の製品だったらしいと判断できる。
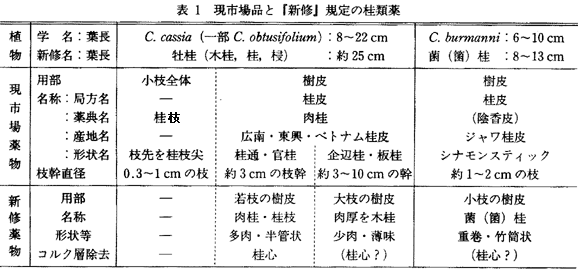 3-3 小結②(表1)
3-3 小結②(表1)
(1) 漢代前からの梫・木桂(牡桂)あるいは桂を、7世紀唐政府の『新修』はC. cassiaないしC. obtusifoliumの樹皮と規定した。これは『局方』の桂皮や『薬典』の肉桂におおむね該当する。
(2)牡桂の若枝の樹皮は多肉で乾燥すると半巻状になり、『新修』はこれを肉桂・桂枝といい、いまの桂通等に相当する。上等品はコルク層を削り去り、桂心と呼んだ。大枝の樹皮は品質が劣るが、厚い皮を木桂といい、今の企辺桂や板桂に相当する。
(3) 漢代から記載された菌桂は健康増進目的の香辛料で、薬物の桂(牡桂)とは効能でも明瞭に区別されていた。
(4) 唐政府がいう菌桂はC. burmanniの小枝の樹皮と考えられ、重なり巻いた竹筒状の製品で、現在のシナモンスティックにほぼ相当する。大枝の樹皮は気味を欠くので利用不能だった。
(5)『新修』に初めて薬物として記述された桂枝は、現在の桂皮(肉桂)に該当する。しかし小枝全体を薬物とする現在の桂枝は、まだ本草書に出現していない。
4 西晋~六朝代仲景医方の桂類
3世紀初頃に成立した仲景医書そのままが出土したり伝存する例はない。しかし旧態を比較的保存した西晋~六朝時代の医方書はいくつか伝わり、そこに仲景医方の引用も発見できる。それらを仔細に検討し、各時代ごとの桂類薬名と薬物を考察してみたい。
4-1 『張仲景方』
984年の丹波康頼『医心方』は隋唐以前の医書を多数引用し、ほぼそのままの姿で現代に伝えられた。この『医心方』には、『張仲景方』から桂を配剤する桑根白皮湯と桂心を配剤する半夏湯が引用される41)。
当『張仲景方』は891-897年頃の『日本国見在書目録』が著録する「張仲景方九巻」に恐らく該当し、『隋書』経籍志に著録の「張仲景方15巻」や『高湛養生論』の逸文(『太平御覧』巻722所引)にいう「王叔和編次張仲景方論、編為三十六巻」の系統と考えられる42)。王叔和による仲景医書の編集は282年以前なので43)、この桑根白皮湯と半夏湯も3世紀後半の処方に由来する可能性があろう。そこに桂枝ではなく、現在仲景医書に例外的にみえる桂や桂心が配剤されている点に注意したい。
4-2 『肘後百一方』
310年頃に葛洪は『肘後救卒方』を編纂し、それを500年に陶弘景が増補して『肘後百一方』とした。これは北宋校正医書局の校訂を経ず、金代になって楊用道が付広し、楊用道本の系統のみ現代に伝わる44)。その文章は『医心方』所引の『葛氏方』などと相当に合致するので、葛洪・陶弘景の面目をよく保存していると考えられる。
本書には張仲景八味腎気丸方が載り、無記名だが麻黄湯・小建中湯と同一薬味の処方もあり、みな桂が配剤されている45)。一方、葛洪が書いたと判別できる文章には、「凡治傷寒方甚多、其有諸麻黄・葛根・桂枝・柴胡・青竜・白虎・四順・四逆二十余方、並是至要者」とある46)。この桂枝とは前後からして桂枝湯に相違ない。
ところで『肘後百一方』の処方には筆者の概算で仲景の3処方を含め、桂が58回、桂心が20回、肉桂が4回、牡桂と桂肉が各1回配剤されている。これは陶弘景が『集注』で「単名桂、入薬最多」と述べていたことと符合する。しかし薬名としての桂枝は一切なく、仲景処方でも桂が配剤されるのに、桂枝(湯)の方名が記される。とするなら葛洪や陶弘景の時代、桂枝という特殊な語彙は処方名に使用されるのが第一義であり、およそ通常の薬名ではなかったと判断していい。また葛洪が『肘後卒急方』を編纂した310年頃すでに桂枝湯の方名があったことも分かり、現存記録ではこれが最初と思われる。
4-3 『小品方』
陶弘景以前の成立で、その後の改変が少ないと判断される医方書を筆者らは近年発見した。前田家・尊経閣文庫所蔵の古巻子本『小品方』巻1である。当書は454-473 年に陳延之が著し、日本に渡来したのは 649年以前の写本と推定された47)。この『小品方』序文には18種の参照文献を列挙し、うち「張仲景弁傷寒并方九巻」と「張仲景雑方八巻」が注目される。また巻1前半の「述旧方合薬法」では「合湯、用桂・厚朴…」「桂、一尺若数寸者…」48)と桂のみを記す。
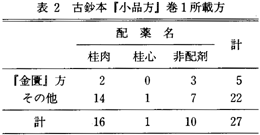 当本巻1の後半には計27処方が記載され、うち16方に桂肉、1方に桂心が配剤されている。また27方のうち『傷寒』方と関連するものはないが、『金匱』方と方名が類似し、かつ同一薬味の処方が5方あり、うち厚朴湯と桂支湯加烏頭湯の2方に桂肉が配剤されている(表2)。各々は『金匱』の厚朴七物湯と烏頭桂枝湯に該当する。桂肉の名称は唐代までの本草書になかったが、『肘後百一方』に1回記載されていたので、六朝の医方家の一部で使用された桂心ないし肉桂の別称かと思われる。
当本巻1の後半には計27処方が記載され、うち16方に桂肉、1方に桂心が配剤されている。また27方のうち『傷寒』方と関連するものはないが、『金匱』方と方名が類似し、かつ同一薬味の処方が5方あり、うち厚朴湯と桂支湯加烏頭湯の2方に桂肉が配剤されている(表2)。各々は『金匱』の厚朴七物湯と烏頭桂枝湯に該当する。桂肉の名称は唐代までの本草書になかったが、『肘後百一方』に1回記載されていたので、六朝の医方家の一部で使用された桂心ないし肉桂の別称かと思われる。
さて桂支湯加烏頭湯であるが、この「桂支」もいままでの検討になかった。もっとも可能性が高いのは、桂枝と同義に解釈することだろう。馬王堆医書には長枝を「長支」49)、『素問』『霊枢』には四肢を「四支」50)と記す例がある。当本巻1の27処方の配剤薬でも芍薬を「夕薬」、茯苓を「伏苓」と記し、同様の例は『医心方』にも多い。いまひとつは、皮と支の字形が似るので、「桂皮」が「桂支」に転訛した可能性である。たとえば『千金翼方』巻19には大桂皮湯が載り、皷と鼓は別字だが同音・同義という例もある。しかし漢代頃までの文献に桂皮の用例は発見できない17,18)。また音韻学上、隋唐音では枝・皮ともに「支」の韻に所属するが、それ以前の古音では支・枝が第二部、皮が第六部の韻で一致しない51)。したがって桂支湯は桂枝湯に釈読するのが妥当だろう。*追記(明・無名氏本『霊枢』14-6b3に「大腸者皮」を「大腸者支」に誤記する)
つまり桂枝湯という方名は確かにあった。そして構成薬味もある桂枝湯の古文献における記載は、現在のところ古写本『小品方』巻1が最古ということになる。これに桂枝ではなく、桂肉の薬名で配剤している。一方、主治条文の記述形式に注目すると、桂心配剤方は「治…」なのに、桂肉配剤方はすべて「主…」でまったく違う。陳延之が記述形式を統一せず、参照した文献の記載をほぼ踏襲した証拠である。ならば陳延之が参照した「張仲景弁傷寒并方九巻」や「張仲景雑方八巻」などにも、桂枝という薬名はなかった可能性がきわめて高い。*追記(北斉武平6(575)以前?の『龍門薬方』に桂心1回、桂3回ほどの記載があり、傾向は『肘後方』に近い。『外台秘要方』3-29a-4に「范汪(巻33、東晋350頃)又桂枝湯、療天行𧏾病方。 桂心二両、小藍二両。」、14-2b-2に「深師(巻9、5世紀末)療中風、汗出乾嘔、桂枝湯方。桂心、甘草(炙)、 各三両、大棗十二枚(擘)。右三味切、以水五升煮取二升半、分三服。 一方用生薑五両」とある。)
4-4 小結③
(1)旧態を比較的保存する3世紀後半~5世紀後半の医方書に、計7方の仲景医方を見い出した。うち4方に桂が、2方に桂肉が、1方に桂心が配剤されていた。これは時代の経過に従い、仲景医方の桂類薬名も書き改められていたことを示唆する。
(2)500年の『肘後百一方』では桂の配剤が最も多く、次いで桂心・肉桂・牡桂・桂肉の順だった。出土漢代医書でも桂が一般的だったので、これは漢代の影響が六朝時代にも及んでいたことを物語る。
(3) 桂枝湯の方名は少なくとも310年以前から存在していた。しかし桂枝湯を含め薬名としての桂枝の記載は一切なく、当時の桂枝は方名のみに使用される特殊な語彙と判断された。なお現中国の桂枝に相当すると判断できる薬物の記載もなかった。
5 唐代仲景医方の桂類
5-1 敦煌文書P.3287の仲景医方
フランスのPaul Pelliotが1908年に敦煌の莫高窟で入手した古文書類はいまパリ国立図書館に所蔵され、中には医学関係の文献も少なくない。うち巻子本のP.3287は計149行が残存し、第105-114行にかけて桂枝湯と葛根湯の記載がみえる52)。その桂枝湯は桂心・白勺薬・生薑・甘草・大棗、葛根湯は生葛根・黄芩・白勺薬・桂心・麻黄・生薑・甘草・萎蕤・大青・大棗から構成され、ともに桂枝ではなく桂心が配剤される。
P.3287の文字に唐の睿宗・李旦の避諱はないが、太宗・李世民の「世」ないし「葉」、および高宗・李治の「治」を避諱で欠筆するので、高宗時代(650-683)の筆写と推定されている53)。すなわち唐代7世紀後半頃には、仲景医方の桂枝湯に桂心を配剤する例が確かにあった。またPelliotやSteinの敦煌文書には、非仲景医方ではあるが桂心配剤方が少なからずある。その一方、桂枝配剤方は1首も見いだせなかった。
ちなみに同じ西域文書では龍谷大学大宮図書館に大谷文書がある。うちトルファンで1912年頃に発掘された物価文書は、交河郡城(トルファン)の官員が742年夏頃に公定市価を記録したもので54)、その3033号と3099号の2紙に桂心の薬価が記されている55)。ただし、これら物価文書を含め、大谷文書にも桂枝の記載はない。
以上のように7世紀後半頃の敦煌文書は桂枝湯にも桂心を配剤し、桂心は8世紀中頃に西域のトルファンにまで流通していた。が、桂枝という薬名は西域出土の医薬文書に1例も発見できなかった。したがって唐代7-8世紀の薬名は桂心が主流で、薬名としての桂枝はほとんど使用されていなかった可能性が高い。
5-2 唐本『千金方』の仲景医方
現在、広く通行している『千金方』(650-658年頃)は、林億らの宋改を経て1066年に出版1)された北宋版の系統に基づくので、ここでは宋改本『千金方』と呼ぶ。また宋改を経ていない南宋版が日本にあり、これを未宋改本『千金方』と呼ぶ。さらに唐代に日本に伝来した『千金方』が現存し、『真本千金方』と通称される。『真本千金方』と同系統は丹波康頼『医心方』にも引用されており、その引用文を仮に唐本『千金方』と呼びたい。
以上のうち、唐代の面目に直接遡ることが可能なのは『真本千金方』と唐本『千金方』である。ただし『真本千金方』の現存部分は巻1なので、仲景医方との対応処方がない。そこで『医心方』にみえる唐本『千金方』の全引用文を精査してみた。
この結果、処方に配剤された桂類薬名はすべて桂心で、他の名称は一切なかった。うち『金匱』方と対応する以下の4方に桂心が配剤されていたが56)、むろん『金匱』はそれらに桂枝を配剤する。
a.『医心方』巻6治胸痛方第1:胸痺之病…不知殺人方(『金匱』胸痺心痛短気篇:枳実薤白桂枝湯)
b.『医心方』巻6治肺病方第13:大建中湯(『金匱』血痺虚労病篇:小建中湯)
c.『医心方』巻9治淡(痰)飲方第7:青竜湯・木防已湯(『金匱』痰飲咳嗽篇:大青竜湯・木防已湯)
ところで『医心方』所引書でも、300年前後の『張仲景方』や『葛氏方』などには桂、5世紀の『小品方』と6世紀の『如意方』など一部には桂肉の配剤方がみえる57)。そして桂・桂肉を除くと、『医心方』に200余書から引用された多量の桂類配剤方はほぼすべて桂心を記す。『医心方』巻1に『医門方』から引用される桂枝加附子湯・桂枝麻黄湯(麻黄湯)でも、桂枝ではなく桂心が配剤されていた58)。したがって『医心方』の編纂では薬名を桂心に統一しておらず、医方書での薬名は桂が古く、六朝頃に桂肉が一部で用いられたが、六朝~隋唐代は桂心がごく一般的だったと判断できる。この点からすると、唐本『千金方』が桂心だけなのは『医心方』を編纂した丹波康頼の作為ではない。原『千金方』の編纂時か、それが日本に渡来するまでの間に桂心に統一された可能性しかない。
一方、『医心方』の多量な桂類配剤方は桂心・桂・桂肉しか記さないので、唐以前の医方書に記された桂類薬はおよそ樹皮製品で、小枝全体を薬物とした可能性はほぼないと思われる。また桂枝という薬名も『医心方』は記載しないので、唐代までの医方書に桂枝が配剤されることはほとんどなかったと思われる。すると、桂枝という薬名で配剤する現在の『傷寒』『玉函』『金匱』は、唐以前に遡る書としてきわめて異例となってしまう。しかし仲景医書の条文や処方が異例なのではない。『医心方』だけでも、唐以前の医方書に記載された同類条文や対応処方の引用は相当な数に上る。異例とすべきは『傷寒』『玉函』『金匱』の3書のみ薬名のほぼすべてを桂枝とすること、その桂枝を小枝全体の薬物と解釈することである。
5-3 宋改本・未宋改本『千金方』の仲景医方
唐本『千金方』の検討結果を踏まえた上で、宋改本・未宋改本についても検討したい。唐本ほど旧態を伝えていない可能性もあるが、より多くの仲景医方が記載されているからである。まず唐本のa~c方について予備調査してみた。
c方(青竜湯・木防已湯)はともに宋改本『千金方』巻18痰飲第6に該当文がある59)。宋改本では木防已湯主治文の字句が増加し、『金匱』とほぼ同内容に変化していたが、桂心が配剤されている。青竜湯は宋改本で小青竜湯とされ、構成薬は巻18咳嗽第5の小青竜湯に一括して記され、桂心が配剤される。b方(大建中湯)は宋改本巻17肺虚実第2に該当文があり60)、主治文は大差ない。薬味にも桂心を記すが、方名は『金匱』と同様に小建中湯に変化していた。
a方「胸痺之病…不知殺人方」の該当条文は宋改本巻13胸痺第7にあり61)、新たに『金匱』方と同名の「枳実薤白桂枝湯」、および『金匱』と略同の主治文が増加していた。しかも方名中の「桂枝」と呼応し、配薬名も桂枝になっていた。他方、未宋改本では巻13胸痺7にa方の該当文がある62)。その記述は宋改本と合致せず、逆に桂心を配剤する点や条文字句のほとんど、各薬物の分量・助数詞までも唐本と一致していた。すると唐代の『千金方』では一律に桂心で記されていたのに、a方に限っては宋改段階ないし宋改に使用した底本の段階で桂枝に改められ、『金匱』と同じ枳実薤白桂枝湯の方名と主治文が付加されたと判断できる。当結果をふまえ、宋改本の巻9・10傷寒門を検討してみた。
 宋改本傷寒門の処方で構成薬が記され、それが『傷寒』『金匱』と対応するのは50方を越す。他方、桂類を配剤するのは傷寒門に29方あり、うち25方に桂心、4方に桂枝が配剤されていた。両者の共通方で桂心を配剤するのは五苓散・麻黄湯・大青竜湯・小青竜湯・茯苓(苓桂朮甘)湯・黄耆芍薬桂苦酒湯・鼈甲煎丸・白虎加桂湯、桂枝を配剤するのは桂枝湯・桂枝二麻黄壹湯・桂枝加黄耆湯である(表3)。この方名と配薬名に相関関係があるのは一目瞭然だろう。桂枝配剤方の方名には必ず「桂枝」がある。桂心配剤方は方名に「桂枝」がなく、あったとしても黄耆芍薬桂苦酒湯と白虎加桂湯の「桂」にすぎない。
宋改本傷寒門の処方で構成薬が記され、それが『傷寒』『金匱』と対応するのは50方を越す。他方、桂類を配剤するのは傷寒門に29方あり、うち25方に桂心、4方に桂枝が配剤されていた。両者の共通方で桂心を配剤するのは五苓散・麻黄湯・大青竜湯・小青竜湯・茯苓(苓桂朮甘)湯・黄耆芍薬桂苦酒湯・鼈甲煎丸・白虎加桂湯、桂枝を配剤するのは桂枝湯・桂枝二麻黄壹湯・桂枝加黄耆湯である(表3)。この方名と配薬名に相関関係があるのは一目瞭然だろう。桂枝配剤方の方名には必ず「桂枝」がある。桂心配剤方は方名に「桂枝」がなく、あったとしても黄耆芍薬桂苦酒湯と白虎加桂湯の「桂」にすぎない。
ところで、『小品方』では桂支湯加烏頭湯に桂肉、『医門方』では桂枝加附子湯・桂枝麻黄湯に桂心が配剤され、唐以前では方名と配薬名が矛盾する例もある。そして宋改本『千金方』は方名に桂枝がある処方のみ桂枝を配剤し、方名と配薬名の矛盾が解消されていた。a方は唐本と未宋改本で桂心だったが、宋改本では桂枝だった。唐代から宋代までの伝写過程で、これらの相違が自然に生じる可能性はまずない。すると唐本と宋改本の相違は名称矛盾を回避する意図が濃厚な改変と推測できよう。ちなみに朮類名称について宋改本『千金方』の新校方例に、「如白朮一物、古書惟只言朮、近代医家咸以朮為蒼朮、今加以白字、庶乎臨用無惑矣」と林億らが明言するので、『傷寒』『玉函』『金匱』もすべて白朮に統一されたことが論証されている63)。当然、桂枝についても宋改による改変を疑うべきだろう。
一方、この改変には名称の矛盾解消以外に、物としての桂心と桂枝の相違が関係しているかも知れない。薬物としての桂枝は『新修』が初出だが、その規定で桂枝と桂心に本質的な相違はなかった。しかも『新修』の当規定を宋改担当者は必ず知っている。なぜなら『千金方』巻1の「七情表」は本来、『集注』から引用したことが『真本千金方』と敦煌本『集注』から明らかで、これを宋改本『千金方』は『新修』の「七情表」で完全に改変しているからである64)。彼らが『新修』の内容を熟知していたのは疑問の余地もない。しかも同じ仲景の発表剤にもかかわらず、宋改本『千金方』は桂枝湯類のみ桂枝で、麻黄湯・大青竜湯等には唐本のまま桂心を記す。以上からすると宋改本の時点でも桂心と桂枝に物としての本質的相違を考えていないので、唐本と宋改本の相違は方名と配薬名の矛盾解消が目的らしいと判断される。
5-4 唐政府本『傷寒論』の桂類
唐政府は医生の学ぶ医方書に、719年の開元7年令まで『小品方』と『集験方』を指定していた。のち唐の760年に規定された医官の登用試験は10問中2問を『張仲景傷寒論』から出題し65)、林億らも宋改本『千金方』の校定後序に「臣嘗読唐令、見其制為医者、皆習張仲景傷寒陳延之小品」と記す。以上からすると開元7年令に次ぐ737年の開元25年令で医生の学習書に『張仲景傷寒論』が指定されたのは疑いない66)。むろんこの唐政府本は伝存しない。
一方、王燾の『外台秘要方』(以下『外台方』)には18巻本『(張)仲景傷寒論』の引用文が多数あり67)、内容の多くは『傷寒』『金匱』とほぼ対応する。王燾は唐の官僚で、『外台方』を完成した752年の自序に「余幼多疾病、長好医術」「久知弘文館図籍方書等」という。弘文館は唐政府の図書館なので、737年指定の『張仲景傷寒論』を必ず所蔵していた。ならば752年に完成した『外台方』が引用する『(張)仲景傷寒論』18巻は唐政府本に間違いなく、唐代の桂類薬名を反映している可能性も高い。ただし『外台方』の伝本は宋改系版本しかなく、『千金方』の例から推せば、たとえ宋版でも唐代の面目を保持しているとは速断できない。唐代の『外台方』を窺えるのは『医心方』に引用される7条68)のみだが、桂類配剤方はない。そこで宋改を経てはいるが現存最善の宋版『外台方』を底本とし、唐政府本の桂類薬名を慎重に検討することにした。
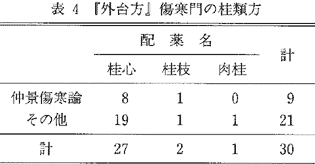 まず『外台方』巻1・2の傷寒門にて予備調査した。その結果(表4)、桂類配剤方は30方あり、うち9方が『仲景傷寒論』、21方が他書からの引用だった。『仲景傷寒論』の9方では、巻1の桂枝湯のみ桂枝を配剤し、他の8方は巻1の桂枝附子湯でも巻2の桂枝湯・麻黄湯・葛根湯でもみな桂心を配剤していた69)。他書から引用の21方でも『小品方』の射干湯に肉桂、『古今録験方』の橘皮湯に桂枝のみで、他の19方は『范汪方』の桂枝二麻黄一湯も『古今録験方』の大青竜湯もみな桂心が配剤されていた70)。
まず『外台方』巻1・2の傷寒門にて予備調査した。その結果(表4)、桂類配剤方は30方あり、うち9方が『仲景傷寒論』、21方が他書からの引用だった。『仲景傷寒論』の9方では、巻1の桂枝湯のみ桂枝を配剤し、他の8方は巻1の桂枝附子湯でも巻2の桂枝湯・麻黄湯・葛根湯でもみな桂心を配剤していた69)。他書から引用の21方でも『小品方』の射干湯に肉桂、『古今録験方』の橘皮湯に桂枝のみで、他の19方は『范汪方』の桂枝二麻黄一湯も『古今録験方』の大青竜湯もみな桂心が配剤されていた70)。
以上のように傷寒門の桂類配剤方は、その90%に桂心が記載されていた。この点は『千金方』の検討結果からしても、唐代の医方書として順当な姿である。また方名に桂枝がある4方のうち3方は桂心を配剤し、宋改本『千金方』のような方名と薬名の一致が図られていない。他方、『外台方』のほぼ全主治文は「療…方」の形式で、しばしば方後に「右…味擣」と記す。これを『医心方』でみると本来は「治…方」「凡…物冶」であることが多い。いずれも唐の官僚である王燾が高宗の諱の「治」および字形の似た「冶」を避け、治を療、冶を擣に改め、『外台方』を編纂した証拠である。かくも顕著な避諱に宋改を担当した儒者が気付かないはずはない。宋の刊行物で唐の避諱を踏襲する必要もない。つまり宋改時に本来の文字に改変可能なのに、王燾の旧のまま放置している。同じ宋改を経てはいるが、『外台方』はこの点からも『千金方』ほど改変されていない可能性が考えられる。
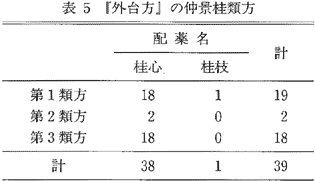 当結果をふまえ『外台方』所引の『仲景傷寒論』全体を検討してみた。『外台方』全40巻には、『仲景傷寒論』の条文・処方と判断できる引用文が以下の3類ある(表5)。第1類は王燾が文頭に「仲景傷寒論」と記し、次条以下の文頭に「又」と記す直接引用文である。これに該当する桂類配剤方は19方あった。うち桂枝を配剤するのは前述した『外台方』巻1の桂枝湯のみ。他の18方はみな桂心を配剤し、巻4の桂枝湯加黄耆や巻7の抵党烏頭桂枝湯・柴胡桂枝湯のように方名中に「桂枝」を持つ例もあった71)。あるいは巻4の黄耆芍薬桂心酒湯や桂心生薑枳実湯のように方名中に「桂心」があり72)、配薬名と合致する例もある。
当結果をふまえ『外台方』所引の『仲景傷寒論』全体を検討してみた。『外台方』全40巻には、『仲景傷寒論』の条文・処方と判断できる引用文が以下の3類ある(表5)。第1類は王燾が文頭に「仲景傷寒論」と記し、次条以下の文頭に「又」と記す直接引用文である。これに該当する桂類配剤方は19方あった。うち桂枝を配剤するのは前述した『外台方』巻1の桂枝湯のみ。他の18方はみな桂心を配剤し、巻4の桂枝湯加黄耆や巻7の抵党烏頭桂枝湯・柴胡桂枝湯のように方名中に「桂枝」を持つ例もあった71)。あるいは巻4の黄耆芍薬桂心酒湯や桂心生薑枳実湯のように方名中に「桂心」があり72)、配薬名と合致する例もある。
第2類は他の方書からの引用文末付近に、王燾が「傷寒論…同」「張仲景論…同」などと注記する文章である。これに該当する桂類配剤方は『外台方』巻1の桃人承気湯と巻3の五苓散があり73)、いずれも桂心を配剤していた。
第3類は文末に細字双行で「此本仲景傷寒論方」などと宋改の注がある文章である。これに該当する桂類配剤方は『外台方』巻1から巻23までに18方あり、すべて桂心を配剤していた。なかには前述した『范汪方』の桂枝二麻黄一湯や70)、巻23所引『集験方』の桂枝加附子湯のように74)、方名に桂枝を持つ例もある。
第1類と第2類は王燾の引用と注記によるので、唐政府本の佚文に相違ない。この21方に桂枝は1方のみ。他の20方はみな桂心を配剤するが、方名に「桂枝」「桂心」を持つ不統一な例もある。当傾向は『外台方』傷寒門の予備調査でも同様だった。第3類も同様だった。つまり方名と配薬名に意図的統一の形跡がないので、第1に少なくとも桂類薬名については王燾の段階でも宋改の段階でも大きな変化はなかったはずである。また薬名の大多数は桂心であり、『医心方』の分析でも六朝~隋唐代では桂心の薬名が一般的だったので、第2にそれが『外台方』に反映し、かつ宋改でも変化しなかったと考えられる。この第1・第2の特徴は『仲景傷寒論』の逸文にも共通して認められたので、第3に唐政府本『傷寒論』の桂類薬名は宋改本『外台方』でもおよそ変化していないと推定できる。
したがって唐政府本は現在の『傷寒』『金匱』とほぼ対応するにもかかわらず、桂類を配剤する21方中の20方は桂心だったと判断できる。第3類も含めると39方中38方が桂心なのである。ならば現在の『傷寒』『玉函』『金匱』の桂枝は相当に疑わねばならない。
ところで唐政府本には1例だけ桂枝湯に桂枝が配剤されていた。しかし桂心を配剤する桂枝湯も王燾は唐政府本から引用している。すると、これまで漢代から唐代までの医方書を検討した結果からして、その桂枝の実体が桂心だったとしても、桂枝の名称は古来からの配薬名と認め難い。『外台方』の成立時から宋改までの約300年にわたる伝写過程で、桂枝湯の方名につられ半ば偶然に誤写され、それが踏襲されてきたと推定するのが自然ではなかろうか。
5-5 小結④
(1) 医方書での薬名は桂が古く、六朝頃に桂肉が一部で用いられたが、六朝~隋唐代は桂心が一般的である。この傾向は仲景医方でも同じである。
(2)唐以前の医方書に、桂枝の薬名で配剤することまずない。もしあったなら、それは後世の誤写に由来するか、宋改時点で改変された可能性がきわめて高い。唐代の仲景医方でも同じなので、現在の『傷寒』『玉函』『金匱』の桂枝は相当に疑わしい。
(3) 唐以前の医方書や唐代の仲景医方に記された桂類薬はすべて樹皮製品で、小枝全体を薬物に使用した可能性はほぼない。
(4)唐代の仲景医方でも桂枝湯類については、宋改本『千金方』は桂枝を配剤して方名と配薬名の矛盾を解消していた。しかし宋改の担当者も桂枝を樹皮製品と理解していた可能性が高い。
6 宋初『傷寒論』の桂類
北宋初期の淳化3年(992)に勅撰された『太平聖恵方』(以下『聖恵方』)全100巻の巻8-14は傷寒と関連雑病の部分で、各処に仲景医書の佚文らしきものが見える。とりわけ巻8は現『傷寒』の別伝本の性格が強く、『聖恵方』の成立年に因み淳化本『傷寒論』と呼ばれる75)。この淳化本は時代的に唐政府本と宋改本の中間に位置するだけに、桂類薬の考察にも看過できない。ただし『聖恵方』は大部分の文章に出典を記載せず、巻8の『傷寒』対応文も引用文献を記さない。そこで、まず淳化本の由来と性格をあらかじめ検討しておきたい。
6-1 淳化本『傷寒論』の性格
『聖恵方』の勅撰には宋政府の蔵書も利用された。証拠は宋政府の蔵書目録『崇文総目』の佚文に著録の「食医心鑒三巻 昝殷撰」76)にある。本書は亡佚したが、朝鮮の『医方類聚』全266巻(1477年刊)にある引用文を幕末の多紀元堅らが輯佚。この多紀輯佚本を明治初に来日した羅振玉が購入し、帰国後に活字出版した。一方、『医方類聚』は「金匱方」を43回引用し、その字句は元版『金匱』とほぼ完全に合致するので77)、『医方類聚』の引用は改変が少ないと判断できる。そこで『聖恵方』食治門の巻96・97をみると、羅振玉刊『食医心鑑』とほぼ合致する論や治方を引用していた。『聖恵方』の勅撰に宋政府の蔵書を利用した証拠である。ただし『聖恵方』が引用する『食医心鑑』の論は省略・改変が多く、治方主治文と薬名もしばしば改変されていたが、桂心はすべて桂心のままだった78)。したがって『聖恵方』巻8でも利用書の文章そのままと判断するのは危険で、多少なりとも節略・改変があることを予測しなければならない。
6-2 淳化本『傷寒論』の桂類
淳化本は計25篇からなる。全篇は大きく序論・脈論と、発病の日数篇、三陰三陽篇、治法の可不可篇、そして処方篇に分けられる。この処方篇を設けて、薬味・分量・調剤法・服用法を末尾に一括するのはひとつの特徴といえよう。これは少なくとも唐代までは遡れる仲景医書の一形式だからである79)。
そこで処方篇「傷寒三陰三陽応用湯散諸方」を分析してみた。処方篇には薬蒸による発汗法を含め、計50方が載る80)。この数も作為的だが、湯剤のほぼすべては宋政府の『和剤局方』と同様、散剤を煎じる宋代特有の調剤法である。これは明らかに淳化本段階の統一なので、処方の他の記述も素直に信用できないだろう。
当50方のうち桂枝配剤方は第1方の桂枝湯から順に、桂枝附子湯、桂枝芍薬湯、桂枝麻黄湯、桂枝人参湯、麻黄湯、朮附湯、第9方の小柴胡桂枝湯まで計8方あった。すなわち第7方の麻黄附子湯に桂類が配剤されない以外、他の桂枝配剤方は連続して前半にまとめられている。また麻黄湯と朮附湯以外の6方は、みな方名に桂枝の2字がある。しかも当処方篇の目録は桂枝芍薬湯を桂心芍薬湯と記す。「三陰三陽篇」の主治条文でも桂心芍薬湯で81)、桂枝芍薬湯の記載はない。一方、それら以外の処方はすべて桂心が配剤され、第12方の葛根湯から第43方の桃人承気湯まで計11方あった。いずれも方名に桂類のない処方ばかりで、後半にまとめられている(表6)。
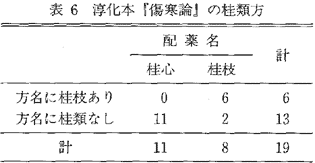 この方名と配薬名の相関は明瞭だろう。桂枝湯など方名に桂枝や桂心がある処方は前半に一括され、みな桂枝が配剤される。それ以降は方名に桂類のない処方で、みな桂心が配剤される。桂枝と桂心を物として区別したのではない。方名と配薬名に矛盾が生じないよう、薬名を改変したのである。また桂枝芍薬湯は主治条文と処方篇目録ともに「桂心」芍薬湯の方名なので、本来は桂心が配剤されていただろう。さらに処方篇の調剤法では「擣」が多用され、これは前述した唐の避諱の遺存なので、巻8に利用された文献は確実に唐人の編集を介している。ならば処方篇の他の桂枝配剤方も本来、唐代方書の一般名称だった桂心が配剤されていた、と推定できる。
この方名と配薬名の相関は明瞭だろう。桂枝湯など方名に桂枝や桂心がある処方は前半に一括され、みな桂枝が配剤される。それ以降は方名に桂類のない処方で、みな桂心が配剤される。桂枝と桂心を物として区別したのではない。方名と配薬名に矛盾が生じないよう、薬名を改変したのである。また桂枝芍薬湯は主治条文と処方篇目録ともに「桂心」芍薬湯の方名なので、本来は桂心が配剤されていただろう。さらに処方篇の調剤法では「擣」が多用され、これは前述した唐の避諱の遺存なので、巻8に利用された文献は確実に唐人の編集を介している。ならば処方篇の他の桂枝配剤方も本来、唐代方書の一般名称だった桂心が配剤されていた、と推定できる。
当改変が淳化本とその利用文献のいずれで生じたのかは分からない。ただし淳化本の処方篇全体は、前述のように宋政府方式にほぼ統一されている。すると方名に桂類を持つ処方の配薬名や方名まで、桂枝に統一したのは淳化本段階かも知れない。ともあれ宋初の段階でも仲景医方に桂心が配剤され、桂枝は桂心の異名と理解されていたのは疑いない。唐本『千金方』にある仲景医方の桂心が、宋改本『千金方』では桂枝に変化した例があった。宋改以前でも、宋初の淳化本には実物と無関係に薬名を桂心から桂枝へ、意図的に統一した例が存在する。伝写過程で方名と薬名に矛盾が多々生じていた医書を、出版を前提に政府が校訂するなら、この統一は当然の処置かも知れない。同じ宋代でのち初めて出版物となった現在の『傷寒』『玉函』『金匱』が、全体的に桂枝で統一されている不可思議さは、淳化本にその前兆を窺うことができた。
6-3 小結⑤
(1) 淳化本『傷寒論』は半数以上の処方に桂心を配剤するので、宋初でも仲景医方に樹皮が用いられていた。
(2) 淳化本の桂枝配剤方には本来、桂心が配剤されていたと推定された。桂心が桂枝に改変されたのは、方名と配薬名の矛盾解消のためと理解された。
(3) 淳化本の桂枝は『新修』と同じく桂心の異名なので、宋初でも小枝全体の桂枝はほとんど存在しなかったと思われる。
(4) 伝本間で異同の多い医書を政府が出版を前提に校訂するなら、淳化本にみられた桂心から桂枝への改変などは当然の処置だった可能性がある。
7 林億らの統一
7-1 『金匱』の付方と性格
これまで仲景医書の宋改直前まで、千年以上にわたる桂類薬名・薬物の変遷を検討してきた。その結果、『傷寒』『玉函』『金匱』の桂枝は、宋改の段階で全体的に統一された可能性が考察の過程で最後まで残った。
この宋改の様子は宋改本とその底本を比較するなら、比較的容易に推知できる。しかし宋改を受けた書の底本が伝存する例はない。『千金方』だけは欠巻本ながら宋改を経ない書も伝わるが、それが宋改の底本と同系かは何ともいえない。ところが唯一の例外が『金匱』にある。なぜなら『金匱』の宋改底本は節略が多かったので、宋改時に少なからぬ処方を付方として扶翼した82)。この付方の大部分については、出典書ないし佚文を載せる書が伝存するからである。ならば出典と付方を比較検討することで、宋改の様子も明らかになるだろう。
『金匱』には現存最善本の元版を用い、これに付方と明記、ないし出典を方名上に略記して付方と判断される処方は計27方ある。うち構成薬味まで記すのは22方、その8方には桂枝が配剤され、他の桂類薬名は一切ない。そこで当8方について出典文と対照しながら検討した。
7-2 古今録験続命湯
『金匱』中風歴節病篇の付方に古今録験続命湯がある83)。『古今録験方』は唐初・甄権の作で散佚したが、宋版『外台方』巻14は同じ続命湯を『古今録験方』から引き、桂心を配剤する84)。『外台方』主治文の2行目なかばに「姚云、与大続命湯同」と記すのは大字文なので、『外台方』を編纂した王燾が姚僧垣『集験方』(6世紀後半)からつけた注と分かる。一方、『金匱』は王燾注とほぼ同文を主治文末尾に細字双行で記す。したがって『金匱』の続命湯条は『古今録験方』からの直接引用ではない。『外台方』からの間接引用である。他方、『外台方』文の末行には「汪云、是仲景方」とある。当文も大字なので王燾の注で、彼が『范汪方』(350頃)を見て記した文と分かる。この王燾注から林億らは続命湯条を仲景の佚文と判断し、『金匱』の付方としたのである。しかし桂心は桂枝に改めた。
7-3 崔氏八味丸
『金匱』中風歴節病篇の付方には崔氏八味丸もある85)。「崔氏」は7世紀後半の崔知悌が著した『崔氏(纂要)方』10巻だろう。本書も伝わらないが、『外台方』巻18に「崔氏…張仲景八味丸方」と記し、『金匱』とほぼ対応する文が引用される86)。つまり『崔氏方』が仲景の八味丸と記すので、『金匱』の付方とされた。ただし『崔氏方』の直接引用か、『外台方』からの間接引用かは定かでない。しかし『外台方』に徴して桂心が本来の配剤薬名と推定できるが、『金匱』は桂枝とする。
7-4 千金翼炙甘草湯
『金匱』血痺虚労病篇の付方に千金翼炙甘草湯があり、方名下に細字双行で「一云、復脈湯」と林億らが注する87)。『千金翼』も林億らが『金匱』と同年頃に校刊したので1)、この炙甘草湯は『千金翼』の直接引用とみていい。じじつ林億らが復脈湯の別名を注記するように、元版『千金翼』巻15にほぼ同じ主治文の復脈湯が載る88)。方名の相違はさておき、『千金翼』の復脈湯は桂心を配剤する。
ところで古今録験続命湯と崔氏八味丸では考察を省いたが、薬量・調剤法は千金翼炙甘草湯でも出典の復脈湯と一致しない。その原因は『千金翼』復脈湯文の末行に林億らが注する、「仲景名炙甘草湯、…見傷寒中」から分かる。すなわち『傷寒』をみると巻4に炙甘草湯が載り、その薬量・調剤法ともに『金匱』と一致する89)。『玉函』も一致する90)。とすれば千金翼炙甘草湯が次の操作で『金匱』の付方とされたのは自明だろう。林億らは『千金翼』から復脈湯の主治文のみ付方に引用した。が、唐の避諱で「主虚労不足…」となっていたのを「治虚労不足…」とするなど、文字の一部を改めた。一方、方名・薬量・調剤法は『千金翼』に従わず、『金匱』以前に校刊ずみの『傷寒』『玉函』と統一。それら改変の一部については、校異の注を『金匱』『千金翼』の双方に記した。しかし薬名・薬量・文字の改変については言及しない。あまりにも多岐にわたるからだろう。
ともあれ『金匱』付方の千金翼炙甘草湯と『千金翼』の復脈湯を比較することで、宋改の様子を垣間見ることができた。これは桂心から桂枝への薬名改変が、『傷寒』『玉函』『金匱』という、仲景医書間での記載統一の一環でなされた可能性を強く示唆している。もちろん桂心と桂枝を同一薬物とみなしていることは疑うべくもない。
7-5 千金桂枝去芍薬加皀莢湯
『金匱』肺萎肺廱咳嗽上気篇の付方に千金桂枝去芍薬加皀莢湯がある91)。『千金方』も林億らが『金匱』と同年に校刊したので1)、当方は『千金方』の直接引用に相違ない。そこで宋改本『千金方』をみると巻17にほぼ同じ主治文の当方が載り、桂枝を配剤する92)。さらに『真本千金方』や唐本『千金方』も調査すべきだが、該当部分は伝存や引用がない。未宋改本『千金方』も該当部分を欠巻する。一方、宋版『外台方』巻10では王燾が「千金…出第十七巻中」と注し、ほぼ同じ主治文の桂枝去芍薬加皀莢湯を引用する。そして桂心が配剤される93)。すでに唐政府本『傷寒論』の考察で検討したように、宋版『外台方』の桂類薬名は王燾の段階でも宋改の段階でも大きな変化がないと考えられた。とするなら宋改以前の『千金方』は当方に桂心を配剤していたに相違なく、それを宋改本『千金方』も『金匱』も桂枝に改めたのである。
7-6 外台黄芩湯
『金匱』嘔吐噦下利篇の付方には外台黄芩湯がある94)。当方は『傷寒』の黄芩湯と同名異方で、主治文も違う。一方、『玉函』の黄芩人参湯は当方と異名同方だが、主治文を欠く。『金匱』付方の当方はもちろん『外台方』からの直接引用で、宋版『外台方』は巻8に載せ、桂心を配剤する95)。その王燾注に「仲景傷寒論…出第十六巻中」と記すので、当方は唐政府本『傷寒論』巻16が本来の出典だったと分かる。なお唐政府本『傷寒論』全18巻は巻10までが傷寒部分で、巻11以降が雑病部分だったと考えられる96)。それで当方が『金匱』の付方とされた。なお『医心方』も巻14第28に同一薬味で同内容の黄芩湯を4世紀の『范汪方』から引用し、桂心を配剤する97)。つまり当方は唐代でも、あるいは六朝代でも桂心だったが、『金匱』で桂枝に改められたのである。
7-7 千金内補当帰建中湯
『金匱』婦人産後病篇の付方に千金内補当帰建中湯がある98)。宋改本『千金方』では巻3にほぼ同条文の当方があり、桂心を配剤する99)。未宋改本『千金方』でも巻3にあり、ほぼ同条文だが方名を「内補当帰湯達中」とし、一字の桂を記していた100)。すると当方には医方書の薬名として最も古い桂が『千金方』でも記されていたが、のち宋改本『千金方』の底本段階、あるいは宋改の段階で桂心に変化し、さらに『金匱』で桂枝に改変されたことが分かる。
7-8 外台柴胡桂枝湯
『金匱』腹満寒疝宿食病篇の付方に外台柴胡桂枝湯がある101)。宋版『外台方』では巻7に主治文をやや異にする同方を載せ、桂心を配剤する102)。しかし両主治文に差異があるので、にわかに双方が引用と出典の関係とは認め難い。
ところで『外台方』条文の文頭・文末にある王燾注によると、同方は唐政府本『傷寒論』の巻15つまり雑病部分からの引用と分かる。『外台方』巻7がこの唐政府本『傷寒論』巻15から柴胡桂枝湯とともに引用するのは、二物大烏頭煎・抵党烏頭桂枝湯・当帰生薑羊肉湯の3方である103)。いずれも『金匱』腹満寒疝宿食病篇に該当の処方・条文があり、それぞれ(大)烏頭煎・(抵党)烏頭桂枝湯・当帰生姜羊肉湯に対応する104)。さらに『外台方』に載る柴胡桂枝湯はこの1方のみで、他に異名同方もない105)。以上からすると『金匱』付方の外台柴胡桂枝湯は、宋版『外台方』巻7の柴胡桂枝湯とみてまず間違いない。したがって原方は桂心で、それを『金匱』が改変したことが分かる。
7-9 「附外台秘要方」柴胡桂姜湯
『金匱』瘧病篇は「附外台秘要方」と明記して牡蠣湯・柴胡去半夏加括蔞湯・柴胡桂姜湯の3方を載せ、うち柴胡桂姜湯が桂枝配剤方である105)。前2方は宋版『外台方』巻5の瘧病門が、唐政府本『傷寒論』巻15から引用する牡蠣湯・小柴胡去半夏加栝楼湯とそれぞれ対応する107)。しかし柴胡桂姜湯の対応方は『外台方』瘧病門になぜかない。同一薬味なら宋版『外台方』巻1に唐政府本『傷寒論』巻3から引用の小柴胡湯、および宋版『外台方』巻2に唐政府本『傷寒論』巻4から引用の小柴胡桂薑湯があり、いずれも桂心を配剤する108)。しかし主治文はともに『金匱』付方の柴胡桂姜湯と違う。それで山田業広は、「今本外台无攷、脈経千金亦不載此条、豈林億等所見有之、而今之外台係脱落也」という109)。あるいはそうかも知れない。ただし『金匱』の柴胡桂姜湯が桂枝なのに『外台方』の別条同方が桂心なのは、やはり林億らの改変を間接的に示唆している。
以上、『金匱』の付方で桂枝を配剤する8方につき、引用出典に遡って比較検討を加えた。この結果、もともと桂枝の薬名で配剤されていたと判断できる処方は1方もなく、本来は7方が桂心、1方が桂ないし桂心であった。当結果は、この8方が宋改で『金匱』に転載された際、桂枝に改変されたことを明瞭に証明している。もちろん付方だけ桂枝に改変する理由はない。すでに淳化本の段階から桂心と同義で桂枝が混用されていた。つまり『傷寒』『玉函』『金匱』の記載を統一するため、桂心の意味で方名と矛盾しない「桂枝去皮」に、付方も含め宋改で一律に改変されたのである。したがってこの桂枝は樹皮である。
7-10 小結⑥
(1)林億らは桂類配剤方を『金匱』付方に転載する際、方名に桂枝が有る無しにかかわらず、配薬名を桂枝に統一した。この事実は、付方と同じ改変が『傷寒』『玉函』『金匱』の全書にわたり宋改で実行されたことも証明する。3書にわずかに記される桂・桂湯や桂心は、その痕跡である。
(2)『傷寒』『玉函』『金匱』の桂枝は、『新修』にいう肉桂の別名である。また「桂枝去皮」の指示はコルク層除去を意味しており、唐以前から使用されていた桂心のことである。
(3) 仲景医書・医方の桂枝は樹皮で、小枝全体ではない。
8 結論
桂類薬名と桂類薬物の関連と変遷を、仲景医書の宋改まで約1300年にわたる記録などから検討した(表7)。この考察結果は以下のように結論できる。なお宋改から現代までの約950年間で、仲景医方の桂枝に中国と日本で解釈・使用の相違が生じた原因と歴史も考察すべきだが、紙幅の関係で別稿に譲りたい。
(1)桂類植物の樹皮製品に対し後漢時代まで桂の薬名が一般的に用いられ、その樹皮のコルク層はふつう除去されていた。この製品は前2世紀に埋葬された墓から出土しており、それらに対して桂心の薬名が唐代まで一般に用いられていた。唐代の桂心も日本に現存する。
(2)10世紀までの医学文献にみえる桂・梫・木桂・牡桂・桂肉・肉桂・桂心・桂枝の語彙は、みな樹皮製品に対して用いられていた。659年編纂の唐政府薬局方『新修』は、それらの基原植物を主にC. cassiaないしC. obtusifoliumと規定していた。当製品は『局方』の桂皮および『薬典』の肉桂にほぼ相当する。
(3) 菌桂の語彙は小枝の樹皮が重なり巻いた竹筒状の製品に紀元前3世紀から使用され、用途は健康食品ないし香辛料であった。この基原植物を『新修』はC. burmanniと規定し、当製品は現在のジャワ桂皮によるシナモンスティックにほぼ相当する。
(4)漢末に仲景が整理した医方書に桂枝(支)湯の方名があった可能性は否定できない。しかし6世紀までに桂枝という薬名の用例はなく、唐代前後の仲景医方は多くに桂心や桂が配剤されていた。この理由で、桂枝湯などに桂枝ではなく桂心が配剤され、方名と配薬名の語彙に矛盾が生じていた。それで桂心…湯という名称の処方もあった。一方、桂類植物の小枝全体が、薬物として11世紀以前に使用された痕跡もなかった。したがって仲景の時代で桂枝の薬名が使用された可能性、および小枝全体が薬物として配剤された可能性はきわめて低いことが示唆された。
(5)北宋初期の『太平聖恵方』出版時に、方名に桂枝がある仲景医方については桂心と同義で桂枝の名称を用い配剤する例が出現した。しかし桂心の名称は当時もまだ主流だった。
(6)仲景医書が北宋政府により校訂・初刊行されたとき、仲景の3書で記載を統一する必要から、桂類薬の名称は桂心の意味として「桂枝去皮」に一部の疎漏を除き統一された。同時に方名も桂心…湯などは桂枝…湯などに改められ、配薬名と方名の矛盾が解消された。したがって仲景医書のあらゆる版本に記載される桂枝は、『薬典』が規定する小枝全体のCinnamomi Ramulusではなく、『局方』が規定する樹皮のCinnamomi Cortexに該当する。
[本研究費の一部は金原一郎記念医学医療振興財団の第9回研究交流助成金によった]
文献および注
1)岡西為人:中国医書本草考、井上書店、東京、p.192-199(1974)。
2)日本公定書協会:第十二改正日本薬局方解説書・第二部D、廣川書店、東京、p.271(1992)。
3)中華人民共和国衛生部薬典委員会:中華人民共和国薬典・1990年版第一部、人民衛生出版社・化学工業出版社、北京、p.110(1990)。
4)文献3)、244頁。
5)張仲景:(明・趙開美本)宋板傷寒論、燎原書店、東京、p.416(1988)。
6)張仲景:(清・陳世傑本)金匱玉函経、燎原書店、東京、p.365(1988)。
7)張仲景:(元・鄧珍本)新編金匱方論、燎原書店、東京、p.28・89・153(1988)。この桂湯条の対応条文は『外台方』巻28(文献69、p.547)にみえ、桂心湯と記す。
8)文献7)、41頁。
9)文献5)、p.156・331。文献6)、p.338。文献7)、p.64。
10)文献5)、p.97・438。文献6)、 p.341。
11)星川清孝:楚辞、新釈漢文体系第34巻、明治書院、東京、p.29(1970)。
12)市原亮吉ら:礼記・上、全釈漢文体系第12巻、集英社、東京、p.175(1971)。
13)郝懿行:爾雅義疏、上海古籍出版社、上海、p.1074(1983)。
14)段玉裁:説文解字注、成都古籍書店、成都、p.252(1981)。
15)袁柯:山海経校注、上海古籍出版、上海、p.459(1983)。
16)陳夢雷:古今図書集成・草木典、鼎文書局、台北、p.2249(1985)。
17)諸橋轍次:大漢和辞典、大修館書店、東京、p.6029(1986)。
18)張玉書ら:佩文韵府、上海古籍書店、上海、p.23・36・587・735・762・779・1191・1379・1814・2041・2044・2558・2560・3397・4088・4601(1983)。
19)湖南農学院・中国科学院植物研究所:長沙馬王堆一号漢墓出土動植物標本的研究、文物出版社、北京、p.29-32(1978)。
20)朝比奈泰彦ら:正倉院薬物、植物文献刊行会、東京、p.228-249(1955)。
21)江村治樹ら:馬王堆出土医書字形分類索引、文部省昭和61年度科学研究費補助金総合研究A・中国古代養生思想の総合研究成果報告書2、p.35(1987)。
22)赤堀昭:流沙墜簡と居延漢簡の医方簡、山田慶兒編・新発現中国科学史資料の研究-訳注篇、京都大学人文科学研究所、京都、p.405-415(1985)。
23)甘粛省博物館等:武威漢代医簡、文物出版社、北京、木簡番号3・8・10・11・31・44・46・52・79・80甲・ 82甲・82乙(1975)。
24)著者不詳:(明・無名氏倣宋本)霊枢、素問・霊枢、日本経絡学会、東京、p.226・242(1992)。
25)楊上善:(仁和寺本)黄帝内経太素・中、東洋医学善本叢書2、東洋医学研究会、大阪、p.16・454(1980)。
26)皇甫謐:針灸甲乙経、人民衛生出版社、北京、p.32・129(1982)。
27)艾晟ら:(宋版)経史証類備急本草、東洋医学善本叢書32、オリエント出版社、大阪、p.283-287(1992)。
28)文献27)、 p.287-288。
29)尚志鈞ら輯校:呉普本草、人民衛生出版社、北京、p.60(1987)。
30)岡西為人:本草概説、創元社、大阪、p.64(1977)。
31)呉洛:中国度量衡史、商務印書館、台北、p.225(1981)。
32)江蘇新医学院:中薬大辞典、上海科学技術出版社、上海、p.179・890(1977)。
33)成都中医学院主編:中薬鑑定学、上海人民出版社、上海、p.224(1977)。
34)尚志鈞輯校:名医別録、人民衛生出版社、北京、p.35-36(1986)。
35)文献27)、p.288-289。
36)蘇敬ら:(影写仁和寺本)新修本草、上海古籍出版社、上海、p.65(1985)。
37)文献17)、p.10052。
38)文献32)、p.981。
39)東京都内で1995年4月に購入した市場品のシナモンスティックは、スパイスハウス社(東京)がC. zeylanicum、SPICEISLAND(USA) がC. burmanni、McCORMIC (USA) がC. cassia、朝岡香辛料社(東京)がC. cassiaないしC. obtusifoliumによる製品で、いずれも直径1-2cmの枝皮と思われ、コルク層は完全に除去されていた。
40)堀田満ら:世界有用植物事典、平凡社、東京、p.270(1989)。
41)丹波康頼:(安政版)医心方、人民衛生出版社、北京、p.227・465 (1993)。
42)岡西為人:宋以前医籍攷、古亭書屋、台北、p.33-37(1968)。
43)小曽戸洋:『脈経』総説、東洋医学善本叢書8、東洋医学研究会、大阪、p.348(1980)。
44)真柳誠:中国医学史Ⅰ-主要医薬文献史2「張仲景医書」およびその研究書、日本漢方協会、東京、p.34-35 (1985)。
45)楊用道:葛仙翁肘後備急方、人民衛生出版社、北京、p.60・85(1982)。
46)文献45)、p.37。これに続け「診候須明、悉別所在撰大方中」と記す「大方」とは、葛洪の『玉函方』百巻だろう。
47)小曽戸洋:『小品方』書誌研究、小品方・黄帝内経明堂古鈔本残巻、北里研究所附属東洋医学総合研究所、東京、p.65-80(1992)。
48)文献47)、p.12-13・38。
49)馬王堆漢墓帛書整理小組:馬王堆漢墓帛書肆・釈文注釈篇、文物出版社、北京、p.28(1985)。
50)小林健二・宮川浩也:素問・霊枢総索引、日本内経医学会、東京、p.425-426(1993)。
51)頼惟勤:説文入門、大修館書店、東京、p.223-235(1983)。
52)東洋文庫所蔵マイクロフィルムからの焼き付けによる。
53)馬継興ら:敦煌古医籍考釈、江西科学技術出版社、南昌、古医籍考釈篇p.2(1988)。
54)真柳誠:唐代の薬価記録-トルファン出土物価(市估)文書、漢方の臨床、42、658-660(1995)。
55)小田義久:大谷文書集成 貳、法蔵館、京都、p.8・24(1990)。
56)文献41)、p.150・159・204。
57)たとえば文献41)でp.90の『葛氏方』に桂、p.87の『小品方』と p.109『如意方』に桂肉の配剤がみえる。
58)文献41)、p.4。
59)孫思邈:(宋版)備急千金要方・中、東洋医学善本叢書10、オリエント出版社、大阪、p.652(1989)。
60)文献59)、p.555。
61)文献59)、p.289-290。
62)孫思邈:(宋版)新雕孫真人千金方、東洋医学善本叢書12、オリエント出版社、大阪、p.402(1989)。
63)野上真里ら:宋代以前の医薬書に記された朮類の名称と基源について、生薬学雑誌、39、35-45(1985)。
64)渡邊幸三:伝統的本草書の七情表に対する文献学的研究、日本東洋医学会雑誌、 5、20-27(1954)。
65)王溥:唐会要・巻82、世界書局、台北、p.1525(1988)。
66)丸山裕美子:日唐医疾令の復元と比較、東洋文化、68、189-218(1988)。
67)小曽戸洋:宋版『外台秘要方』所引書名人名等索引、文献43)、 p.231。
68)小曽戸洋:『医心方』引用文献名索引、日本医史学雑誌、32、98(1986)。
69)王燾:(宋版)外台秘要方、東洋医学善本叢書4・5、東洋医学研究会、大阪、p.30・31・42・43(1980)。
70)文献69)、p.49・50・41・44。
71)文献69)、p.89・145・146。
72)文献69)、p.89・135。
73)文献69)、p.40・73。
74)文献69)、p.457。
75)野淵紘:太平聖恵方所出の傷寒論の異本、漢方の臨床、25、663-672(1978)。
76)銭東垣:崇文総目輯釈、中国歴代書目叢刊第1輯上、現代出版社、北京、p.126(1987)。
77)真柳誠:『金匱要略』の文献学的研究(第1報)、日本医史学雑誌、34、414-430(1988)。
78)たとえば羅振玉刊の『食医心鑑』(影印本、歴代本草精華叢書1、上海中医薬大学出版社、上海、1994)をみると7bの畢撥粥方、12bの治五噎飲食不下胸中結塞痩弱無力方、13aの桂心粥方に桂心が配剤され、『聖恵方』巻96に引用された対応文も桂心を記す。
79)文献44)、p.38。
80)王懐隠:(宋版)太平聖恵方・1、東洋医学善本叢書16、オリエント出版社、大阪、p.324-334(1991)。
81)文献76)、p.315。
82)文献44)、p.21。
83)文献7)、p.47-48。
84)文献69)、p.272。
85)文献7)、P.49。
86)文献69)、p.349-350。
87)文献7)、p.55。
88)孫思邈:(元版)千金翼方、東洋医学善本叢書13、オリエント出版社、大阪、p.756(1989)。
89)文献5)、p.200。
90)文献6)、p.367。
91)文献7)、p.62。
92)文献59)、p.586。
93)文献69)、p.190。
94)文献7)、p.124。
95)文献69)、p.127。
96)文献44)、p.19。
97)文献41)、p.319。
98)文献7)、p.140。
99)孫思邈:(宋版)備急千金要方・上、東洋医学善本叢書9、オリエント出版社、大阪 、p.215-216(1989)。
100)文献62)、p.131-132。
101)文献7)、p.75-76。
102)文献69)、p.146。
103)文献69)、p.145-146。
104)文献7)、p.73-74。
105)孫中堂:方剤索引、高文鋳校注・外台秘要方、華夏出版社、北京、p.968-1028(1993)。
106)文献7)、p.42-43。
107)文献69)、p.105・95。
108)文献69)、p.30・52。
109)山田業広:金匱要略札記、山田業広撰集1、名著出版、東京、p.288 (1984)。
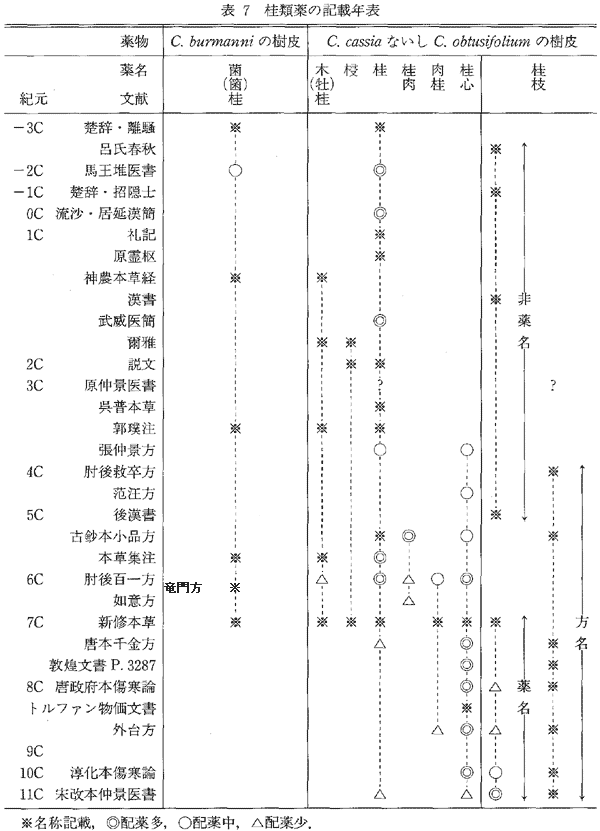
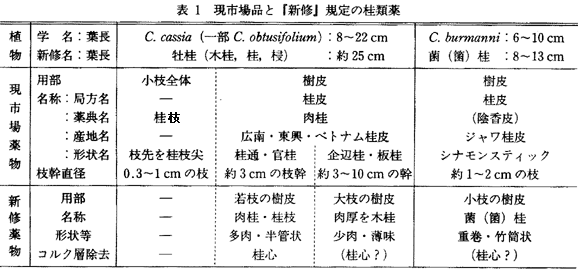 3-3 小結②(表1)
3-3 小結②(表1)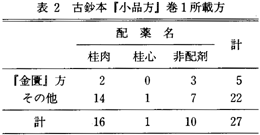 当本巻1の後半には計27処方が記載され、うち16方に桂肉、1方に桂心が配剤されている。また27方のうち『傷寒』方と関連するものはないが、『金匱』方と方名が類似し、かつ同一薬味の処方が5方あり、うち厚朴湯と桂支湯加烏頭湯の2方に桂肉が配剤されている(表2)。各々は『金匱』の厚朴七物湯と烏頭桂枝湯に該当する。桂肉の名称は唐代までの本草書になかったが、『肘後百一方』に1回記載されていたので、六朝の医方家の一部で使用された桂心ないし肉桂の別称かと思われる。
当本巻1の後半には計27処方が記載され、うち16方に桂肉、1方に桂心が配剤されている。また27方のうち『傷寒』方と関連するものはないが、『金匱』方と方名が類似し、かつ同一薬味の処方が5方あり、うち厚朴湯と桂支湯加烏頭湯の2方に桂肉が配剤されている(表2)。各々は『金匱』の厚朴七物湯と烏頭桂枝湯に該当する。桂肉の名称は唐代までの本草書になかったが、『肘後百一方』に1回記載されていたので、六朝の医方家の一部で使用された桂心ないし肉桂の別称かと思われる。 宋改本傷寒門の処方で構成薬が記され、それが『傷寒』『金匱』と対応するのは50方を越す。他方、桂類を配剤するのは傷寒門に29方あり、うち25方に桂心、4方に桂枝が配剤されていた。両者の共通方で桂心を配剤するのは五苓散・麻黄湯・大青竜湯・小青竜湯・茯苓(苓桂朮甘)湯・黄耆芍薬桂苦酒湯・鼈甲煎丸・白虎加桂湯、桂枝を配剤するのは桂枝湯・桂枝二麻黄壹湯・桂枝加黄耆湯である(表3)。この方名と配薬名に相関関係があるのは一目瞭然だろう。桂枝配剤方の方名には必ず「桂枝」がある。桂心配剤方は方名に「桂枝」がなく、あったとしても黄耆芍薬桂苦酒湯と白虎加桂湯の「桂」にすぎない。
宋改本傷寒門の処方で構成薬が記され、それが『傷寒』『金匱』と対応するのは50方を越す。他方、桂類を配剤するのは傷寒門に29方あり、うち25方に桂心、4方に桂枝が配剤されていた。両者の共通方で桂心を配剤するのは五苓散・麻黄湯・大青竜湯・小青竜湯・茯苓(苓桂朮甘)湯・黄耆芍薬桂苦酒湯・鼈甲煎丸・白虎加桂湯、桂枝を配剤するのは桂枝湯・桂枝二麻黄壹湯・桂枝加黄耆湯である(表3)。この方名と配薬名に相関関係があるのは一目瞭然だろう。桂枝配剤方の方名には必ず「桂枝」がある。桂心配剤方は方名に「桂枝」がなく、あったとしても黄耆芍薬桂苦酒湯と白虎加桂湯の「桂」にすぎない。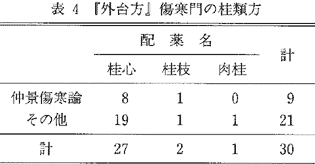 まず『外台方』巻1・2の傷寒門にて予備調査した。その結果(表4)、桂類配剤方は30方あり、うち9方が『仲景傷寒論』、21方が他書からの引用だった。『仲景傷寒論』の9方では、巻1の桂枝湯のみ桂枝を配剤し、他の8方は巻1の桂枝附子湯でも巻2の桂枝湯・麻黄湯・葛根湯でもみな桂心を配剤していた69)。他書から引用の21方でも『小品方』の射干湯に肉桂、『古今録験方』の橘皮湯に桂枝のみで、他の19方は『范汪方』の桂枝二麻黄一湯も『古今録験方』の大青竜湯もみな桂心が配剤されていた70)。
まず『外台方』巻1・2の傷寒門にて予備調査した。その結果(表4)、桂類配剤方は30方あり、うち9方が『仲景傷寒論』、21方が他書からの引用だった。『仲景傷寒論』の9方では、巻1の桂枝湯のみ桂枝を配剤し、他の8方は巻1の桂枝附子湯でも巻2の桂枝湯・麻黄湯・葛根湯でもみな桂心を配剤していた69)。他書から引用の21方でも『小品方』の射干湯に肉桂、『古今録験方』の橘皮湯に桂枝のみで、他の19方は『范汪方』の桂枝二麻黄一湯も『古今録験方』の大青竜湯もみな桂心が配剤されていた70)。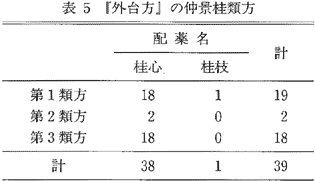 当結果をふまえ『外台方』所引の『仲景傷寒論』全体を検討してみた。『外台方』全40巻には、『仲景傷寒論』の条文・処方と判断できる引用文が以下の3類ある(表5)。第1類は王燾が文頭に「仲景傷寒論」と記し、次条以下の文頭に「又」と記す直接引用文である。これに該当する桂類配剤方は19方あった。うち桂枝を配剤するのは前述した『外台方』巻1の桂枝湯のみ。他の18方はみな桂心を配剤し、巻4の桂枝湯加黄耆や巻7の抵党烏頭桂枝湯・柴胡桂枝湯のように方名中に「桂枝」を持つ例もあった71)。あるいは巻4の黄耆芍薬桂心酒湯や桂心生薑枳実湯のように方名中に「桂心」があり72)、配薬名と合致する例もある。
当結果をふまえ『外台方』所引の『仲景傷寒論』全体を検討してみた。『外台方』全40巻には、『仲景傷寒論』の条文・処方と判断できる引用文が以下の3類ある(表5)。第1類は王燾が文頭に「仲景傷寒論」と記し、次条以下の文頭に「又」と記す直接引用文である。これに該当する桂類配剤方は19方あった。うち桂枝を配剤するのは前述した『外台方』巻1の桂枝湯のみ。他の18方はみな桂心を配剤し、巻4の桂枝湯加黄耆や巻7の抵党烏頭桂枝湯・柴胡桂枝湯のように方名中に「桂枝」を持つ例もあった71)。あるいは巻4の黄耆芍薬桂心酒湯や桂心生薑枳実湯のように方名中に「桂心」があり72)、配薬名と合致する例もある。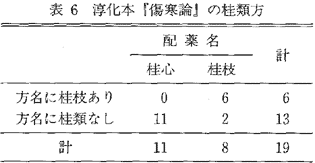 この方名と配薬名の相関は明瞭だろう。桂枝湯など方名に桂枝や桂心がある処方は前半に一括され、みな桂枝が配剤される。それ以降は方名に桂類のない処方で、みな桂心が配剤される。桂枝と桂心を物として区別したのではない。方名と配薬名に矛盾が生じないよう、薬名を改変したのである。また桂枝芍薬湯は主治条文と処方篇目録ともに「桂心」芍薬湯の方名なので、本来は桂心が配剤されていただろう。さらに処方篇の調剤法では「擣」が多用され、これは前述した唐の避諱の遺存なので、巻8に利用された文献は確実に唐人の編集を介している。ならば処方篇の他の桂枝配剤方も本来、唐代方書の一般名称だった桂心が配剤されていた、と推定できる。
この方名と配薬名の相関は明瞭だろう。桂枝湯など方名に桂枝や桂心がある処方は前半に一括され、みな桂枝が配剤される。それ以降は方名に桂類のない処方で、みな桂心が配剤される。桂枝と桂心を物として区別したのではない。方名と配薬名に矛盾が生じないよう、薬名を改変したのである。また桂枝芍薬湯は主治条文と処方篇目録ともに「桂心」芍薬湯の方名なので、本来は桂心が配剤されていただろう。さらに処方篇の調剤法では「擣」が多用され、これは前述した唐の避諱の遺存なので、巻8に利用された文献は確実に唐人の編集を介している。ならば処方篇の他の桂枝配剤方も本来、唐代方書の一般名称だった桂心が配剤されていた、と推定できる。