���߂��^�����u�w�����ϐ����E�����x���v�w�a�����Ј㏑�W���x��S�S�����A�G���^�v���C�Y�A1988�N6�����ꕔ����
�w�����ϐ����x�w�����ϐ������x���
�^�� ��
��A���҂Ɛ���
�@�����̒��҂ł��錵�p�a�̓`�͎j�����Ɍ����Ȃ��B�������w�����ϐ����x�i�ȉ��w�ϐ����x�Ɨ����j�Ɓw�����ϐ������x�i�ȉ��w�����x�Ɨ����j�̌��p�a�����i�O�҂��`�A��҂��a�Ƃ���j�A����сw�ϐ����x�̑v���{�Ǝ������ʖ{�i��q�j�ɑO�t�̍]�����i�b�Ƃ���j���A�ނ̊T�����M�����Ƃ͂ł���B
�@�b�ɂ��Ό��p�a�̎��͎q��B�`�a�b�ɋL���N���ƒn�����A�\�O���I���̓�v�E��N�i���̍]���Ȑ��q���j�̜I�R�ɂĊ�����Ƃƒm���B����A�ނ̐��v�N��͎��̂悤�ɐ��肳���B�`�b�̋L�N���w�ϐ����x�̐����͕�S���N�i���O�j�ł���B�܂��`�ł͏\���ň�Ƃ��J�n��A�O�\�]�N���o�āw�ϐ����x�����Ƃ����B����ɂa�̋L�N���w�����x�̐����͙��~�O�N�i���Z���j�ł���A�����ł͈�Ƃ��n�߂Č\�]�N�Əq�ׂ�B�ȏォ��t�Z����ƁA���p�a�͂��悻�c���N�ԁi����܁`���Z�Z�j�̐��܂�B�\�]�̈��O�N�Ɂw�ϐ����x���������A���\���̈���N�Ɂw�����x���A�v�N�͂���ȍ~�ƂȂ�B
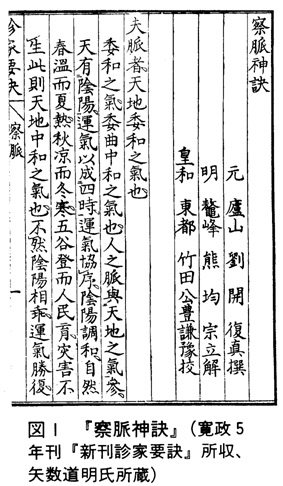 �@���Ă`�ɂ͔���菑�ɐe���݁A�\��ŗ��J�i���𗧔V�A���͕��^�j�ɓ��債�A�ܔN�Ԉ�w���C�߂��Əq�ׂĂ���B���J�̓`�́w��N�{�u�x[1]�Ɍ����A�w�������v�x�����ƋL���A�����͖k���}���قɉÖ��O�\�O�N�i��܌l�j���D�]���{����������B�܂��w�i���^�j���O�_�����x�ꊪ�i�����Ȋw�@�}���ق����O���ł������j�Ɓw����������v�x�ꊪ�i�{�������˕����w���_����X�x�ƍ����̒��N�ł������j�̒����́A������������ܔN�i���l��j�Ɏ������L����Ă���B�㏑�ɂ́u�O��㗫�J���^��B�O������l���q��p�a�}���v�ƋL����Ă���̂�[2]�A���p�a�͎t�̏��ɐ}����������قǑ��̖�l�������炵���B�܂����J�ɂ́w�������i�x�܊��̒����������炵�����i�����אl�w�v�ȑO��Ѝl�x�l���l�Łj�A�����͕s�ځB���̑��A�킪���ł͗��J�̏��ɖ��̌F�@�������������w�@���_���x�ꊪ�i�w����听�x����̘^�o�A�}�P�j�����s����Ă���B
�@���Ă`�ɂ͔���菑�ɐe���݁A�\��ŗ��J�i���𗧔V�A���͕��^�j�ɓ��債�A�ܔN�Ԉ�w���C�߂��Əq�ׂĂ���B���J�̓`�́w��N�{�u�x[1]�Ɍ����A�w�������v�x�����ƋL���A�����͖k���}���قɉÖ��O�\�O�N�i��܌l�j���D�]���{����������B�܂��w�i���^�j���O�_�����x�ꊪ�i�����Ȋw�@�}���ق����O���ł������j�Ɓw����������v�x�ꊪ�i�{�������˕����w���_����X�x�ƍ����̒��N�ł������j�̒����́A������������ܔN�i���l��j�Ɏ������L����Ă���B�㏑�ɂ́u�O��㗫�J���^��B�O������l���q��p�a�}���v�ƋL����Ă���̂�[2]�A���p�a�͎t�̏��ɐ}����������قǑ��̖�l�������炵���B�܂����J�ɂ́w�������i�x�܊��̒����������炵�����i�����אl�w�v�ȑO��Ѝl�x�l���l�Łj�A�����͕s�ځB���̑��A�킪���ł͗��J�̏��ɖ��̌F�@�������������w�@���_���x�ꊪ�i�w����听�x����̘^�o�A�}�P�j�����s����Ă���B
�@����ɗ��J�͛��ÕF�i���͎������l�j�Ɏt������p���C�߂��A�ƒ������w�����q�������h�����x���ɋL����Ă���[3]�B���ÕF����N�̐l�ŁA�~���N�ԁi��ꎵ�l�`��ꔪ��j�ɂ����Ċ��A���E�m����w�ʔ��o�x�ւ̒��ߏ��O����A�w�i�����^�l�j�����x�ꊪ�Ȃǂ̒���Œm����B�ȏ�̂悤�ɁA���p�a�͓�v����̓�N�̒n�ň㖼���͂������ÕF�|���J�|���p�a�Ƒ����w���̈�Ƃł������B
��A�\��
�@�w�ϐ����x�̍\���́u�_�����悻���\�A�������悻�l�S�A�����ď\���ƂȂ��A�ϐ����ƍ����v�A�Ɓw�����x�̎����ɋL����Ă���B��q���邪�A���{�ɂ͌��p�a�̎���̓�v���{�Ƃ���Ɋ�Â��Îʖ{��a���{���`�����A������������ǂ���̍\���ł���B
�@�w�����x�̍\���́A���̎����Ɂu�����Ȃ��ɂ܂���\�A�]���Ȃ��ɓ�\�l�v�ƋL����Ă���B��q�̖{���������ʖ{�́A�����Ɗ���`���̔����ɓ�\��]�E���\���������A�����̋L�ڂ���⏭�Ȃ��B����͏����̊���E�\���������Ă��邽�߂ł���B�����œ��ʖ{���{�ɁA���I�����i�ꎵ����`�ꔪ�j�͒��N�́w������ځx��������茇���̓�]�E�\������₵�A���S�ȏ��Ƃ��Ċ��s���Ă���B
�@�Ƃ��낪�����ł͗����Ƃ��ɐ������ɂ͂��łɐ���ɂȂ��A�Ȍ㌻�݂܂ł̊��{�͑S�ė����̈핶���W�߂��\�Z�_���E��S�l�\�]���̔����{�A�܂��͗����̘a���{���E�ĕ҂����s���S�{�ł���B������ɂ��Ă��A���{�̍\���͈�ؕۂ���Ă��Ȃ��B
�O�A���e�ƌ㐢�ւ̉e��
�@�w�l�ɑS�����ځx[4]�́w�ϐ����x��]���Ď��̂悤�Ɍ����B�u�����̋c�_�͕����A�������������~�͂��邱�ƁA���X�ɐ[���m�Z�ɒ�����]�X�v�A�ƁB�܂������́w�Í��ʕϐm�����x���������A�u�\�A�ł������ϐ����̖���ÂԁB�������ɂ����A�����p����Α���������v�Ƃ��L���Ă���B
�@���āA�w�ϐ����x�̘_������сw�����x�̕]���ɂ́A�e���Ɂw�f��x�w��o�x��w�����v���x�w�i�����j�a����_�x�w������x�Ȃǂ��������_��������B�܂����f�a�E��n���̏��������Ȃ��炸���p����Ă���B�Ƃ�킯�w�a�܋Ǖ��x�w�O�����x�̉e���͑����ɑ傫���B�Ⴆ�ΌܐώU�E�؊W�U�E���h�U�E�\�_���Ȃǂ́A����������̓��o�T�Ƃ��鏈���ł���B�w�ϐ����x�ł͂��̑��ɁA���l�ɛ��m��̍������@�A���Z��{�с{�ށ{�R}��v����s�����A����Ɏ����ّ̑O�\���_���A���\�Ɋs�m���̎Y���\��_���ȂǁA�����̖��ԓI���Â܂ő����ɍL�͈͂���̘^����Ă���B
�@�����������ɂ�����w�ϐ����x�w�����x�̉e���͂��܂茩���Ȃ��B����͗�������v���邢�͌���̊��s�ȍ~�A�\�����I�ɕs���S�ȕ����{���w�l�ɑS���x�Ɏ��߂���܂ł̊ԁA�|���{�̗��z�����`�Ղ��Ȃ����ƁB��v�������́w�؎��v���x�w�؎��ޕ��x�A���́w����W���x�A���́w�i�y��T�x�w�Í��㑱��S�x�w�{���j�ځx�ȂǁA�\�Z���I�܂ł̈ꕔ������ɂ߂đ啔�̏����ɂ������p����Ȃ��������Ƃ��w�i�ɍl������B
�@����A���{�ł͑��������q����̈ҏ@��r�w�{���F�t���x�i��l�j�Ɉ��p����A�������S�́w�ڈ㏴�x�i��O�Z�l�j�Ɓw�������x�i��O��܁j�Ɂw�ϐ����x���ʂɈ��p���Ă���B�܂肻�̐�����A���\�N���o�����āA�킪���ŗ��p�����Ƃ���ƂȂ����B��k������ɂȂ�ƁA�m�E�L�ׂ́w���c���x�i��O�Z�O���j�Ɂw�ϐ����v�w�����x����̈��p��������B��������̐����Ǝv����w�V���x�i���㊪����A��k�̋{�����@�}�������فE��㒆�V���}���ّ��B�a�C�Ƃ̒��Ɩڂ����m�a�������{����̓]�ʁB��p�{�͏�����f�̋����j�ɂ��w�ϐ����x�w�����x���������B�ȏ�̓��{���ō]�ˎ���Ɋ��s���ꂽ�̂́w���c���x�݂̂ŁA��������㐢�ɍL�����z�����킯�ł͂Ȃ��B�㐢�ɉe����^�����R���p�N�g�Ȉ㏑�ł́A�Ȓ������O�́w�[猏W�x�i����l�j�Ɂu���]�o�Ёv�̈ꏑ�Ƃ��āw�ϐ����x���������Ă���B���炭���ꂪ�{���̖������߂��ł������̂��̂ł��낤�B
�@�]�ˊ��ɂȂ�ƁA�{�����o�T�Ƃ��鏈���������̕����ɓ]�ڂ����悤�ɂȂ�B�Ƃ�킯�]�ˊ��S�ʂɂ킽�舤�p���ꂽ�w�Í����b�x���͂��߁A�w���ڕ��v��x�w�܌�����x�Ȃǂ̖����ɂ��{����w�����x����̘^����A������l�����Y�t���Ă��閼���͏��Ȃ��Ȃ��B�Ⴆ�Γ��A���q�E�����t�C�ہi���Ԑt�C�ہj�E�A�B���E�`�ړ��Ȃǂ́A�F��������Ēm��ꂽ�w�ϐ����x�̏����ł���B
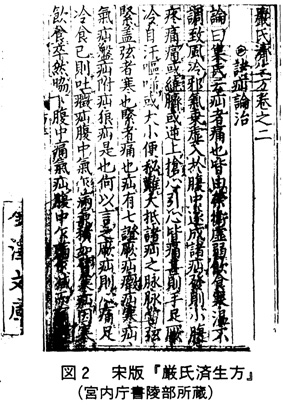 �l�A�`�{
�l�A�`�{
�k�����ϐ����l
�@�v���{
�@�{�������˕��i�g�t�R���ɋ����A�}�Q�j����ё�k�E�̋{�����@�i�Ȓ����{���@�����j�����B�O�҂͎����ƍ]�����i������l�t�����j����ъ���`�܁E���E�オ�v���B���͕�ʂ��ȂĔz����A�ژ^�������B��҂͕�SᡉN�N�̚��p�a�u�����Z�������v�ܗt�A�ژ^�\�O�t�𑶂��邪�]�����������A�v���͊����̑�\���t�܂łŁA���͑S�ĉe�ʂ��ȂĔz����A�u�{���@�U���v�u���_{䇁{��}�^���U�L�v�u���A�����v����їk��h�U��L�l�킪�悳���B���҂Ƃ��ɑv�����͓��l�̔Ŏ��ŁA��v�̌������Ɩڂ����[5]�B
�@�Ȃ����]�ˎ��̌����i�u�w�����ޏ؈㏑��S�x���v�w�a�����Ј㏑�W���x�掵�S�A��㔪��j�ɂ��A��p���������}���ُ����̑v�Łw�V�听����x�i���K�������j�́A�v���w�ϐ����x�{���Ƒv���w�����x�����̔Ŗ�p���A�����E���Җ��݂̂ߖʼn����E�s�����ꂽ����̈�{�ł��邱�Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B�����ē����{���̑啔���́A��q�̋{�����{�E��k�̋{�{�Ƃ͕ʔłȂ̂ŁA�v�ł͍Œ��킠�������ƂɂȂ�B
�A�����{
�@����縜�C�w�l�ɏ���縒��x�ɒ��^�����B���݂��̏������L���ژ^�͓��E���Ƃ��ɂȂ��A�����炭�U�Â����Ǝv����B���邢�͌���ɁA�O�q�́w�V�听����x���s����������O�Ɉ�s���ꂽ�������������m��Ȃ��B
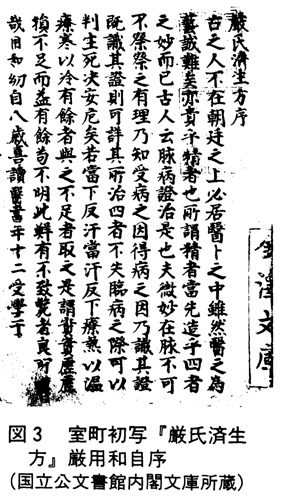 �B�������ʖ{
�B�������ʖ{
�@�����������ٓ��t���ɏ����i�]�ˈ�w�ً����j�B�����E�]�����E�ژ^����і{������E��̈���̂݁B������t�i�}�R�j�ɂ́u���Ɂv�̈�L������A���̑O�ɂ́w�����x������t���Ԃ����܂�Ă���B��������L�̐^�U�͏��ʔN��Ɗ֘A���ď��������邪�A���䎁[6]�͖k�����ŖS��ɋ��ɂ��Ǘ������̖����ɂē悳�ꂽ�Ɛ�������B
�@�܂���k�̋{�����@�}�������قɂ��A��������ʖ{�E���Z�Ɂi�������`�\�j����i�ώ����Z�����A�̊ύ��Z��l�Z�Z�E�Z��l�Z���j������B���{�͖����t�A��܍s�E�s��ŁA�u�������L�v�u�������^�}���L�v�ƕs�ڈ�L�O��E�k��h����L�l�킪�悳���B��ɂ́A�u���{���Ꮏ�n���A������O�S�N�O��{�A�����V������A�W��l���L�A�ʎ�����A�b�Џ��t�A�铌�����A��{�{��}�A���A�����v�u�������N�}�ˁv�A��2�����Ɂu�V����\���~�A�B�������v�̎��ꂪ����B�Ȃ��������^�w��В��^�x�i��k�̋{���j�ɋȒ�������̓��䕶�ɌÏ��e�v�{���Ƒ����A�����ȍ~�������Ï��{���ɑތ����������ƋL�����A�Ƃ��Ɍ����݂͕s�ځB
�C���ۏ\��N�i�ꎵ�O�l�j�A���ʎ}�����{
�@�����������ٓ��t���ɂق������B�����������E�b��ʌ����E�ژ^�E�{���\������Ȃ�A���p�a���E�]�����������B���s�o�܂͌�q����B
�k�����ϐ������l
�@�v���{
�@�w�����x�̌��p�a�����͓��������s����Əq�ׁA�O�q�̂悤�ɑ�p�����}���ُ����́w�V�听����x���v���w�����x�����̔Ŗ�p���Ă����̂ŁA�ԈႢ�Ȃ��v�ł͑��݂����B���������̌�A���ł̏����L�^�͂Ȃ��A�����Ɏ���ꂽ�Ǝv����B
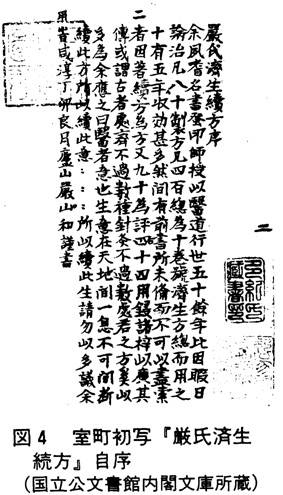 �A�������ʖ{
�A�������ʖ{
�@�����������ٓ��t���ɏ����i�]�ˈ�w�ً����j�B�S�͖̂{������`���̈���Ŋ���E�\�������A�ژ^�͂Ȃ��B�{���̎����͑O�f�̓����ɑ��w�ϐ����x�����ʖ{�Ɍ���ĒԂ����܂�Ă���B�܂������i�}�S�j����і{�������ɂ́A�Ƃ��Ɂu���I��������v�u�I�z�����ˑ��㏑�v�Ȃǂ̈�L���悳���B�Ȃ��w��В��^�x�͌Ï��{�Ƃ��āA���͉Ɩ{�Ɓu���Ɂv��L������]�ˈ�w�ٖ{�̓����L���Ă���B
�B�����ܔN�i�ꔪ���j���I�����늧�{
�@������w�����}���فE���k��w�t���}���فE�ÉÓ����ɁE����}���فE�k���}���ُ����B���p�a���E�{�������E���A����ѓ��͌�{�C�{��}�Ƒ��I����������Ȃ�B���s�o�ܓ��͌�q����B
�k�ϐ����E�����̍����{�l
�@�w�l�ɑS���x�����{
�@�����̑p���w�i�y��T�x�Ɉ��p�����w�ϐ����x�w�����x�Õ����ɂ܂Ƃ߁A�w�l�ɑS���x�i�ꎵ���܁j�Ɏ��^�������́B�\���E���e�Ƃ��ɋ��Ԃ��������Ă���B
�A���E�����l�N�i�ꔪ�����j���w���A������w�p���x�����{�i�}�T�j
�@���̒������Ҏ[�������p���ɁA�O�f�́w�l�ɑS���x�{����сw�l�ɑS����v�x���������������́B��㔪��N�ɂ͍Y�B�s�Ë����X�����p���S�̂��e��A�܂����ܘZ�N�ɂ͐l���q���o�ŎЂ��{���݂̂��e��P�s���Ă���B������������E���e�Ƃ��w�l�ɑS���x�{�Ɠ��l�B
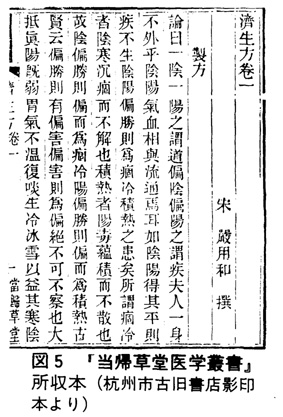 �B��㔪�Z�N�l���q���o�ŎЉ���w�d�������ϐ����x
�B��㔪�Z�N�l���q���o�ŎЉ���w�d�������ϐ����x
�@�{���͑O�f�̘a���w�ϐ����x�Ƙa���w�����x�̓��A���]�Ȓ��㌤���������g�炪�ĕ҂��ȑ̎��ɉ��߂����́B�O���E���E�ϐ��������E���������E�{���E�����������Ȃ�B���e�́w�l�ɑS���x�{��芮�S�����A���{�̍\���������ĕ҂̈Ӌ`�͏������B
�@�ȏ�w�ϐ����x�̓`�{�l��A�w�����x�̓`�{�O��A�����{�̎O�Ŗ{���Љ���B����̕����ɂ͓��e�Ƙa���ł��邱�Ƃ��l�����A�w�ϐ����x�͍����������ٓ��t���ɑ��̋��ۏ\��N���{�i�����s�����j�A�w�����x�͓�����w�����}���ّ��̕����ܔN���{�i���I���������j���{�ɑI�������B�܂��w�ϐ����x�̌��p�a���ƍ]�������A�����������ٓ��t���ɑ��̌Îʖ{���⑫���邱�Ƃɂ����B
�܁A�e���{�ɂ���
�k���ۏ\��N���w�����ϐ����x�\���l
�@���{�̊��L�ɂ��ƁA�o�Ō��̋ʎ}���͋��s�̏��X�A�������Y�ł���B�܂����̊��s�o�܂͈��������ƍb��ʌ��̏����Ȃǂ��m�邱�Ƃ��ł���B
�@���������i���A�j�͍b��ʌ��̏��ɘQ�Ԃ̈�ƂƏq�ׂ���ȊO�A�s�ڂł���B�����̏��ɂ��A�ނ͖{���̒��I���{�O��𖼉Ƃ�����B�������Z���������N��̋��ۏ\���N�i�ꎵ�O��j�A�ʂ̎ʖ{�����Q�����ʎ}���̖|����]�ɂ��A�ēx����ŒE����������Ƃ����B����A���ۏ\��N�i�ꎵ�O�l�j�̍b��ʌ����ɂ��ƁA���Ė^���X���{���̖|������悵�A�Z�{���˗����ꂽ�������ɒE�R�����������B�K�������������{�ɂ�芮�S�ƂȂ����̂ŁA�ĂэZ�����P�_�������o�ł��邱�Ƃɂ����A�Əq�ׂ�B
�@�b��ʌ��i�������ցj�͋��s�̈�Ƃł���B���̎��Ղ͂��܂�m���Ă��Ȃ����A�w�ϐ����x�o�łƓ��N�̋��ۏ\��N�ɁA�w�ϐ������x�{�̗����_�w��w�����x�ɌP�_���{���Ċ��s�B�����ܔN�i�ꎵ�l�Z�j�ɂ͎����w����I���x�O���i���یܔN�A�ꎵ��Z�����j�����s�B������N�i�ꎵ�l�܁j�ɂ́w�Í����b�x�̏o�T�E��E������A�܂������₵�Ċ��s�B����ɕ��̍b��S���i�h���j���w���u���W�x�ɕ��^�ꊪ�������A���l�N�i�ꎵ�l�j�Ɋ��s�B���ܔN�i�ꎵ�܌܁j���̓��R�쟷�́w�����i�_�j�������x�ɏ����L���A���N�s�˂����w���Ӂx���Ȃǂ̊�������Ă���B
�@�Ȃ���c�@���́w�c������`�x�̉��{����i��ܔ����`��Z�l�܁j�̍���[7]�A�b��ʌ��͌���̖�l�ƕt�L����B���������҂̔N��͂��Ȃ�u����̂ŏ��㌺��̖�l�ł͂Ȃ��A���̌���̖剺�����������m��Ȃ��B
�@�Ƃ���Łw��㏑�X�ÓT�Жژ^�x��\�l���i����O�H�j�́A�u���ۓ�N�����b��ʌ����M���^�E���ێO�N���������B���V�E�⑊�ƍl�{�i���E�m���w�{���V�ҁx�����Z����B�����A�u�����ʌ����v�ƋL�����Ɂu�b�ꎁ�v�u�ʌ��V��v�̓����������j�v�Ƃ����w�{���V�Ҕ����x����i��Z���~�j���ڂ���B����Ɂw����I���x�ɂ͌����l�N�i�ꎵ�O��j�̏������B�i��Z�Z���`�ꎵ�l�Z�j��������A�u�i�ʌ��́j�ߒ�h�������āA�{�����o�ł��邱�ƂɂȂ����̂ŏ��������߂��v�Ƃ����B�ʌ��̒�̍b��h���͏������B�̖�l�ŁA�����Ɂw��a�{���L���x�⏼���q�T�i���B�̎q�j�Ƌ��҂́w�p��{�m��ҁx�i�ꎵ�܋㊧�j������B�Ƃ���Ȃ�ʌ��͌��B�����N���ŁA�ʎ������R���������낤�B
�@�ʌ��̊w����]���O�p�́A�u���������v�u�ƍD�Õ��A���\�ِV���v�Ɓw�Í����b�x�̏��ɕ]���Ă���B�܂��O�p�͒ʌ��d���́w�Í����b�x�����܂�ɔ���A���z�̎����܂Œl�オ�肵���ƌ`�e����̂ŁA���̍D�]�Ԃ肪�M����B���̒ʌ��̔����́A�w�ϐ����x�Ɋ����̍Ō�Ɂu�܂��w�����x������ꂸ�⊶�ł���v�A�Ƃ��̑��݂�������������������m���悤�B
�@���Ȃ݂ɓ��a���w�ϐ����x���A�O�q�̑v�ł���ьÎʖ{�Ɣ�r���Ă݂��B���p�a���E�]��������������_�͎c�O�����A�ژ^�͕����̒E�R���⑫����A�{���͈ꕔ�������s���E���l�߂܂őv�łƂقڈ�v���Ă���B���������ē��a���{�͕�v�łƌ����ʂ܂ł��A���{�ɒ����ɍZ�����ꂽ�|���łƕ]���Ă悢���낤�B
�k�����ܔN���w�����ϐ������x�����y���l
�@���{�͑��I���������Q�㏑�̕�������悵���w�q���b�ҁx�̈�Ƃ��āA�w�����富o�x�w�{�����`�x�ƂƂ��Ɋ��s�������̂ł���B������������͈������Ȃ������炵���A�����{�͋ɂ߂ď��Ȃ��B
�@���{�����������s�����_�@�́A�O�q�́w�����x�Îʖ{���f���̓��͌�{�C�{��}�����̖�l��蓾�����ƂɎn�܂�[8]�B���͉Ƃ͑��I�Ɠ��l�ɑ�X�̈㊯�ŁA�l��ڊ��[�Ɏq���Ȃ������̕����ȁi���j�j�̒퍶�V�i��j�j��{�q�Ƃ��A�ܑ�ړ��͒��[�Ƃ��Ă���B���������[���q���Ȃ��A���̎���i�O�j�j�𒉖[�̖v��ɍĂї{�q�Ƃ��A�Z��ړ��͌�{�C�{��}�i�����j�Ƃ���[9]�B
�@���đO�q�̌Îʖ{�ɂ́A�}�S�̂��Ƃ����͉Ƃ̑����ɑ��I�Ƃ̈���悳���B�����茳{�C�{��}���{���������Ƃ̑��I�Ƃɏ��n�������Ƃ��킩��B�Ƃ���Łw�o�ЖK�Îu�x�i�ꔪ�ܘZ���j���L�����͎����w�����x�Îʖ{�ꊪ�ɂ́A����Ɂu���Ɂv�̈�L�������łɂ���Ƃ����B�܂����I�������a���w�����x���땶�ɓ������Ƃ��q�ׂ�B����A�O�q�́w��В��^�x�ł́A���I���̈�w�ٖ{�Ɂu���Ɂv��L������Ƃ����B�Ƃ��낪�}�S�̓��t���ɖ{�ɂ͂��ꂪ�Ȃ��A����̂��}�R�́w�ϐ����x�Îʖ{�̎����ł݂̂ł���B����Ɠ��͉Ƃ͂��Ƃ��ƁA�u���Ɂv��̗L�����Ⴄ�Îʖ{�w�����x��_���������Ă����̂��낤�B�����āu���Ɂv��L�̂���{��悸��w�قɏ��n�������A����͌��݂ɓ`��炸�A�̂���L�̂Ȃ��{����w�قɏ��n���A���ꂪ���݂̓��t���ɂɓ`������A�Ɛ����ł���[10]�B
�@�Ƃ����ꌳ���͖{���͌�{�C�{��}���ؗ���A���̊���Ə\�̌����ɋC�t�����B�ނ͘a���w�����x����Ɏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u�f���̓��͌N�͂��Ċ���ɋ��Ɉ�L�̂����{�����A������Č뎚�������A���̕]���Ə����̐��͏����̋L�ڂƕ������Ȃ��B�����Œ��N�́w������ځx�̊e��Ɉ��p�����{���̘Õ��ɂ��Z���E�������A����Ɍ����̓�]�E�\�����⑫���Ċ��S�Ȃ��̂Ƃ����B����Ă���������Đ��ɓ`����i�ȉ����j�v�A�ƁB�w������ځx�i��l�l�܍��j�͌�Ɋ쑽���������؊�����p���Ĉ�������ɍL�܂������A�����͂��łɒ��N�ɂ��Ȃ��A���{�ɂ̂ݓ`�����Ă�����w�S���ł���B�������{�ɂ̂ݓ`���̌Õ�������g������Ƃ́A�܂��ɂ��̌b�܂ꂽ���������o�E���p���������I�Ƃ�]�ˈ�w�ق̊w���ƌ��͂ɂ���Ă̂ݍs�������Ɛтƌ���˂Ȃ�܂��B
�@���a���w�����x�̐��m�x�͓�v�̌����{�����݂��Ȃ��ȏ�A�������邷�ׂ��Ȃ����A���̌Îʖ{�Ɋr�ׂ�Ȃ�Ίi�i�ɗD��Ă���B�܂��ژ^�̂Ȃ��_�͕s�ւ����A�Îʖ{�ɂ��Ȃ��̂ŁA�����͂����ċ��Ԃ̉��ς�]�܂Ȃ������̂��낤�B���̂��Ƃ́w������ځx����̏S�Õ��������Ɂu���v�Ƃ��ĕt���A�����Ɋ���Ə\�ɔz�����Ă��Ȃ����Ƃ�����M����B���������ē��a���{�̑̍ق͂��Ă����A���e�I�ɂ͌����̌������Ƃ��A�قڊ��S�Ȃ��̂ƍl���Ă悢���낤�B
�q��������ђ��r
[1]�w�㕔�S���x���O�O���ŁA��k�E�|���ىe��A���ܔ��B
[2]�X���V��w�o�ЖK�Îu�x�i�w�ߐ�������w���W���x�O�������A�����E�����o�ʼne��A��㔪��j�l�Z�ܕŁB
[3]���I�����w�i�����j��Ѝl�x��ŁA��k�E��V���ǁA��㎵�܁B�����N�u�w���^�l�����x�ًU�v�w����G���x����Z�N��Z���Z��O�`�Z��ܕŁB�����N�u���ÕF�������w�y���w�p���A�v�w���؈�j�G���x�����O��`�O���ŁA�����B
[4]�i{���{�e}��w�l�ɑS�����ځx���Z���ŁA�k���A���؏��lje��A��㔪�܁B
[5]��������w���������K���u�x�O�Z���ŁA�����E���Ï��@�A��㔪�O�B
[6]����ہw���t���ɏ����̌����x�ꔪ�Z�`�ꔪ�O�ŁA�����E�֓����X�A��㔪�Z�B
[7]��c�@���w�c������`�x�i�w�ߐ�������w���W���z��㊪�����A�����E�����o�ʼne��A��㔪�O�j�O�O�ŁB
[8]�Ό������i�u�V�����̋��ɋ����㏑���v�A�w�b����Ɂx�\�����A���ܘZ�j�͓��{����肵���͓̂��͒��[�Ƃ��A���̔����N���������Ƃ���B����������͌����̂����f���̓��͌�{�C�{��}���A���̌Z�̒��[�ƂƂ�Ⴆ�����Ƃɂ���F�ł���B
[9]�w�V�������d�C���ƕ��x��\��E��㎵�ŁA�����E���Q���ޏ]���s��A���Z�Z�B
[10]�Ό������i�O�f��[8]���f�����j�́w�o�ЖK�Îu�x�̋L�ڂ��A�u���Ɂv��L�̂���w�ϐ����x�Ɂw�����x�����Ԃ����܂�Ă�������Ƃ��邪�A���ۂ͌Ï��{�����݂��Ă������ƂɋC�Â��Ȃ��������߂̌�F�ł���B
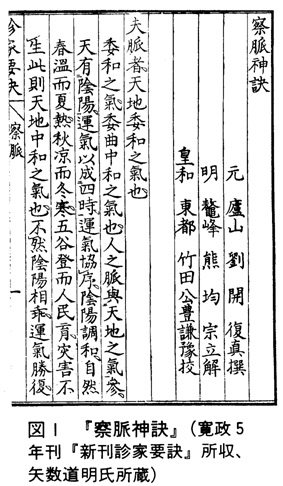 �@���Ă`�ɂ͔���菑�ɐe���݁A�\��ŗ��J�i���𗧔V�A���͕��^�j�ɓ��債�A�ܔN�Ԉ�w���C�߂��Əq�ׂĂ���B���J�̓`�́w��N�{�u�x[1]�Ɍ����A�w�������v�x�����ƋL���A�����͖k���}���قɉÖ��O�\�O�N�i��܌l�j���D�]���{����������B�܂��w�i���^�j���O�_�����x�ꊪ�i�����Ȋw�@�}���ق����O���ł������j�Ɓw����������v�x�ꊪ�i�{�������˕����w���_����X�x�ƍ����̒��N�ł������j�̒����́A������������ܔN�i���l��j�Ɏ������L����Ă���B�㏑�ɂ́u�O��㗫�J���^��B�O������l���q��p�a�}���v�ƋL����Ă���̂�[2]�A���p�a�͎t�̏��ɐ}����������قǑ��̖�l�������炵���B�܂����J�ɂ́w�������i�x�܊��̒����������炵�����i�����אl�w�v�ȑO��Ѝl�x�l���l�Łj�A�����͕s�ځB���̑��A�킪���ł͗��J�̏��ɖ��̌F�@�������������w�@���_���x�ꊪ�i�w����听�x����̘^�o�A�}�P�j�����s����Ă���B
�@���Ă`�ɂ͔���菑�ɐe���݁A�\��ŗ��J�i���𗧔V�A���͕��^�j�ɓ��債�A�ܔN�Ԉ�w���C�߂��Əq�ׂĂ���B���J�̓`�́w��N�{�u�x[1]�Ɍ����A�w�������v�x�����ƋL���A�����͖k���}���قɉÖ��O�\�O�N�i��܌l�j���D�]���{����������B�܂��w�i���^�j���O�_�����x�ꊪ�i�����Ȋw�@�}���ق����O���ł������j�Ɓw����������v�x�ꊪ�i�{�������˕����w���_����X�x�ƍ����̒��N�ł������j�̒����́A������������ܔN�i���l��j�Ɏ������L����Ă���B�㏑�ɂ́u�O��㗫�J���^��B�O������l���q��p�a�}���v�ƋL����Ă���̂�[2]�A���p�a�͎t�̏��ɐ}����������قǑ��̖�l�������炵���B�܂����J�ɂ́w�������i�x�܊��̒����������炵�����i�����אl�w�v�ȑO��Ѝl�x�l���l�Łj�A�����͕s�ځB���̑��A�킪���ł͗��J�̏��ɖ��̌F�@�������������w�@���_���x�ꊪ�i�w����听�x����̘^�o�A�}�P�j�����s����Ă���B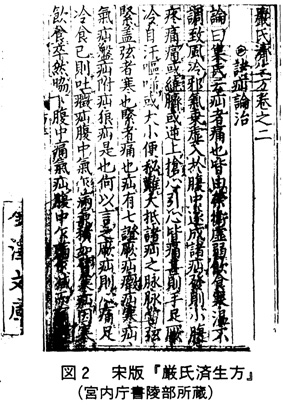 �l�A�`�{
�l�A�`�{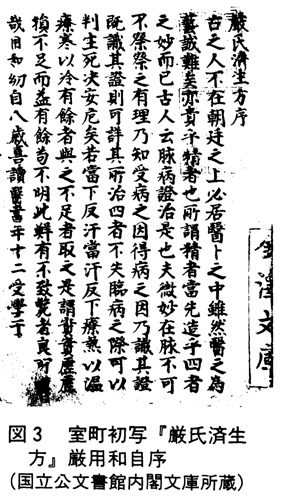 �B�������ʖ{
�B�������ʖ{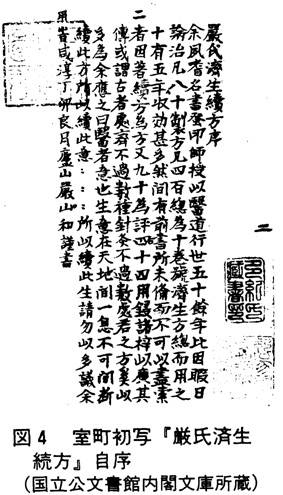 �A�������ʖ{
�A�������ʖ{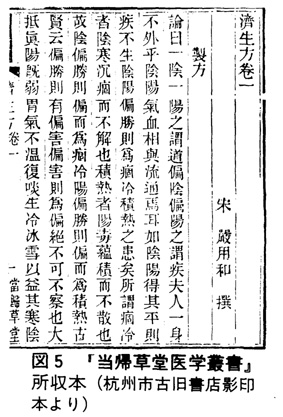 �B��㔪�Z�N�l���q���o�ŎЉ���w�d�������ϐ����x
�B��㔪�Z�N�l���q���o�ŎЉ���w�d�������ϐ����x