←戻る
真柳誠「『名医類案』解題」『和刻漢籍医書集成』第10輯所収、エンタプライズ、1990年12月
『名医類案』解題
真柳 誠
一、編者と成立
〔江瓘の伝〕
本書を編纂した江瓘の伝は正史にない。しかし同郷の友人で進士の汪道昆[1](一五二五~九三)は、「明処士江民瑩墓志銘」[2]を撰文し、詳しく事跡を述べている(王旭光ら「江瓘年譜」『中華医史雑誌』47巻3期183-188頁、2017に詳細な事跡が発表された)。そこで以下に要点を整理し、現代語訳しておく。
江処士は名を瓘、字を民瑩、号を篁南また江山人という。現在の安徽省歙県の出身。父の慕公と母(鄭安出身)の第三子で、弟に民璞季公がある。明・弘治十六年(一五○三)の生まれで、長子に応元、次子に応宿(字は少微)がある。会稽(今の浙江省紹興市)に応宿の病を治療に行った帰途、嘉靖四十四年(一五六五)八月二十六日に病没した。享年は六十三。
江瓘が十四歳の時、病没した母は瞑目していなかった。これは子供達がまだ大成していないので瞑目できないのだと思い、発憤して進士を志した。そこで詩文を学び、まず県官を受験したが落第。父に商いの修業を命ぜられ、しばらくこれに努めた。
その後、歙県に来た督学使者の推挙で民璞と共に県の学生となった。翌年、郷試(科挙の第一試)を受けたが、再び落第。これよりさらに発憤し、弟に休息するよう請われてもきかず、寒暑・昼夜の別なくひたすら余力を遺さず読書した。
こうする内に発病し、数升も嘔血した。しかし医者に十数回かかっても治らない。それで医学の入門書を色々と調べ、自分で処方したところ治癒した。だが学業を始めるとまた発病のくり返しで、十年以上が過ぎてしまった。
いくら大成のためとはいえ、かくも身を軽んじては何も得られない。遂にこう悟り、学官をあきらめ、挙子の業をやめた。そして門をとざして自在に寝起し、『離騒』『素問』の諸書は机に放置し、雑事も気にしないようにしたところ、急に学業が進むようになった。
嘉靖二十三年(一五四四)に弟が進士に挙げられた時、江瓘はこれで母も瞑目できると安堵し、心から喜んだ。また江瓘は、その詩文で広く名が知られるようになり、各地で名土と交流を重ねた。
彼の性格はおだやかで誰とでも接したが、迎合せず当否をはっきり述べた。とりわけ国事に関心が深く、傾聴に値する文論を著している。例えば飢饉の年、浙江のある司は被災地への米穀の販売を禁止したが、彼は『春秋』の大義を引いて禁止令の取消を上書したほどであった。
なお『四庫全書総目』によれば、江瓘には『江山人集』(詩五巻、文二巻)もあり、文より詩が優れているという。また『武夷游稿』『游金陵詩』の二集もあったが伝わらず、各序文が『江山人集』の末尾に付されるのみという[3]。
〔成立〕
本書には以下の序文と跋文がある。
①嘉靖二十八年(一五四九)の江瓘自序
②嘉靖三十一年(一五五二)の游震得序
③万暦十四年(一五八六)の許国序
④万暦十九年(一五九一)の江応宿跋
⑤年代無記の張一桂序
これらによれば、本書の成立はおよそ二段階に分けられる。
第一段階:①の文頭に記すように、江瓘が『褚氏遺書』にある「博く渉りて病を知り、多く診して脈を識り、屢用して薬に達す」[4]、という名言に感動。そして博歴の目的で古今名賢の治法を集め、自己の意見と知見も加えて「十二巻、為門一百八十有寄」に編纂し、序文を草した一五四九年である。
④に息子の応宿は、父がこれを二〇年かけて集めたと記す。ならば江瓘は一五二九年頃、およそ二七歳の時に着手したのであろう。この年齢は、彼の伝にある一〇年以上の病で進士をあきらめた頃とほぼ一致する。江瓘は本書を完成後の一五五二年、游震得より②の序を得ているが、結局一五六五年に没するまで発刊には至っていない。
第二段階:江応宿は刊行を前提とし、④の跋文を記している。すなわちこの一五九一年が、本書の最終成立年である。応宿はここで次のようにいう。
二十歳の時、方伯(布政使)の職にあった叔父の滇南に従い、呉・越・斉・楚・燕・趙(江蘇・浙江・山東・河北など)に行き、前人の治験を博採した後、故郷に帰った。しかし父の書は未刊のままで久しく、これでは散逸の恐れがある。そこで遺稿の編次に補遺を加えること一九年、書きなおすこと五回。さらに兄の応元と共に考訂し、刊行に至ることができた、と。
ところで⑤の張一桂序は年代不明であるが、その一部が④に転用されているので、一五九一年以前に書かれているだろう。また③⑤ともに、本書を刊行する父の遺志をはたせないことを、涙ながらに訴える応宿の様子が述べられている。したがって応宿は五年ほど努力し、刊行にこぎつけたらしい。
一方、本書の病門数を応宿は「二百有奇」と記し、実際に数えてみると計二〇五門に分けられている。これは江瓘の自序でいう数より、約二〇ほど多い。本書の凡例に応宿は自己の治験を補足したと記す。かつ多くの病門に応宿の治験や按語もあるので、病門数が増えたのだろう。さらに応宿が各地で博採したという先人の治験例も増補されており、これも増加の一因と思われる。
ともあれ一九年を費し、かなりの増補がなされているので、本書全体の成立年は江応宿跋の一五九一年と考えるべきである。
二、構成と内容
〔構成〕
本書は全一二巻二〇五門よりなるが、それらはおよそ以下の内容に分類されている。
巻一:外因による病など一一門
巻二:内傷による病など九門
巻三:神経・中枢性の病など一四門
巻四:胃腸の病など八門
巻五:虚損の病など一三門
巻六:疼痛の病など一六門
巻七:頭部・顔面の病など二一門
巻八:出血性や下半身の病など一五門
巻九:皮膚の病など一四門
巻一〇:同右二八門
巻一一:婦人の病二一門
巻一二:小児の病三五門
このように各治験例は、比較的整然と配列された病門に分けられている。また江瓘の凡例によれば、各病門内ではおよそ治験者の年代順に配列し、自己の治験は末尾に付したという。本書に「江篁南治~」とある治験がそれである。さらに応宿が増補した自己の治験は、「江応宿治~」「江少微治~」と記される。本書の記載で所々に二字落しの文章があるが、これらは各治験に対する江父子の按語である。「宿按~」と書き出すのが応宿のものなので、それ以外が江瓘の按語である。
本書の凡例後には、治験を引用した「諸家姓名」として、計一九三名が挙げられている。しかし中には、同一人物を書名や号などで重複して記すものが少なくない。例えば先に「羅謙甫(天益)」を挙げ、後でその著書をあたかも人名のように「(衛生)宝鑑」とするもの。あるいは「葛洪」と「抱朴子」、「王好古」と「海蔵」、「唐・甄権」と「甄権」などである。
しかし引用された医家各人について、ここに解説するのはもとより不可能である。必要の際は、左記の二書が便利なので参照されたい。
李云ら『中医人名辞典』、北京・国際文化出版公司(一九八八)
李経緯ら『中医人物詞典』、上海辞書出版社(一九八八)
また引用した書も、計一五〇が挙げられている。そのいくつかは当時まで、はたして伝存していたか疑われる。しかし医書以外の書からも、これだけの範囲から治験を取り出しているのだから、本書の価値は大きい。
〔内容〕
本書は各医家の治験を類編したものである。それゆえ各治験ではなく、それに対する江瓘の按語に特色が現れている。これについては『四庫全書総目』に的確な論評[5]があるので、以下に翻訳しておこう。
本書に採られた治験は、『史記』『三国志』所載の秦越人(扁鵲)・淳于意(倉公)・華佗の諸人から、下は元明の諸名医まであまねくひろい取られている。これを二〇五門に分け、各々に病情・方薬が詳説される。また江瓘が随事これらに評論した注も加えられている。
例えば傷寒門には、便秘で汗が出る証の許叔微による治験がある。これを衆医は、陽明病の自汗で津液が漏れ出しているのだから、蜜煎導を用いるべきだとした。しかし許叔微はこれに大柴胡湯を用い、効を収めている。江瓘はこれに対し、やはり蜜煎導がおだやかでよい、と述べている。
また転胞門には、胎児が妊婦の膀胱を圧迫する証の朱丹溪による治験があり、妊婦の手で胎児を押し上げさせよという。これに対し江瓘は、こんな治療法はなく、正しくないと述べている。およそこの類で、その反駁と訂正の多くには、精緻にいたる発明が頗る多い。
ただし尸蹶門に付載の針治験では、『酉陽雑俎』所載の話で、高句麗の名人は頭髪を針で貫く、という虚事を引く。これは治療に一つも関係ない。難産門では『焦氏類林』に載る于法開の治験で、肥羊の焼肉を十数切食べさせて針をしたら出産した、という話を引く。しかし羊肉を食べさせる意味は不明で、どの穴に針をしたのかもわからない。これらはいたずらに異聞を広めるのみで、医療に益はなく、ただ驚かせ奇をてらう類にすぎない。
しかしながら医家の法律とすべきは、もとより本書の十に八、九を占める。
三、版本
本書には中国と日本の版本があるが、朝鮮版は見当らない。また清以降の中国版は現存が多いので、所蔵先は省略する。
〔中国刊本〕
①明・万暦十九年(一五九一)博少山刊本 国立公文書館内閣文庫・アメリカ国会図書館・中国中医研究院・南京図書館所蔵。
②清・乾隆三十五年(一七七〇)新安鮑氏知不足斎刊本
③四庫全書所収本
④清・同治十年(一八七一)蔵修堂刊本
⑤清・光緒十一年(一八八五)信述堂刊本
⑥清・光緒十四年(一八八八)刊本
⑦清・光緒二十年(一八九四)著易堂刊本
⑧清・光緒二十二年(一八九六)耕余堂鉛印本
⑨清・宣統元年(一九〇九)刊本
⑩同右年、上海書局石印本
⑪清末、仁和陳立方写刻本
⑫一九一四年、上海鴻文書局石印本
⑬一九一六年、同上石印本
⑭一九三七年、上海世界書局鉛印本
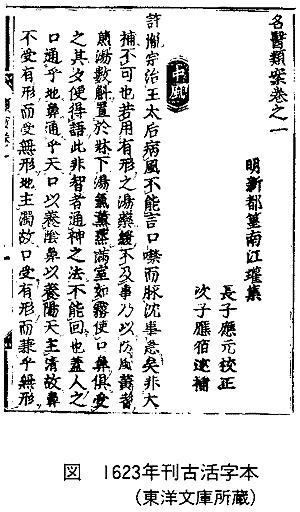 ⑮一九五七年、北京人民衛生出版社影印本
⑮一九五七年、北京人民衛生出版社影印本
⑯一九八二年、同上影印本
以上、中国刊本は一六種を数えたが、まだ数版本はあるかも知れない。また台湾からは⑮のリプリント版も出ている。
これらの内、初刊本の①はもちろん貴重であるが、魏之琇(玉横)が①の誤字・脱文を正し加注した②は善本と称されている。⑮⑯はその影印本である。また⑤⑦⑧⑨⑫は、魏之琇の『続名医類案』との合刊本である。
〔日本刊本〕
⑰元和九年(一六二三)梅寿刊古活字本 東洋(岩崎)文庫(図)
⑱同上年、梅寿刊整版本 武田科学振興財団杏雨書屋・北京大学図書館所蔵
⑲寛永十二年(一六三五)杉田勘兵衛重印本 神宮文庫・武田杏雨書屋所蔵
⑳寛文元年(一六六一)野田庄右衛門重印本 研医会図書館・国立国会図書館・国立内閣文庫(巻八欠)・東北大学図書館・武田杏雨書屋・中国中医研究院図書館・南京図書館所蔵
以上の和刻本の内、⑰は中国の①を復刻したもの。⑱は⑰の序跋を①と同じ写刻体に彫り直した以外、⑰を完全に覆せ彫りして整版に改めたもの。その版木で版元が移り、後刷されたのが⑲⑳である。したがって⑰に訓点等がない点を除けば、基本的にはいずれも同一版本といえる。そこで今回の影印復刻には、研医会図書館所蔵の⑳本を底本とした。
四、後世への影響
治験例に按語つまり考察が加えられたいわゆる医案は、その具体性ゆえに時代・流派を越え、診療の参考となるところが大きい。古くは『史記』の扁鵲倉公列伝中に、秦末から前漢の前二世紀に活躍した名医・淳于意の治験が二〇数例ほど記録され、後世に多くの資料を提供している。このような名医の伝記の一部をなす治験例は、『史記』以来の正史をはじめ、様々な史書・地方志などに散見される。
一方、かつて医書の中では治験を独立した篇などに集めることが少く、医方書の各病門中か、本草書の各薬物条の末尾などに記録される程度であった。これがいわゆる医案として定着するのは、医学議論が盛んとなった金元以降といえよう。
李東垣の『内外傷弁惑論』『脾胃論』『蘭室秘蔵』、王好古の『湯液本草』、あるいは張子和の『儒門事親』などには、医案を基に医論を展開する形式の記述がきわめて多い。そして『東垣試効方』はもはや完全な医案書であり、朱丹溪の『格致余論』は医案に基づく医論集となっている。
しかし各医家の医案を集成したのは、江瓘の『名医類案』が嚆矢である。入門書の低レベルや、面白味のない理論書に飽足らぬ人々に本書は広く歓迎され、後世に多大な足跡を遺した。これを中国と日本に分け、簡単に紹介してみよう。
〔中国での影響〕
先に挙げたように、本書は現在までの中国で一六回以上も出版され続けている。しかもそれは初版から約二〇〇年を経た一七七〇年に、魏之琇が改訂版を出した以降に集中している。そしていずれも魏之琇本の復刻である。つまり中国では魏氏本を介し、本書が評価され続けているといえる。
魏琇之(一七二二~一七七二)は字を玉横、号を柳州という。銭塘(浙江省杭州)の出身。本書を改訂すると同時に、新たに『続名医類案』六〇巻(今本は三六巻)を編纂した。この書は之琇の没後、「四庫全書」に収められたほか、一八八五年以降は『名医類案』とペアで刊行されることが多い。
本書はこのように清代から大流行したが、その影響下になった同類の著作も少なくない。それらを列挙すると以下のようである。
魏之琇『続名医類案』(一七七二)
兪震『古今医案按』(一七七八)
沈源『奇症』(一七八六)
呉金寿『三家医案合刻』(一八三一)
羅定昌『医案類録』(一八八二)
姜成之『龍砂八家医案』(一八八九)
柳宝詒『柳選四家医案』(一九〇〇)
何廉臣『全国名医験案類編』(一九二七)
秦伯未『清代名医医話精華』(一九二九)
徐衡之『宋元明清名医類案』(一九三四)
上には民国代までを挙げたが、革命後も少くない。また個人の医案書は汪機の『石山医案』(一五一九)などを皮切に、現代まで厖大な量に達している。とりわけ最近一〇年ほどは、革命前からの老中医の減少もあり、それらの医案が精力的に中国各地で出版されている。
〔日本での影響〕
本書が日本へいつ渡来したかを徴すべき史料は見当らない。しかし他書の例からして、一五九一年の初刊本がほどなく渡来し、日本で一六二三年に復刻されるに到ったのであろう。本書はその後、一六六一年までに計四回出されたわけであるから、反応は中国より早かった。というのも中国では初刊後、一七七〇年まで復刻されていないからである。
しかし中国とは逆に、本書は一八世紀以降の日本では復刻されていない。断定はできないが、その背景に古方派など一七世紀末からの医学の日本化があり、それで本書の参考価値が減じたのかも知れない。
わが国では曲直瀬玄朔の『医学天正記』(一六〇七)をはじめ、吉益東洞『建殊録』(一七六三)、中神琴溪『生生堂治験』(一八○三)、浅田宗伯『橘窓書影』(一八八六)に至るまで、数多くの医案書が江戸期に著されている。さらに『名医類案』を模して編纂されたものに、下津春抱の『本邦名医類案』(一七〇七)がある。
この書は曲直瀬道三以下、名古屋玄医あたりまで、およそ一七世紀中に活躍した医家全二一名の医案が、計五五の病門別に分類されている。その後、各医家の治験を集めた書は出されていなかったが、安井広迪編の『近世漢方治験選集』全一三巻が一九八六年に出版されている。これには計二一医家の治験集が収められる他、『本邦名医類案』も付録として加えられ利用価値が高い。
一方、近年の漢方層の広まりに伴い、現代の治験を集めた書も少なからず出版されている。漢方が伝統医学である限り、先人の治験の価値は今後とも失われないであろう。
文献および注
[1]汪道昆は、同じく同郷の呉崑の『医方考』にも序を草している。
[2]一七七〇年、知不足斎刊『(重訂)名医類按』の付録(一九八二年、北京・人民衛生出版社影印本三七六頁)による。
[3]永瑢ら『四庫全書総目』影印本一六〇五頁、北京・中華書局(一九八一)。
[4]この文章は『褚氏遺書』の弁書篇にあり、広く医書に接することの重要性を述べている。『褚氏遺書』は江戸の刊本もあるが、『《褚氏遺書》校釈』(河南科学技術出版社、一九八六)が最近出版されている。
[5]前掲文献[3]、八七四頁。
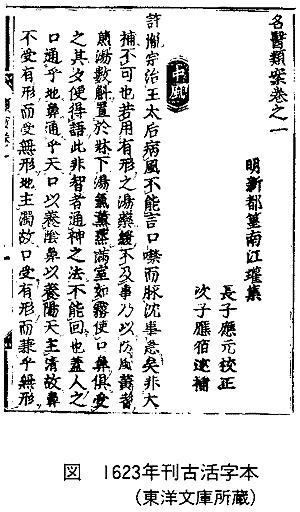
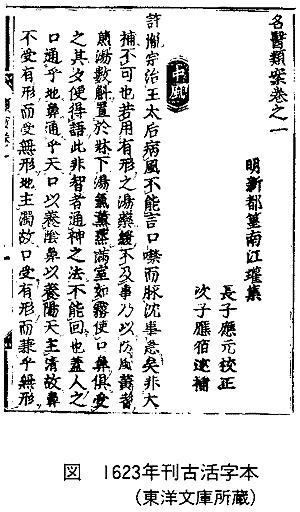 ⑮一九五七年、北京人民衛生出版社影印本
⑮一九五七年、北京人民衛生出版社影印本