『傷寒明理論』『傷寒明理薬方論』解題
真柳 誠
一、著者と成立
著者の成無己について正史は伝を載せず、その生没年等の詳細は不明である。しかし序文などの資料より概略を推定することはできる。
成無己の友人である厳器之の「傷寒明理論序」(一一四二)および「注解傷寒論序」(一一四四)によると、成無己は聊摂(現在の山東省陽穀県)の出身。家は代々の儒医で「性識明敏。記聞該博」、また「議論該博。術業精通」と記される。一方、張孝忠の跋文(一二〇五)によれば、成無己は一一五五・五六年に九十余歳で健在だったので、北宋の嘉祐・治平年間(一〇五六〜一〇六七)の生まれと推測している。このことは王鼎が「注解傷寒論後序」(一一七二)で、十七年前に臨潢にて九十余歳の成無己が治療するのを見た、と記すこととおよそ符合する。かつそこには『傷寒明理論』(以下『明理論』と略す)は十五年前に邢台で出版されたが、『注解傷寒論』(以下『注解』と略す)は未刊なので出版することにした、とも記されている。
ところで明代の徐鎔は医統正脈本『金匱要略』の序文(一五九八)で成無己は七十八歳で『明理論』を、八十歳で『注解』を著したという。その根拠は定かでないが、厳器之の序文も勘案すると、成無己の生年は治平元年(一〇六四)頃となる。そして『明理論』は七十八歳の一一四二年、『注解』は八十歳の一一四四年の成立。没年は九十数歳の一一五六年以降ということになる。
成無己の著作は『明理論』三巻とこれに後付の『傷寒明理薬方論』(以下『方論』と略す)一巻、および『注解』十巻が伝わるのみで、他は知られていない。前述の王鼎がいう『明理論』(および『方論』)の邢台刊本は一一五七年頃の刊行になるので、成無己はその時あるいは生存していたかもしれない。しかし『注解』の初刊は王鼎らの記載より一一七二年なので、すでに成無己の没後と思われる。
なお成無己の出身地・聊摂はもと北宋の地であったが、一一二五年に宋朝が南転の後は金朝の地となっている。したがって一説に成無己を宋人ともするが、その活躍年代からすると金人とするのが妥当であろう。
二、構成と内容
『明理論』三巻は、上巻に「発熱」から「煩熱」の十八病症、中巻に「虚煩」から「短気」の十八病証、下巻に「揺頭」から「労復」の十四病症の計五十病症を項目に立て、各々について診断・病理・治療処方を論じている。それらの病証はいずれも『傷寒論』中から選択されたもので、本書の二十数年前に朱肱が著した『傷寒活人書』も同様の形式である。
『方論』一巻は『傷寒論』の代表的処方二十方について、その適応症と作用機序を述べたものである。このように『傷寒論』の処方だけに解釈を加えたものとして、本書は現存書中で恐らく最初のものと思われる。また本書には成無己の著作中で唯一の自序も前付され、彼の医学理論の根幹を知ることができる。
さて『明理論』の内容であるが、成無己は十数種の書を引用して論説の根拠としている。引用回数の多い順に主な書名(カッコ内は回数)を挙げると、「経」(六六)・「内経」(一七)・『金匱要略』(八)・『針経』(八)・『難経』(四)・『脈経』(三)などとなる。「経」は『傷寒論』、「内経」は『素問』、『針経』は現在の『霊枢』に該当する書のことである。『傷寒論』の病症説明という本書の性格からして、『傷寒』『金匱』『脈経』の引用は当然だが、それらに次ぐ「内経」系医書の重視は『方論』や『注解』にも共通する特徴といえよう。
『方論』ではこの傾向がより著しく、『素問』の引用(二八回)が『傷寒論』の引用(一七回)を上回るほどである。また『素問』からの引用は、多くが同書の運気論に富む「至真要大論」の文であり、当傾向は『明理論』『注解』にも同様に見られる。そうした成無己の姿勢は『方論』の自序中で集約的に述べられている。
例えば彼は自序中で、『神農本草経』序録による上薬を君、中薬を臣、下薬を佐使とする説を否定する。そして代わりに、病を主治するのが君薬その補佐が臣薬、臣薬に応ずるのが使薬とする説を主張している。この主張は文体まで「至真要大論」の記載と同じである。またその後半にて解説される処方の大中小・緩急・奇偶の七分類(通行本では序の文頭で、大小・緩急・奇偶複を「七方」と呼ぶ)も、同じく「至真要大論」とそれへの王冰注からの引用が大部分である。
この七分類を彼は「七方」と呼び、同序の冒頭に述べる宣通・補瀉・軽重・渋滑・燥湿の「十剤」とともに、両処方分類の呼称は元・明・清の諸家に広く用いられた。ちなみに「十剤」は、『嘉祐本草』所引の陳蔵器『本草拾遺』序例文中で、薬物の作用をこの十種に総括したのがオリジナルの出典であり、それを成無己が処方分類に転用したにすぎない。さらに『方論』中には「本草」の引用が四回あるが、いずれも同じく『本草拾遺』序例文であり、個々の薬物条文からの引用は見えない。
ところで『方論』本文での処方解説の特徴は、自序中にも強調される薬物の四気(寒熱温涼)と六味(酸苦辛鹹甘淡)の徹底した応用にある。その論法はやはり「至真要大論」など『素問』の運気七篇に依拠しているが、恣意的引用や字句の改変等が少なくない。例えば桂枝湯の説明では「内経」を引き、「風淫の勝つ所、平するに辛を以てす」と記す。ところが本来の「至真要大論」文は、「平するに辛涼を以てす」であり、成無己が「涼」を省略していることがわかる。つまり当文を引用して説明したい桂枝の気味は辛熱なので、原文どおりに「辛涼」と引用すると、熱と涼で矛盾するからに他ならない。
一方、論説の出発点とする個々の薬物の気味においても、同様の操作がしばしば見られる。例えば麻黄には独特の渋味があり、『神農本草経』はそれを「味苦」と記すが、修治でもしない限り甘味は感じない。ところが『方論』では麻黄湯条で甘苦、小青竜湯条で甘辛、大青竜湯条では甘と麻黄の味を記す。その理由は麻黄の発表作用を、各所に彼が引く『素問』の「辛甘は発散させ陽となす」「辛は散ずる」にて説明するため、あえて甘味や辛味を付加したからに相違ない。
以上のように、成無己は従来の諸説を独自の観点から発展させ、それを一貫した論法で『傷寒論』の病症・処方の解釈に応用している。しかしそれらはあくまでも『傷寒論』という古典の解釈の一環としてであり、決して具体的な臨床面に言及するものではない。したがってその強引とも思われる論法は、当然ながら成無己自身も意識した上と考えられる。
三、後世への影響
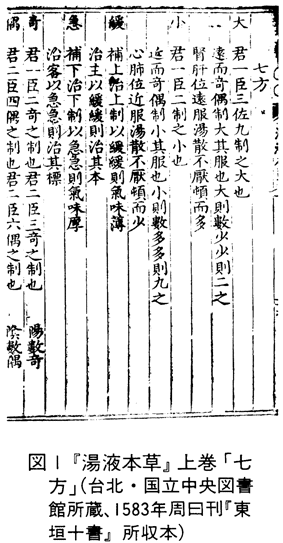
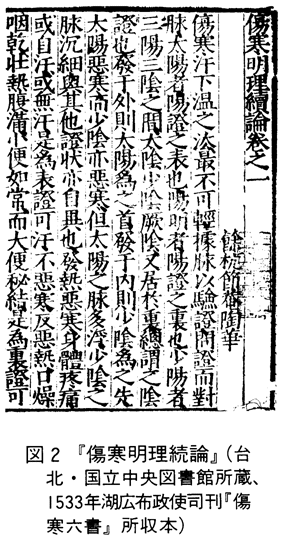 前述のごとく、『素問』など「内経」系医書の記載を根拠に説明する成無己の論法は、一見すると理路整然と体系だっている。しかも処方を作用面から「十剤」、構成薬から「七方」に整理し強調したのは彼が初めてである。それゆえこれらの論法や処方分類は『傷寒論』研究の枠を越え、以後広範な臨床医書の記載にも転用され発展してゆく。
前述のごとく、『素問』など「内経」系医書の記載を根拠に説明する成無己の論法は、一見すると理路整然と体系だっている。しかも処方を作用面から「十剤」、構成薬から「七方」に整理し強調したのは彼が初めてである。それゆえこれらの論法や処方分類は『傷寒論』研究の枠を越え、以後広範な臨床医書の記載にも転用され発展してゆく。
金元時代では成無己より四十年ほど後の劉完素や張元素、また王好古らの著作中に成無己の論法が色濃く反映されているのが見える。例えば張元素『医学啓源』上巻の「主治心法」や下巻の「用薬備旨」、また王好古『湯液本草』の「七方・十剤」(図1)などには、出典こそ記さないが明らかに成無己の所説を発展させた記述がある。
明・清代では『傷寒論』研究の隆盛にともない、多くの研究書が成無己の所説を出発点、あるいは批判的に継承している。さらには陶華の『傷寒明理続論』一巻(一四四五頃、図2)のように、『明理論』を補遺する目的の書まで出現している。後述のように明・清代にかけて十数回も『明理論』と『方論』が刊行されている事実も、また成無己の所説が歓迎されたことを物語るものといえよう。
他方、日本に成無己の著作が伝えられた時期は判然としていない。しかし南北朝時代の僧・有隣著『福田方』(一三六三頃)の引く『傷寒論』の注文が『注解』の文章であるから、少なくともそれ以前に舶載されていたことが知れる。『明理論』『方論』については同時代の記録に見えず、現在知られるのは慶長年間刊の古活字本からである。武田科学振興財団杏雨書屋蔵の同版には、慶長十五年(一六一〇)に曲直瀬玄朔が訓点を加えている。したがって『明理論』『方論』の日本での初刊はそれ以前で、玄朔も両書に目を通していたことがわかる。
後述するが、両書は江戸時代に四回刊行され、その内の三回までが江戸初の古活字版である。つまり江戸初期にやや流布したものの、両書の日本における影響は刊行回数から見ても中国のそれほどではない。その理由には、江戸中期からの『傷寒論』ブームで、「内経」医書の記載を論拠とする解釈法が強く排撃されたこと。江戸後期の主流を占めた考証学派の研究においても、『明理論』『方論』に多見されるような都合のよい論法が否定されたこと、などが背景にあるように思われる。
四、版本
『明理論』『方論』の現存版本を中国・日本の出版地別に、刊行年順で挙げると左記のようである。
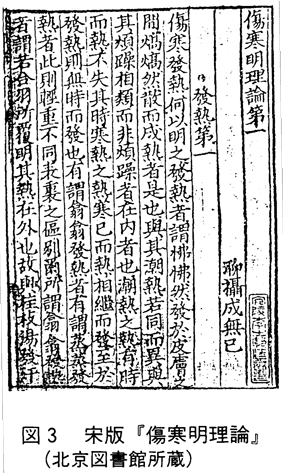
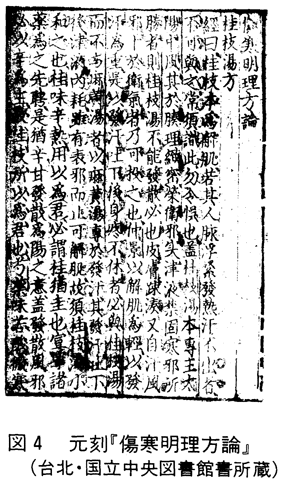 〔中国刊本〕[1][2]
〔中国刊本〕[1][2]
①宋刊本、北京図書館(図3)、湖南省中山図書館蔵。当版の刊年は定かでないが、あるいは王鼎の「注解傷寒論後序」にいう一一五七年頃の邢台刊本か。なお台北・国立中央図書館蔵の影宋写本の版式は図3と異なる。
②元刊本、台北・国立中央図書館蔵(図4)。清・黄氏士礼居旧蔵。『明理論』の目録と巻一前三葉、『方論』の自序・目録と後二葉を欠き、当該部分を影宋写本と旧写本にて補う。
③明刊本六種、安正堂刊本、巴応奎校補刊本(二巻補論二巻)、葛澄刊本、万暦二十九年(一六〇一)歩月楼刊『医統正脈全書』『傷寒全書』所収本、閔芝慶刪補刊本(附『傷寒闡要』七巻)、不詳明刊本。
④清刊本八種、常州双白燕堂陸氏刊本、同治年間刊本、光緒六年(一八八〇)掃葉山房刊本、光緒二十年(一八九四)成都崇文斎鄭氏刊『仲景全書』所収本、光緒二十二年(一八九六)湖南書局刊本、広州大文堂刊本、光緒三十三年(一九〇七)京師医局刊『医統正脈全書』所収本、不詳清刊本。
⑤民国刊本五種、民国元年(一九一二)江東書局石印本、民国五年(一九一六)千頃堂書局石印『仲景全書』所収本、民国十二年(一九二三)補刻『医統正脈全書』所収本、民国十八年(一九二九)受古・中一書店石印『仲景全書』所収本、民国二十五年(一九三六)鉛印『中国医学大成』所収本。
⑥現中国刊本三種、一九五五年商務印書館鉛印本、一九五七年上海衛生出版社鉛印本、一九八一年上海科学技術出版社鉛印本。
(なお本書は『四庫全書』にも収録される)
〔日本刊本〕
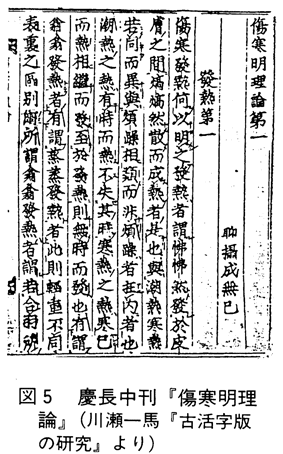
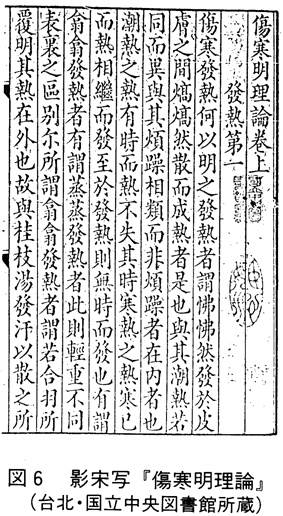 ①慶長十五年(一六一〇)前刊古活字白口本(図5)、武田科学振興財団杏雨書屋、大東急記念文庫蔵。当版と中国刊本②の影宋写本(図6)および後述の古活字版二種は、行数・字詰がともに同一。『経籍訪古志』[1]はその文字の精善なること明版の比にあらず、と評す。
①慶長十五年(一六一〇)前刊古活字白口本(図5)、武田科学振興財団杏雨書屋、大東急記念文庫蔵。当版と中国刊本②の影宋写本(図6)および後述の古活字版二種は、行数・字詰がともに同一。『経籍訪古志』[1]はその文字の精善なること明版の比にあらず、と評す。
②元和中(一六一五~一六二三)古活字白口本、宮内庁書陵部蔵(存巻三)。当版はあるいは前掲の慶長版と同版か。
③寛永元年(一六二四)梅寿刊古活字小黒口本、東北大学附属図書館、武田科学振興財団杏雨書庫ほか蔵。
④享保十三年(一七二八)洛陽万巻堂刊本、東北大学附属図書館、武田科学振興財田杏雨書屋ほか蔵。当版には林権兵衛らの刊記がある。
以上、現存の刊本は中国版が二十四種、日本版が四種を数えることができた。ちなみに楊守敬の『観海堂書目』には朝鮮活字本を記す。しかし同版の記録は他になく、かつ楊守敬が『留真譜』に載せる書影の書式等は、図5などの日本古活字版と完全に一致している。したがって岡西らも疑うごとく[1]、あるいは楊守敬が日本の古活字版を朝鮮の所刊と誤認したのかもしれない。
今回の復刻では以上の検討をふまえ、伊東定幹が訓点を施した享保十三年万巻堂刊本より、東北大学附属図書館蔵本を底本に影印した。なお伊東定幹(貞卿、紫霞)は江戸の医家で、他にも清・張倬の『傷寒兼証析義』三巻に句読を加え、同じく享保十三年に刊行したことが知られている。
ちなみに当享保十三年刊本は、厳器之の「傷寒明理論序」、成無己の「傷寒明理薬方論序」、張孝忠の「傷寒明理論序」の順に序を配し、『方論』を『明理論』の第四巻としている。しかし宋版や元版の構成から見ると、成無己の「方論序」は本来、『方論』の前に置かれるべきであろう。また張孝忠の「明理論序」は、元来が『注解』『明理論』『方論』の三書を南宋代に合刊した際の跋文であるので、書末に配すべき性格のものである。
文献
[1]岡西為人ら『宋以前医籍考』四七四-四八二頁、台北・古亭書屋、一九六九年初刊。
[2]中医研究院ほか『中医図書連合目録』二三七-二三八頁、北京図書館、一九六一年刊。