←戻る
真柳誠・小曽戸洋「漢方古典文献解説・28−金代の医薬書(その4)」『現代東洋医学』11巻2号99-105頁、1990年4月
漢方古典文献概説(28) 金代の医薬書(その4)
Medical texts in Jin period(4): Makoto MAYANAGI, Hiroshi KOSOTO (Department of History of Medicine, Oriental Medicine Research Center of the Kitasato Institute, Tokyo)
真柳誠・小曽戸 洋(北里研究所附属東洋医学総合研究所医史文献研究室)
今回は金代シリーズの締めくくりとして、金〜蒙古間の医家中、後世に最大の影響を与えた李東垣の著作を一括して紹介したい。
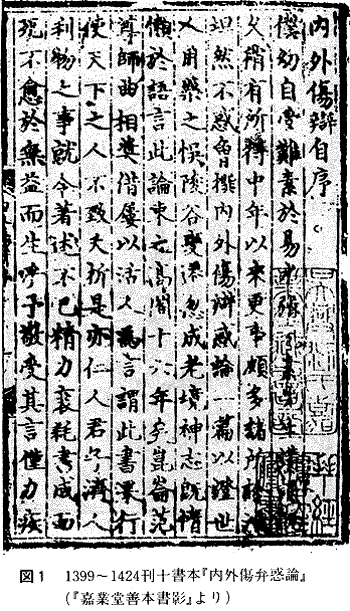 『内外傷弁惑論』(1247成)(図1)
『内外傷弁惑論』(1247成)(図1)
金元四大家の一人、李東垣の撰になる医論・医方の書。全3巻。書名を『内外傷弁』や『弁惑論』としたり、2巻本や1巻本とする版本もあるが、内容に相違はない。
東垣の伝は『元史』に収められている。しかし治験が主で伝自体はいたって簡略なので、硯堅の「東垣老人伝」(1267)[1]から要点を整理しておこう[2]。
李東垣の諱は杲、字を明之という。東垣はその号である。家は真定(河北省正定地区)の代々の資産家で、大定年間(1161〜89)初には真定や河間(河北省河間県)で一番の大地主だった。
幼い頃から群児と異なり冗談もいわず、長じては忠信に篤かった。かつて歓楽街に足を踏み入れたこともなく、接待で妓女に触られればその服を燃やし、妓女が無理に飲ませた酒は大吐したという。
学は『論語』『孟子』『春秋』などを修め、書院を建てて儒者を接待したり、金銭の援助をした。また泰和(1201〜08)の飢鍾では施しを与え、多くの民を救ったこともある。しかし母の病死に無力だったのを悼痛し、医名高い易水(河北省易水県)の潔古老人張元素に大金を払って師事し、数年でその法をことごとく会得した。
その後は済源(河南省済源県)で監税官となった。当地では疫病が流行しており、医者は誤治で死に至らしめるばかりだった。そこで一方を製し、秘かに衆目の集まる所に掲げた。本方で効のない者はなく、人々は仙人の所伝として石にきざんだが、東垣が医に精通するのを知る者はなかった。次いで東垣は戦乱を避けて汴梁(河南省開封県)に行き、ようやく医を以て公卿間に交遊した。しかしここも壬辰(1232)の変で蒙古兵の包囲にあい、その解除後に北渡して東平に寓居。郷里の真定に還ったのは甲辰(1244)年である。
東垣は晩年になって、その道を後世に伝える弟子を友人の周徳父に相談したところ、羅天益を紹介された。そして天益は貧苦にもかまわず、東垣に就いて喜び3年学んだ。
臨終に際し東垣は平素の著述の順次をそろえ、内容別に机にならべて天益にこう告げた。この書を汝に託すのは李杲・羅天益のためではない。天下後世のためである。けっして湮滅させてはならない。これを広め行わせよ、と。この時、東垣は年72、辛亥(1251)の2月25日であった。
以上の伝より、東垣は1180〜1251年の人とわかる。なおいくつかの事跡は年代を記さないが、筆者の考察によれば以下のようである[3]。
東垣は泰和2年(1202)に税務官として済源に赴任している[4]。すると張元素に師事したのは赴任前の数年なので、およそ1199〜1201年で東垣が20〜22歳の頃となろう。また金は蒙古の侵入で1214年に北京から開封に遷都したので、東垣が開封に逃れて医業を始めたのも、1214年以降の35歳を過ぎた頃と思われる。王好古が東垣に師事したのはこの期間である。
一方、1232年の壬辰の変で開封を離れ、故郷の真定に帰り着いた年を伝は1244年とする。しかし東垣は1243年12月の真定における治験を記録しているので[5]、実際は1243年の末頃らしい。さらに天益が東垣に師事したのを十数年間[6]、あるいは1243年に入門したとの説もある[7]。しかし前説では東垣が帰郷する以前の1238年頃から天益が師事したことになり、伝の記述と一致しない。そこで年月のある東垣の治験を各書に調査すると、1244〜46年間はまるでなく、1247〜49年の間に集中している。しかも大多数は天益が師の治験等を整理した『東垣試効方』中の記録である。ならば天益の入門は1247年頃の可能性が高く、東垣が没するまで少なくとも5年間は師事したと考えられる。なお東垣の『傷寒会要』(失)に寄せた元好問の序は[8]、東垣の子として執中の名を挙げるが、それ以外に記録は見えない。
さて『内外傷弁惑論』は現存する東垣の著作中、自序がある唯一の書である。1247年に記されたその自序には、草稿ができてから16年間そのままにしておいたという。すると東垣が53歳の1232年に、つまり壬辰の変の年に本書の基本的内容は完成していたらしい[9]。東垣はその後、戦乱を避けて北方の各地を巡りながら、自説に基づく治験をさらに重ねたのであろう。本書の「腎之脾胃虚方」には、1243年における下痢の治験が記されている[10]。そしてこれら草稿を整理し、本書を完成したのが自序の1247年、東垣68歳の時である。自分の学を世に伝えるため、羅天益を入門させたのもこの頃であるから、本書の完成と後継者の養成は東垣にとって同じ意味があったに相違ない。
本書は計26篇からなり、大きく3つの内容に分けられる。第1〜13篇は内傷証と外感証の弁別を中心とする論説で、本書名はこれに由来する。とりわけ第1篇の「弁陰証陽証」はその総説であり、壬辰の変で日々数千人が病死するのを目撃した体験から、外感と内傷を弁別する重要性が強い口調で説かれている。
第14〜21篇は各論部で、脾胃などの内傷が起る機序を論じ、各々に対応する処方と加減が挙げられている。その導入をなす第14篇の「飲食労倦論」では、陰火と呼ぶ脾胃の虚による発熱が提起される。そしてこれは外感による発熟とは違うので、『素問』の記載を根拠に温剤で陰火を治す方法を唱える。次いでこの見解から補中益気湯を掲げ、立方趣旨を詳細に解説している。次篇の「四時用薬加減法」でも四季の症状に応じた補中益気湯の加減が述べられ、東垣の本方に対する自信が窺える。
第22〜26篇は処々に方名を挙げるが、再び内傷の治療を述べた論説となっている。ただしここではそれまでの温補ではなく、内傷病も時には寒薬や利水・吐下の剤が必要、と強調される。そして末篇の「説病形有余不足当補当瀉之理」は、その篇名が示すように、本書全体を概括した結論となっている。なお著名な処方では、補中益気湯以外に朱砂安神丸や生脈散・葛花解醒湯などの出典が本書である。
本書は自序の1247年に初刊されたとの見解もあるが[11]、根拠もなく相当に疑わしい。筆者はこの点について、後述の『脾胃論』『蘭室秘蔵』とほぼ相前後し、元代の1276年に羅天益が刊行したと考えている[3]。現存の版本では広東省中山図書館に元刊本が所蔵されるが、未見につきその当否は不詳。本書はその後、遼藩の簡王が明初の1399〜1424年間に初刊した『東垣十書』に収録されて以来、中国・朝鮮・日本にて翻刻が重ねられている。図1は劉翰怡『嘉業堂善本書影』(1929)所載の図。同書目録はこれを元刊本と記すが、同版他書との比較から筆者は上述の初刊十書本と審定した[12]。なお本書の江戸刊本は『和刻漢籍医書集成』に影印収録してある。
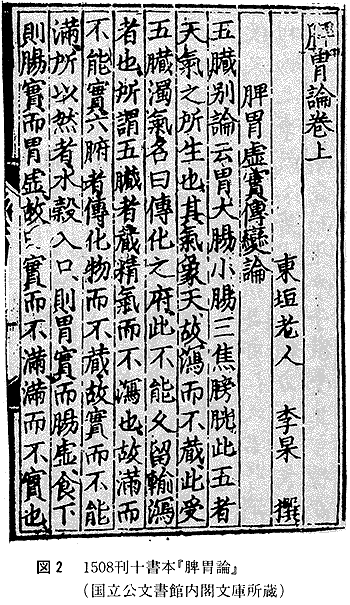 『脾胃論』(1249成)(図2)
『脾胃論』(1249成)(図2)
李東垣の撰になる医論・医方の書。全3巻。2巻や4巻にする版本もあるが、いずれも内容に相違はない。本書に東垣の自序はないが、友人の元好問は次のような序を寄せている。
かつて壬辰の変の五六十日間、百万人近くの人が飲食労倦で没したが、皆これを傷寒のためと思っていた。その後、東垣が内外傷と飲食労倦傷を弁じた論を見て、世医の誤りを知った。学に暗いと、かくも人を誤るものである。東垣の著論はすでにこれを指摘しているが、世医はにわかに理解できない。そこで、さらに『脾胃論』を著した。東垣の両著は、千年の惑を去るものといえよう。もしこの書が刊行されるなら、もはや壬辰のごとき薬禍は起るまい。己酉(1249)7月、遺山・元好問序。
この序にいう東垣が先に著した「内外傷と飲食労倦傷を弁じた論」とは、『内外傷弁惑論』に他ならない。したがって東垣は同書を1247年に完成の後、本書の整理に着手[13]、元好問序の1249年に本書を完成したとみなせる。東垣はこの時70歳、没前2年である。なお元好問(1190〜1257)は遺山と号し、金代の文人。東垣の患者でもあり、壬辰の変以後の逃避行を6年間ともにしている。先に東垣の『傷寒会要』(失)に序(1238)を草したほか、自から『集験方』(1242自序、失)を編纂したり、周候『周氏衛生方』(失)にも序を寄せている[14]。
『脾胃論』の内容は、医論36篇と方論63篇より構成されている[15]。全体は内傷と外感の弁別治療を論じた前著を一歩進め、書名のごとく脾胃の重視を強く主張している。東垣流が補土派と呼ばれる所以である。本書の多くは帰郷後に書きためていた100近い旧稿を、最晩年の約2年で寄せ集め、加筆して一書としたしたのであろう。それゆえ一部の論旨に重複が見えたり、前著の転載であったり、やや繁雑な感は否めない。
しかし名論も多い。巻頭の2篇、「脾胃虚実伝変論」「脾胃勝衰論」はその筆頭といえよう。また書末の2篇では体力の衰えを嘆き、精神的養生を述べたりしており、晩年の様子が窺える。前著にない治験では、「調理脾胃治験」中に数例がある。その内の2例は1248年のもので、衰弱にもかかわらず臨床と著述を行っていたことがわかる。この時期の治験例は他に『東垣試効方』中に多見されるが、そのうち本書にふさわしい例のみが選ばれたらしい。
なお現在の日本でも常用される半夏白朮天麻湯は、本書に載る頭痛の症例に東垣が創方したもので、方意も詳しく解説されている。
本書の初刊は羅天益が後序を記した1276年と考えられる。この天益序刊の元刊本は現伝しない模様。現存の版本では1399〜1424年間に初刊された『東垣十書』所収本が最古で、武田科学振興財団杏雨書屋に架蔵(貴418)されている。同書屋の蔵書目録はこれを1276年の羅天益刊本と記すが、同版他書との比較より、筆者は初刊の十書本と審定した[12]。本書はこれ以降、十書本として中国・日本・朝鮮で翻刻が重ねられている。図2は現存第2の古版で、国立公文書館内閣文庫所蔵の正徳3年(1508)熊氏梅隠堂刊十書本である。なお江戸刊の十書本は『和刻漢籍医書集成』に影印収録した。
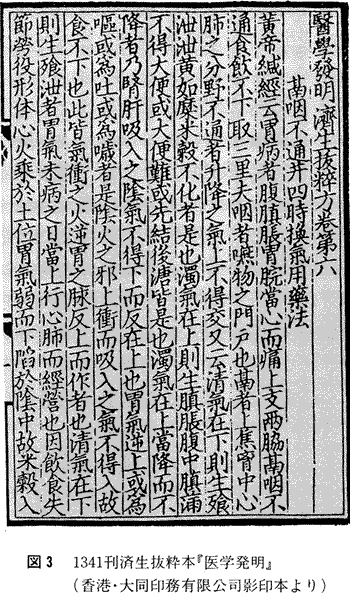 『医学発明』(1249頃成)(図3)
『医学発明』(1249頃成)(図3)
李東垣の撰になる医論・薬論・医方の書。現1巻。『東垣試効方』の硯堅序(1266)は、東垣の著作の一つとして本書名を挙げる[16]。かつて元刊の9巻本の記録もあったが[17]、現存しないようである。丁光迪は本書の明抄善本の記載より、成立は『内外傷弁惑論』の完成(1247)以降、書名は羅天益の修学が終えたことを記念しており、天益が本書を刊行したという[18]。天益の入門は1247年頃で、伝には3年喜び学んだとあるから、一応の修学終了は1249年頃となる。したがって本書の成立年もこの頃と考えられる。
現存するのは、元刊『済生抜粋』(1341)の巻6に収められる1巻の節略本(図3)が最古。また『医統正脈全書』(1601)所収の1巻本などもあるが、内容はいずれも大同小異。本邦では済生抜粋本を底本に甲賀通玄が訓点を加え、享保19年(1734)に2巻本に改め翻刻している。いま済生抜粋本より、本書の篇目を以下に掲げておく。
隔咽不通並四時換気用薬法、本草十剤、中風同従高墜下、嘔欬気喘、飲食労倦論、四時用薬加減法、滑脈生頽{痜+頁}疝、瀉之則脹已汗之則瘡已、大陰所至為於満中満霍乱吐下、諸脈按之無力所生病証、諸脹腹大皆属抄熱、諸嘔吐酸皆属於熱、諸痿喘嘔今立熱喘寒喘二方、諸脈有関有格有覆有溢、損其腎者益其精、上部有脈下部無脈其人当吐食傷大陰也、幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥秘、脚気論、中風有三、肺寒則面白生痰喘咳搐唾、五邪相干、淹疾瘧病、百病在気在血、治病必須求責。
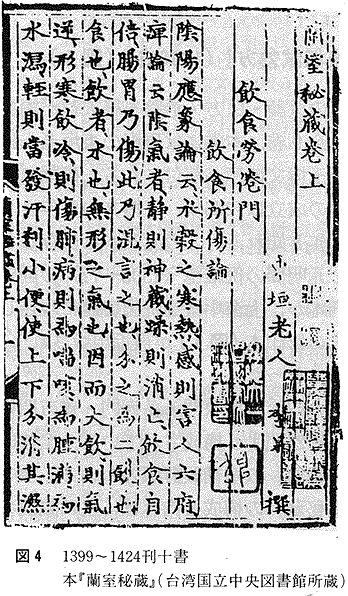 『蘭室秘蔵』(1251成)(図4)
『蘭室秘蔵』(1251成)(図4)
李東垣の撰になる方論書。全6巻。2巻や3巻とする版本もあるが、計21篇の病門構成などの内容に相違はない。
本書に東垣の自序はなく、羅天益の序(1276)が唯一である。これによると本書6巻は先師東垣先生の所輯であり、刊行して天下万世に広めたいという。すると本書の初刊は1276年と知れるが、東垣が完成させた年はわからない。実際のところ、本書は東垣が臨終で天益に遺した草稿を基本に、東垣の指示に従い天益が書物の体裁に編纂したものである[3]。したがって本書の内容は東垣のものであるから、成立は彼が没した1251年とするのが妥当である。本書名は『素問』などに記される黄帝の書庫「霊蘭の室」に由来し、もちろん羅天益の命名であろう。
本書は病門別に論と処方を集成した方論書である。その病門は第1篇の飲食労倦門に始まり、次いで中満腹脹門・心腹痞門・胃院痛門など脾胃の内傷による病門が続き、さすがに東垣らしい。全篇はこのように内科の病門のみならず、眼耳鼻口歯などの五官科、そして婦人科・外科・小児科の順に病門がたてられている。
本書に収載の処方はその病門別方論書の性格ゆえ、東垣の他著よりはるかに多い。およそ280首にのぼる収載方は、多くが東垣の創方にかかる。そのうち本書を出典とする処方では、腰痛門の(当帰)拈痛湯などが著名である。
本書は前述のように1276年に羅天益が初刊したが、この元刊6巻本は恐らく現存しない。他の元版としては、北京図書館と台湾国立中央図書館に3巻本が所蔵されている。いずれも未見だが台湾所蔵本は旧北平図書館蔵本で、その記録によれば明刊本の可能性も高い[19]。またかつて元刊本の所蔵記録は多いが[20]、その一つ『平津館鑑蔵書籍記』が記す元刊本の版式と書名の特徴は、明・正徳3年刊の十書本と同一である。
本書も十書本として、中国・朝鮮・日本ともに刊本は多い。図4は1399〜1424年間の初刊十書本で、台湾国立中央図書館の所蔵である。江戸刊の十書本は『和刻漢籍医書集成』に影印収録した。
 『東垣試効方』(1266成)(図5)
『東垣試効方』(1266成)(図5)
東垣の医論・医方・治験を羅天益が編集した書、全9巻。本書には硯堅の東垣老人伝と序、および王博文の序が前付される。硯堅の序年より本書の成立は1266年、王博文の序年より初刊は1280年と知れる。この元刊本は伝存しない。ただし元明間の倪維徳(1303〜77)の翻刻した明初刊本が、上海中医学院図書館に現存している。その影印本(図5)が最近出版され[1]、利用が容易となった。
本書の内容は薬象門・各病門・雑方門に大別され、計24門より構成されている。全体的には『蘭室秘蔵』の増補改訂版といえる。なぜなら『蘭室秘蔵』の構成と内容は、主に東垣の遺言と遺稿に従ったため、一部の病門は方のみで論がなかったり、1門中に2論や3論あったり、方論書としての体裁をやや欠いていた。そこで天益が師事中に筆録した治験・処方・医論を増補し、再編して本書を作成したものと考えられるからである。
したがって本書には東垣の前掲諸書と重複する内容も多いが[21]、本書のみの医論や治験も少なくない。また旧態が失われていないので、今後は東垣の代表著作として、充分に研究・利用されるべき書といえよう。
『傷寒会要』(1238成)
東垣の撰になる傷寒研究書。元好問が本書に寄せた1238年の序文が伝わるのみで[8]、刊行された形跡もない。その序は「傷寒則著会要三十余万言」というので、かなり大部だったと思われる。また内容については、「其説曰。傷寒家、有経禁・時禁・病禁。此三禁者、学医者人知之」と記す。『脾胃論』の「用宜禁論」篇には、時禁・経禁・病禁・薬禁などの語があり、本書との関連も考えてよかろう[22]。
『用薬法象』(1251前成)
東垣の撰になる薬論書。全1巻。李時珍『本草綱目』序例は本書名を挙げ、「祖潔古珍珠嚢、増以用薬凡例・諸経嚮導・綱要活法、著為此書」と説明する。硯堅の「東垣試効方序」が東垣の著作として記す『薬象論』も同一書と思われる。これら書名の単行刊本は伝わらず、成立は東垣の没年以前とするしかない。
一方、王好古の『湯液本草』には、「東垣先生薬類法象」「東垣先生用薬心法」の各篇がある。その細目中には李時珍の言と符合するものがあり、多くの内容は『本草綱目』序例に「李杲曰」として引かれる文と一致する。さらに『東垣試効方』巻1の薬象門もほぼ同内容である。つまり本書のおよその内容は、『湯液本草』『東垣試効方』『本草綱目』などから窺うことが可能である。
なお『東垣処方用薬指掌珍珠嚢』2巻(1468初刊)や[23]、それとほとんど同内容の『珍珠嚢』1巻(明初刊『医要集覧』所収)は、本書の系統に後人が増補改訂したものとみられる。
以上、東垣の自著とみなしうる7書をとり挙げてみた。このほか可能性が高い書に、『脈訣指掌病式図説』1巻がある。この書は1601年に序刊の『医統正脈全書』に収められており、校訂した呉勉学は朱丹渓の著作としている。しかし中には壬辰の変を目撃した記載があるので、多紀元胤は東垣の著作と考定した[24]。また岡西為人は本書に付された序の年を1248年と推測するが[25]、恐らく当を得ない[3]。したがって成立年は不詳。内容は前後に相当な混乱があり、元胤はこれを明の本屋のしわざと見ている。
さらに『活法機要』1巻(『済生抜粋』および『医統正脈全書』所収)も、東垣の著作とされることがある。しかしこれが劉完素『素問病機宜保命集』3巻の節略たることは、すでに当金代シリーズ(その2)で指摘した。また熊均の『医学源流』は東垣の書として『瘡瘍論』『医説』の2書も挙げるが、それらや真偽を論ずべき資料は伝存しない。
注および文献
[1]この伝は『東垣試効方』(明・倪維徳校刊本、上海科学技術出版社影印、1984)に前付されている。
[2]硯堅の「東垣老人伝」は李濂『医史』巻5にも引用されている。『東垣試効方』の伝で意味不明な字句については、嘉靖26年(1547)序刊の『医史』(国立公文書館内閣文庫所蔵)の引用文によった。
[3]真柳誠「『内外傷弁惑論』『脾胃論』『蘭室秘蔵』解題」、『和刻漢籍医書集成』第6輯、東京・エンタプライズ(1989)。
[4] 『東垣試効方』巻9の「時毒治験」による。
[5] 『蘭室秘蔵』自汗門と『東垣試効方』巻9に見える。
[6]羅天益『衛生宝鑑』に寄せた王酴の序(1283)に記される。任応秋『中医各家学説』(上海科学技術出版社、1980、p.72)、裘沛然ら『中医歴代各家学説』(上海科学技術出版社、1984、p.116)、李聡甫ら『金元四大医家学術思想之研究』(北京・人民衛生出版社、1983、p.158)、李雲ら『中医人名辞典』(北京・国際文化出版公司、1988、p.557)も同説を記すが、根拠は挙げていない。
[7]丁光迪『中医各家学説・金元医学』、江蘇科学技術出版社(1987)、p.277。この説も根拠を記さないが、東垣の帰郷年を天益の入門年と考えているらしい。
[8]多紀元胤『医籍考』、北京・人民衛生出版社(1983)、p.412。
[9]上掲注[6]所引『金元四大医家学術思想之研究』(p.160)は、1247年から単純に16年を引いて1231年を草稿の完成とする。しかし著述の契機が壬辰の変にあるのだから、それは当を得ない。
[10]この治験は『脾胃論』の「調理脾胃治験」にも転載されている。
[11]賈維誠『三百種医籍録』、ハルピン・黒竜江科学技術出版社(1982)、p.265。
[12]真柳誠「『東垣十書』解題」、『和刻漢籍医書集成』第6輯、東京・エンタプライズ(1989)。
[13]ただし本書末尾の「遠欲」と題する文は、「残六十有五」というので、1244年に書かれている。つまリ一部には従来の草稿を混えており、1247年よりこれらの整理と著述を開始した、と考えられる。
[14]上掲文献[8]、p.679。
[15]ただし『済生抜粋』巻7に収められた本書は大幅に節略された1巻本である。
[16]上掲注[1]所引文献、p.16。
[17]岡西為人『宋以前医籍考』、台北・古亭書屋(1969)、p.1004。
[18]丁光迪『東垣学説論文集』、北京・人民衛生出版社(1984)、p.44。
[19]当版には「明善堂」「安楽堂」の蔵書印記があり、この両印記は杏雨書屋所蔵の初刊十書本の『脾胃論』にもある。(2005,6,15追記:安楽堂は康煕帝第十三子・允祥(避諱前は胤祥、1686〜1731)の蔵書堂号である。允祥は康熙61年(1722)に怡親王に封ぜられ、豊富な善本古籍・美術品を収蔵した。以後代々も怡親王を世襲して蔵書をほこったが、咸豊11年(1861)に怡親王・載垣が西太后の計略で自尽(自殺)に処され、このとき収蔵品が巷間に流出した)。
[20]上掲文献[17]、p.1000。
[21]『済生抜粋』巻16の『蘭室秘蔵』節略本もその書名下に「東垣先生試効」とやや小さな字で記すので、当時の『蘭室秘蔵』は『東垣試効方』と大差なかったのかも知れない。
[22]『四庫全書総目』(北京・中華書局影印、1981、p.870)は王好古の『比事難知』に説明して、東垣の『傷寒会要』は失われたので、『此事難知』から内容を窺うしかないという。しかし元好問の序から推すかざり、両書の内容に共通点はないように思える。
[23]本書の朝鮮翻刻本は官内庁書陵部に2部現存している。
[24]上掲文献[8]、p.209。
[25]岡西為人『中国医書本草考』、南大阪印刷センター(1974)、p.158。
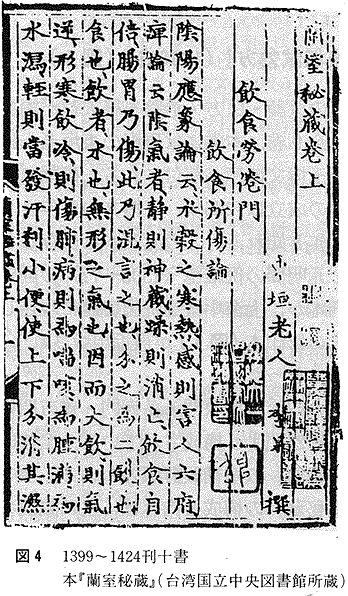 『蘭室秘蔵』(1251成)
『蘭室秘蔵』(1251成)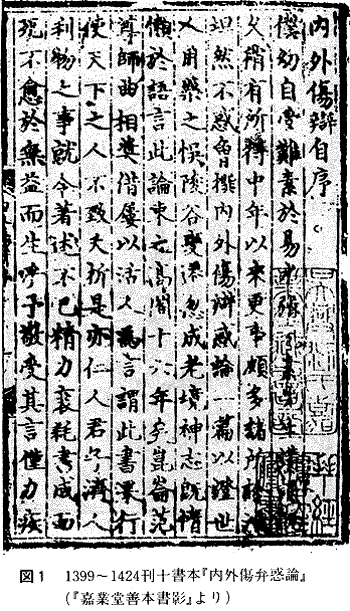 『内外傷弁惑論』(1247成)(図1)
『内外傷弁惑論』(1247成)(図1)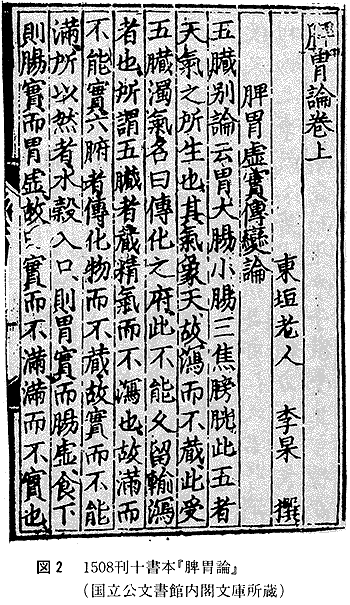 『脾胃論』(1249成)(図2)
『脾胃論』(1249成)(図2)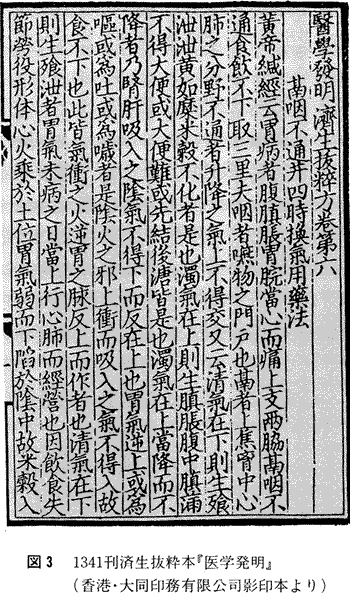 『医学発明』(1249頃成)(図3)
『医学発明』(1249頃成)(図3)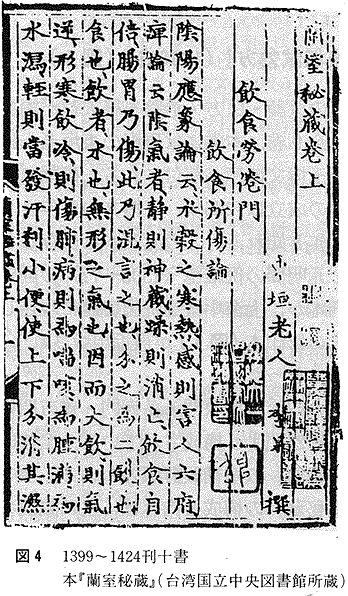 『蘭室秘蔵』(1251成)(図4)
『蘭室秘蔵』(1251成)(図4) 『東垣試効方』(1266成)(図5)
『東垣試効方』(1266成)(図5)