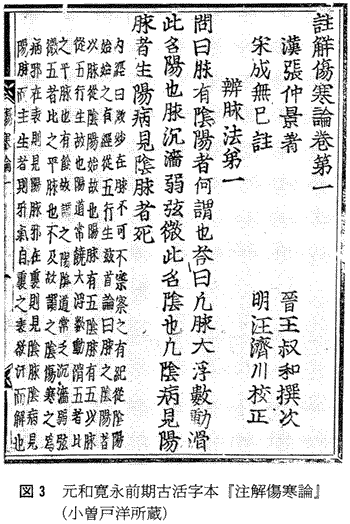←戻る真柳誠・小曽戸洋「漢方古典文献解説・25-金代の医薬書(その1)」『現代東洋医学』10巻3号101-107頁、1989年7月
漢方古典文献概説(25) 金代の医薬書(1)
真柳 誠・小曽戸 洋(北里研究所附属東洋医学総合研究所医史文献研究室)
Medical texts written in the Jin period (1):
Makoto MAYANAGI, Hiroshi KOSOTO
(Department of History of Medicine, Oriental Medicine Research Center of the Kitasato Institute, Tokyo)
北満州奥地のツングース系民族・女真族は、1114年その支配者・遼を満州の地から追い、翌年、首領・阿骨打(金の太祖)は帝位について国号を金と称した。1125年、第2代の太宗は遼を滅ぼし、翌年には宋の首都汴京(開封)を陥落させ、江北の地を占領。1127年、徽宗・欽宗父子をはじめとする多くの補虜、厖大な戦利品を獲て北に帰った。
補虜を免れた徽宗の子・康王は、河南に逃れて即位し、南宋第1代の高宗となった。1138年には臨安(杭州)への遷都を余儀なくされた。以後、元に滅亡されるまで臨安に都を置き、江南の地を制した宋朝の時代を南宋(1127-1279)という。この南宋時代の医薬書については、前回まで6回にわたって詳述した。
一方、江北の地を制した金は、第3代煕宗の1142年、南北の国境を定めて宋と和睦したが、クーデターによって第4代皇帝の座についた海陸王は、1153年に燕京(北京)へ遷都。1161年には大軍をもって南を攻めたが失敗した。第6代章宗以後は国力が衰え、宋の反撃に苦渋した。第7代衛紹王のとき蒙古の侵略を受け、第8代宣宗のとき燕京から開封へ都を退き、さらに河南の地を転々とし、ついに第9代哀宗の1234年、蒙古と宋の連合軍によって滅ぼされた。金(1115-1234)とはこの金王朝の支配した時代である。だから、年代的には南宋時代の前期と重複している(年表参照)。
この時代、すなわち江北の金国人として活躍した著名な医家に、成無己・劉完素・張元素・張子和らがいる。今回と次回では、これらの人々の著作について成書年代を追って紹介しよう。
『傷寒明理論』(1142序)(図1)
成無己の撰になる『傷寒論』研究書1)全4巻であるが、正確には『傷寒明理論』3巻(『明理論』と略)と『傷寒明理方論』1巻(『方論』と略)からなる。成無己の伝を古くに記したものはないが、厳器之の「傷寒明理論序」(1142)および「注解傷寒論序」(1144)、また王鼎の「注解傷寒論後序」(1172)や張孝忠の跋文(1205)などから次のようなことがわかる。
成無己は聊摂(山東省陽穀県)の出身。家は代々の儒医で、その学術は「性識明敏、記聞該博」「議論該博、術業精通」などと評された。無己の著作は『明理論』『方論』と『注解傷寒論』(『注解』と略)しか知られていない。『明理論』『方論』は無己が78歳の1142年に成った後、1157年頃に邢台の某氏が初刊したという。『注解』は無己が80歳の1144年に成り、1172年に王鼎が初刊している。これから逆算すると、成無己の生年はおよそ北宋の治平元年(1064)頃となる。また王鼎は金の正隆元年(1156)頃に、臨潢にて90余歳の成無己が治療するのを見たと記すので、没年は1156年以降だろう。
なお成無己の出身地の聊摂はもと北宋の地であるが、1125年以後は金朝の地となっている。したがって呉勉学などは無己を宋人とするが、その活躍年代からすると金人とするのが妥当である。また本邦では、一般に成「無已(ムイ)」 と呼びならわされているが、漢語の意味からはオノレナシの訓になる「無己(ムキ)」と呼ぶのが適切に思われる。ちなみに『千金翼方』孫思邈序中に「余幼智蔑聞、老成無己、……」なる用例がある。現在の中国でも「無已(ムイ)」とする例をみない。
『明理論』3巻は上巻と中巻に各々18病症、下巻に14病症の計50病症を項目に立て、それぞれについて診断・病理・治方を論じている。これらの病症はいずれも『傷寒論』中から選択されたもので、本書の30数年前に朱肱が著した『傷寒活人書』に似た体裁となっている。以下に本書の編目を掲げる。
〔巻上〕 発熱・悪寒・悪風・寒熱・潮熱・自汗・盗汗・頭汗・手足汗・無汗・頭痛・項強・頭肱・胸脇痛・心下満・腹満・少腹満・煩熱
〔巻中〕 虚煩・陳煩・懊憹・舌上白胎・衂・噦・咳・喘・嘔吐・悸・渇・振・戦慄・四逆・厥・鄭声・{言+嚴}語・短気
〔巻下〕 揺頭・瘈瘲・不仁・直視・鬱冒・動気・自利・筋惕肉{日+閏}・熱入血室・発黄・発狂・霍乱・畜血・労復
『方論』1巻は『傷寒論』の代表的20処方について、その適応症と作用機序を述べている。このように『傷寒論』の処方だけに解釈を加えたものとして、本書は現存書中でおそらく最初のものと思われる。以下に『方論』の編目を掲げておく。
傷寒明理薬方論序・桂枝湯・麻黄湯・大青竜湯・小青竜湯・大承気湯・大柴胡湯・小柴胡湯・梔子豉湯・瓜蔕散・大陥胸湯・半夏湯・茵蔯蒿湯・白虎湯・五苓散・理中圓・四逆湯・真武湯・建中湯・脾約圓・抵当湯
また本書には成無己の著作中で唯一の自序(記年はない)も付され、彼の医学理論の根幹を知ることができる。すなわちその序で、処方はその作用面から宣・通・補・瀉・軽・重・渋・滑・燥・湿の10タイプに分けられるとし、これを「十剤」と命名している。さらに構成薬の面からは大中小・緩急・奇偶に分け、これを「七方」と命名している2)。「十剤」「七方」の処方分類の呼称は、張元素・王好古をはじめとして、以後の金・元・明・清の諸家に広く用いられた。しかしいずれも成無己の説がオリジナルではなく、「七方」は『素問』至真要大論の記載とその王冰注、「十剤」は陳蔵器『本草拾遺』の序例文からの転用である。
『明理論』『方論』の現存刊本には、諸図書目録などによれば次のようなものがある(清以降の版本はすこぶる多い。いま繁を避けて省略する)。
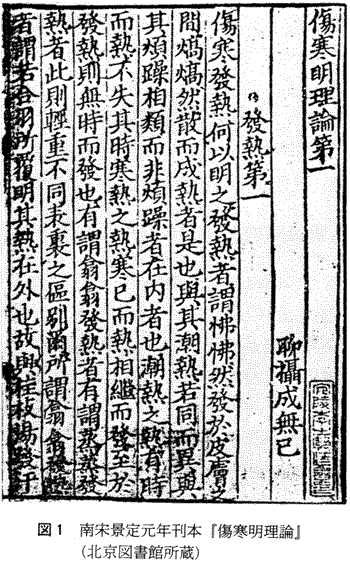 〔宋刊本〕 北京図書館に『明理論』の宋刊残欠本が現存する(図1)。馮懐徳3)によれば、本版は南宋の景定元年(1261)に建安の慶有堂が刊行したもので、『明理論』の巻上中が原刻、『明理論』巻下と『方論』は清の写本で補配してあるという。この宋刊部分の版式は台湾・国立中央図書館所蔵の影宋写本と異なるので、あるいは別の宋刊本がかつてあったのかも知れない。なお『中医図書連合目録』は湖南省中山図書館所蔵の宋刊本を著録するが、その仔細は不詳。
〔宋刊本〕 北京図書館に『明理論』の宋刊残欠本が現存する(図1)。馮懐徳3)によれば、本版は南宋の景定元年(1261)に建安の慶有堂が刊行したもので、『明理論』の巻上中が原刻、『明理論』巻下と『方論』は清の写本で補配してあるという。この宋刊部分の版式は台湾・国立中央図書館所蔵の影宋写本と異なるので、あるいは別の宋刊本がかつてあったのかも知れない。なお『中医図書連合目録』は湖南省中山図書館所蔵の宋刊本を著録するが、その仔細は不詳。
〔元刊本〕 台湾・国立中央図書館所蔵。清末の大蔵書家の一人、黄丕烈の旧蔵書である。『明理論』の目録と巻1前3葉、『方論』の自序・目録と後3葉を欠き、当該部分を影宋写本と旧写本にて補配する。本版については張鈞衡の『適園蔵書志』などにも記録がある。
〔明刊本〕 ①嘉靖42年(1563)年葛澄刊本。②嘉靖44年(1565)巴応奎校補刊本。③万暦29年(1601)刊『医統正脈全書』所収本。④安正堂刊本。⑤閔芝慶刊本。①は葛澄の言によれば宋版を底本に翻刻したらしい。しかし『経籍訪古志』はこれを「此本訛誤頗多、固非善本」と酷評し、また③は①に基づくとも指摘している。②も宋版を底本としており、馮3)は字句のほとんどが北京図書館の宋刊本と一致するという。
〔日本刊本〕 ①慶長15年(1610)前古活字白口本。②元和中(1615-23)古活字白口本。③寛永元年(1624)梅寿刊古活字小黒口本。④享保13年(1728)洛陽万巻堂・林権兵衛ら刊本。①は武田科学振興財団杏雨書屋と大東急記念文庫、②は宮内庁書陵部(存巻3)、③は東北大学附属図書館ほかに各々所蔵されている。以上①~③の古活字版3種は行数・字詰がともに同一で、かつ前述の元刊本に補配される影宋写本とも一致する。さらに『訪古志』はその文字の精善なること明版の比にあらずと絶賛するので、あるいは宋刊本を底本とするのかも知れない。④本は江戸の医家である伊藤定幹が訓点を施したものである。昨年、筆者ら編の『和刻漢籍医書集成』第1輯に影印収録したので、披見は容易。
ちなみに楊守敬の『観海堂書目』には朝鮮活字本を記録する。しかし同版の記録は他になく、また楊守敬が『留真譜』に載せる書影の書式等は日本古活字本と完全に一致している。したがって岡西為人も『宋以前医籍考』で疑うごとく、あるいは楊守敬が日本の古活字本を朝鮮の所刊と誤認したものかと疑われる。
『注解傷寒論』(1144序)
成無己の撰になる『傷寒論』の注釈書。全10巻。『傷寒論』の全文、すなわち弁脈法・平脈法・{疒+至}湿暍脈証篇から三陰三陽病篇と陰陽易差後労復病篇、および可不可の諸篇にわたり注釈を加えたものとして、本書はおそらく最初の、少なくとも現存最古の文献である。ただし末尾の可不可計8篇については、正文の多くが三陰三陽の各篇に重出しているため、それらを省いてかなり簡略化されている。その状態を正文の文字数について『(宋板)傷寒論』と比較すると下表のようである4)。
| 『傷寒論』 | 『注解傷寒論』 |
| 不可発汗篇 | 893 | 482 |
| 可発汗篇 | 1412 | 152 |
| 発汗後篇 | 1169 | 28 |
| 不可吐篇 | 170 | 0 |
| 可吐篇 | 165 | 108 |
| 不可下篇 | 2100 | 1184 |
| 可下篇 | 1625 | 237 |
| 発汗吐下後篇 | 3056 | 0 |
以上のように、『注解』は必ずしも『傷寒論』の正文の全体と構成を保持しているわけではない。しかしそれが逆に利用に便利なため、本書は成本『傷寒論』あるいは単に「成本」とも通称され、『傷寒論』そのものに代わるテキストとして後世に計り知れない影響を遺すこととなった。かつその注釈は内経系医書、とりわけ「素問」の至真要大論など「運気七篇」の所説に立脚し、『傷寒論』の研究・解釈に革新的な一面を拓いた。しかも成無己注自体、あたかも『素問』の主冰注と同様、今や古典的性格すらあり、『傷寒論』研究に不可欠なものとなっている。
この成無己注にはいくつかの特徴がある5)。一つは正文の解釈に『素問』『針経(今の『霊枢』)』『難経』『脈経』『玉函経』『金匱要略』『千金要方』『外台秘要方』など、諸古典の記載を広く引用して客観性を与えようとしていること6)。いま一つは処方の解説において、構成薬の気味を基礎とする薬理説の応用と、薬能・方能の簡称化が一貫してなされていることである。後者の論旨には問題点が多々あるが、いわゆる「金元薬理説」のさきがけとして、劉完素・張元素以下の諸医家に与えた影響は無視できない7)。
本書の初刊は『明理論』の解説に記したごとく、金の大定12年(1172)と思われる。この初刊本は伝わらないようであるが、その後も歴代にわたり翻刻が重ねられた。現代までの版本が30種を越すことも、本書が後代いかに歓迎されたかを物語ろう。よって以下には、明代までの現存版を紹介することにする。
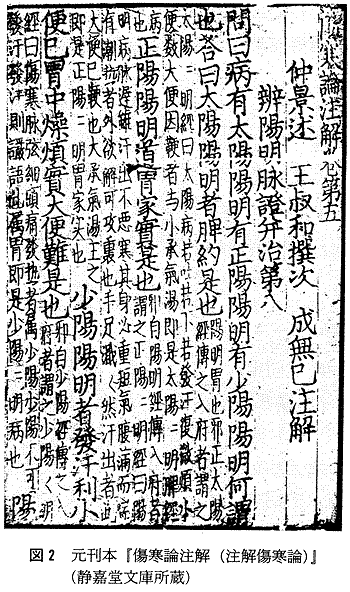 〔元刊本〕 元刊本は東京の静嘉堂文庫と中国の北京大学図書館とに伝わっている。
〔元刊本〕 元刊本は東京の静嘉堂文庫と中国の北京大学図書館とに伝わっている。
静嘉堂文庫本(図2)は陸心源の旧蔵本である。現存は巻4の途中から巻10末尾までの残欠本で、巻9の末葉のみ匡郭が大きい。毎巻頭と末尾の書名はすべて「傷寒論注解」となっている。以上の点および版式は、天保6年(1835)に多紀氏の躋寿館が元版を基に影刻したものと完全に一致している8)。多紀氏が所蔵していたこの元版9)の現所在は不明。『訪古志』によれば、後述の明版3種は同版に基づくが、各々誤謬が多いという。
北京大学図書館本は元初の所刊とされる完帙で、運気の図も巻頭に付されるというが未見10)。あるいは孫星衍の『平津館鑑蔵書籍記』が著録する元・大徳8年(1304)孝永堂重刊本と同版か。
〔明刊本〕 現在知られる明刊本は、以下のようである。
①正徳4(1509)年、熊宗立種徳堂刊本11)。宮内庁書陵部に毛利高標が文政中、幕府に献上したものが所蔵されている。同書は巻1と2を欠き、また補写も混える。『訪古志』によれば、かつて多紀家にも同版があったという。
②嘉靖24年(1545)、汪済川刊本。東北大学付属図書館、武田科学振興財団杏雨書屋ほか所蔵。『訪古志』は本版の底本を前掲の元刊本と認めている。本版はかつて『四部叢刊』に影印収録され、現存それに基づく鉛印本が中国・香港・台湾より出版されており、入手は容易。
③嘉靖39年(1560)、熊氏種徳堂春軒刊本。江戸医学館旧蔵本が国立公文書館内閣文庫に所蔵されているほか、武田科学振興財団杏雨書屋にも架蔵されている。『訪古志』は本版の底本を上掲の汪済川本とする12)。しかし本版の熊氏種徳堂本と前掲①の版とがいかなる関係にあるかは未詳。
④万暦27年(1599)、趙開美刊「仲景全書」所収本。江戸幕府の紅葉文庫旧蔵本が国立公文書館内閣文庫に架蔵されているほか、中国・台湾にも現存する。『訪古志』は本版の底本も前掲の元刊本であるという。本版は北京の人民衛生出版社が影印出版しており、入手は容易である(*2004年4月6日補記:近年の調査結果より次の新事実が明らかになった。上記の「仲景全書」は北京の中国中医研究院所蔵本が趙開美第一版、瀋陽の中国医科大学所蔵本と台北の故宮博物院所蔵本が趙開美第二版、東京の内閣文庫所蔵本は明末清初の模刻本である)。
⑤万暦29年(1601)、呉勉学編刊「古今医統正脈全書」所収本。『明理論』などと一括して同時に単行もされており、現存本は多い。『訪古志』では本版も元版の翻刻とするが、上掲の趙開美「仲景全書」で添付された「医林列伝」を転録するので、趙本も参照されたと思われる。
⑥崇禎(1628-44)頃、程衍道刊本。台湾国立中央図書館所蔵。程衍道は『外台秘要方』の刊行でも知られる明清間の医家。本版の存在はこれまで斯界に知られていない。成無己注を他版のごとく細字双行とせず、大字の1字落としにする点、また版心に刻工名を刻したり、字様・版式等を嘉靖頃の仿宋版風にする点など、程衍道の作為が窺われる。
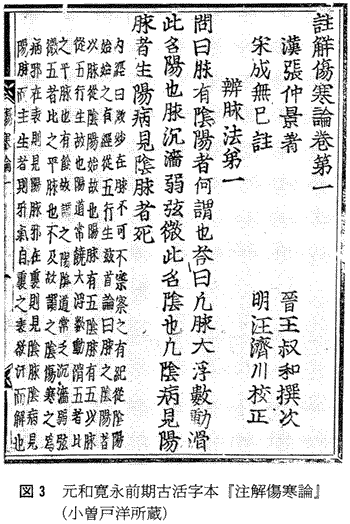
以上、元・明の刊本をとり挙げてきたが、その善本性で元版の右に出るものはない。『注解』の正文は成無己の改編を経てはいるが、『傷寒論』の字句の校勘には必須文献であるから、元版もしくは躋寿館影元本の今後の影印復刻が期待される(*補記:躋寿館影元本は1992年3月に『和刻漢籍医書集成』第16輯に影印収録した)。
次に本書の日本への伝播について触れておこう。本書は南北朝時代(1333-92)、すでに渡来していたらしい。というのは、有隣の『福田方』(1362成)に『傷寒論』と明記のうえ引用があり、「注云」として成無己注まで引用されているからである13)。おそらく元刊本が舶載されていたのであろう。ただし有隣が直接見たのは伝鈔本の可能性もある。
江戸時代前半、一般に『傷寒論』というと、この『注解傷寒論』、もしくはそれに基づくテキスト(成本)を指すほど、本書は広くわが国に流布した。わが国最初の『傷寒論』の出版は、元和寛永前期頃(1615-33)に開版された汪済川本に基づく古活字版『注解傷寒論』(図3)を嚆矢とする14)。万治2年(1659)を初版とする和製『仲景全書』には、『注解』の代わりに張卿子の『集注傷寒論』が編入されたが、いわゆる宋版は除かれて翻刻されなかった15)。また同じく万治頃の版と考えられる活字本『傷寒論』も、『注解』より成無己注を削除して作製されたテキストである16)。後に何万部と刷られ市場を独占した香川氏小刻本『傷寒論』も、同類のものである。
こうして江戸後期には、成無己注を去った成本『傷寒論』という奇妙なテキストの横行する現象が生じ、『注解』自体は古方派の排撃にあって日本では埋没してしまった。多紀氏の江戸医学館では『注解』の善本が世にないため、前述のように家蔵の元刊本を天保6年(1835)に影刻した。しかしこれもさほど多くは現伝しない。以上述べたように、『注解』自体の和刻本は、元和寛永古活字版と天保影元本の2版にとどまる。中国では清朝だけでも10数版をゆうに上回り、その差は両国の『傷寒論』研究の相違を端的に物語るものといえよう。
注および文献
1)真柳誠「『傷寒明理論」『傷寒明理薬方論』解題」『和刻漢籍医書集成」第1輯、エンタプライズ(1988)。
2)通行本では序の冒頭で、大小・緩急・奇偶複を「七方」と呼んでいる。
3)馮懐徳「点校叙言」『傷寒明理論闡釈』p.5、四川科学技術出版社(1988)。
4)小曽戸洋「『傷寒論』『金匱玉函経』解題」『(元・鄧珍本)金匱要略』所収、燎原書店(1988)。
5)任応秋『中医各家学説』p.94、上海科学技術出版社(1980)。
6)ただし、成無己は各典籍から自説に都合のよい部分のみをいく度も引用する傾向があり、牽強付会ともとれる点も少なくない。またその引用文には字句の省略や改変が多々見られるが、希には所引文献の校勘に利用できるものもある。
7)真柳誠「『傷寒明理論』『注解傷寒論』に見る薬理説の検討」、日本薬学会第105年会口演抄録(1984)。
8)この躋寿館影元版は、巻1~3についてのみ巻頭・巻末の書名を「註解傷寒論」としている。
9)森立之は『訪古志』に注記して、これは紙墨や字体からみて元版ではなく、明代に元版を基に翻刻したものと考えている。
10)北京大学図書館には、李盛鐸が明治31~34年に駐日清国公使として赴任した時や、その前後に購入した日本旧蔵の医書が多い。ただしこの元初刊本は李氏蔵本ではないので、『訪古志』著録の多紀氏旧蔵本とは別版と思われる。
11)岡西(『中国医書本草考』p.233)は、熊宗立の活躍年と当版の刊年に隔たりがあることから、「正徳」が「正統」の誤りでなければ、当版は熊宗立が以前刊行したものの再刻本ではないかと疑う。
12)岡西(『宋以前医籍考』p.366)は当版の存在を知らず、このため『訪古志』の記す熊氏明(種の誤植)徳堂本を正徳4年刊本と誤認し、正徳刊本が嘉靖の汪済川本に基づけるはずがない、と失考している。
13)小曽戸洋「『福田方』組成文献の解析」『日本医史学雑誌』33巻1号(1987)。
14)関信之ら「日本最古の『傷寒論』の版本-古活字版」『日本東洋医学雑誌』39巻4号(1989)。
15)真柳誠「別本『仲景全書』の書誌と構成書目」『日本医史学雑誌』34巻1号(1988)。
16)本版は国立公文書館内閣文庫に多紀氏旧蔵本が1本存する。処方の薬名下にその気味を記すことなどより『注解』から作製されたことがわかる。
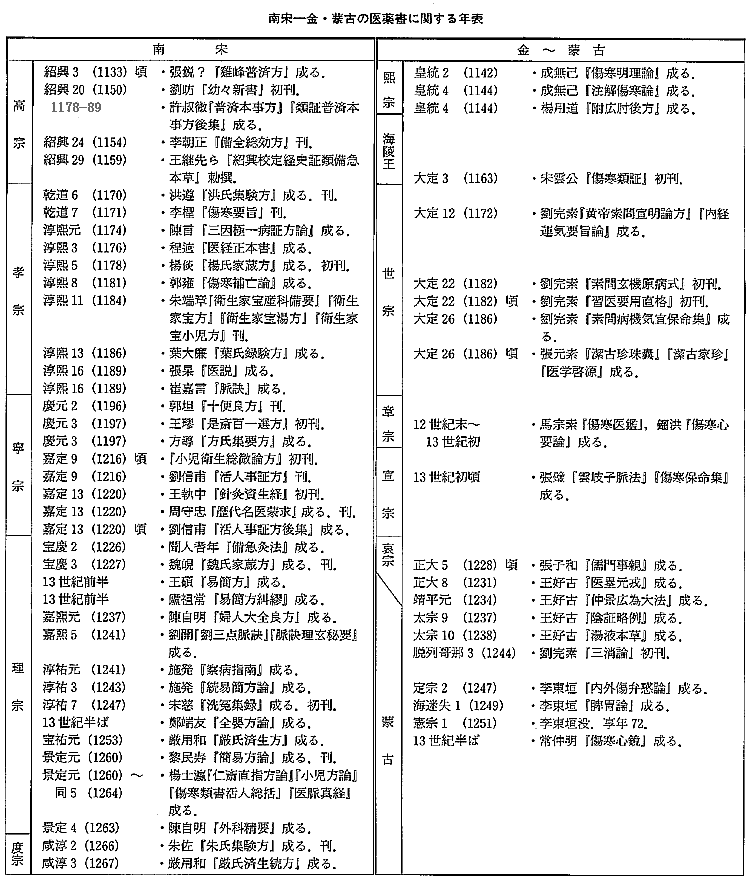
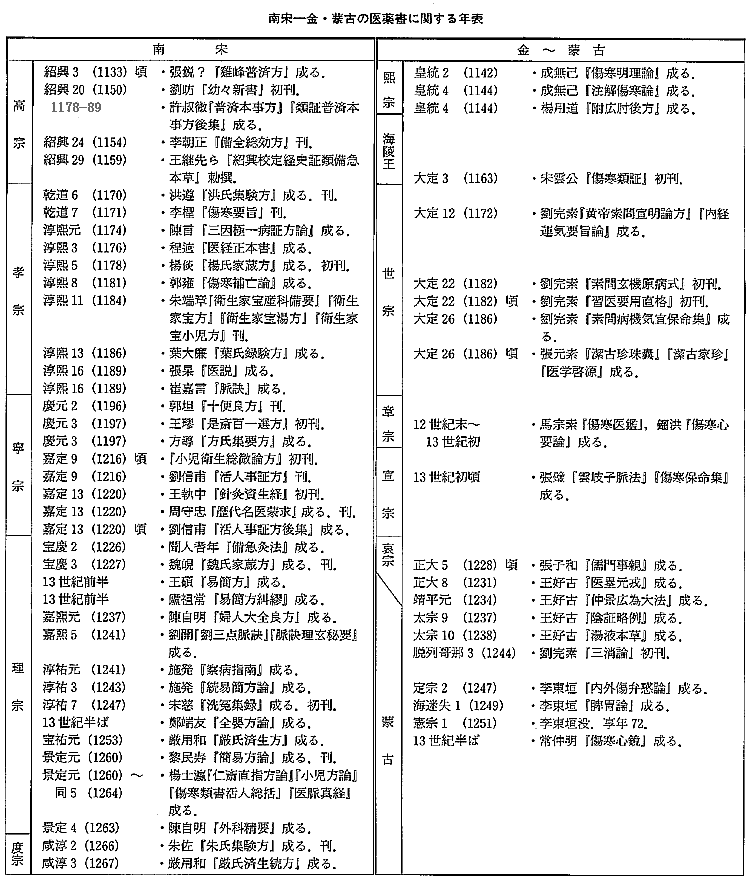
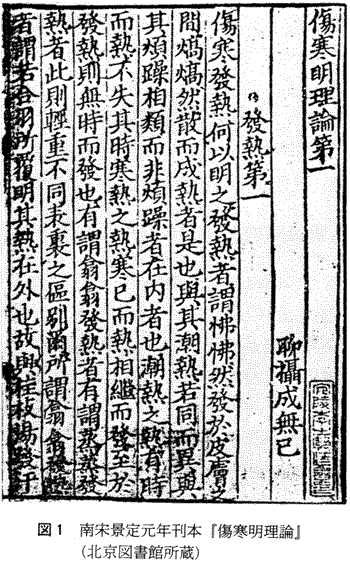 〔宋刊本〕 北京図書館に『明理論』の宋刊残欠本が現存する(図1)。馮懐徳3)によれば、本版は南宋の景定元年(1261)に建安の慶有堂が刊行したもので、『明理論』の巻上中が原刻、『明理論』巻下と『方論』は清の写本で補配してあるという。この宋刊部分の版式は台湾・国立中央図書館所蔵の影宋写本と異なるので、あるいは別の宋刊本がかつてあったのかも知れない。なお『中医図書連合目録』は湖南省中山図書館所蔵の宋刊本を著録するが、その仔細は不詳。
〔宋刊本〕 北京図書館に『明理論』の宋刊残欠本が現存する(図1)。馮懐徳3)によれば、本版は南宋の景定元年(1261)に建安の慶有堂が刊行したもので、『明理論』の巻上中が原刻、『明理論』巻下と『方論』は清の写本で補配してあるという。この宋刊部分の版式は台湾・国立中央図書館所蔵の影宋写本と異なるので、あるいは別の宋刊本がかつてあったのかも知れない。なお『中医図書連合目録』は湖南省中山図書館所蔵の宋刊本を著録するが、その仔細は不詳。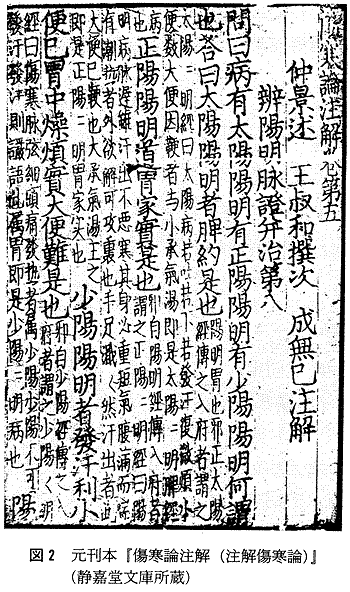 〔元刊本〕 元刊本は東京の静嘉堂文庫と中国の北京大学図書館とに伝わっている。
〔元刊本〕 元刊本は東京の静嘉堂文庫と中国の北京大学図書館とに伝わっている。