 福井市城戸ノ内町の一乗谷には、南北約二キロメートルにわたって戦国大名・朝倉氏の遺跡がひろがっている。朝倉氏は文明三年(一四七一)以来、ここに居城を中心とした城下町をかまえた。天正元年(一五七三)の八月十三日、五代目城主の朝倉義景は敦賀で織田信長軍に大敗、十五日に一乗谷へ逃げ帰ったが、十八日には信長軍の焼き打ちにあう。一乗谷は二十日まで燃え続けたという。今ここは「一乗谷朝倉氏遺跡」の名で、国の特別史跡に指定されている。
福井市城戸ノ内町の一乗谷には、南北約二キロメートルにわたって戦国大名・朝倉氏の遺跡がひろがっている。朝倉氏は文明三年(一四七一)以来、ここに居城を中心とした城下町をかまえた。天正元年(一五七三)の八月十三日、五代目城主の朝倉義景は敦賀で織田信長軍に大敗、十五日に一乗谷へ逃げ帰ったが、十八日には信長軍の焼き打ちにあう。一乗谷は二十日まで燃え続けたという。今ここは「一乗谷朝倉氏遺跡」の名で、国の特別史跡に指定されている。真柳 誠
“Tang-ye Bencao” Excavated from the Asakura Family Site
by Makoto MAYANAGI
Burnt fragments
of a medical manuscript were excavated from the Asakura(朝倉)Family
Site in 1985. From the study of the characters seen on the fragments, the
following conclusions have been drawn :
l) The fragments
are parts of a manuscript of the "Tang-ye Bencao(湯液本草)",
a book of materia medica written by Wang Haogu(王好古)
in the Yuan dynasty of China.
2) There is a
high possibility that this manuscript of the "Tang-ye Bencao" was
a faithful copy based on the "Dongyuan Shishu(東垣十書)"
edition published by the Xiongshi Meiyintang (熊氏梅隠堂)
in 1508, during the Ming dynasty of China.
3) For all of
the 36 fragments on which characters could be seen, a corresponding part
of the Xiongshi edition could be found, and every character has
been deciphered correctly. Assumptions were made about the characters and
the corresponding parts of the Xiongshi edition for those fragments
which could not be torn off.
4) For the latter
part of the Muromachi period in Japanese history, a relationship was found
between the acceptance of Chinese medicine through a group of books of
the Xiongshi edition, the cultures of the Asakura family
and the commercial town Sakai(堺),
and the activities of some intellectuals.
緒言
一九八五年、福井市の一乗谷朝倉氏遺跡より医書写本の焼片塊が出土した。当焼片に見える墨跡の釈文[1]にもとづき、筆者と小曽戸洋はこれを元・王好古の『湯液本草』の一部と判定し、再釈文および概要が発掘を当時担当された清田善樹により報告された[2]。小曽戸もまた概要を報告した[3]。
しかし、その後も調査研究の進展にともなう新知見があいつぎ、出土焼片の残存部位と墨跡の釈文に重ねて訂正の必要性を認めるに至った。かねて当発見から明らかにしうる、室町後期における中国医学受容の側面についても考察を加えることにした。
一 医書焼片の出土
 福井市城戸ノ内町の一乗谷には、南北約二キロメートルにわたって戦国大名・朝倉氏の遺跡がひろがっている。朝倉氏は文明三年(一四七一)以来、ここに居城を中心とした城下町をかまえた。天正元年(一五七三)の八月十三日、五代目城主の朝倉義景は敦賀で織田信長軍に大敗、十五日に一乗谷へ逃げ帰ったが、十八日には信長軍の焼き打ちにあう。一乗谷は二十日まで燃え続けたという。今ここは「一乗谷朝倉氏遺跡」の名で、国の特別史跡に指定されている。
福井市城戸ノ内町の一乗谷には、南北約二キロメートルにわたって戦国大名・朝倉氏の遺跡がひろがっている。朝倉氏は文明三年(一四七一)以来、ここに居城を中心とした城下町をかまえた。天正元年(一五七三)の八月十三日、五代目城主の朝倉義景は敦賀で織田信長軍に大敗、十五日に一乗谷へ逃げ帰ったが、十八日には信長軍の焼き打ちにあう。一乗谷は二十日まで燃え続けたという。今ここは「一乗谷朝倉氏遺跡」の名で、国の特別史跡に指定されている。
遺跡の正式な発掘は一九六七年に開始され、一九八五年には第五一次の調査がなされた。その六月、遺跡のほぼ中央で町屋・武家屋敷が密集した一画の建物跡の裏手、三箇の大甕が埋設されていたカメピットSX三一一五付近の焼土層から、ひとかたまりの炭化紙片が出土した。かろうじて分離された焼片のうち、三六枚(写真1)にはわりあいはっきりと墨跡が残っている。当時、発掘調査を担当した清田氏は、そのうち三四枚の釈文(図1)から、これを「金元時代の医家の説をも取り入れた医学書(冊子本)の一部」[1]と推定した。
当焼片の写真と釈文を携えた清田氏が、鑑定の依頼に小曽戸氏を訪ねてこられたのは一九八七年十一月九日のことである。これに筆者も同席し、一見して小曽戸氏ともども頭をかかえこんだ。李東垣の名と臓腑・経絡にかんする文字があるので、たしかに金元流の医書のようにみえる。
しかし、かりに中国書だとして、李束垣(一一八○〜一二五一)から一乗谷が焼かれた一五七三年までの間にあらわれた書は数多い。逆に日本の著述ならば、この間の伝存書はかなり少なく、場合によっては佚書の可能性も考えられたからである。絶望的とはいえ、焼片の史料価値と清田氏の熱意に動かされ、とりあえず手許の中国医書から照合してみようと、まず大きく見当をつけることにした。
 いくつかの理由から医方書の可能性があることも話しあったが、図1釈文(23)の「不用酒」だけは腑におちない。酒を医療に用いるのは古くからあるが、あえて用いないと記すのはかなり不自然なのである。とすれば瀉下薬の大黄など、気を降下させるという薬物を、気を上昇させるという酒で加工するのが適当かどうか、の記述ではあるまいか。この説は李東垣の師である金代の張元素あたりの提唱[4]らしく、金元以降の本草書なら瀉下薬の記述に「不用酒」があっても不思議ではない。
いくつかの理由から医方書の可能性があることも話しあったが、図1釈文(23)の「不用酒」だけは腑におちない。酒を医療に用いるのは古くからあるが、あえて用いないと記すのはかなり不自然なのである。とすれば瀉下薬の大黄など、気を降下させるという薬物を、気を上昇させるという酒で加工するのが適当かどうか、の記述ではあるまいか。この説は李東垣の師である金代の張元素あたりの提唱[4]らしく、金元以降の本草書なら瀉下薬の記述に「不用酒」があっても不思議ではない。
筆者はそこで代表的金元本草の『湯液本草』からあたることにして、手近な版本で大黄の頁を開いてみた。たしかに「不用酒」の句がいくつかあり、その前後には図1釈文の(12)(18)(24)とほぼ合致する字句がある。さらに前後の薬物の条文にも一致する字句が見つかった。また(20)「珎(珍)」と(24)「象」など文頭の文字は、『湯液本草』のみにある引用文献名の略称であることに気づいた。しかも(3)(12)(14)(17)(18)(20)のように二行で隣合わせにある文字は、いずれも『湯液本草』の原文では一六字かそれに相当するスペースを置いて出現している。つまり焼片は『湯液本草』にまちがいなく、およそ一行一六字で筆写されていたことまで、その日のうちに判定することができた。
この鑑定にもとづいた釈文の訂正と補足、および各焼片の『湯液本草』における該当部位が、さっそく清田氏により追加報告された[2]。筆者も検討を続けていたが、のち焼片の筆写底本に関する知見が加えられた。また焼片を実見する機会にも恵まれ、より完全な該当部位の確定と釈文が可能となった。
二 『湯液本草』
宋以降の中国書は多く刊本を介して日本に伝来している。刊本は復刻を重ねるたびに字句や版式が変化していくので、焼片の釈文にも筆写の底本とした版本系統が明らかとなれば都合がよい。しかし、これを論定するまえに、『湯液本草』と筆者の王好古[5]についても簡単にふれておく必要があるだろう。
王好古は号を海蔵、字を進之といい、いまの河北省趙県の出身。はやくから経学に通じ、進士に挙げられている。のち医をこころざし、張元素と李東垣に師事した、金末から元にかけての時期を代表する医家である。しかし正式な伝は残されておらず、生年・享年ともに不明であるが、およそ一二〇〇年以前の生れ、一二四八年以降の没と推定できる。著作は『湯液本草』(一二四八年成立)のほか、『伊尹湯液仲景広為大法』四巻(一二三四年成立)、『陰証略例』一巻(一二三六年成立)、『医塁元戎』一二巻(一二三七成立)、『此事難知』二巻(一二四八年または一二六四年の成立)、『{ヤマイダレ+斑}論萃英』一巻(成立年不詳、節略本)が伝存している。
『湯液本草』の湯液とは煮出した汁をいう。『史記』殷本紀に、伊尹が殷の湯王に仕えるため料理人から身をおこした故事がみえる。また『漢書』芸文志・方技に、当時あった医書の一つとして『湯液経法』三二巻があげられている。そこで王好古は、伊尹がいにしえの本草にもとづいて『湯液経法』を著述、後漢の張仲景がそれを敷衍し、傷寒治療の大法たる『傷寒論』を著した、と考えた[6]。『湯液本草』や『伊尹湯液仲景広為大法』は、この歴史に溯る意味をこめた書名なのである。
『湯液本草』の源泉は師・張元素の『潔古珍珠嚢』であると自序にいう。さらに兄弟子であり師でもある李東垣の『用薬法象』ほか、計四四余家の引用と王好古の薬能論から成っている。それら引用文献名は「珍」「象」と略記され、焼片判定の手掛りとなった。本書の最終稿は一二四八年に完成しているが、すぐに刊行されたかどうかは記録がない。
 現存するもっとも古い版本は元の一三三五年刊本で、中国に二本所蔵されているというが[7]、未見につき内容や刊年の真偽はわからない。筆者が調査したところでは、朝鮮版・日本版を含めた他版はすべて、明初に編纂された叢書『東垣十書』の所収本系統である[8]。この調査が問題解明の第一歩であった。というのも出土焼片は一乗谷が焼かれた一五七三年以前の刊本を介した写本だから、底本となった版本の候補をしぼることができるのである。以下、候補となりうる全版本について、必要な書誌事項を列記してみよう。
現存するもっとも古い版本は元の一三三五年刊本で、中国に二本所蔵されているというが[7]、未見につき内容や刊年の真偽はわからない。筆者が調査したところでは、朝鮮版・日本版を含めた他版はすべて、明初に編纂された叢書『東垣十書』の所収本系統である[8]。この調査が問題解明の第一歩であった。というのも出土焼片は一乗谷が焼かれた一五七三年以前の刊本を介した写本だから、底本となった版本の候補をしぼることができるのである。以下、候補となりうる全版本について、必要な書誌事項を列記してみよう。
(a)明・遼藩第一版:『東垣十書』の初版で、明・太祖の第一五子、簡王(朱植)の編。簡王が荊州(いまの湖北省)に改封された一三九九年以後、没する一四二四年以前の刊行。この版の『湯液本草』は現存しないが、同版の他書からみて一紙二〇行、一行一七字と推定される。巻数は不詳。(*1995年4月27日に北京・中医研究院図書館の子21-1298・2巻3冊・行17字本『湯液本草』を実見、右図)では一乗谷の焼片は、もともと右のどの系統の本を筆写したのだろうか。まず出版情況をみよう。(d)以外はいずれも準政府刊行物であり、そのころ日本にまで伝来する可能性があるとは、にわかに推論できない。それにたいして(d)は市販書である。この熊宗立らの出版した医書群は日本に古渡り本の現存が多く[9]、当時かなり輸入されたらしい。伝存書数も中国をはるかにうわまわる。しかも周知のように、日本の最初(一五二八)と第二番目(一五三六)の印刷医書は、ともに熊宗立編刊書の復刻。くわえて第二番目の出版は一乗谷でなされている。とすればまず(d)ではないかと疑うべきだろう。(b)明・遼藩第二版:簡王の孫、靖王の再版。刊行は靖王の子、恵王が序を記した一四八四年。この版の『湯液本草』も現存しないが、同版の他書からみて一紙二〇行、一行一八字と推定される。巻数は不詳。
(c)明.遼藩第三版:恵王の子、光沢王が一五二九年に再々版したもの。『湯液本草』は一紙二二行、一行二〇字で全二巻。
(d)明・熊氏梅隠堂本:一五〇八年の刊行。熊氏梅隠堂は明初に多数の医書を出版した書賈、熊宗立の一族と推定される[9]。『湯液本草』は一紙二〇行、一行一七字で全二巻。
(e)李氏朝鮮・乙亥活字本:内医院による一四八八年刊本[10]。現存するのは『湯液本草』下巻のみで、二巻ないし三巻本。一紙一八行、一行一七字である。
(f)李氏朝鮮・整版本:およそ中宗後半(一五二九〜四四)頃の内医院刊本[8]。『湯液本草』は一紙二〇行、一行二〇字で全二巻。
一方、出土焼片は一行がおよそ一六字で筆写されていた。清田氏は再報告で[2]、さらに一紙二〇行で書写されていたことも解明し、そこから筆写本のどこが焼け残ったかを推定している。焼片は罫線のない筆写本だから、行数・字詰めは不定であってもよい。それなのに一紙二〇行・一行一六字と一定していることは、書式にまで気くばりして書写したことを窺わせる。あるいは原本の書式そっくりに写したのであろうか。
ところが上述の各版本に、一紙二〇行・一行一六字のものはない。ただし『東垣十書』のなかでも、『湯液本草』だけは例外だった。大多数の版本は、文章や各薬物の条文の一行目だけ行頭から書き出し、次行からは一字落として記すのである。それで実際には、各行の大部分が一文字少ない字数となっている。いま二〇行・一七字の(d)、あるいはそれと同じ書式と推定される(a)と、同一の書式による写本があったとしよう。そして一六字の部分のみ焼片として残存した、と仮定しよう。そうすると、焼片が一紙二〇行・一行一六字の写本と判断された理由の説明がつく。
(a)の『湯液本草』は残念ながら現存しない(追記:上図の1点が北京に現存していた)。そこで、国立公文書館内閣文庫にただ一つ現存する(d)の『湯液本草』二巻と、焼片写真および釈文をつきあわせてみた。見開いたかたちの内閣文庫本上で、焼片の文字に該当する部分を線で囲むのである。結果は明瞭だった。典型例を図2〜5に示そう。いずれも綴目を中線にして、左右ほぼ対称である。冊子本が焼け残るとすると、ごく自然な形といえるだろう。


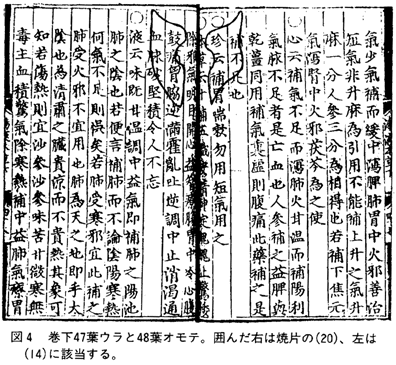

こうして墨跡が認められた三六枚の焼片はすべて、図2の巻下三六葉ウラから、図5の巻下五三葉オモテまでに該当部分を見出すことができた。いずれも綴目を中線にして左右三・五行、しかも行の上二文字目から八・五文字目までである。単純に計算して、第三六葉ウラから五三葉オモテまでの字数は約五四〇〇。その断片三六枚の文字が、みな一定の相関関係をもって右の範囲内に収まっている。このようなことは、決して偶然には起りえない。焼片となった写本が、(d)の熊氏梅隠堂本に限りなく近い書式で筆写されていたことが明白となった。
ただ残された問題が一つある。(a)の『湯液本草』は現存しないにもかかわらず、伝存する『湯液本草』以外の(a)(d)の『東垣十書』所収本は、書式と巻数・葉数淡完全に一致することである。したがって、(d)はこの範囲内において(a)の忠実な復刻と判断され、(a)の『湯液本草』も(d)のそれと同じ書式だったと推定できる。そこで(a)系統から焼片の写本がつくられた可能性も検討すべきだが、肝心の(a)本『湯液本草』がない。
残された方法は一つ、(a)(d)所収の各書が今日まで伝承されてきた経緯を調べ、その情況証拠から推論するより他にない。
(a)の所収書は上海中医学院図書館に『局方発揮』と『内外傷弁』が各一本[11]、台湾の国立中央図書館に『蘭室秘蔵』が一本[12]、武田科学振興財団杏雨書屋に『医経溯{サンズイ+回}集』と『脾胃論』が各一本[13]、それぞれ現存する[14]。上海中医学院の二書は、かつて呉蹇(一七三三〜一八一三)[15]の拝経楼にあり、のち劉承幹(一八八二〜一九六三)[16]の嘉業堂をへて現在に伝えられた[17][18]。杏雨書屋の『医経溯{サンズイ+回}集』には丁申(〜一八八〇)・丁丙(一八三二〜一八九九)[19]の蔵書印「八千巻楼所蔵」があり、同書屋の『脾胃論』とともに「明善堂覧書画印記」「安楽堂蔵書」の印記[20]もある。台湾中央図書館所蔵の『蘭室秘蔵』には、「韓縄大一名煕字仔藩読書印」「韓縄大印」「煕」「仔藩」「仔藩審定」など同一人の印記と、「馮唐孫敬閲」の墨書がある。このように以上の五本すべてに中国人旧蔵の証拠を多々認められるが、日本人の所作と考えられる装訂や書き入れ、また蔵書印記もない。したがって、いずれの書も二〇世紀前半まで中国にて伝承されたと判断できる。
一方、(d)の所収書は日本の内閣文庫にひと揃いの『東垣十書』として一〇本[21]、杏雨書屋に『(新刊東垣十書)脾胃論』が一本[22]、北京の中国中医研究院図書館に『新刊束垣十書内外傷弁』が一本[23]、それぞれ現存する[24]。内閣文庫の一〇本は江戸幕府の紅葉山文庫(楓山秘府、御文庫)旧蔵書で、御文庫へは寛永十五年(一六三八)以前に入庫している[25]。杏雨書屋本と中医研究院本は内題や刊年など以外の書誌情報がなく、伝承経緯を知ることができない。
以上のごとく、現存する(a)所収書に日本で古くから伝承されたものはなく、(d)所収書は日本での伝存本数が多い。(a)の伝承情況には、地方政府の刊行であることが関係しているかも知れない。まして出版地が内陸の荊州となれば、日中交易を担った沿岸の商人が入手する可能性はさほど高くないと思われる。他方、(d)は民間の出版であり、当然ながら一般にも市販された。しかも出版者の熊氏がいた建陽(福建)を出帆する船は、古くから日中交易の相当量を占めている[26]。こうした点から、(a)と(d)で伝存情況を異にする背景がある程度理解されよう。
それは同時に(a)の『湯液本草』、ないしその精写本が当時の日本に伝来した可能性の低さを傍証する。さらに前述のごとく、日本の最初と第二番目の印刷医書は熊氏の書であり、しかも第二番目の出版地は当時の一乗谷であった。これらの事情を勘案するならば、出土焼片の筆写底本が(d)であった蓋然性はかなり高い、と断定してほぼ間違いないだろう。
三 残存焼片の該当部位と釈文
焼片の筆写底本は、ほぼ熊氏梅隠堂本と論定できた。たとえ(a)の遼藩第一版であったとしても、書式・字句に大差はあるまいと判断された。いずれにせよ、焼片の部位を確定し、正確に釈文する資料が得られたのである。
そこで以下に焼片の番号順に釈文を掲げ、残存部位を熊氏本『湯液本草』巻下における第何葉のオモテ「a」からウラ「b」と、第何行で記す。たとえば42b・7-9は、巻下第四二葉ウラ第七〜九行を示す。なお行頭の空格を含めた第何字目であるかを釈文末行の左に傍記し、異体字などは常用漢字ないし正字に適宜あらためた。
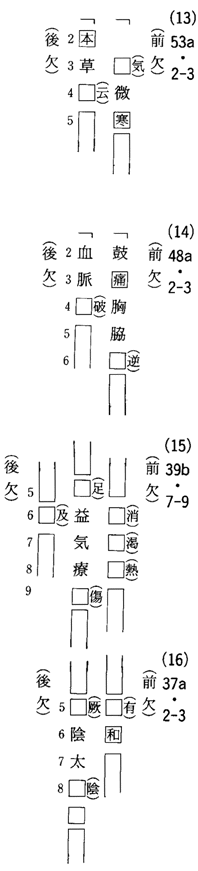


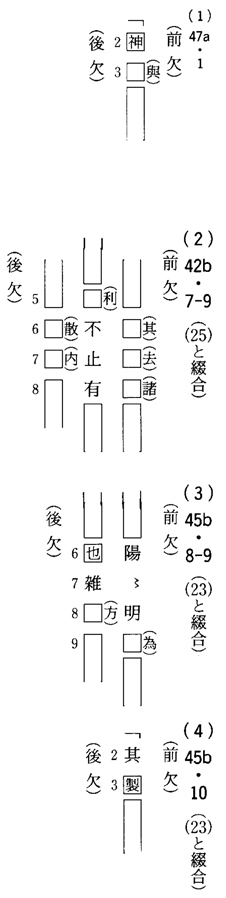
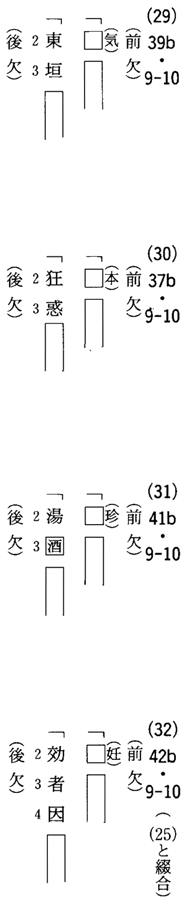
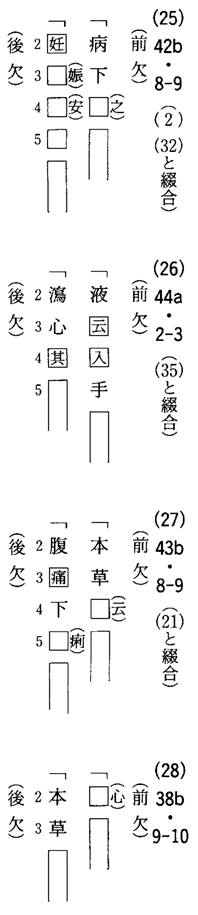


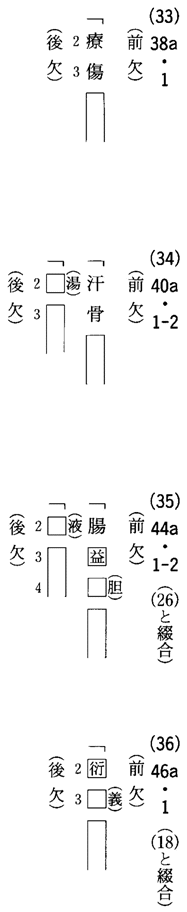
 清田氏は初報で(34)まで、再報で(35)までの釈文を示したが、これで写真1の焼片三六枚すべてについて追加と訂正ができた。また清田氏の調査時には判読できた文字のうち、その後周囲がやや欠損した焼片も認められた。しかし、これ以外にも残存の焼片は多い。筆者は朝倉氏遺跡資料館のご好意で目睹させていただき、五八枚まで数えることができたが、ふつうの息づかいでも舞いあがると注意され、紙製ピンセツトですら触れられない状態であった。したがって、保管された裏面に墨跡の有る無しも十分には確認できず、あるいは文字の判読可能な焼片がまだほかにあるのかも知れない。
清田氏は初報で(34)まで、再報で(35)までの釈文を示したが、これで写真1の焼片三六枚すべてについて追加と訂正ができた。また清田氏の調査時には判読できた文字のうち、その後周囲がやや欠損した焼片も認められた。しかし、これ以外にも残存の焼片は多い。筆者は朝倉氏遺跡資料館のご好意で目睹させていただき、五八枚まで数えることができたが、ふつうの息づかいでも舞いあがると注意され、紙製ピンセツトですら触れられない状態であった。したがって、保管された裏面に墨跡の有る無しも十分には確認できず、あるいは文字の判読可能な焼片がまだほかにあるのかも知れない。
一方、目視の範囲でも、何枚かが付着した焼片を認めた。それらを剥がせば、文字の読める焼片はさらに増加しようが、きわめてもろい現状ではままならない。しかし、残存部位を熊氏梅隠堂本と突き合わせれば、下に付着した焼片の文字を推測することは可能である。そこで数枚の付着が認められた焼片について、可能性が高い付着片の該当部位と文字を、釈文と同様に以下に示しておこう。
右のような例はまだ多いと思われるが、これ以上の追求にもはや現実的意義はないだろう。『湯液本草』はいまも復刻本があり、その熊氏梅隠堂本も現存するからである。なによりも焼片出土の意義は、室町時代後期の医界と熊氏刊行医書、そして一乗谷との関連に求められねばなるまい。
四 熊氏本医書と一乗谷・堺の文人
わが国その他には熊氏梅隠堂など、熊氏を冠した書賈による明初期の刊行医書が数多く現存している。それらは書目数のみでも三〇数種にのぼり、当時としては当時としては相当の出版量といえる。
多くは刊行者に熊宗立の名を記し、刊年も正統元年(一四三六)から成化十年(一四七四)までの三八年間に集中する。熊宗立の生没年は不詳だが、小曽戸氏はこの活躍年より推して、永楽年間(一四○三〜二四)から成化年間(一四六五〜八七)の人であり、その他は熊宗立の一族による刊行とみる[9]。
さて日本最初の印刷医書は、熊宗立の編刊になる『医書大全』の復刻であった。『医書大全』の初版は熊宗立自序の正統十一年(一四四六)とみられるが、日本版の復刻底本には成化三年(一四六七)の熊氏種徳堂刊本が用いられている。室町後期の大永八年(一五二八)、堺の豪商阿佐井野宗瑞(一四七三〜一五三二)が私財を投じてこれを復刻したのである。宗瑞は名医の竹田定祐月海(一四六○〜一五二八)と交際があって医に通じ、月海の兄、竹田薬師院円俊高定(一四五五〜一五二九)は堺の名医であった[27][28]。
この阿佐井野版『医書大全』には、学僧の月舟寿桂幻雲(一四六○〜一五三三)が刊行の跋文を寄せている。幻雲は竹田月海・高定の兄弟とも交遊があった。すなわち幻雲は、月海肖像に賛して月海を熊宗立にたとえ、高定肖像に賛し、彼等の父の竹田昭慶(一四二○〜一五○八)は李東垣・王好古・熊宗立の書を渉猟したと記す[29]。幻雲の豊富な医学知識は、国宝の黄善夫刊宋版『史記』(国立歴史民族博物館所蔵)の「扁鵲倉公列伝」に書き入れた、三○種もの医書の引用から十分にうかがえる[30]。幻雲はそこに『湯液本草』など『東垣十書』所収の四書や、竹田昭慶の『延寿類要』(一四五六年成立)も引く。とすれば、幻雲が竹田家や阿佐伊野家との交際を通じて、交易で栄えた堺などを経由した『東垣十書』や熊氏本医書を見ていたことは、ほぼ疑いないだろう。
一方、幻雲は曹洞宗宏智派と親しく、代々宏智派に帰依した朝倉氏の招きで、七回も一乗谷に下向していた[9][31]。おなじく一乗谷に招かれ、幻雲とも親交のあった僧に一栢、のち還俗した谷野雲庵(〜一五五六までは在世)がいる。この一栢が四代目朝倉孝景の求めで、天文五年(一五三六)に一乗谷で復刻した熊宗立『俗解八十一難経』こそ、日本で第二番目の印刷医書にほかならない。『俗解八十一難経』は正統三年(一四三八)の自序だが、復刻の底本は成化八年(一四七三)熊氏中和堂刊本であり、復刻の版木は今なお一部ながら現存する[32]〜[34]。
一栢[35][36]は永正十一年(一五一四)以前から京におり、同十七年以前頃まではそこにとどまって医と易を講じ、和気明重宗鑑(〜一五二〇)も師事したという。一乗谷では養子の三崎安指(一五一三〜一六〇七)に牛黄円その他の医薬の法を伝授し、いまも続く三崎家には一栢の手沢医書一〇数冊が保存されている。明版の『俗解八十一難経』とその越前一乗谷版以外はすべて熊氏本による写本で、多くは一栢の自筆である。このうち『俗解難経抄』にみえる享禄二年(一五二九)の奥書には「右此難経抄両冊者、二十年前於和泉府自筆之」、また表紙の裏には「新刊勿聴子(熊宗立)俗解八十一難経巻之一/性細書之頭圏者延寿院之講義也/延寿院講釈之時聞書」とある。すなわち一五〇九年頃、一栢は和泉府(堺)で熊宗立『俗解八十一難経』を抄写し、そこに延寿院の講義を書きこんでいたのである。
延寿院が誰かはよく分らない。しかし当時の堺には前述の竹田高定がおり、父の竹田昭慶は『延寿類要』を著している。そして竹田家は昭慶の祖父、昌慶が渡明時に得た牛黄円の製法を伝えている[28]。一栢が三崎安指に伝えたのも牛黄円であった。以上から推して、一栢が堺で竹田高定に熊宗立の医書などを学んだ可能性は高いと思われる。
さらに堺と一乗谷、そして一栢とをむすぶ人物がいる。儒者の清原宣賢(一四七五〜一五五〇)である。宣賢も朝倉氏の招きでたびたび一乗谷に下向し、晩年はここに居住して没した。京都大学附属図書館清家文庫にある『易学啓蒙通釈口義』(重文)には、宣賢の自筆で「一栢講、月舟聞書」とあり、一栢の講義を月舟(幻雲)が聞き、その内容を宣賢が読んでいたと分る[31]。
他方、宣賢は堺とも関係があった。堺では享禄元年(一五二八)に普門院宗仲論師が『韻鏡』を刊行、阿佐井野家は宗瑞の没した翌年の天文二年(一五三三)に無注本『論語』を刊行しているが、ともに宣賢が跋文を記しているのである[37]。また『韻鏡』については、一栢も発音器官図で説明した科学的な『韻鏡聞書』を著している[38]。
以上をまとめてみよう。
福建の熊氏が刊行した医書群は当時かなり伝来しており、一部は堺に舶載されていた[27]。堺には医に通じた豪商の阿佐井野宗瑞、名医の竹田高定がいた。一方、一乗谷に招かれた幻雲・一栢・宣賢は相互に交遊があり、しかも堺の文化と深くかかわっていた。そして幻雲は竹田氏の賛辞に熊宗立の名を挙げ、『湯液本草』も研究に使用している。一栢は熊氏本医書を堺で学び、その多くを筆写している。この幻雲と一栢が、堺と一乗谷で復刻された熊氏本医書、すなわち日本で最初と第二の医書出版に関与していたのである。
この新しい医学文化のスポンサーの堺と朝倉氏。堺と一乗谷を結ぶ彼ら文人たちの活躍。彼らが主な医学テキストとして受容した熊氏本。以上の相互にはっきりとした関連をみた。それらの詳細および当時と後世におよぼした影響は、今後さらに検討すべき課題である。
総括
(一)朝倉氏の遺跡より一九八五年に出土した冊子本医書写本の焼片は、元・王好古『湯液本草』の断簡であった。
(二)当焼片の写本は、明の一五〇八年に熊氏梅隠堂が刊行した『東垣十書』所収本を忠実に筆写した可能性が高い。
(三)墨跡の認められる三六枚の焼片すべてについて、残存した部位の確定と妥当な釈文が可能となった。未剥離の一部焼片についても、残存の部位と文字が推定できた。
(四)室町後期における熊氏刊行医書群を介した中国医学の受容、これに果した堺と朝倉氏の文化、それらを結ぶ文人たちの活躍に、明瞭な関連を認めた。
謝辞 当研究の端緒を開かれた岐阜教育大学の清田善樹講師、出土焼片の調査と焼片写真の掲載に便宜をいただいた福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館、論文資料を御教示いただいた同資料館の佐藤圭主査および北里研究所東洋医学総合研究所の小曽戸洋医史学研究部部長、拙文の校閲をいただいた文部省国際日本文化研究センターの山田慶兒教授の御厚意に、衷心の謝意を申し上げる。
引用文献と注
[1]『特別史跡 一乗谷朝倉氏遺跡ⅩⅦ 昭和六十年度発掘調査整備事業概報』九頁、福井県立朝倉氏遺跡資料館、一九八六
[2]清田善樹「朝倉氏遺跡出土の『湯液本草』断簡」『朝倉氏遺跡資料館紀要 一九八七』二〇〜二五頁、同資料館、一九八八
[3]小曽戸洋「一乗谷遺跡出土の『湯液本草』残紙」『漢方の臨床』三六巻三号、三四六〜三五〇頁、一九八九
[4]張元素『医学啓源』一六四頁・二〇〇頁、北京・人民衛生出版社、一九七八
[5]真柳誠「『湯液本草』『此事難知』解題」、小曽戸洋・真柳誠編集『和刻漢籍医書集成・第六輯』解説篇三七〜四四頁、東京・エンタプライズ、一九八九
[6]この考えかたは、皇甫謐(二一五〜二八二)の作と伝えられる「黄帝三部針灸甲乙経序」に述べる内容の踏襲である。
[7]中国中医研究院図書館『全国中医図書連合目録』一六二頁、北京・中医古籍出版社、一九九一
[8]真柳誠「『東垣十書』解題」、前掲文献[5]、二〜一八頁
[9]小曽戸洋「『名方類証医書大全』解題」、小曽戸洋・真柳誠編集『和刻漢籍医書集成・第七輯』解説篇二〜一六頁、東京・エンタプライズ、一九八九
[10]三木栄『朝鮮医書誌』二二七頁、大阪・三木栄、一九五六
[11]上海中医学院図書館『上海中医学院 中医図書目録』一七九・二七九頁、同学院、一九八〇(同目録に各々元刊本として載る)
[12]台湾国立中央図書館『国立中央図書館善本書目増訂本第二冊』四七三頁、同館、一九六七(同目録に明初刊黒口巾箱本として載る)
[13]武田科学振興財団『杏雨書屋蔵書目録』二九・七三八頁、京都・臨川書店、一九八二(同目録に各々、明刊本〔貴二六〕・至元十三年序刊本〔貴四一八〕として載る)
[14]このほか図版等の実見に及んでいないが、『北京図書館古籍善本書目』(同館篇、北京・書目文献出版社、一九八七)の記載によれば、一四八八五号の明刊『格致余論』(一二五六頁)と一四八八六号の明刊『局方発揮』(一二六〇頁)は、(a)所収本の可能性を疑うことができる。また藩承弼・顧廷竜『明代版本図録初編』(台北・文海出版社、一九七一)の五一一頁に載せる明初覆刊元本『脾胃論』は、明らかに杏雨書屋のそれと同版別本の(a)所収本であるが、本図録編纂(一九四一)当時の所蔵先も以後の所在も不明である。
[15]鄭偉章・李万健『中国著名蔵書家伝略』一一〇頁、北京・書目文献出版社、一九八六
[16]前掲文献[15]、二六六頁
[17]朱偉常「封面小識」『上海中医薬雑誌』一九八六年一期、三五頁、一九八六
[18]両書の図版は劉承幹『嘉業堂善本書影』(一九二九)の巻四に載るが、同『書影』の目録は両書を元刊本と記す。
[19]前掲文献[15]、一八三頁
[20]両印は誰のものか未詳だが、もとは北平(北京)図書館にあり、今は台湾の国立中央図書館所蔵の(b)本『蘭室秘蔵』(同館の目録は元刊本と記す)にも押捺されている。
[21]内閣文庫『内閣文庫漢籍分類目録』二三三頁、同文庫、一九五六(同目録に楓・一〇冊・子三四函・九号として載る)
[22]前掲文献[13]、七三八頁(同目録に杏六〇八七として載る)
[23]中医研究院図書館『館蔵中医線装書目』一七八頁、北京・中医古籍出版社、一九八六
[24]このほか図版等の実見に及んでいないが、王重民『中国善本書籍提要』(上海古籍出版社、一九八三)二五六頁の記載によれば、米・国会図書館蔵の明刻『湯液本草』は(d)所収本の可能性を疑うことができる。また前掲文献[23]一四一頁の明初新刻東垣十書本も、(d)所収本の可能性がある。さらに孫星衍(一七五三〜一八一八)の『平津館鑑蔵書籍記』(岡西為人『宋以前籍考』一〇〇〇頁、台北・古亭書屋、一九六九)に記す元版『新刊東垣先生蘭室秘蔵』も(d)所収本であろうが、現所在は不明。
[25]大庭脩「東北大学狩野文庫架蔵の御文庫目録」『関西大学東西学術研究所紀要』三号、三二頁、一九七〇
[26]大庭脩『江戸時代における中国文化受容の研究』二一〜三〇頁、京都・同朋社出版、一九八六
[27]三木栄「室町時代の堺の医事」『和泉志』一九号、一九五九
[28]新村拓『日本医療社会史の研究』七二〜八一頁、法政大学出版局、一九八五
[29]幻雲「幻雲文集」『続群書類聚』第一三輯上三八四〜三八五頁、同書完成会、一九八六
[30]水澤利忠『史記会注考証校補』八巻九七頁、同書刊行会、一九六六
[31]佐藤圭「『湯液本草』の出土ー一乗谷と文化人」『れきし』二八号八〜一〇頁、一九九一
[32]野村英一「西福寺の八十一難経版木」、福井県教育委員会編『文化財調査報告』第一六集一二〜一四頁、同委員会刊、一九六六
[33]岩治勇一「越前朝倉版『俗解八十一難経』の版木(各版木の記載事項について)」『若越郷土研究』一九巻五号八一〜八五頁、一九七四
[34]真柳誠・小曽戸洋「現存する日本第二の医書印刷の版木」『漢方の臨床』三七巻四号三六〇〜三六二頁、一九九〇
[35]平泉洗「越前国一乗ヶ谷版の医書と一栢老人」『芸林』一一巻二号一〇九〜一一四頁、一九六〇
[36]岩治勇一「谷野一栢をめぐる朝倉の医学考」『若越郷土研究』一八巻三号四七〜五六頁、一九七三
[37]川瀬一馬『古活字版之研究』八四〜九〇頁、安田文庫、一九三七
[38]太田晶二郎「韻鏡三話」『田山方南先生華甲記念論文集』三九五〜四〇八頁、同記念会、一九六三。なお同論文は宣賢の『韻鏡」跋文が、建仁寺禅僧・常庵竜崇の代作であることも指摘する。
※本稿は一九九〇年の日本医史学会二月例会における発表を敷衍したものである。