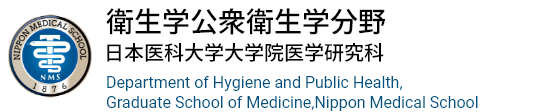環境要因の呼吸器疾患に及ぼす影響および化学予防に関する実験的研究
-李英姫
環境要因の呼吸器疾患の発症・増悪リスクとしての寄与の程度、および分子機構に基づいた予防対策について実験的研究を行っています。主に微小粒子状物質(PM2.5)および超微小粒子(UFP)による酸化ストレス作用がアレルギー性気管支喘息、肺線維症病態へ及ぼす影響について、動物モデルおよびin vitro細胞実験を用いて検討しています。さらに、抗酸化物質や抗菌活性を持たないマクロライド新規誘導体が化学予防対策に寄与できる可能性について検討しています。
循環器疾患の予防に向けた環境・社会的要因に関する疫学研究 ― リスクの早期発見と健康格差への対応を目指して
–加藤活人
循環器疾患の予防を目指す取り組みの一環として、これまでに前糖尿病(耐糖能異常)や軽度の炎症マーカーが動脈硬化の早期指標とどのように関連するかを検討するなど、糖代謝異常の初期段階に関する研究を行ってきました。
加えて近年では、人間が生活の中で影響を受ける多様な「環境」が循環器疾患の発症や重症化にどのように関与するかを、公衆衛生学および疫学の視点から明らかにする研究に取り組んでいます。この「環境」には、気温や気圧、季節、曜日、時間帯といった自然・時間的要因に加え、社会経済的状況や地域特性、ジェンダーといった社会的決定要因(SDOH)も含まれます。
これらの要因が、心筋梗塞や大動脈解離、うっ血性心不全などの急性循環器疾患の発症リスクや重症化に与える影響を、臨床疫学的手法を用いて検討し、科学的根拠に基づく予防対策や健康格差の是正に貢献することを目指しています。
人生100年時代を「自分ごと」にデザインする:リハビリテーション専門職によるセルフマネジメント支援の可能性
-陣内裕成
人生100年時代。誰もが健やかに、そして自分らしく生きることを願う社会において、私たちは自治体や企業と連携し、セルフマネジメント支援に着目した革新的なプログラム開発に取り組んでいます。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーション専門職は、本来、人々の健康を支える上で欠かせない存在です。しかし、現状では公衆衛生の領域、特に地域における予防活動に携わる者はごくわずか。これは、現行の社会保障制度がその力を十分に活かしきれていない現状を示唆していると考えています。
私たちは、リハビリテーションの現場で培われる、機能回復と自立支援のための専門的な知識と技術こそが、「地域・職域の元気な方を増やす健康づくり」に大きく貢献すると確信しています。それは、失われた機能を取り戻すだけでなく、その人が持つ潜在的な能力や、それを補うための工夫(代償機能)を的確に評価する視点があるからです。たとえば、リハビリテーション専門職は、長期的な視点から二次的な障がいのリスクを予測し、その人の生活環境や地域社会の資源を総合的に評価することができます。痛みにお困りの方に対して、理学療法士は姿勢や動作といった「動く」機能に着目し、適切な運動療法や物理療法を提供します。
さらに、複雑な課題に対しては、義肢装具や歩行補助具、住環境の調整といった多角的なアプローチを組み合わせ、その人にとって最適な解決策を探ります。私たちの支援の根底には、常に「機能回復」と「自立支援」という明確な軸があります。だからこそ、私たちは一方的なアドバイスに留まらず、その人が自分自身で健康を管理していくための方法を、それぞれの状況に合わせて丁寧に導き出すことができるのです。
私たちは、このようなリハビリテーションの知見を活かした地域や医療現場での新しいモデルづくりとその実装に情熱を燃やしています。人手が足りていません。もし、この考えに共感し、共に未来の健康づくりを方向付ける活動にご関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひお力をお貸しください。
活動紹介
- 60年以上に亘る地域コホート研究CIRCS<The Circulatory risk in Communities Study>
- 山武市との介護予防に関する共同事業「転倒骨折予防プロジェクト」
- 山武市シルバー人材センターとの安心安全就労に関する共同事業「健康になる就労プロジェクト」
- 医療/介護レセプトや高齢者ニーズ調査等の二次データを活用したヘルスサービス研究:広範な全国規模の視点と詳細な地域レベルの視点からの分析
- 10万人規模の大規模コホート研究「JPHC Study <Japan Public Health Center-based
グランザイム3の健康指標としての応用可能性の検討
-平田幸代
グランザイム3は、ヒト末梢血リンパ球に存在し、細胞性免疫における殺細胞機能に関与すると考えられているプロテアーゼです。本酵素は、殺細胞作用の強弱によってリンパ球内に産生され、 あるいは血液中に漏出してくると考えられています。我々は、グランザイム3の基礎的な性状から、個々人の細胞性免疫機能の強弱との関係、病態における本酵素の関与について研究を行っています。 さらに、新しい健康指標の一つとして応用する可能性について検討しています。
コリンエステラーゼによる肝の脂肪化の評価についての検討
-平田幸代
年々肥満の人が増加しており、それに伴って脂肪肝の人も増加しています。脂肪肝は肝細胞に中性脂肪が30%蓄積した状態のことで、肥満者で脂肪肝を合併していると、肥満症の診断基準に該当し、適切な治療が必要です。コリンエステラーゼは肝臓でつくられる酵素で、脂質代謝にも関連しているため、脂肪肝ではコリンエステラーゼの値が上昇します。
我々は、肝細胞における脂肪蓄積時のコリンエステラーゼの産生や性状について研究しています。そして、コリンエステラーゼによる肝の脂肪化の評価について検討しています。そして最終的には、脂肪肝、肥満、メタボリックシンドロームに対する予防対策に貢献できればと考えています。
免疫記憶を支える細胞の生存と機能維持のしくみの解明
-伊藤亜里
私たちは、免疫応答の中核を担うT細胞およびB細胞が、長期にわたって生体内で「記憶」として維持される仕組みに注目しています。免疫細胞の一部は、初回の病原体やがん細胞への応答後も生き残り、再び同じ脅威にさらされたときに迅速かつ強力に反応できるよう、特別な分化・代謝状態を獲得します。
私達は、T細胞ががん微小環境下でも長期に機能を保つ仕組みや、抗体産生を担う形質細胞が長期間生存するための環境応答性の特性に焦点を当て、その分子基盤や代謝特性を解析しています。これらの知見は、がん免疫療法やワクチン、自己免疫疾患の新たな治療戦略の基盤となることが期待されます。ここに紹介した以外にも、転写因子と腫瘍の関連など、様々な研究を行っております。免疫学・分子生物学・遺伝子工学・腫瘍学に興味のある方、お気軽にご連絡ください。