���{�l�E��p�l�̖�s���p�ӎ������\��k�m�і�s�̗�\
02L1040Y�@�쑺���q�i����������U�A�w�������F�^���@���j
����
�@��p�̊ό��n�Ƃ��đ����̐l�œ��키��s�B��p�l�ɂƂ��Đ����Ɍ������Ȃ��ꏊ�ł��钆�ŁA�C�O����̊ό��q�������Ă��Ă���B��p�l�ɂ��ό��q�ɂ��l�C�̂����s�ł��邪�A��s�̖��͂͂ǂ��ɂ���̂��B�����g�A��p�𗷂������ɖ�s�ɖ�������A���̋^���Nj��������Ɗ������B
�@�{�_���ł́A��k�m�і�s�œ��{�l�Ƒ�p�l�ɃA���P�[�g�������s���A����҂��ǂ̂��炢��s�𗘗p���₷�����𖾂炩�ɂ��Ă����B�����Ĉȉ��̂��Ƃ��l������B
(1)���{�l�Ƒ�p�l�ɁA��s�̔F���x�E�����x�ɂǂ̂��炢����������̂��B
(2)�l�̑����ɂ���āA��s�̔F���x�E�����x�ɍ���������̂��B
(3)���p�ړI�ȂǗ��̍s���ɂ���āA��s�̔F���x�E�����x�ɍ���������̂��B
(4)��s�̖��͂͂ǂ��ɂ���̂��B
�܂��A�����̂��Ƃ𖾂炩�ɂ������ʂ���A��s�̂ǂ̕��������P�������Ɋό��q�����p���₷���Ȃ�̂����l���Ă݂����B
�{�_���ł͐l���̌h�̂��ȗ������B�܂��A�g�p���銿����JIS�R�[�h�����ɂ����p�����E�l���p�����������Ƃ��A����ɂȂ������͐������g�p�����B
���́@��s����
��s����҂̈ӎ���s���ɂ��Č�������Ă���_����N�㏇�ɂ܂Ƃ߂�B�ȉ��̘_���͑S�āA��s�Œ������s���������ʂ͓��v���g���ĕ��͂��Ă���B�܂��A�ߋ��ɏo���ꂽ���ʂƉۑ�𖾂炩�ɂ��邱�ƂŁA�����̌�����i�߂�肪����Ƃ���B
������(1995)�u��k�s��s����҂̓��@�ƍw���s�ׂ̌����v[1]
��s�ɍs�����@�����s�ׁE���F�m�ɂ��Ė��炩�ɂ����B����炪���ʂ�N��Ȃǂ̑����ɂ���ĕω�����̂��ǂ������N���X�W�v�ŕ��͂��A�e�������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B
��ƎŁA�юq���Aḉ����A緜}���A���u�m(1998)�u��s����s�ׂ̔�r�ƌ����|�i���A�m�сA�ؐ��X�O��s�̗�|�v[2]
�O�̖�s�ŃA���P�[�g�ƖK��C���^�r���[��p���āA����҂̖�s���F���Ɩ�s�ł̏���ԓx�𖾂炩�ɂ����B�܂��A�قȂ��s�ɂ��������҂́A��s�ɑ���F���i���ɏ��i�̎�ނɑ��锽���Ɗ��C���[�W�j�̍������������邱�Ƃ����������B
��Ǝ�(2002)�u���̌��̊ϓ_�ɂ���s�����Ɖe���v�f�����v[3]�@
19�̖�s�Ől�X�̖�s���̌��ɂ��Ē������A�`����s�Ɨ��z��s�̊��̌������𖾂炩�ɂ����B�����ɈقȂ��s�ł͊��̌����قȂ邱�Ƃ�\���A��s�̌`�Ȃǂ̊��v�f�ƘI�X�̎�ނȂǂ̎Љ���v�f�͊��̌��ɉe�����邱�Ƃ��l�@����B
��C�A�����A���i��(2002)�u�����O�ό��q�ɑ���ό���s�̊��v�f�d�v���F���y�і����x�̌����|���Y�s�Z���ό���s�̗�|�v[4]
���{�l�Ƒ�p�l�̖�s���ւ̏d�����x�A�����x�𖾂炩�ɂ��A�����ɂ��č��ЂƑ����̈Ⴂ�ɂ���č����o�邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B��Ǝł�[2]�́A�قȂ��s�ɂ��������҂͖�s�ɑ���F���̍���������A�Ƃ������ʂ��Q�l�ɂ��A���Ђ̈Ⴄ����҂ɒ��ڂ��Ă���B
�s�ۗ�(2003)�u�I�X��s��ԑ����ɑ������ҏ���Ԃ̉e�������|��p�䒆�s���b�������ؖ�s�Ɠ��{��B�����s�����X�X�̗�|�v[5]
�����Ƒ䒆�̘I�X��s�̋�ԓ�����T�������B�܂��A�قȂ�Ǝ�̘I�X�ɖK������҂́A�Ǝ�ɂ���Ĕ��������鎞�Ԃɍ����o��̂��𖾂炩�ɂ����B����ɁA���ʂ����ԁA��s�̐l�����x�ɂ���ď���Ԃɍ��������邱�Ƃ��l�@����B
�s�×�(2003)�u�m�і�s�@�o�c�Ǘ��̌����v[6]
�I�X�c�Ǝ҂ɂƂ��Ďm�т̔��H�L��̊����O�ƌ�ŏ����ɉe�������������A����ɐ��{�̐���ɂ��Ă̖����x���B�܂��A���H�L�ꊮ���O�ƌ�ɂ��ď���҂̖����x�����A�m�і�s�������ō����I�ł����S�ȏ��Ɗ��֔��W���邱�Ƃ��l����B
�s�×�(2004)�u�m�і�s�ڋq�����x���́|����������w�w������s�ׂ̗�|�v[7]�@
��s�̃T�[�r�X�̎��Ə���Җ����x�̊W����Nj������B����Ɋw���̈قȂ��w���ł́A��s�̘I�X�Ə��X�̃T�[�r�X�̎��ɑ��閞���x�ɈႢ�������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B
�]�r�P(2004)�u�ē��Њό��q�̐V��Nj��Ǝs����̌����v[8]
�V��Nj��͍��Ђ̈Ⴄ�ό��q�ō��������邩�ǂ����𖾂炩�ɂ����B����ɁA�l��������̈Ⴂ�͐V��Nj��ɉe���������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B[1]�������A[2]��Ǝł�A[3]��Ǝł̘_�����Q�l�ɂ��Ă��邪�A����炪���グ�Ă������s�ׂ��s�̔F���Ƃ͕ʂ̐V��Nj��Ƃ����_�ɒ��ڂ��Ă���B
����綦(2005)�u��k�s�I�X���H�����y�ш֎q�̑��^���\�̌����v[9]
��s�Ŏg����֎q�̕��́A�g�p���@�A�ގ��A�@�\�̌����B�m�сA�ؐ��X�A�ʉ��X�A�`�͊X��s�Ŕ̔�����Ă���H�ו��A���i�ׁA�֎q�ɂ��ĕ��͂��ǂ̂悤�Ȉ֎q���g������ɖ�s�����W����̂�����������B
�ؔ@(2005)�u��s�����ɑ�����m�o�̉e���|�m�сA�Ս]�X�A�t���s�̗�v[10]
���{�l�Ƒ�p�l�̖�s���F���𖾂炩�ɂ��邱�ƂŁA��s�̔F���͍��Ђ⑮���ɂ���ĕω����邱�Ƃ��ؖ������B����ɁA��s�̎�ނ�A����҂̏���s���ɂ���Ă��e�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B
�@�����̌����ʼn�����[1]�A��Ǝł�[2]�A��Ǝ�[3]�A��C��[4]�A�s�×�[7]�A��[10]�@�̘_���́A����҂̖�s���F���E�����x�E���F���E����s�ׂɂ��Č������A��ɖ�s�ɑ���u�F���v�ɂ��Ď�舵���Ă���B�����Ă��́u�F���v�͌l�̑����⍑�ЁE����s�ׁE��s�̎�ނȂǂɂ���ĉe������A�Ƃ������Ƃ����܂ł̌����ŏؖ�����Ă���B�܂��A��p�ł͖�s�ɂ��Ă̌���������̂ɂ�������炸�A���{�Ō�������Ă�����̂͋͂��ł���A�u�F���v�ɂ��ď�����Ă�����̂͌�������Ȃ��̂����B�����Ŏ��͓��{�l�Ƃ��Ċό��q�̎��_�����s�����Ă������Ǝv���B��̓I�ɂ͓��{�l�ό��q�̒����l���𑝂₵�A�u�F���v�̕]�����p�l�Ɣ�r����B����ɔ�r�����łȂ��A�ό��q�ɂƂ��Ė�s�͂ǂ̂悤�Ɍ����Ă���̂���Nj����Ă����B
���� ��s�ɂ���
��s�Ƃ́A�Ȍ��Ɍ����Ɓu��𒆐S�ɓ��키�����I�X�̏W�܂�v�ł���B���{�ɂ͖�s�Ƃ������̂͑��݂��Ȃ����A�����Č����Ȃ�u���̃A�����v�Ɓu�����̉���X�v�������������̂ł��낤���B��p�̖�s�͗l�X�ȏꏊ�ɑ��݂��A������������̐l�X�œ�����Ă���̂������I���B���܂��p�̕����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ���s���ǂ��������̂������̏͂ł͓`���Ă����B����ɁA�ό��q�̖�s���p�ɂ��Ē��ׁA�ό������̈�ł���m�і�s����̓I�ɏЉ��B
1. ��s�Ƃ�
��k�s�s��Ǘ����̒�`[11]�ɂ��Ɓu��s�Ƃ́A��̂U������P�Q���܂ł��c�Ǝ��ԂƂ��A�@�L���ȊǗ��̉��ʼnc�Ƃ������ꂽ�I�X�̂��Ƃł���A��k�s���ɖ�Ԃ̋x���A�X�V�сA����ꏊ�������́v�Ƃ���B���̒��Ŋό���s�́u����҂��X�V�сA���������ł��A50km�ȓ��ɐ��{���F�߂�ό������A������Y�����鏊�v�ƒ�`����Ă���B
�@�����̖�s�́A�_�⎛�A�����Ȃǂ̊W���琶�܂�A����ɌX�̎s�ꂩ���̎s�ꂪ�`�����ꂽ�ƌ����Ă���B�I�X���l�͑����̗����邱�ƂɂȂ�c�Ǝ��Ԃ����тĂ������悤��[11]�B
���X�Ɣ��W���Ă�������s�ł��邪�A�����܂Ől�X�ɂƂ��Č������Ȃ����݂ɂȂ������R�ɂ͎��̂��Ƃ��l������B
���o�ϗv�f�F�l�X�̎��v�ɉ������ቿ�i�ȉ��i�ݒ�B
���@���ʂł̗v�f�F��s�ɑ���@�߂̕s����A�����܂肪�ɂ����߈ړ����̘I�X���������A�ړ�������Œ�ւƕω����Ă������B
���Љ�v�f�F�s�s�̋}���Ȕ��W�ɔ_�Ƃ͂��Ă����Ȃ��Ȃ�A�_�Ƃ����߂ĘI�X���l���n�߂�l�������Ă������B
������҂̎��v�F���l�ȕ����y���g�߂Ŏ�ɓ���邱�Ƃ��ł���B
���ό��v�f�F�ό������̈�Ƃ��Ċό��q�̗��p�𑝂₷���߂ɁA�ό������{����s�̔��W�𑣐i�B
�ቿ�i�ő��ʂȏ��i�Ƃ��邪�A��s�Ŏ�舵���Ă����̓I�Ȃ��̂ɂ��Ă͖{��3.�ŐG��邱�Ƃɂ���B
2. �ό��q�̗��p
��s�̗��p�҂͒n���ɏZ��20��A30��̎�҂��������A�S�̓I�Ɍ���Ǝq������N�z�̕��܂łƕ��L���B����ɁA�N�X�C�O����̊ό��q�̗��p�������Ă��Ă���B
�ȉ��Ɏ����\�́A2003�N����2005�N�ɑ�p�ɖK�ꂽ�ό��q�i���{�A�A�����J�A���`�A�}�J�I�A�؍��A�}���[�V�A�A���[���b�p�A�I�[�X�g�����A�l�j�ɁA��ԗL�����Ǝv���ό�������₢�����ʂł���B��s���ό��������Ɠ�����l�X�����|�I�ɑ������Ƃ��킩��B�\���́u�l/�S�l�v�͕S�l�̊ό��q���œ��Y�ό�������K�ꂽ�l�����w���B
�\2-2-1 2003�N�`2005�N�@�ό��q��v�ό������@���ʕ\[12]
| �� �� | 2003�N | 2004�N | 2005�N | ||||||
| �ό����� | �l�� | ���Ύ��� (�l/�S�l) | �ό����� | �l�� | ���Ύ��� (�l/�S�l) | �ό����� | �l�� | ���Ύ��� (�l/�S�l) | |
| 1 | ��s | 2271 | 45.37 | ��s | 2486 | 49.23 | ��s | 2946 | 58.81 |
| 2 | �̋{�����@ | 1105 | 22.08 | �̋{�����@ | 1327 | 26.28 | ��k101 | 1817 | 36.27 |
| 3 | �����L�O�� | 999 | 19.96 | �����L�O�� | 1235 | 24.46 | �̋{�����@ | 1661 | 33.16 |
| 4 | ���咬 | 484 | 9.67 | ��k101 | 917 | 18.16 | �����L�O�� | 1562 | 31.18 |
| 5 | ��份 | 433 | 8.65 | ���咬 | 711 | 14.08 | ��份 | 900 | 17.97 |
| 6 | �W�� | 372 | 7.43 | �W�� | 663 | 13.13 | ���咬 | 876 | 17.49 |
| 7 | �����K | 321 | 6.41 | ��份 | 648 | 12.83 | �W�� | 758 | 15.13 |
| 8 | ���R�� | 309 | 6.17 | ��k�@���� | 484 | 9.58 | �����K | 635 | 12.68 |
| 9 | �k�� | 252 | 5.03 | �����K | 397 | 7.86 | ���R�� | 566 | 11.3 |
| 10 | ���D�t�@�V�� | 235 | 4.7 | �z���R | 396 | 7.84 | �z���R | 448 | 8.94 |
3. �m�і�s�ɂ���
�m�і�s�͏��^�iMRT�Ƃ������B���{�̒n���S�{�d�Ԃ̌ď��j�����K�w�t�߂ɂ���A�哌�H�A��͘H�A���јH�̎O�哹�H�Ɖw�O�Ɍ��m�їՎ��s��Ő��藧���Ă���B
���N�̔��W�ɂ��A�m�і�s�͍��ۓI�ɂ��m���x�̂����s�ɂȂ������A�ɉh�̗��R�ɂ͈ȉ��̂��Ƃ��l������[13]�B
(1) �Ǝ킪�����A�����i�������Ȃ��A�K���ł���B
(2) �l�q�s�i���K�w�j�ƕ��јH�ɑ���o�X�̉^�s���֗��ł���B
(3) �ߕӂɊw�Z�������A�w���ɂƂ��Ė�s�����ی��x���ɗV�ԏꏊ�ƂȂ�B
(4) �c�Ǝ��Ԃ������A�����������̂P���A�Q���܂ʼnc�Ƃ��Ă���X������A��^�̐l�̎��v�����Ă���B
�܂��A�ό��q�ɗL���Ȗ�s�ɂ��Ĉȉ��̕\�ɂ܂Ƃ߂����A���̕\������m�і�s�̋K�͂��傫�����Ƃ��킩��B�܂��A���H�ނ��������Ƃ��ό��q�ɂƂ��Ă͖��͓I�ł���B
�\2-3-1�@��s���i��ޒ�������[14]
| ��s�� | ����[15]�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | ��y��1 | ���H��2 | �����i��3 | �ƒ뻰���4 | ��������5 | ���̑���6 |
| �m�і�s | ��p�ő�̃X�P�[���A�ό��q������ | 44 | 308 | 199 | 69 | 293 | 28 |
| �^�͊X��s | �������Y���A�P�{�� | 37 | 200 | 137 | 42 | 199 | 39 |
| ���ٖ�s | ��p��w�̋߂��A��Ҍ����̏��i | 31 | 209 | 43 | 49 | 127 | 47 |
| �t���s | ���w���X�A���ېF�L���ȓX���ڗ��� | 10 | 145 | 7 | 10 | 17 | 22 |
| �ؐ��X��s | �ό��q�����̏��X�X�̕��͋C | 5 | 70 | 19 | 4 | 15 | 14 |
��1 ��y�F�˓I�A�����������A�C�V��A�֓����A�ʐ^�فA�肢�A���X�A����A��������A��
��2 ���H�ށF�L�����A������A��A�Ă����A�g�����A���y�̃I�����c�A�C�J�̂Ƃ�݃X�[�v�A�^�s�I�J�~���N�e�B�[�A�}���S�[�����X�A���{�����A��
��3 �����i�F�ዾ�A�X�q�A����A���z�A�x���g�A�A�N�Z�T���[�A��
��4 �ƒ�T�[�r�X�F�ƒ�p�i�A�G�݁A���^�d�����i�A�Q��A�H�i�A�R���r�j�A��
��5 �����ށF�ߗށA�C�A���ϕi�A��܁A�}�t���[�A��
��6 ���̑��F���e�A�ԉ��A�肢�فA�ʐ^����X�A�_�A��
�ȉ��̕\�͊C�O�ό��q���K����v��s�̊��������������̂ł���B�\���́u�l/�S�l�v�͕S�l�̊ό��q���œ��Y��s��K�ꂽ�l�����w���B�������m�і�s�͑��̖�s��傫�����������Ĉ�ԍ������Ƃ��킩��B
�\2-3-2�@2004�N,2005�N�@�ό��q���K�ꂽ��v�ό���s�@���ʕ\[�P6]
| �� �� | 2004�N | 2005�N | ||||
| �ό���s | �l�� | �l/�S�l | �ό���s | �l�� | �l/�S�l | |
| 1 | �m�і�s | 1,638 | 32.44 | �m�і�s | 2,017 | 40.27 |
| 2 | �ؐ��X��s | 399 | 7.90 | �ؐ��X��s | 327 | 6.53 |
| 3 | �^�͊X��s | 188 | 3.72 | �^�͊X��s | 147 | 2.93 |
| 4 | ���Y�Z����s | 80 | 1.58 | ���Y�Z����s | 125 | 2.50 |
| 5 | ��_����s | 74 | 1.47 | ��_����s | 85 | 1.70 |
| 6 | 猉��X��s | 69 | 1.37 | �Ս]�X��s | 79 | 1.58 |
| 7 | �Ս]�X��s | 67 | 1.33 | ���ٖ�s | 74 | 1.48 |
| 8 | ���ٖ�s | 49 | 0.97 | 猉��X��s | 63 | 1.26 |
| 9 | �t���s | 39 | 0.77 | �t���s | 56 | 1.12 |
| 10 | �y�ؖ�s | 7 | 0.14 | �䒆���b��s | 26 | 0.52 |
�ό��q�Ɉ�Ԓ��ڂ���Ă����s�Ƃ������Ƃō���A�����ꏊ�Ƃ��Ď��͎m�і�s��I�B
��O�́@�������@
���̏͂ł́A�{�����̐ݖ�ɂ��āA�����Ώێ҂̌�����@�A�A���P�[�g�̕��@�A����Ƀf�[�^�̕��͕��@�ɂ��ďq�ׂĂ����B
1. �ݖ�v
�����ł́A�{�����̐ݖ₪�ǂ̂悤�ɂ��č\�����ꂽ�̂��������B�{�A���P�[�g�́A�傫��������ƂS�̍��ڂɕ�����Ă���B
(1)��s�̃C���[�W�i�F���j
(2)��s�ɑ��閞���x
(3)���̍s��
(4)�l�̑���
(1)(2)�ɂ��Ă͎���ɑ��Ă̓��ӓx��5�i�K�]���ŁA(3)(4)�ɂ��Ă͑I���ŋL������`���Ƃ����B�����̍��ڂ͈ȉ��ɏq�ׂ���e���Q�l�ɂ��Ȃ���쐬�����B
�k��s�̔F���v�f�l
���䗷�q����y�ѓ��������̒������ʂƒؔ@�A��ƎŁA�s�×ς̒������ڂ��Q�l�ɂ����B
�@�ؔ@[17]�́A��s���C���[�W����`�e����30�l�̑�w���ɓ����Ă��炢�A85�̌`�e�����o�����B�����āA���̒�����ǂ̌`�e������s�ɓ��Ă͂܂邩���A40�l�̌������ɓ����Ă��炢�A30���ȏ�̉�ꂽ���̂��̗p���A15�̌`�e�����擾�����B����ɁA�ߋ��ɍs��ꂽ��Ǝł̌���[18]�Ƒ��̌����҂��s���������ŏo�����`�e���������A�����悤�Ȍ`�e���͏Ȃ��ŏI�I�Ɉȉ��Ɏ���24�̌`�e�����g�p�����B
���������A�y�����A���G���Ă���A�`���I�A�ʔ����A�ς킵���A���₩�ȁA�����A���������A�����I�ȁA�댯�ȁA�Y��A�L���A���邢�A����I�ȁA�����A�Ɠ��ȁA�i�l�X�́j�₽���A�����ۂ��A�����ȁA�������A�L���ȁA�����I�ȁA���l�ȁ@
�����̊��o�I�ȔF���̑��ɁA��s�����p���₷�����ǂ����𑪂鍀�ڂ�lj����A���̐�s�������Q�l�ɂ��Ȃ���ݖ�(1)��ݒ肵���B
�ݖ�(1)
�@��ʎ�i�͕֗��A�A�댯�ȁA�B�L���A�C�ʔ����A�D���������A�E�q���Ǘ��͗ǂ��A�F�������A�G���������A�H�X�g���X�A�I���G�s���A�J�c�Ǝ��Ԃ͒Z���A�K���͋C�͗ǂ��A�L�֗��A�M�����A�N���t�̖��i���{�l�̂݁j�A�O�C���[�W�ʂ�i���{�l�̂݁j�A�P�ό��q�Ɋ��߂�i��p�l�̂݁j
�k��s�����x�̗v�f�l
�ڋq�����̍\���v�f�Ƃ��āA�s�×�[19]�́A���̂悤�ɕ��ނ��Ă���B
(1)��ƃC���[�W�i�Ԑڗv�f�j�F���ی슈���A�Љ�v�������@
(2)�T�[�r�X�i���ڗv�f�j�F�A�t�^�[�T�[�r�X�A�̔����̐ڋq�ԓx�A�X�ܓX���̕��͋C
(3)���i�i���ڗv�f�j�F���i���l�i�`�A�F�A�i���A�@�\�A���i�Ȃǁj
�ȏォ�炷��ƁA���i���l�����łȂ��A�X���̐ڋq�ԓx��X�̕��͋C�Ȃǂ����ړI�ɖ����x�ɉe�����A����ɂ͊��ی슈�����ǂ̂��炢�s���Ă��邩�A�Ƃ�������ƃC���[�W�܂ł��ԐړI�ł͂��邪�e����^����悤���B
�����ŁA���䗷�q����y�ѓ���������[20]�����グ�A���ۂ̖�s�ɑ��閞���x�ɂ��čl���Ă����B���̒����ł́A�C�O�ό��q�ɑ��čs��ꂽ���̂ł���B�ό������̒��ōł��D���ȏꏊ���m�і�s�Ɠ������l�ɑ��Ă��̗��R�������B
�\3-1-1�@�m�і�s���D���ȗ��R
| ���R | �l�� | ���R | �l�� |
| ���₩�Ŗʔ��� | 96 | �V�N | 3 |
| ���䗿������������ | 64 | �݂Ă܂�鏊������ | 2 |
| �H�ו����������� | 59 | �s���̕����ł��� | 1 |
| �����������̂����� | 40 | �ƂĂ��傫�� | 1 |
| ���i������ | 34 | ���� | 1 |
| ���{�ɂȂ� | 15 | �s�s���i���ǂ� | 1 |
| �H�ו��̎�ނ����� | 13 | ���{�̍Ղ�̂悤�� | 1 |
| �������� | 12 | �l�X���e�� | 1 |
| ��p�̕����ł��� | 6 | �b�c������ | 1 |
| ���ʂȕ��͋C | 5 | ���͂����� | 1 |
����A�m�і�s���D���ł͖������R�ɂ́A�l�������i7�l�j�A�ǂ����������i2�l�j�A�s�q���A���t���ʂ��Ȃ��A�X���̑ԓx���ǂ��Ȃ��A���{�l�������A�H�ו��������ۂ��i�e1�l�j���̉�������B
���̌��ʂ���ȉ��̉��������Ƃ��킩��B
���H�ו��ɂ���
�����i�ɂ���
����s�̕��͋C�i���₩���j�ɂ���
����3�_�͐�Ɏ��グ���ڋq�����̍\���v�f�̒��ڗv�f�i�T�[�r�X�E���i�j�ɓ��Ă͂܂�B
�����̂��Ƃ܂��A�k�ݔ��l�k�]�ƈ��l�k���i�l�k�H�ו��l�̂S�ɂ��Ė����x�ׂ�ݖ�(2)��v�����B
�ݖ�(2)
�k�ݔ��l�@�g�C���̐��A�A�S�~���̐��A�B�H���p�̐Ȃ̐��A�C�Ŕ͐l�ڂ��Ђ���
�k���i�l�@��ށA�A�~�������A�B�i���A�C���i
�k�]�ƈ��l�@�X���͐e���A�A�X���͐M���ł��邩
�k�H�ו��l�@��ށA�A�H�ׂ������A�B���A�C���i
�k�ړI�n�C���[�W�̌`���ߒ��l
�ړI�n�C���[�W�̌`���ɂ��āABeerli&Martin[21]�͍\���}��p���Ă��邪�A���̐}�ɂ��ĕ��͂�v������ƈȉ��̂悤�ɐ������Ă���B
���̍\���}�́A���߂Ă̗��s�҂ƃ��s�[�^�[����ʂ�����@�ō��ꂽ���̂ł��邪�\���}����邱�Ƃ��\�ɂȂ����̂́A
�����ʂɉe�������X�̃O���[�v�ɂ��F���C���[�W�̊Ԃɂ́A����Ⴂ�����݂��邩������Ȃ��B
�����s�[�^�[�͍ŏ��ɖK���O�̏���v���o���̂ɋ�J���邪�A���߂Ă̗��s�҂̏ꍇ�ł́A���̏�ƔF���C���[�W�̊W�͂��邱�Ƃ��ł���B
�����߂Ă̗��s�҂ƃ��s�[�^�[�̊Ԃɂ́A�ނ炪�ȑO�̂��̏ꏊ��K�₵�Ă������ǂ����ɂ���āA�ړI�n�Ɋւ���m�����x���Ɣނ�̓��@�ɈႢ���o�邩������Ȃ��B
�Ƃ��������R����ł���B
�}3-1-1�@�ړI�n�C���[�W�̍\���}[21]
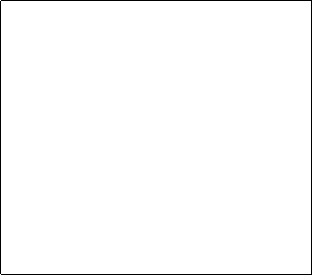
![]()
![]() ���(Information Sources)
���(Information Sources)
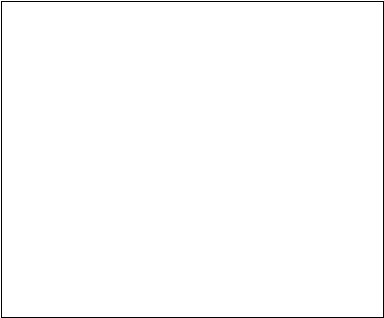 �����̗v��(Secondary)
�����̗v��(Secondary)
�U��(Induced) �@�@�@�@�ړI�n�m�o�C���[�W
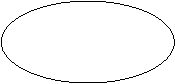 �L�@�I(Organic) �@ �iPerceived Destination Image)
�L�@�I(Organic) �@ �iPerceived Destination Image)
�@����(Autonomous)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�F���C���[�W
����v�ȗv��(Primary)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �iCognitive image�j

![]()
![]() �@�ȑO�̌o��(Previous Experience)�@�@�@�@�@�@
�@�ȑO�̌o��(Previous Experience)�@�@�@�@�@�@
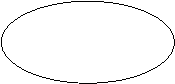 �K��̋��x(Intensity of visit)�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�S�̃C���[�W
�K��̋��x(Intensity of visit)�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�S�̃C���[�W
�@�@�@�@�@�@�@�@�@����C���[�W�@�@�@(Overall image)
 �l�v�f(Personal Factors)�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �iAffective
image�j�@�@
�l�v�f(Personal Factors)�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �iAffective
image�j�@�@
�����@(Motivations)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���n�q�̌o���iVacation Experience)
![]() ���Љ�l�����v����
���Љ�l�����v����
(Socio-demographic
Characteristics)
![]()
�@���̍\���}����A�ړI�n�̃C���[�W�`���ɂ͏�ƌl�v�f���e������A�Ƃ������Ƃ��킩��B��͎�v�ȗv���Ƒ��̗v���ɕ�����邪�A�L���A���f�B�A�Ȃǂɂ��U���iInduced�j�A�m�l����̏��ɂ��L�@�I�Ȃ��́iOrganic�j�A�j���[�X��h�L�������^���[�ɂ�鎩���iAutonomous�j�Ƃ������ԐړI�ȏ��ɂ��Ă͑��̗v���ƂȂ�B����A���ږړI�n��K�ꂽ���ƂŎ擾���ꂽ���v�ȗv���ɂȂ�A����͈ȑO�̖K��o���iPrevious Experience)��A�؍ݏꏊ�ɂǂꂭ�炢������������Ƃ������K��̋��x(Intensity of visit)�Ƃ������̂ł���B
�@�l�v�f�Ɋւ��ẮA���ʁA�N��A������x�A�Ƒ��A���C�t�T�C�N���A�Љ�K���A���Z�̏ꏊ�Ƃ������l�̎Љ�l�����v�����iSocio-demographic Characteristics)�A�S���w�I�Ɍ��铮�@(Motivations)�A�n�q�̌o���iVacation Experience)�ɂ���Ēm�o�C���[�W���`�������悤���B�����̗v���ɂ���āA������x����Ă���F���C���[�W�ɁA�ړI�n�ł̎��̌��ɂ��m�o�C���[�W������邱�ƂŁA�F���C���[�W�͊���C���[�W�ݏo���A�����͑S�̂̃C���[�W�����グ��A�Ƃ������\���ł���B
����ɁA�C���[�W�̌`���T�O�ɂ��Ēؔ@[22]�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
����҂̓��@�ƈӗ~�͉��߁i��ɒm�o�ƔF���̑��݊W�ɂ��j�̌��ʂ������A�F���Ƃ͌o�����������ł���A���̃C���[�W�ɂ̓v���X�ƃ}�C�i�X���܂�ł���B
�F���A�m�o�A����̕]���͑S�̃C���[�W�ɒ��ډe�����A���O�́i���j�C���[�W��o����̃C���[�W�ɊԐړI�ɉe������Ƃ���ɂ܂Ŏ���B�܂��A�l�v�f�͌̂̓����������͓��ݗv�f���܂�ł���A����͎���Ɋ���A���o�ɂ܂Ŏ���A�C���[�W�ߒ����`������B
�������܂Ƃ߂�ƁA�ړI�n�C���[�W�́A�l�̓��@�⎖�O���o0;; ;;ppp;/��ߋ��̌o���A����Ɍl�v�f�ɂ���Č`�������A�Ƃ������Ƃł���B���̂��Ƃ܂��āA�ݖ�(3)�ł͗��́i��s�ł́j�s���ɂ��ē���ʂɁA�ݖ�(4)�ł͌l�̑����ɂ��Ċe���⍀�ڂ�ݒ肵���B
�ݖ�(3) ���̍s���ɂ���
�k���{�l�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �k��p�l�l
�@ ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��s���p�p�x
�A ����ړI�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A��s���p�ړI �@�@
�B ��s���̗L���@�@�@�@�@�@�B ��ʎ�i
�C ��ɂ��ā@�@�@�@�@�@�C ���s��
�D ��s���p�ړI
�@�ݖ�(4) �l����
�@ ����
�A �N��
�B �ƒ��
�C �E��
�D ����
�E �Z��
2. �������@
�@2006�N8��25������9��10���܂ŁA��k�s�m�і�s�̔��H�e���g������L���i�ʐ^A�j�A����Ƀe���g���i�ʐ^B�j�ɂāA��p�l�A���{�l�ό��q�ɃA���P�[�g�������s�����B�������Ԃ́A�ł�����҂��W�܂鎞�ԑсA��7������10�����炢��ڈ��Ƃ��čs�����B�����Ώێ҂͌��肹���A�����_���ɑI�o�����B
�@�A���P�[�g����ɂ��ẮA��p�l207�l�A���{�l204�l�A�����f�[�^�Ƃ��Ďg�p�ł�����̂́A��p�l200�l�i�L�������97���j�A���{�l202�l�i99���j�A���v402�l�i98���j�ƂȂ����B�A���P�[�g�p���͕t�^1.�i���{�l�p�j��2.�i��p�l�p�j���Q�ƁB
�ʐ^A. ���H�e���g������L��ʐ^ B. ���H�e���g��


3.�@���͕��@
�@�A���P�[�g�œ���ꂽ�f�[�^�͂���\�t�g�ɂ́A�G�N�Z����SPSS���g�p�����B�ȉ��Ɏg�p�������͕��@�������B
(1)���q�����v�i�G�N�Z���j
���{�l�A��p�l���ꂼ��̐��ʂ�N��Ȃǂ̌l��{������A��s���p�p�x��ړI�Ȃǂ̗��̍s���ɂ��āA�S�����ŕ\���B
(2)���ϒl�E�W�����iSPSS�j
���{�l�E��p�l���ꂼ��́u���p���₷���v�ɂ��Ă̕��ϒl�E�W�����B
(3) t����iSPSS�j
�u���p���₷���v�ɂ��Ă̓����r���s���B�܂��A5.�̕��U���͂Ɠ��l�A��ҊԂɗL�Ӎ��������邩�ǂ����ׂ�B
(4)�N���X�W�v�i�G�N�Z���j
�u���̍s���v�Ɓu�����v���N���X�W�v������O���t������B
(5)���U���́iSPSS�j
�@�u�����v�Ɓu���p���₷���v�̗L�Ӎ�����B
�A�u���̍s���v�Ɓu���p���₷���v�̗L�Ӎ�����i�L�Ӎ��̌����鍀�ڂ̃O���t���j�B
��l�� ���ʂƕ���
���̏͂ł́A�A���P�[�g�����œ���ꂽ�f�[�^���W�v���ASPSS��G�N�Z�����g���ĕ��͂������ʂ�\������B1.��{�����f�[�^�̕\���A2.���p���₷���̓����r�A3.���̍s���ƌl�����̊W�A4.�l�����̈Ⴂ�͗��p���₷���ɂ��Ⴂ���o��̂��A5.���̍s���̈Ⴂ�͗��p���₷���ɂ��Ⴂ���o��̂��A�Ƃ������Ƃ����Ă����B
1. ��{�����f�[�^�E�E�E(1)�l��{�����A(2)���̍s��
��s�ɗ��Ă�����{�l�A��p�l�̌l��{�����Ɨ��̍s���ɂ��Ĉȉ��̕\�ɂ܂Ƃ߂��B
(1)�l��{����
�\4-1-1�@���ʁ@�@�@�@�@ �@�@�@�@�k���{�l�l�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�k��p�l�l
| ���� | | �l�� | �� | | �l�� | �� |
| �j�� | 82 | 40.6 | 82 | 41.0 | ||
| ���� | 120 | 59.4 | 118 | 59.0 | ||
| ���v | 202 | 100.0 | 200 | 100.0 |
�\4-1-2�@�N��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���{�l�l�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�k��p�l�l
| �N�� | | �l�� | �� | | �l�� | �� |
| 18���� | 0 | 0.0 | 7 | 3.5 | ||
| 18�`24 | 81 | 40.1 | 81 | 40.5 | ||
| 25�`34 | 82 | 40.6 | 76 | 38.0 | ||
| 35�`44 | 18 | 8.9 | 12 | 6.0 | ||
| 45�`54 | 12 | 5.9 | 16 | 8.0 | ||
| 55�`64 | 8 | 4.0 | 6 | 3.0 | ||
| 65�Έȏ� | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | ||
| ���v | 202 | 100.0 | 200 | 100.0 |
�\4-1-3�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�k���{�l�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k��p�l�l
| �� | | �l�� | �� | | �l�� | �� |
| ���� | 156 | 77.2 | 154 | 77.0 | ||
| �����A�q���Ȃ� | 25 | 12.4 | 21 | 10.5 | ||
| �����A�q������ | 21 | 10.4 | 25 | 12.5 | ||
| ���v | 202 | 100.0 | 200 | 100.0 |
�\4-1-4�@�E�Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���{�l�l�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�k��p�l�l
| �E�� | | �l�� | �� | | �l�� | �� |
| ������ | 13 | 6.4 | 15 | 7.5 | ||
| ��Ј� | 91 | 45.0 | 59 | 29.5 | ||
| ���c�� | 2 | 1.0 | 8 | 4.0 | ||
| �w�� | 67 | 33.2 | 73 | 36.5 | ||
| ���R�� | 6 | 3.0 | 17 | 8.5 | ||
| ��w | 10 | 5.0 | 11 | 5.5 | ||
| ���E | 7 | 3.5 | 6 | 3.0 | ||
| ���̑� | 6 | 3.0 | 11 | 5.5 | ||
| ���v | 202 | 100.0 | 200 | 100.0 |
�\4-1-5�@�����i����j�@�@�@�@�@�k���{�l�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�k��p�l�l
| ����(�~) | | �l�� | �� | | �i�����j | �l�� | �� |
| 10���ȉ� | 76 | 37.6 | 2���ȉ� | 97 | 48.5 | ||
| 10�`15�� | 22 | 10.9 | 2�`4�� | 66 | 33.0 | ||
| 15�`30�� | 72 | 35.6 | 4�`7�� | 26 | 13.0 | ||
| 30�`50�� | 18 | 8.9 | 7�`10 �� | 6 | 3.0 | ||
| 50�`80�� | 4 | 2.0 | 10���ȏ� | 5 | 2.5 | ||
| 80���ȏ� | 4 | 2.0 | | | | ||
| ���� | 6 | 3.0 | | | | ||
| ���v | 202 | 100.0 | ���v | 202 | 100.0 |
�� 1��p���͖�3.5���{�~
�\4-1-6�@�Z���@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���{�l�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k��p�l�l
| �Z�� | | �l�� | �� | | �Z�� | �l�� | �� | | �Z�� | �l�� | �� |
| ���� | 60 | 29.7 | �� | 4 | 2.0 | ��k | 157 | 78.5 | |||
| ��� | 35 | 17.3 | ��� | 3 | 1.5 | ���̑� | 43 | 21.5 | |||
| ���� | 19 | 9.4 | �ޗ� | 3 | 1.5 | | |||||
| �_�ސ� | 16 | 7.9 | �啪 | 3 | 1.5 | ||||||
| ��t | 7 | 3.5 | �ΐ� | 2 | 1.0 | ||||||
| ���� | 6 | 3.0 | �{�� | 2 | 1.0 | ||||||
| ���s | 6 | 3.0 | �V�� | 2 | 1.0 | ||||||
| ��� | 6 | 3.0 | ��k | 2 | 1.0 | ||||||
| ���m | 5 | 2.5 | �� | 1 | 0.5 | ||||||
| �L�� | 5 | 2.5 | �Q�n | 1 | 0.5 | ||||||
| | 4 | 2.0 | ���m | 1 | 0.5 | ||||||
| �O�d | 4 | 2.0 | ���Y | 1 | 0.5 | ||||||
| ���� | 4 | 2.0 | | | | ||||||
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
(2)���̍s��
�k���{�l�l
�\4-1-8�@����ړI ����ړI �l�� �� �ό� 172 85.1 �r�W�l�X 11 5.4 ���w 7 3.5 �m�l�ɉ�� 9 4.5 ���̑� 3 1.5 �\4-1-10�@�u�m���Ă����v�Ɠ��������́A���ɂ���Ēm��܂������H ���O���� �l�� �� �e���r 36 17.5 �K�C�h�u�b�N 105 51.0 ���s��� 6 2.9 �V���E�G�� 5 2.4 �C���^�[�l�b�g 21 10.2 �m�l 29 14.1 ���̑� 4 1.9
�\4-1-7�@����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
| ����� | �l�� | �� |
| 1�� | 160 | 79.2 |
| 2�� | 22 | 10.9 |
| 3�� | 5 | 2.5 |
| 4�� | 3 | 1.5 |
| 5��ȏ� | 12 | 5.9 |
�\4-1-9�@��p��K���O�����s��
���݂�m���Ă��܂������H
| ��s�̑��� | �l�� | �� |
| �m������ | 137 | 67.8 |
| �m��Ȃ����� | 65 | 32.2 |
�\4-1-11�@��s�𗘗p����ړI�i�����j
| ��s���p�ړI | �l�� | �� |
| ������ | 68 | 17.6 |
| �V�� | 85 | 22.0 |
| �ɂԂ� | 15 | 3.9 |
| �H�� | 139 | 36.0 |
| �ό����������� | 78 | 20.2 |
| ���̑� | 1 | 0.3 |
�k��p�l�l
�\4-1-13�@��s���p�ړI�i�����j ���p�ړI �l�� �� ������ 128 26.6 �V�� 93 19.3 �ɂԂ� 94 19.5 �H�� 165 34.2 ���̑� 2 0.4 �\4-1-15�@���i��s�ֈꏏ�ɍs���l�i�����j ���s�� �l�� �� ��l 19 5.3 �F�B 162 45.5 ���l 70 19.7 �Ƒ� 74 20.8 ���� 30 8.4 ���̑� 1 0.3
�\4-1-12�@��s���p�p�x
| ���p�p�x | �l�� | �� |
| ���� | 8 | 4.0 |
| �T4.5�� | 3 | 1.5 |
| �T2.3�� | 17 | 8.5 |
| �T1�� | 25 | 12.5 |
| ��2�� | 31 | 15.5 |
| ���P�� | 61 | 30.5 |
| 2,3������1�� | 31 | 15.5 |
| ���̑� | 24 | 12.0 |
�\4-1-14�@��s�܂ł̌�ʎ�i�i�����j
| ��ʎ�i | �l�� | �� |
| �l�q�s | 169 | 42.6 |
| �k�� | 14 | 3.5 |
| ���]�� | 7 | 1.8 |
| �� | 65 | 16.4 |
| �I�[�g�o�C | 88 | 22.2 |
| �o�X | 51 | 12.8 |
| ���̑� | 3 | 0.8 |
(3)����
(1)�l��{�����̕\����m�і�s�͓��䋤�ɒj�����������̗��p�������A��ƂȂ闘�p�ҔN��w��18~34�̎�҂ł���A�Ƃ������Ƃ��킩��B����Ė����҂̗��p�����|�I�ɑ����B
�E�ƂɊւ��ẮA�������s�����̂��ċx�݂Ƃ������Ƃ������Ă����{�l�ł͉�Ј�����ԑ����A���ɑ����̂��w���ł������B����A��p�l�͊w������ԑ��������B
�����Ɋւ��ē��{�l�́A10���~�ȉ��E15~30���~���������A����͊w���Ɖ�Ј��̗��p���������ƂɊW����̂ł͂Ȃ��낤���B�܂���Ј��̒��ł�10~15���~�����Ȃ����Ƃ���A�����ĉ��N���o��Ј��⍂�����Ă����Ј��̑��������ԁB��p�l��2�����ȉ��A2~4�����������������A��p�l�̕��Ϗ��C����3�����O��[23]�Ƃ������Ƃ��l����ƁA��������w���Ɖ�Ј��̗��p�ɊW���Ă���Ɛ���ł���B
�@�Z���Ɋւ��ẮA���{�l�͓������痈���l�������A�����ő��A�����̏��ƂȂ����B��p�l�͑�k���痈���l��8���Ƃ�͂�n���̐l�̗��p�������B
(2)���̍s���ɂ��ē��{�l�́A��p�ɖK���̂����߂ĂƂ����l�������������A���s�[�^�[�̒��ł��m�і�s�𗘗p����l�����\���邱�Ƃɂ����ڂ������B��s�����O�ɒm���Ă����Ɠ������l�͖�7���ŁA���̒��Ŕ����ȏ�̐l���K�C�h�u�b�N�ɂ���Ēm�����Ɠ������B���܂��p�̃K�C�h�u�b�N�ɖ�s����肠���Ȃ����̂͂Ȃ����Ƃ���A�K�C�h�u�b�N�̉e���͑傫���ƍl������B��s�𗘗p����ړI�ɂ��ẮA�H���A�ό�����������A�V�сA�������Ƃ������ł������B�����������ό�����������Ɠ�����l�����������̂��ʔ������ʂł���A���p�҂���s�ɉ������߂Ă���̂����l����肪����ƂȂ�B
��p�l�ɂ��āA���p�p�x�͐l�ɂ���ėl�X�ł��邪�A��1��ȉ��Ɠ�����l���������z���A�T1��ȏオ3���ɖ����Ȃ����Ƃ���A�p�ɂɎm�і�s�𗘗p����l�͏��Ȃ��̂ł��낤�B��s���p�ړI�ɂ��ẮA�H���Ɣ����������������B��s�܂ł̌�ʎ�i�͂l�q�s���K�w���߂��ɂ��邱�Ƃ���l�q�s�̗��p�������A��p�l�Ȃ�ł͂̃I�[�g�o�C�̗��p�����������B�܂��A�F�B�ƈꏏ�ɖ�s�֍s���Ɠ�����l�����������B
2. ���p���₷���̕��ϒl�A�����r
�@��s�̗��p���₷���ɂ��ē��{�l�A��p�l���ꂼ��5�i�K�]���œ����Ă�������B
�\4-2-1�ł͖�s�̔F���x�ɂ��āA�\4-2-2�ł͖�s�����x�ɂ��Ĉȉ��̌��ʂ��o���B�܂����{�l�Ƒ�p�l�̕��ϒl�̍��ɈӖ������邩�ǂ���t������g�p�����炩�ɂ���B
(�P)��s�F���x
�\4-2-1�@��s�F���x�̕��ϒl�A�����t����
| | ��s�F���x | | ���ϒl | �W���� | | ���ϒl | �W���� | | t �l | �L�ӊm�� (����) |
| ���{�l | ��p�l | �����r | ||||||||
| 1 | ��ʎ�i�͕֗� | 4.12 | 0.87 | 4.35 | 0.66 | -2.918 | 0.004** | |||
| 2 | �댯�ȏ� | 2.63 | 0.79 | 2.90 | 0.86 | -3.247 | 0.001** | |||
| 3 | �L�� | 3.75 | 0.95 | 2.75 | 1.08 | 9.883 | 0.000** | |||
| 4 | �ʔ����� | 4.27 | 0.69 | 3.75 | 0.81 | 7.032 | 0.000** | |||
| 5 | �������� | 3.72 | 1.13 | 3.93 | 0.84 | -2.130 | 0.034* | |||
| 6 | �q���Ǘ��͗ǂ� | 2.34 | 0.76 | 2.47 | 0.82 | -1.624 | 0.105 | |||
| 7 | ���{�Ɏ����ꏊ������ �^������ | 2.48 | 1.08 | 3.76 | 0.84 | -13.207 | 0.000** | |||
| 8 | ������������������ | 2.97 | 1.14 | 3.39 | 0.94 | -4.071 | 0.000** | |||
| 9 | �X�g���X�����܂� | 2.13 | 0.89 | 2.77 | 1.06 | -6.517 | 0.000** | |||
| 10 | ���G�͕s���� | 2.67 | 1.11 | 3.48 | 0.98 | -7.700 | 0.000** | |||
| 11 | �c�Ǝ��Ԃ͒Z�� | 2.30 | 0.85 | 2.45 | 0.82 | -1.759 | 0.079 | |||
| 12 | ���͋C�͗ǂ� | 3.90 | 0.78 | 3.25 | 0.92 | 7.622 | 0.000** | |||
| 13 | �֗��� | 3.68 | 0.84 | 3.98 | 0.81 | -3.611 | 0.000** | |||
| 14 | �ƂĂ������ł��� | 3.82 | 0.84 | 3.58 | 0.78 | 2.940 | 0.003** | |||
| 15 | ���t�̖�肪������ | 2.74 | 1.12 | | | | | |||
| 16 | �C���[�W�ʂ肾���� | 3.62 | 0.94 | | | | | |||
| 15 | �ό��q�Ɋ��߂� | | | 3.98 | 0.83 | | | |||
*p��0.05
, **p��0.01
��p�l�Ƃ̕��ς̍���0.5�ȏ�o�����ڂ́u�L���v�u�ʔ����v�u���{�Ɏ����ꏊ������v�u�X�g���X�v�u���G�͕s���v�u���͋C�͗ǂ��v�ł���B�����o�����ڂ�����ƁA���{�l�͑�p�l�����u�X�g���X�v�u���G�͕s���v�Ȃǃ}�C�i�X�C���[�W�̓��ӓx���Ⴍ�A�u���͋C�͗ǂ��v�u�ʔ����v�Ȃǃv���X�C���[�W�̓��ӓx���������Ƃ��킩��B
(2)��s�����x
�\4-2-2�@��s�����x�̕��ϒl�A�����t����
| | ��s�����x | | ���ϒl | �W���� | | ���ϒl | �W���� | | t �l | �L�ӊm�� (����) |
| | �k�ݔ��l | ���{�l | ��p�l | �����r | ||||||
| 1 | �g�C���̐��͏\�� | 2.50 | 0.79 | 2.15 | 0.92 | 4.018 | 0.000** | |||
| 2 | ���ݔ��̐��͏\�� | 2.56 | 0.90 | 2.48 | 1.05 | 0.890 | 0.374 | |||
| 3 | �H���p�̐Ȃ̐��͏\�� | 3.09 | 1.03 | 2.74 | 1.04 | 3.471 | 0.001** | |||
| 4 | �Ŕ͐l�ڂ��Ђ� | 3.77 | 0.82 | 3.51 | 0.99 | 2.894 | 0.004** | |||
| | �k�]�ƈ��l | | | | | | | |||
| 1 | �X���͐e�� | 3.54 | 0.82 | 3.41 | 0.88 | 1.620 | 0.106 | |||
| 2 | �X���͐M���ł��� | 3.06 | 0.69 | 3.13 | 0.82 | -0.874 | 0.383 | |||
| | �k���i�l | | | | | | | |||
| 1 | ���i�̎�ނ͖L�x | 3.79 | 0.98 | 4.05 | 0.84 | -2.777 | 0.006** | |||
| 2 | �~�������̂���ɓ��� | 3.12 | 0.81 | 3.87 | 0.89 | -8.808 | 0.000** | |||
| 3 | ���i�̕i���͗ǂ� | 2.78 | 0.79 | 2.94 | 0.88 | -1.894 | 0.059 | |||
| 4 | ���i�͈��� | 3.84 | 0.88 | 3.36 | 0.96 | 5.298 | 0.000** | |||
| | �k�H�ו��l | | | | | | | |||
| 1 | �H�ו��̎�ނ͖L�x | 3.84 | 0.95 | 4.13 | 0.76 | -3.433 | 0.001** | |||
| 2 | �H�ׂ������̂����� | 3.82 | 0.88 | 4.14 | 0.71 | -3.937 | 0.000** | |||
| 3 | �H�ו��͔������� | 3.76 | 0.82 | 3.96 | 0.84 | -2.328 | 0.020** | |||
| 4 | �H�ו��͈��� | 3.92 | 0.89 | 3.43 | 1.05 | 5.046 | 0.000** | |||
*p��0.05
, **p��0.01
(3)����
�\4-2-1�ł͓��{�l�̕�����p�l������s�ɑ���C���[�W�͗ǂ��Ƃ������Ƃ��킩�������A��s�����x�ɂ��Ă͈ӊO�Ȍ��ʂ��o���B���{�l�͑�p�l�����k���i�l�k�H�ו��l�ɂ��āA���i�����������ڂɑ��閞���x���ǂ���Ⴂ�B�����ŊԈႦ�Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��A����Ŕ�r������ƒl�͒Ⴂ���A���ꂼ��̖����x����������ƕ��ʈȏ�̂�▞���Ƃ������Ƃ���ł���A�Ƃ������Ƃ��B����������̔�r�݂̂ɒ��ڂ��Ă݂�ƁA���{�l�́k���i�l��k�H�ו��l�Ƃ�������̓I�Ȗ����x����p�l�����Ⴂ�̂ɂ�������炸�A��s�S�̂̃C���[�W�͑�p�l�����ǂ��A�Ƃ������Ƃ�������B
�ȏ�̌��ʂ���A�傫��������Ɗό��q�ɂƂ��Ė�s�͗��p���₷���悤�Ɍ����邪�A����ɖ�s�𗘗p���₷������ɂ́A��̓I�ȃ��m�i���i�E�H�ו��j�ɂ��ĉ��P���Ă������Ƃ��K�v�Ȃ̂�������Ȃ��A�Ƃ������Ƃ������邾�낤�B
3. �u���̍s���v�Ɓu�����v�̃N���X�W�v
(1)���{�l
�u���̍s���v�Ɓu�����v���N���X�W�v���邱�ƂŁA��̊W�ɂ��Č��Ă����B�ȉ��͓��{�l�̇@����A�A����ړI�A�B���O���̗L���A�C��A�D��s���p�ړI�ɂ��āu�����v�Ƃ̊W���O���t���������̂ł���B�����Ől�����Ⴂ���́i�{��1���Q�Ɓj�̓��ِ��ɂ��Ă͌X���Ƃ��Ĕc�����A���q�͂��Ȃ��B
*�Z���ɂ��Ă͊e���ɎU����Ă������߁A�������ɂ܂Ƃ߂Ă���B
�O���t4-3-a2 �N��
�@�����
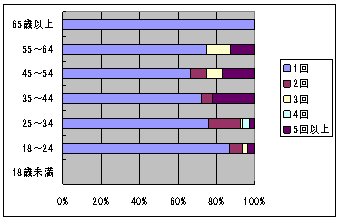
�O���t4-3-a1 ���ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�O���t4-3-a4 �E��

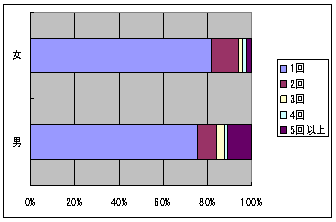
�O���t4-3-a3 �@
�O���t4-3-a6 �Z��

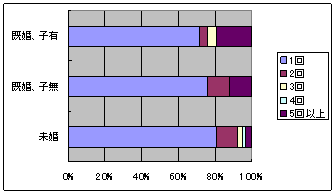
�O���t4-3-a5 �����i�~�j
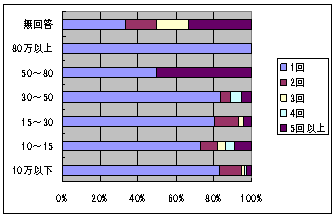
�@�j���͏�������3��ȏ�̃��s�[�^�[�������B�܂��A5��ȏ�Ɠ����鐢���35�Έȏ�A����Ɏ��c�Ƃ͔������߂Ă��邱�Ƃ���A���s�[�^�[�̓r�W�l�X�ł̗��p���������Ƃ��\�z�����B
�O���t4-3-b2 �N��
�A����ړI
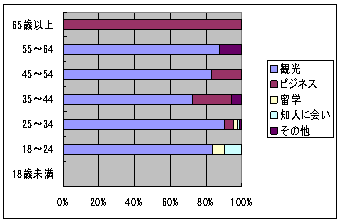
�O���t4-3-b1 ����
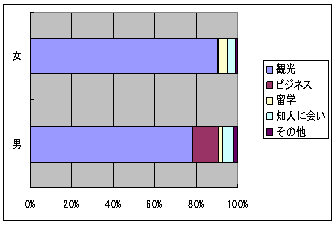
�O���t4-3-b4 �E��

�O���t4-3-b3 ��
�O���t4-3-b6 �Z��
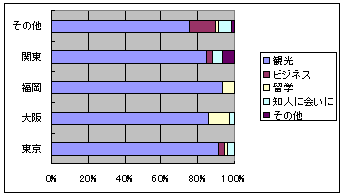
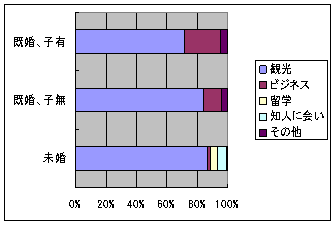
�O���t4-3-b5 �����i�~�j

�ό��ȊO�ɒ��ڂ��Ă݂�ƁA�j���A���ł�35~54�E65�Έȏ�̃r�W�l�X�ړI�̗��p�������B�܂��A���c�Ƃ̃r�W�l�X�ړI���������Ƃ��痈��̗\�z�����������Ƃ��킩��B���w�͊w���������R�Ɓi�t���[�^�[�j�E���E�̕����������Ƃ���w�Z�𑲋Ƃ��Ă��痯�w���Ă���l�������̂��낤�B�܂��A�m�l�ɉ�ɗ����Ɠ�����̂͊w�������������B
�O���t4-3-c2 �N��
�B���O���̗L��
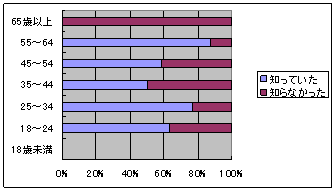
�O���t4-3-c1 ����
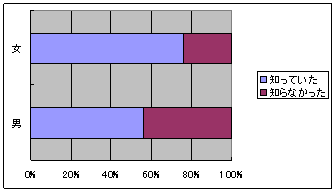
�O���t4-3-c4 �E��
�O���t4-3-c3 ��
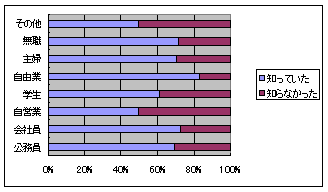
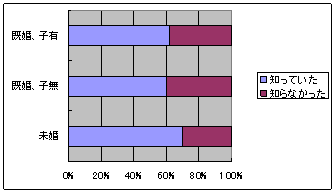
�O���t4-3-c6 �Z��
�O���t4-3-c5 �����i�~�j
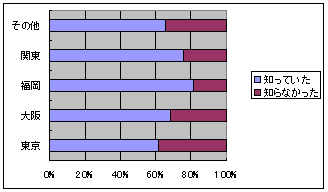

�@��s��m���Ă����Ɠ�����̂͒j�����������̕������������B�܂��A�N��ł�55~64�A����25~34�����������B�w���⎩�c�Ƃ͒m���Ă����l�̊������Ⴍ�A���R�Ƃ̊��������������B����Ɍ����ɂ��ẮA30���~����ƌ����������Ȃ�ɂ�Ēm���Ă���l�̊����͌����Ă������Ƃ��킩��B�Z���Ɋւ��Ă͕����̊��������������B
�O���t4-3-d2 �N��
�C���
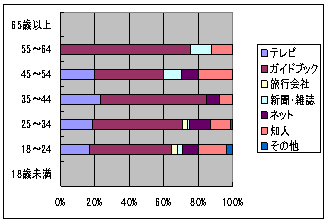
�O���t4-3-d1 ����
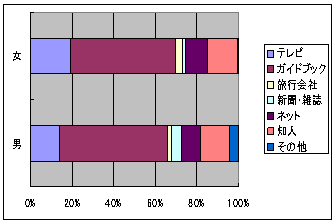
�O���t4-3-d4 �E��
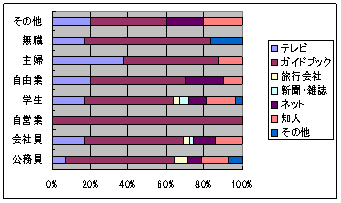
�O���t4-3-d3 ��

�O���t4-3-d6 �Z��
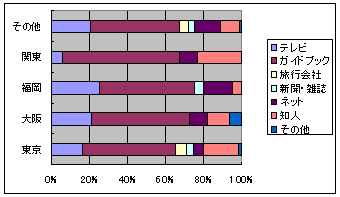
�O���t4-3-d5 �����i�~�j
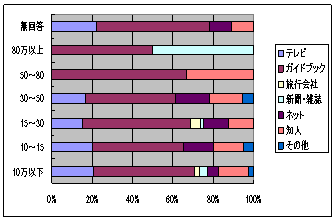
�@�j���Ԃł͑傫�ȈႢ�͌����Ȃ������B�N��ł́A�V���E�G���Ɠ������l��45�Έȏ�ɑ�������ꂽ�B�m�l��������Ɠ������̂͊����҂Ŏq��������l�̊��������������B�܂��A��w�̓e���r����Ƃ��Ă���l���������Ƃ��킩��B�����������Ȃ�ɂ�e���r����Ƃ���l�͌����Ă����A80���~�ȏ�͐V���E�G���̊����������ł���B
�O���t4-3-e2 �N��
�D��s���p�ړI
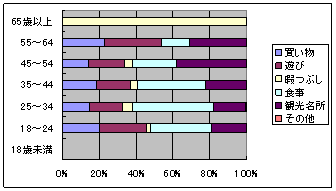
�O���t4-3-e1 ����
�O���t4-3-e4 �E��
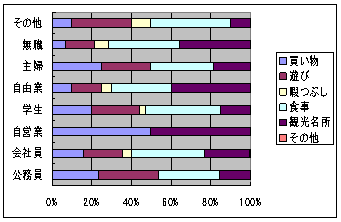
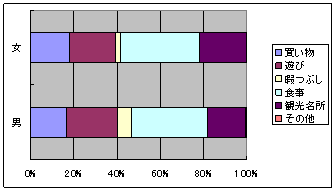
�O���t4-3-e3 ��
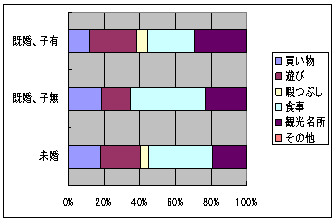
�O���t4-3-e6 �Z��
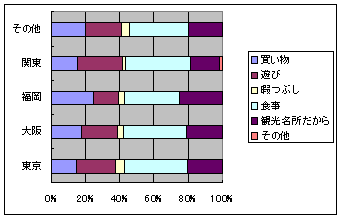
�O���t4-3-e5 �����i�~�j
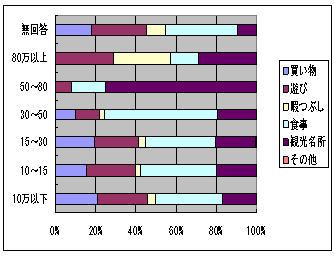
�@���ʁE�E�Z���ł͑傫�ȈႢ�͌����Ȃ������B�N��ɂ��ẮA�ό�����������Ɠ�����l��45~54�ɑ�������ꂽ�B����Ɋό�����������Ɠ�����l�́A���c�ƂƎ��R�ƁA������50���~�ȏ�̐l�ɑ�������ꂽ���Ƃ���A�����̐l�X�͐H���┃�����Ƃ������w���ɑ���ړI�ӎ����ア�ƍl������B
(2)��p�l
�ȉ��͑�p�l�̇@���p�p�x�A�A��s���p�ړI�A�B��ʎ�i�A�C��s���s�҂Ɓu�����v�̊W���O���t���������̂ł���B
�O���t4-3-f2 �N��
�@���p�p�x

�O���t4-3-f1 ����
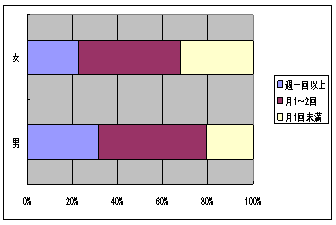
�O���t4-3-f4 �E��
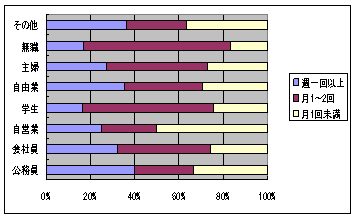
�O���t4-3-f3 ��
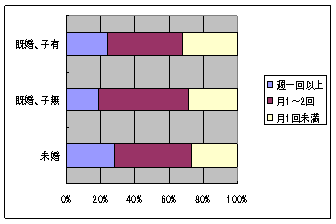
�O���t4-3-f6 �Z��
�O���t4-3-f5 �����i���j
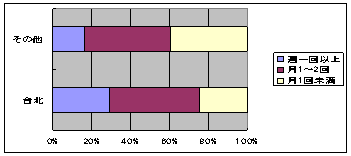
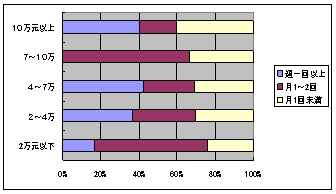
�@���������j���̕������p�p�x�͍����A55~64�̐l�̕p�x�͂��Ȃ荂���B�E�Ƃɂ���ĕp�x�ɂ���������邪�A��1~2��̗��p�͊w���△�E�ɑ������Ƃ��킩��B�����ɂ��Ă�2�����ȉ��̐l�X�̗��p�͕p�ɂł͖������Ƃ��킩��B�Z���Ɋւ��Ă͂�͂�A��k�ɏZ�ސl�̕����p�x�͍����B
�A��s���p�ړI
�O���t4-3-g2 �N��
�O���t4-3-g1 ����
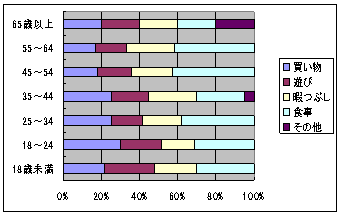
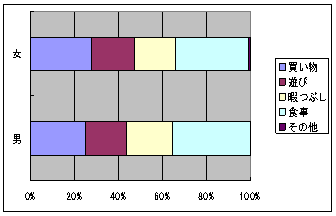
�O���t4-3-g4 �E��
�O���t4-3-g3 ��
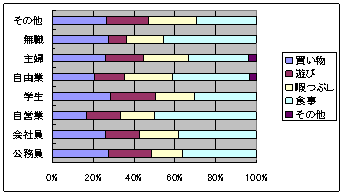
�O���t4-3-g6 �Z��
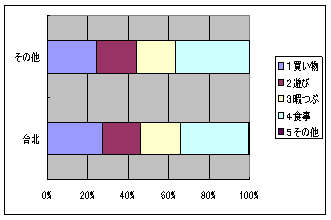
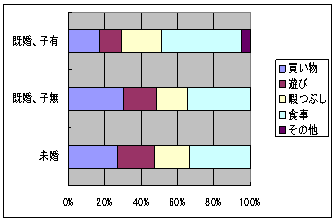
�O���t4-3-g5 �����i���j
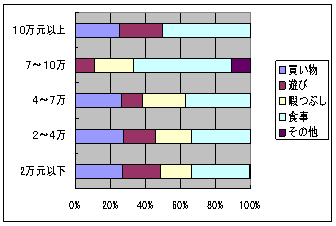
�O���t4-3-h2 �N��
�@���ʁE�N��E�Z���ɂ��ړI�̑傫�ȈႢ�͌����Ȃ������B�����҂Ŏq��������l�͗V�т̊������Ⴍ�H���ł̗��p�������B�E�Ƃɂ��Ă͐H����ړI�Ƃ���l�͎��c�ƁE���E���������Ă���B
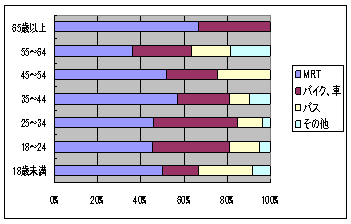
�B��ʎ�i
�O���t4-3-h1 ����
�O���t4-3-h4 �E��
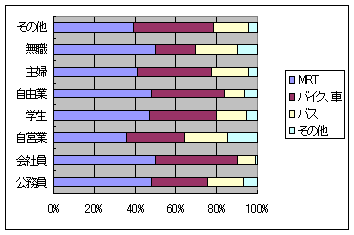
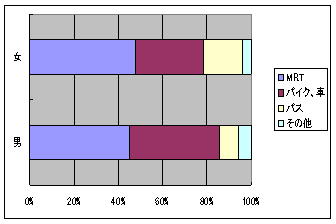
�O���t4-3-h3 ��
�O���t4-3-h6 �Z��
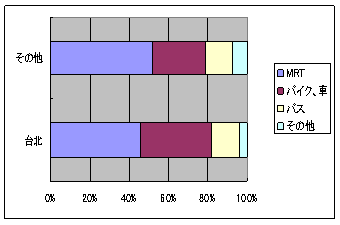

�O���t4-3-h5 �����i���j
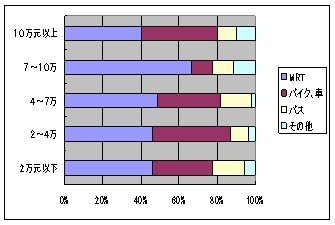
�@�E�����ɂ��Ă͑傫�ȈႢ�������Ȃ������B�j���̃o�C�N�E�Ԃ̗��p�������A�����̓o�X�̗��p�������B�N��E�E�Ƃɂ��Ă͂�������邪���ِ��͌���ꂸ�A�Z���Ɋւ��Ă͋����I�Ȃ��̂�����A��k�ȊO�ɏZ�ސl�X�̕����MRT�̗��p�������B
�O���t4-3-i2 �N��
�C��s���s��
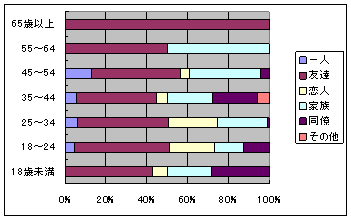
�O���t4-3-i1 ����

�O���t4-3-i4 �E��
�O���t4-3-i3 ��
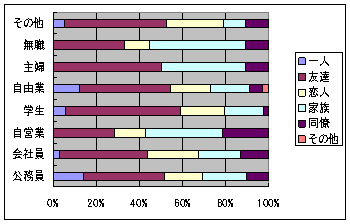
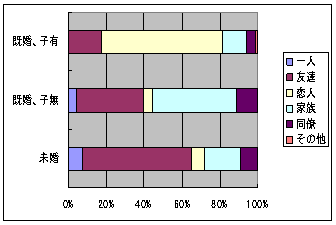
�O���t4-3-i6 �Z��
�O���t4-3-i5 �����i���j
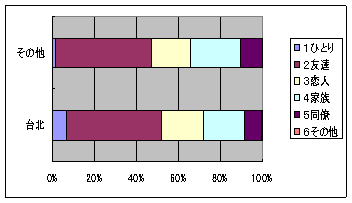
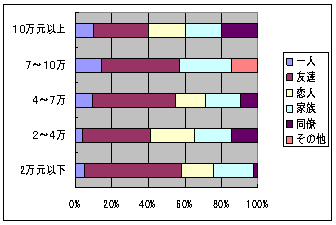
�@�����E�Z���ɂ��Ă͑傫�ȈႢ�������Ȃ������B���l�i�v�w�j�ƈꏏ�ɂƓ�����̂͏��������j���̕��������A�����҂Ŏq��������l�����|�I�ɑ������Ƃ��킩��B�����45~64�̐l�͉Ƒ��Ɠ�����l�������B
(3)����
�ȏ�̃N���X�W�v�̌��ʂ��܂Ƃ߂�ƁA���{�l�ɂ��ẮA����������l�X�͒j���E35~54�E���c�ƂɌ����邱�ƁA�܂�����ړI�̃O���t�ƌX������v���邱�Ƃ���r�W�l�X��ړI�ŗ��p����l�X�ł���B����ɁA��s�̑��݂�m���Ă���l�X�́A�����E55~64��25~34�E���R�Ƃɑ��������A�N��E�E�E�ƁE�����ɂ���Ď�Ƃ������قȂ�B��s���p�ړI�́A�ό�����������Ɠ�����l�X��45��~54�E���c�ƂƎ��R�ƁE����50���~�ȏ�ɑ�������ꂽ�B
�@��p�l�ɂ��ẮA���p�p�x�͔N��E�E�ƁE�����ɂ���Ă���������A�T1��ȏ�ƕp�ɂɗ��p���Ă���̂́A55��~64�E�������ɑ�������ꂽ�B��s���p�ړI�͐H����ړI�Ƃ���l�X�͊����Ҏq���L��E���c�ƂƖ��E�̊��������������B��ʎ�i�͂��ꂼ������������̂̑����ɂ���ČX���͌����Ȃ������B��s���s�҂͉Ƒ��Ɠ�����l�X��45~64�ɑ����A���l�i�v�w�j�Ɠ�����l�X�������Ҏq���L��ɑ������Ƃ���A�v�w�ł̗��p�͗c���q�������Ⴂ�l�X�̂��Ƃł���ƍl���邱�Ƃ��ł���B
4. �u�����v�Ɓu���p���₷���v�̗L�Ӎ�����
���ʂ�N��Ȃǂ̌l���ɂ���āu���p���₷���v�̕]���ɍ���������̂��B�ȉ��A���ʁE�N��E�E�E�ƁE�����E�Z���Ɓu���p���₷���v�̂�����A���U���͂��s���A�L�Ӎ��̌���ꂽ���ڂ��ȉ��ɕ\������B�܂��A����ɂ���āu���p���₷���v���قȂ邱�Ƃ��{�͂�3�Ŕ����������߁A���{�l�E��p�l���čl���Ă����B
(1)���{�l
�@����
�\4-4-1�@���ʂƁu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05 , **p��0.01
| �@���� | ���ϒl | t�l | �L�ӊm�� (����) | |
| �j�� | ���� | |||
| ��s�͍L�� | 4.00 | 3.58 | 3.312 | 0.001** |
| �S�~���̐��͏\�� | 2.40 | 2.68 | -2.173 | 0.031* |
���ʂƁu���p���₷���v�ɂ���t������s�����Ƃ���A�ȏ�̍��ڂɍ��ق�����ꂽ�B�u��s�͍L���v�Ƃ������ڂɑ��A�j���̕���������蓯�ӓx���������Ƃ��킩��B�܂��A�u�S�~���̐��͏\�����v�Ƃ������ڂɑ��ẮA�����̕������ӓx�͍��������B
�A�N��
�\4-4-2�@�N��Ɓu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05
| ���� | F �l | �L�ӊm�� | Scheffe�@ |
| �ʔ��� | 2.436* | 0.049 | �~ |
| ���G�s�� | 3.038* | 0.018 | �~ |
| ���� | 2.506* | 0.043 | �~ |
| �g�C���̐��͏\�� | 3.376* | 0.011 | 2>3 |
| �H�ו��͔������� | 3.278* | 0.013 | 2>6 |
�N��Ɓu���p���₷���v�ɂ��ĕ��U���͂��s�����Ƃ���A�ȏ�̍��ڂɈႢ������ꂽ�B�����̍��ڂɑ��āA�댯���������邽�߂ɑ��d��r���s�����BScheffe�@�i�ȉ��̑��d��r��Scheffe�@���Ӗ�����j���g�p�����Ƃ���A�u�g�C���̐��͏\���v�Ɓu�H�ו��͔��������v�̍��ڂɗL�Ӎ��������A���̑��̍��ڂɂ͌����Ȃ������i�~�j�B
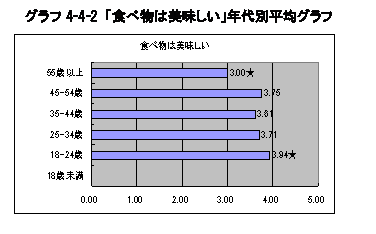 �O���t4-4-1 �u�g�C���̐��͏\�����v�N��ʕ��σO���t
�O���t4-4-1 �u�g�C���̐��͏\�����v�N��ʕ��σO���t
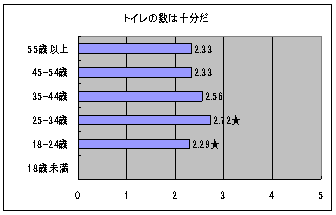
�ȉ��Ɋe���ϒl���O���t�ő��d��r���s�������ʁA�u�g�C���̐��͏\�����v�̃O���t�́A18-24��25-34�̊ԂɗL�Ӎ�������ꂽ�i���j�B�u�H�ו��͔��������v�̃O���t�́A18-24��55�Έȏ�̊ԂɗL�Ӎ�������ꂽ�i���j�B55�Έȏ�ł́A�u�H�ו��͔��������v�ɑ��铯�ӓx�͑��̔N��������Ȃ�Ⴂ���Ƃ��킩��B
�B��
�\4-4-3 �Ɓu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05
| ���� | F �l | �L�ӊm�� | scheffe |
| ���t�̖�肪������ | 3.553* | 0.030 | �~ |
�Ɓu���p���₷���v�ɂ��ĕ��U���͂��s�����Ƃ���A�u���t�̖�肪�������v�̍��ڂɍ��ق�����ꂽ���A���d��r���s�������ʁA�L�Ӎ��͌����Ȃ������B
�C�E��
�\4-4-4�@�E�ƂƁu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05 , **p��0.01
| ���� | F �l | �L�ӊm�� | scheffe |
| �������� | 2.609* | 0.019 | �~ |
| �C���[�W�ʂ� | 2.920** | 0.009 | �~ |
| ���i�̎�ނ͖L�x | 2.629* | 0.018 | �~ |
| �H�ו��̎�ނ͖L�x | 2.493* | 0.024 | �~ |
�E�ƂƁu���p���₷���v�ɂ��ĕ��U���͂��s�����Ƃ���A�ȏ�̍��ڂɈႢ������ꂽ���A���d��r���s�������ʁA�����ɗL�Ӎ��͌����Ȃ������B
�D����
�\4-4-5�@�����Ɓu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05 , **p��0.01
| ���� | F �l | �L�ӊm�� | scheffe |
| �ʔ��� | 2.470* | 0.046 | �~ |
| �H�ו��͔������� | 3.548** | 0.008 | 2>5 |
�����Ɓu���p���₷���v�ɂ��ĕ��U���͂��s�������ʁA�u�ʔ����v�u�H�ו��͔��������v�Ƃ������ڂɍ��ق�����ꂽ���A���d��r���s�����Ƃ���u�H�ו��͔��������v�̍��ڂɂ̂ݗL�Ӎ�������ꂽ�B�ȉ��ɕ��ϒl���O���t�Ŏ����B
�O���t4-4-3�@�u�H�ו��͔��������v�����i�~�j�ʕ��σO���t
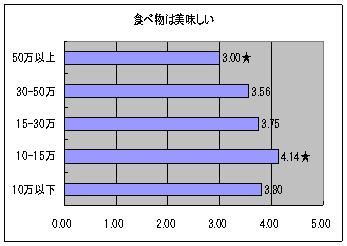 ���d��r���s��������10-15���~��50���~�ȏ�̊ԂɗL�Ӎ�������ꂽ�i���j�B�܂��A10-15���~���猎���������Ȃ�ɂ�A�u�H�ו��͔��������v�ɑ��铯�ӓx�͒Ⴍ�Ȃ��Ă������Ƃ��킩��B���̌��ʂ����s�͏��������ł��邱�Ƃ��킩��B
���d��r���s��������10-15���~��50���~�ȏ�̊ԂɗL�Ӎ�������ꂽ�i���j�B�܂��A10-15���~���猎���������Ȃ�ɂ�A�u�H�ו��͔��������v�ɑ��铯�ӓx�͒Ⴍ�Ȃ��Ă������Ƃ��킩��B���̌��ʂ����s�͏��������ł��邱�Ƃ��킩��B
�E�Z��
�\4-4-6 �Z���Ɓu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05 , **p��0.01
| �@���� | F �l | �L�ӊm�� | scheffe |
| ���{�ɂ������ꏊ������ | 5.732** | 0.000 | 1>2, 4>2, 5>2 |
| �������� | 3.498** | 0.009 | 3>2 |
| �S�~���̐��͏\���� | 2.538* | 0.041 | �~ |
| �H�ו��̎�ނ͖L�x | 3.208* | 0.014 | �~ |
�Z���Ɓu���p���₷���v�ɂ��ĕ��U���͂��s�������ʁA�ȏ�̍��ڂɍ��ق�����ꂽ�B�����̍��ڂɑ����d��r���s�����Ƃ���u���{�ɂ������ꏊ������v�Ɓu���������v�̍��ڂɗL�Ӎ��������A���̑��̍��ڂɂ͌����Ȃ������B�ȉ��Ɋe���ϒl���O���t�Ŏ����B
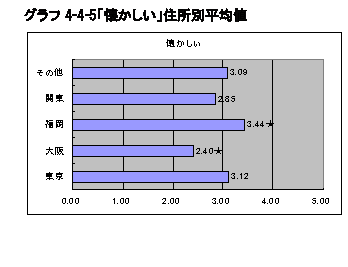 �O���t4-4-4 �u���{�ɂ������ꏊ������v�Z���ʕ��ϒl
�O���t4-4-4 �u���{�ɂ������ꏊ������v�Z���ʕ��ϒl
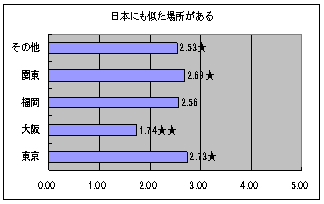
���d��r���s�������ʁA�u���{�ɂ������ꏊ������v�̃O���t�ł́A���ɑ��ē����A�֓��A���̑��̊ԂɗL�Ӎ�������ꂽ�i���j�B���͑����ɔ�ׁA���ӓx���Ⴂ�Ƃ������Ƃ��킩��B�u���������v�̃O���t�ł́A���ƕ����̊ԂɗL�Ӎ�������ꂽ�i���j�B���Ɋւ��Ă̓O���t4-4-4�̌��ʂƊW���āA�u���������v�ɑ��铯�ӓx�͍ł��Ⴂ�̂��낤�B
�܂��A�����͉���Ȃǂ��������Ƃ��瑼�̌��������ӓx�������̂ł͂Ȃ����낤���B
(2)��p�l
���{�l�Ɠ��l�A���ʁE�N��E�E�E�ƁE�����E�Z���Ɓu���p���₷���v��t����A���U���͂��s���A�L�Ӎ��̌���ꂽ���ڂ��ȉ��ɕ\������B����ɕ��U���͂ňႢ������ꂽ���ڂɑ��āA���d��r�iScheffe�@�j���s���A���̍��ڂ̊e���ϒl���O���t�������B
�@����
�\4-4-7�@���ʂƁu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05 , **p��0.01
| ���� | ���ϒl | ���l | �L�ӊm�� �i�����j | |
| �j�� | ���� | |||
| �c�Ǝ��Ԃ͒Z�� | 2.59 | 2.35 | 2.037 | 0.043 |
�@���ʂƁu���p���₷���v�ɂ���t������s�����Ƃ���A�u�c�Ǝ��Ԃ͒Z���v�Ƃ������ڂɑ��Ă̂ݗL�Ӎ�������ꂽ�B���������ۂ̒l�Ƃ��Ă̍��͏������B
�A�N��
�\4-4-8�@�N��Ɓu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05 , **p��0.01
| ���� | F �l | �L�ӊm�� | Scheffe |
| �q���Ǘ��͗ǂ� | 3.215 | 0.008** | 6>1 |
| �������� | 3.295 | 0.007** | 5>2 |
| ���� | 2.585 | 0.027* | �~ |
| �ό��q�Ɋ��߂� | 2.448 | 0.035* | �~ |
| �g�C���̐��͏\�� | 2.347 | 0.043* | �~ |
| �H�ׂ������̂����� | 2.266 | 0.050* | �~ |
| �H�ו��͔������� | 2.634 | 0.025* | �~ |
�N��Ɓu���p���₷���v�ɂ��ĕ��U���͂��s�������ʁA�ȏ�̍��ڂɍ��ق�����ꂽ�B�����̍��ڂɑ����d��r���s�����Ƃ���A�u�q���Ǘ��͗ǂ��v�Ɓu���������v�̍��ڂɗL�Ӎ��������A���̑��̍��ڂɂ͌����Ȃ������B�ȉ��Ɋe���ϒl���O���t�Ŏ����B
*65�Έȏ�̐l�������Ȃ��������߁A55�Έȏ�̒��ɂ܂Ƃ߁A�댯�x���������B
�O���t4-4-5 �u�q���Ǘ��͗ǂ��v�N��ʕ��ϒl�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O���t4-4-6
�u���������v�N��ʕ��ϒl
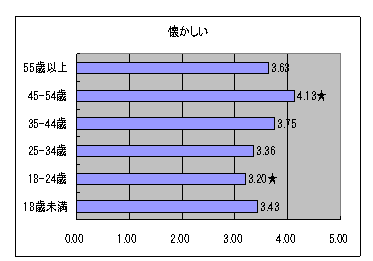
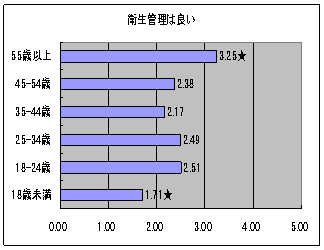
���d��r���s�������ʁA�u�q���Ǘ��͗ǂ��v�̃O���t�ł́A18�Ζ�����55�Έȏ�̊ԂɗL�Ӎ�������ꂽ�i���j�B���̍��ڂɂ��Ă͎�҂̕����A�������]�������Ă��邪�A�u�H�ׂ������̂�����v�u�H�ו��͔��������v�̍��ڂɂ��Ă͎�҂̕��������]�������Ă���B�@�u���������v�̃O���t�ł́A18-24��45-54�̊ԂɗL�Ӎ�������ꂽ�i���j�B
�B��
�\4-4-9�@�@�Ɓu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05 , **p��0.01
| ���� | F �l | �L�ӊm�� | Scheffe |
| �댯 | 3.275 | 0.040* | 2>1 |
| �������� | 4.228 | 0.016* | 3>1 |
| ���G�͕s���� | 3.665 | 0.027* | 1>3 |
| ���i�̎�ނ͖L�x | 5.779 | 0.004** | 1>3 |
| �~�������̂����� | 5.894 | 0.003** | 1>3 |
| ���i�͈��� | 4.017 | 0.020* | 1>3 |
| �H�ׂ������̂����� | 4.364 | 0.014* | �~ |
�Ɓu���p���₷���v�ɂ��ĕ��U���͂��s�����Ƃ���A�ȏ�V���ڂɈႢ������ꂽ�B�����̍��ڂɑ����d��r���s�����Ƃ���A�u�댯�v�u���������v�u���G�͕s�����v�u���i�̎�ނ͖L�x�v�u�~�������̂�����v�u���i�͈����v�Ƃ������ڂɗL�Ӎ��������邱�Ƃ��킩�����B�ȉ��Ɋe���ϒl�������B
�O���t4-4-7 �u�댯�v�ʕ��ϒl�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O���t4-4-8
�u���������v�ʕ��ϒl
�O���t4-4-10 �u���i�̎�ނ͖L�x�v�ʕ��ϒl
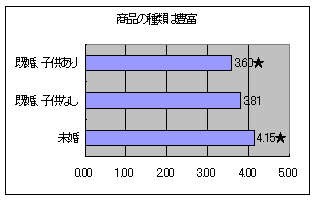
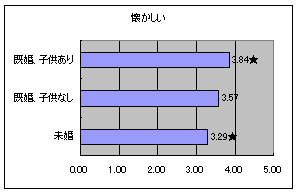
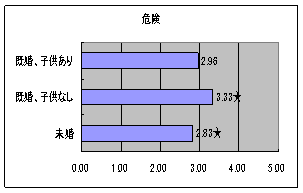
�@�O���t4-4-9 �u���G�͕s�����v�ʕ��ϒl�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
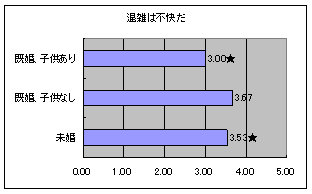
�O���t4-4-12 ����i�͈�����ʕ��ϒl
�@�O���t4-4-11 �u�~�������̂�����v�ʕ��ϒl
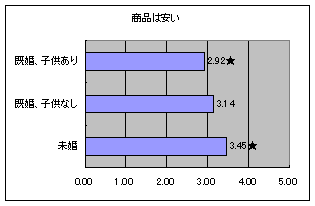
�@
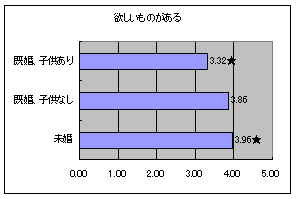
���d��r���s�������ʁA�u�댯�v�̃O���t�����͖����Ɗ����q���Ȃ��̊ԂɗL�Ӎ�������ꂽ���̂́A���̑��̍��ڂɂ��Ă͖����Ɗ����q������̊ԂɗL�Ӎ�������ꂽ�i���j�B
�܂��A�u���i�̎�ނ͖L�x���v�u�~������������v�u���i�͈����v�ƁA���i�ɑ��鍀�ڂ������B���̌��ʂ���l�X�̏ɂ���ď��i�ɑ��閞���x�̈Ⴂ����Ɍ����邱�ƂƁA�����҂̕������i�ɑ��閞���x�������X���ɂ��邱�Ƃ��킩��B
�C�E��
�\4-4-10 �E�ƂƁu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05 , **p��0.01
| ���� | F �l | �L�ӊm�� | Scheffe |
| �ό��q�Ɋ��߂� | 3.431** | 0.003 | �~ |
| �S�~���̐��͏\�� | 3.036** | 0.007 | �~ |
| �H�ו��̎�ނ͖L�x | 3.769** | 0.001 | 3>5 |
| �H�ׂ������̂����� | 2.422* | 0.028 | �~ |
| �������� | 2.178* | 0.047 | �~ |
�E�ƂƁu���p���₷���v�ɂ��ĕ��U���͂��s�������ʁA�ȏ�̍��ڂɈႢ������ꂽ���A���d��r���s�����Ƃ���u�H�ו��̎�ނ͖L�x�v�Ƃ������ڂ̂ݗL�Ӎ�������ꂽ�B�ȉ��ɕ��ϒl�̃O���t�������B
�@*���c�Ƃ̐l�������Ȃ��������߁A���̑��Ɏ��c�Ƃ����邱�ƂŊ댯�x���������B
�@�O���t4-4-13 �u�H�ו��̎�ނ͖L�x�v�̐E�ƕʕ��ϒl
���d��r�̌��ʁA�w���Ǝ�w�̊ԂɗL�Ӎ�������ꂽ�i���j�B
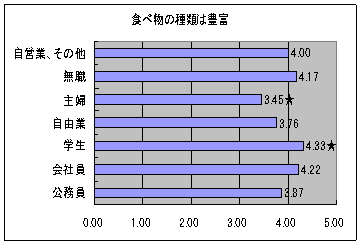
�D����
�\4-4-11�@�����Ɓu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05
| ���� | F �l | �L�ӊm�� | Scheffe |
| �ό��q�Ɋ��߂� | 3.234* | 0.023 | �~ |
| �g�C���̐��͏\�� | 3.390* | 0.019 | �~ |
�����Ɓu���p���₷���v�ɂ��ĕ��U���͂��s�����Ƃ���A�u�ό��q�Ɋ��߂�v�u�g�C���̐��͏\���v�Ƃ������ڂɈႢ������ꂽ���A���d��r���s�������ʂ����ɗL�Ӎ��͌����Ȃ������B
�E�Z��
�\4-4-12�@�Z���Ɓu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05 , **p��0.01
| ���� | ���ϒl | ���l | �L�ӊm�� �i�����j | |
| ��k | ���̑� | |||
| �������� | 3.87 | 4.16 | -2.063 | 0.040* |
| �~�������̂����� | 3.94 | 3.63 | 2.036 | 0.043* |
| ���i�͈��� | 3.44 | 3.05 | 2.404 | 0.017* |
�Z���Ɓu���p���₷���v���Ă�������s�������ʁA�ȏ�̍��ڂɗL�Ӎ�������ꂽ�B�u���������v�̍��ڂɑ��āA��k�ȊO�ɏZ�ސl�X�̕������ӓx�͍����B�܂��A�u�~�������̂�����v�u���i�͈����v�Ƃ��������x�ɂ��ẮA��k�ɏZ�ސl�X�̕����������Ƃ���A��k�ȊO�ɏZ�ސl�X�̕��������x�͒Ⴂ�Ƃ������Ƃ��킩��B
(3)����
�ȏ�̗L�Ӎ�����ŗL�Ӎ�������ꂽ���ڂ��܂Ƃ߂�ƁA���{�l�ɂ��ẮA���ʂɂ���č�������ꂽ�̂́u��s�͍L���v�u�S�~���̐��͏\�����v�ł���B�܂��A�N��ɂ���č�������ꂽ�̂́u�g�C���̐��͏\�����v�u�H�ו��͔��������v�ł���A55�Έȏ�̕]�����Ⴂ���Ƃ���A��s�͎�Ҍ����̐H�ו��������̂ł͂Ȃ����Ƃ����������ł���B����ɁA�����ɂ���č�������ꂽ�̂́u�H�ו��͔��������v�ł���A������10~15���~�ȏ�ɂȂ�ɂ�ē��ӓx���Ⴍ�Ȃ��Ă��邱�Ƃ���A��s�̐H�ו��͏��������ł���Ƃ������Ƃ��킩��B�Z���ɂ���č�������ꂽ�̂́u���{�ɂ������ꏊ������v�u���������v�ł���A�����ɑ����̓��ӓx�͒Ⴍ�A�u���������v�ł͕����̓��ӓx�������������Ƃ���A�Z���̒n�搫�ɂ���Ċ��������قȂ�Ƃ������Ƃ��킩�����B�ƐE�Ƃɂ���Ă͑傫�ȗL�Ӎ��������Ȃ������B
��p�l�ɂ��ẮA���ʂɂ���č�������ꂽ�̂́u�c�Ǝ��Ԃ͒Z���v�ł���A�N��ɂ���č�������ꂽ�̂́u�q���Ǘ��͗ǂ��v�u���������v�ł���A�q���Ǘ��ɑ���55�̓��ӓx�͍����A18�Ζ����̕]���͌��������Ƃ���A55�Έȏ�̐l�����͐̂ɔ�ׂĖ�s�����P���Ă����l�q�����Ă���̂ŁA���̂悤�Ȍ��ʂ��o���̂ł͂Ȃ����Ɛ����ł���B
�ɂ���Ắu�댯�v�u���������v�u���G�͕s���v�u���i�̎�ނ͖L�x�v�u�~�������̂�����v�u���i�͈����v�Ǝ�ɏ��i�Ɋւ��鍀�ڂɗL�Ӎ��������A�����҂̕��������҂ɔ���i�ɑ��閞���x�������Ƃ������Ƃ��킩�����B�܂��A�E�Ƃɂ���č�������ꂽ�̂́u�H�ו��̎�ނ͖L�x�v�ł���A�w���̓��ӓx����������Ŏ�w�̕]���͌������Ƃ������Ƃ��킩�����B����ɏZ���ɂ���č�������ꂽ�̂́u���������v�u�~�������̂�����v�u���i�͈����v�ł���A��k�ȊO�ɏZ�ސl�̕����A��k�ɏZ�ސl���������x���Ⴂ�Ƃ������ʂ��o���B�����ɂ��Ă͎�ȗL�Ӎ��͌����Ȃ������B
5. �ό��q�́u���̍s���v�Ɓu���p���₷���v�̗L�Ӎ�����
4.�ł����ʂ�N��Ȃǂ̌l�̑����ɂ���āu���p���₷���v�̕]���ɍ�������ꂽ���A�����ł͓��{�l�ό��q����p�ɗ����E�ړI�A��s�𗘗p����ړI�ɂ���ĕ]���ɍ���������̂��ǂ����𖾂炩�ɂ���B�܂��A��s�Ɋւ��鎖�O���̗L���A��ɂ���Ă�����������̂���4.�Ɠ��l�ɗL�Ӎ������p���Ȃ���l���Ă����B
�@�����
�\4-5-1 �u����v�Ɓu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05 , **p��0.01
| ���� | F�l | �L�ӊm�� | Scheffe�@ |
| �c�Ǝ��Ԃ͒Z�� | 3.272* | 0.040 | 1>3 |
| �g�C���̐��͏\�� | 4.475* | 0.013 | 1>2 |
| �S�~���̐��͏\�� | 3.532* | 0.031 | 1>2 |
| �H�ׂ������̂����� | 4.812** | 0.009 | 2>3 |
| �H�ו��͔������� | 3.881* | 0.022 | 2>3 |
�u����v�Ɓu���p���₷���v�ɂ��ĕ��U���͂��s�����Ƃ���A�ȏ�5�̍��ڂɍ�������ꂽ�B����ɑ��d��r���s�����Ƃ���A�S�Ă̍��ڂɗL�Ӎ�������ꂽ�B�ȉ��Ɋe���ϒl�������B
�O���t4-5-1 �e�u���p���₷���v�̗���ʕ��ϒl
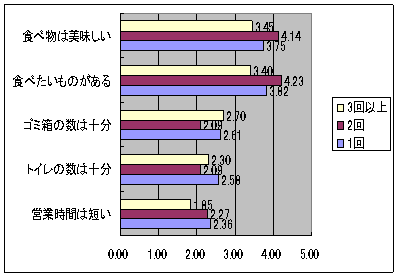 ���U���͂��s�����Ƃ���A�ȏ�5�̍��ڂɍ�������ꂽ�B����ɑ��d��r���s�����Ƃ���A�S�Ă̍��ڂɗL�Ӎ�������ꂽ�B�u�H�ו��͔��������v�u�H�ׂ������̂�����v�Ƃ����H�ו��Ɋւ��閞���x�ɑ��āA�����3��ȏ�̃��s�[�^�[���Ⴂ�Ƃ������Ƃ��킩��B
���U���͂��s�����Ƃ���A�ȏ�5�̍��ڂɍ�������ꂽ�B����ɑ��d��r���s�����Ƃ���A�S�Ă̍��ڂɗL�Ӎ�������ꂽ�B�u�H�ו��͔��������v�u�H�ׂ������̂�����v�Ƃ����H�ו��Ɋւ��閞���x�ɑ��āA�����3��ȏ�̃��s�[�^�[���Ⴂ�Ƃ������Ƃ��킩��B
�A����ړI
�A���P�[�g�̌��ʂł́A��p�ɗ����ړI�͐l�ɂ��l�X�ł��������A�����ł͈��|�I�ɉ̑��������u�ό��i85���j�v�Ɓu���̑��̖ړI�i15%�j�v�ɕ����čl���邱�Ƃɂ����B
�\4-5-2 �u����ړI�v�Ɓu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05 , **p��0.01
| �@ ���� | ���ϒl | t�l | �L�ӊm�� (����) | |
| �ό� | ���̑� | |||
| ���{�Ɏ����ꏊ������ | 2.59 | 1.87 | 3.472 | 0.001** |
| ���G�͕s�� | 2.60 | 3.07 | -2.127 | 0.035* |
| �g�C���̐��͏\�� | 2.55 | 2.17 | 2.504 | 0.013* |
�u����ړI�v�Ɓu���p���₷���v�ɂ��Ă�������s�������ʁA�ȏ�O�̍��ڂɗL�Ӎ�������ꂽ�B�u���G�͕s���v�Ƃ������ڂɑ��Ċό��ȊO�̖ړI�ŗ����l�̕����ό��ړI�̐l��蓯�ӓx�������Ƃ������Ƃ��킩��B�ό��q�́A���̍��G������Ԃ���s�̌����̈�Ƃ��đ����Ă��銴��������B
�B���O���̗L��
�\4-5-3 �u���O���̗L���v�Ɓu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05 , **p��0.01
| �@ ���� | ���ϒl | t�l | �L�ӊm��(����) | |
| ���� | �Ȃ� | |||
| ��ʎ�i�͕֗� | 4.22 | 3.92 | 2.288 | 0.023* |
| �������� | 3.53 | 4.11 | -3.865 | 0.000** |
| �q���Ǘ��͗ǂ� | 2.43 | 2.15 | 2.434 | 0.016* |
| �c�Ǝ��Ԃ͒Z�� | 2.18 | 2.55 | -2.887 | 0.004** |
| �C���[�W�ʂ� | 3.72 | 3.42 | 2.192 | 0.030* |
�ȏ�5�̍��ڂɗL�Ӎ�������ꂽ���A���O�ɖ�s��m���Ă����l�̕��������x�͂ǂ���������Ƃ��킩��B�u�C���[�W�ʂ�v�Ƃ������ڂɑ��Ă����ӓx���������Ƃ���A���O���ɂ���Ė�s�̃C���[�W������A���̌�̎��̌��ɂ���ăC���[�W�����ƂȂ��N���ɂȂ����A�Ƃ������Ƃ��l������B
�C���
�A���P�[�g�̌��ʁA��̑�\�I�Ȃ��̂Ƃ��āu�K�C�h�u�b�N�i51%�j�v�u�e���r�i18%�j�v�u�m�l�i14%�j�v�u�C���^�[�l�b�g�i10%�j�v���������A�u���s��Ёv�u�V���E�G���v�u���̑��v��5���ɖ����Ȃ������B�����ŁA��ł���u�K�C�h�u�b�N�v�u�e���r�v�u�m�l�v�u�C���^�[�l�b�g�v�ɑ��Ă��ꂼ��t������s�������ʁA�u�K�C�h�u�b�N�v�Ɓu���̑��̏�v�ɂ̂ݗL�Ӎ�������ꂽ�B
�\4-5-4 �u��v�Ɓu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05 , **p��0.01
| ���� | ���ϒl | t�l | �L�ӊm��(����) | |
| �K�C�h�u�b�N | ���̑� | |||
| ��ʎ�i�͕֗� | 4.32 | 3.92 | 3.331 | 0.001** |
| �������� | 3.54 | 3.91 | -2.315 | 0.022* |
| �q���Ǘ��͗ǂ� | 2.50 | 2.18 | 3.050 | 0.003** |
| �H�ׂ������̂����� | 3.97 | 3.66 | 2.526 | 0.012* |
| �H�ו��͔������� | 3.89 | 3.63 | 2.251 | 0.025* |
�ȏ��5���ڂɗL�Ӎ�������ꂽ���A�u��ʎ�i�͕֗��v�u���������v�u�q���Ǘ��͗ǂ��v�Ƃ������ڂ̒l�͕\4-5-3�̌��ʂƂقړ��������Ƃ���A�K�C�h�u�b�N�̉e���͑傫���Ƃ������Ƃ��킩��B�H�ו��Ɋւ��閞���x�������̂́A��s�̔��������H�ו����Љ��K�C�h�u�b�N���������炾�낤�B�������A�K�C�h�u�b�N��Ў�ɂ��X��T���Ă�����{�l�̎p����������ꂽ�B
�D��s���p�ړI
��s�𗘗p����ړI�͗l�X�ł��������A�����ł́u�w���ړI�v�Ɓu���̑��̖ړI�v�ŕ]���ɍ���������̂������Ă����B�����Ō����u�w���ړI�v�Ƃ́A�u�������v�u�H���v���Ӗ�����B
�\4-5-5 �u��s���p�ړI�v�Ɓu���p���₷���v�̍��ف@*p��0.05 , **p��0.01
| ���� | ���ϒl | t�l | �L�ӊm�� (����) | |
| �w���ړI | ���̑� | |||
| �ʔ��� | 4.34 | 4.06 | 2.487 | 0.014* |
| �q���Ǘ��͗ǂ� | 2.41 | 2.14 | 2.109 | 0.036* |
| �������� | 3.08 | 2.61 | 2.517 | 0.013* |
| ���͋C�͗ǂ� | 3.99 | 3.61 | 2.547 | 0.013* |
| �֗� | 3.80 | 3.33 | 2.925 | 0.005** |
| ���� | 3.93 | 3.45 | 3.183 | 0.002** |
| ���i�̕i���͗ǂ� | 2.86 | 2.55 | 2.356 | 0.019* |
| �H�ׂ����������� | 3.94 | 3.45 | 3.502 | 0.001** |
| �H�ו��͔������� | 3.89 | 3.37 | 4.050 | 0.000** |
| �H�ו��͈��� | 4.08 | 3.41 | 4.546 | 0.000** |
�ȏ�10���ڂɗL�Ӎ�������ꂽ���A�H�ו��Ɋւ��鍀�ڂ�3���L�Ӎ�������ꂽ�̂��������B�܂��A�S�Ă̍��ڂɑ��āA�u�w���ړI�v�Ɠ������l�̕������p���₷���E�����x�͍����B�u���̑��v�ɂ́u�V�сv�u�ɂԂ��v�u�ό�����������v�Ƃ����ړI���܂܂�Ă���̂����A�u�������v��u�H���v�Ƃ����w���ړI�����ړI�ӗ~���ア�̂��낤�B���̌��ʂ�����̌��ɒ��ڊW����ړI�������đ̌��������ꍇ�Ƃ����łȂ��ꍇ�ł͕]���ɍ����o��Ƃ������Ƃ������邾�낤�B
�k�����l
�ȏ�̌��ʂ��܂Ƃ߂�ƁA���ꂼ��́u���̍s���v�ɂ���āu���p���₷���v�̕]���ɍ����o��Ƃ������Ƃ�������B����ɂ���ėL�Ӎ�������ꂽ���ڂ́u�c�Ǝ��Ԃ͒Z���v�u�g�C���̐��͏\���v�u�S�~���̐��͏\���v�u�H�ׂ�����������v�u�H�ו��͔��������v�ł���A�H�ו��Ɋւ��閞���x�ɑ��Ă̓��s�[�^�[�̕����Ⴂ�Ƃ������Ƃ��킩�����B�܂��A����ړI�ɂ���ėL�Ӎ�������ꂽ���ڂ́u���{�Ɏ����ꏊ������v�u���G�͕s���v�u�g�C���̐��͏\���v�ł���A�ό��ړI�̐l�X�́u���G�͕s���v�ɑ��铯�ӓx���Ⴂ���Ƃ��畵�͋C���y���݂ɗ��Ă���l�q���M����B��s�ɑ��鎖�O���̗L���ɂ���č�������ꂽ���ڂ́u��ʎ�i�͕֗��v�u���������v�u�q���Ǘ��͗ǂ��v�u�c�Ǝ��Ԃ͒Z���v�u�C���[�W�ʂ�v�ł���A���O���Ă����l�̕��������x�͍����Ƃ������ʂ��o���B�܂��A��i�K�C�h�u�b�N�Ƃ��̑��j�ɂ���č�������ꂽ���ڂƌ��ʂ��قڈ�v���A�K�C�h�u�b�N�̉e�����傫���Ƃ������Ƃ��킩�����B����Ɂu�H�ׂ�����������v�u�H�ו��͔��������v�̍��ڂɍ��������A�������K�C�h�u�b�N�����Ă����l�̕��������x�͍��������B��s���p�ړI�ɂ���Ắu�ʔ����v�u�q���Ǘ��͗ǂ��v�u���������v�u���͋C�͗ǂ��v�u�֗��v�u�����v�u���i�̕i���͗ǂ��v�u�H�ׂ������̂�����v�u�H�ו��͔��������v�u�H�ו��͈����v�Ƒ����̍��ڂɗL�Ӎ��������A��������H���Ƃ������w���ړI���������l�X�̕����]���▞���x�������Ƃ������ʂ��o���B�{�͂̂܂Ƃ߂͎��̑��1.���_�ŋL�q����B
��� �܂Ƃ�
�@���̏͂ł͑O�͂̌��ʂ��瓱���o���ꂽ�l�@�����_�Ƃ��Ă܂Ƃ߂Ă����A��s�Ƃ͊ό��q�ɂƂ��Ăǂ��������̂Ȃ̂��𖾂炩�ɂ���B�܂��A��s���ό��q�ɂƂ��Ă�����ɗ��p���₷���Ȃ�ɂ́A�ǂ̕��������P������ǂ��̂����l����B
1. ���_
(1)��s�̔F���▞���x�͓���ɂ���ĈقȂ�@
��l��2.�̌��ʂ��A���{�l�Ƒ�p�l�ł͂قƂ�ǂ̍��ڂɗL�Ӎ�������ꂽ�B���̂��Ƃ����s�ɑ���F���͓���ɂ���ĈقȂ�A�Ƃ������Ƃ�������B�܂��t�̎��_�Ō���ƁA�L�Ӎ��������Ȃ������u�q���Ǘ��͗ǂ��v�u�c�Ǝ��Ԃ͒Z���v�u���ݔ��̐��͏\�����v�u�X���͐e�v�u�X���͐M���ł���v�u���i�̕i���͗ǂ��v�̍��ڂɂ��āA���҂͓����F���������Ă���A�ƌ����邾�낤�B
(2)����҂̌l�����͖�s�̔F���▞���x�ɉe����^����
��l��4.�̌��ʂ���A���{�l�͐��ʁE�N��E�����E�Z���ɂ���āA�܂���p�l�͐��ʁE�N��E�E�E�ƁE�Z���ɂ���āA��s�̔F���▞���x�ɍ����o�邱�Ƃ��킩�����B
(3)��s�̔F���▞���x�͊ό��q�̗���A����ړI�ɂ���ĈقȂ�
��l��5.�̌��ʂ���A����̈قȂ����҂ł́A��ɐݔ��ƐH�ו��̍��ڂɂ��č�������ꂽ�B�܂�����ړI�̈قȂ����҂ł́A�ό��ړI�Ƃ��̑��̖ړI�Ŗ�s�̃C���[�W�Ɛݔ��ɂ��č�������ꂽ�B
(4)�ό��q�̖�s�Ɋւ��鎖�O���́A��s�̔F���▞���x�ɉe����^����
��l��5.�̌��ʂ���A���O�����l�ƂȂ��l�ł͖�s�̃C���[�W�ɍ����o���B����ɃK�C�h�u�b�N�Ƃ��̑��̏�ł͖�s�̔F���▞���x�ɍ��������A�O�҂͌�҂��������x�������Ƃ������ʂ���A��s�C���[�W�̌`���ɃK�C�h�u�b�N�ɂ��e���͑傫���Ƃ������Ƃ�������B
(5)��s�̔F���▞���x�͖�s�̗��p�ړI�ɂ���ĈقȂ�B
��l��5�̌��ʂ���A�ړI���u�H���v�u�������v�Ƃ���u�w���ړI�v�Ƃ��̑��̖ړI�ł́A��s�ɑ���F���ɍ�������ꂽ�B�܂��A10���ڂɍ��ق�����ꂽ���A�w���ړI�̐l�X�̕����S�Ă̍��ڂɑ��A��s�̔F���C���[�W�͗ǂ������x�������Ƃ������ʂ�����ꂽ�B
2.�@�ό��q�ɂƂ��Ė�s�̖��͂Ƃ�
�O�͂ł킩�������Ƃ��܂Ƃ߂�ƁA��s�̗��p�҂͒j�����������̕��������A���p�Ғ��S�w��18~34�A�w���Ɖ�Ј��ł���B
��s�𗘗p������{�l�́A�ό��ő�p�ɗ����l�����|�I�ɑ����A��V���̐l���K��O�����s�̑��݂�m���Ă���K�C�h�u�b�N�ɂ��e�����傫���悤���B�܂��A��s�𗘗p����ړI�͑�p�l�����w���ӗ~�i�������j���Ⴍ�A�H����V�сA�ό�����������Ƃ������R�����������B
�@���{�l�͖�s�̕��͋C�ȂǁA��s�̔F���C���[�W�͑�p�l�����ǂ����A���i��H�ו��Ȃǂ̋�̓I�ȃ��m�ɑ��閞���x����p�l�����Ⴂ�Ƃ������Ƃ��킩�����B���̂��Ƃ͏��i��H�ו��ɑ��閞���x�ɂ���āA�u���͋C�͗ǂ��v�u�ƂĂ������ł���v�Ȃǂ̖�s�̔F���ɂ͉e�����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ������邾�낤�B���Ȃ킿��s�̔F���́A��̓I�ȃ��m�ɍ��E����邱�ƂȂ��A�l�X�̔M�C��A���G�����l�q�A������Ă��镵�͋C�Ȃǂ��琶�܂��A�Ƃ������Ƃ��B
���̂��Ƃɉ����A��s���p�ړI�ɍw���ӗ~���Ⴂ���Ƃ���A�ό��q�ɂƂ��Ė�s�̖��͂Ƃ͑S�̂̕��͋C�ɂ���A�Ƃ������Ƃ������邾�낤�B
��s�̔F���i���ϒl�j�ɂ����āA�u�ʔ�����(4.27)�v�u���G�͕s����(2.67)�v�u���͋C�͗ǂ�(3.90)�v�u�ƂĂ������ł���(3.82)�v�Ƃ����v���X�C���[�W�̕]���������A�}�C�i�X�C���[�W�̕]�����Ⴂ���Ƃ�����ؖ��ł���B�܂��A�u���G�͕s�����v�̍��ڂɂ��ẮA��p�l�͕��ς����u�s���v�ɋ߂��l(3.48)�ł���̂ɑ��A���{�l�́u�s���łȂ��v�ɋ߂��l�Ƃ������Ƃ���A���G����s�̖��͂̈�ƌ������Ƃ��ł��邾�낤�B
�@����Ɂu���{�Ɏ����ꏊ������(2.48)�v�Ƃ������ڂɂ��Ă��l���Ⴂ���Ƃ���s�̖��͂ɊW���Ă���Ǝv����B
�ȏ�̂��Ƃ��܂Ƃ߂�Ɗό��q�ɂƂ��Ė�s�̖��͂Ƃ�
���l�X�̔M�C��A���G�����l�q�Ȃǂ̖�s�S�̂̕��͋C�ł���
�����{�ł͖��킦�Ȃ��Ɠ��̏ꏊ�ł���
�Ƃ������Ƃ������邾�낤�B
3.�@����Ȃ��s�̔��W�Ɍ�����
�Ō�ɁA��s������ɗ��p���₷���Ȃ�悤�ɖ�s�̉��P�_�ɂ��čl���Ă��������B��s�̃C���[�W�]���E�����x���Ⴉ�������ڂ��������
���g�C���̐��͏\����
���S�~���̐��͏\����
�����i�̕i���͗ǂ�
���q���Ǘ��͗ǂ�
�ȏ�4���ڂ͓��{�l�����łȂ��A��p�l�����ʂ̒l(5�i�K�]����3)�����Ⴉ�����B
�����ŁA��s�̉��P�_�ɂ��ĉ��l���̓��{�l�ɘb���Ă���������̂�N��Ɏ����B
�킽�������������Ƃ́A�g�C���̐������ɏ��Ȃ��Ƃ������Ƃł����ˁB��{�I�Ƀg�C��������̂̓X�^�o��g��Ƃ��炢�Ȃ̂Ńg�C���T���ɋ�J���܂��B�����ƃg�C���̐��𑝂₵�Ă����A�����Ƃ����Ɩ�s�̔����������̂��H�ׂ���̂ɁA�Ǝv���Ă��܂��B�i20��A��w���A�����j
���̖�s�����̂܂ܓ��F�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��������S�~�ɂ��č��鎖�͑����ł�����䂪�͂�����̓��̃S�~�͐����ł�����Ƥ�l�������אH�ו����������������܂���l�������͓̂��킢�������ėǂ������Ƃ͎v���̂ł����ǂˡ�i20��A��Ј��A�����j
�H�i�q�����g�C���ݔ������P�̗]�n�͊m���ɂ���܂��B�ł��l�I�ɉ��P��������Ȃ��Ǝv���͕̂����₷���ł͂Ȃ��ł��傤���B�`�͊X��ؐ��X�Ȃǐ������ꂽ�ό���s�ȊO�ł́A����������Ɋe�X�܂��������āA���̑O�ɗ����~�܂�ƁA��납������ė����l�B�ɉ�����A�����ꂻ���ɂȂ�܂��B�i30��A��w�A�����j
�q����Ԃ������������P���Ăق����ł��B�Ⴆ���������̋C��̒��ł̌��ޗ��̈����Ƃ�����ĂȂ�����g���Ƃ��A��nj��ȂǁB���ƌÂ������g��������g��������̉�����Ă����̂����܂ɂ���܂��ˁB�i30��A��Ј��A�����A��p�ݏZ�j
�g�C�������Ȃ��A�����Ȃ������B�o�C�N�������Ċ�Ȃ��i�q�A��ōs���Čy���P�K�������܂����j�B�����ĐH�ׂ�p�̃e�[�u�����@���ĂȂ��B��s�̂��铹�H���ʉ��������肵�ē��ɂ���Ă͐����܂肪���������ɏo���Ă��ĕ����ɂ����B�H��S�~�������Ȃ��B�I���c����������ꏊ�͕t�߂Ɉꃖ�����Ȃ������B��s�͉q���ʂ����܂�C�ɂȂ�Ȃ��^�C�v�̎�҂��s���ɂ͖��͖����悤�ł����A�q�A���_�o���ȔN�����s���ꏊ�ł͂Ȃ��悤�ł��B�i30��A��w�A�����j
����������s�͈̔͂₨�X�̈ʒu�Ȃǂ̈ē����[�������邱�Ƃƃg�C���̖������P���鎖�ł��傤���B�i40��A��p���݈��A�j���j
����ŁA����ێ���]�ސ�������ꂽ�B
��{�I�ɂ́A����ێ��������Ǝv���܂��B�H���悵�A�l�i���ǂ��B�����Ĉ������Ƃ��Ă��A�Œ���̉q���ʂł̋C�z�肪������̂܂܂ł����Ǝv���܂��B�i20��A��w���A�j���j
��s�͂��̂܂܂ł����Ǝv���Ă��܂��B�m���ɉq���ʂł͊��S���܂��A���܂菬�Y��ɂȂ��Ă��܂��ẮA�G���ȕ��͋C�����Ȃ��A�ό��X�|�b�g�Ƃ��Ă̖��͂������Ă��܂�����������ł��B�i20��A��w���A�j���j
���̈ӌ��Ƃ���A���̂܂܂��ǂ��Ǝv���܂��B�G���̒��ŁA�H�ו����̂���s�̗ǂ��Ƃ��낾�ƁB�e�C�N�A�E�g�ł����̃r�j�[���ɖ˂�����ꂽ��A�K�^�K�^�̋����ۈ֎q�ɍ����ĐH�ׂ���ٍ�����ēz�ł���ˁB�i40��A���c�ƁA�j���j
�@
���̂悤�ɉ��P���Ăق����Ƃ������Ɗό��q�p�ɉ��P����Ă��܂�����{���̖�s�炵���������̂Ō���ێ���]�ށA�Ƃ������Ɨl�X�Ȉӌ�������ꂽ���A�����͒j���ɔ�ׂĉq���ʂ��C�ɂ���l�����������B�A���P�[�g�̌��ʂɉ����Ĉȏ�̂��Ƃ܂��Ȃ���A����Ɋό��q����ё�p�l����s�𗘗p���₷���Ȃ�ɂ͂ǂ�������悢�̂������B
(1)�g�C���̐ݒu���𑝂₷
(2)�g�C���ݔ��E�q���ʂ̉��P
(3)���ݔ��̐��𑝂₷
(4)���i�̕i�����P
(5)�H�ו��̉q���Ǘ��Ɖq�����̉��P
(6)�����̊g��
(7)�������H�ɂ�����I�X�̐ݒu�ꏊ�̍H�v
(8)�X�܂̈ʒu�ē��Ȃǂ̏[��
(9)�����ߕӂɂ�����Ԃ̐i���֎~�Ȃnj�ʐ����̉��P
������(4)(8)�����P���邱�ƂŁA�ό��q�ɂƂ��ė��p���₷���Ȃ邩������Ȃ����A�ό��q�p�ɍ��ꂽ��s�Ƃ��Đl�X�̖ڂɉf��댯��������A��s�̖��͂��ꕔ���Ȃ��邩������Ȃ��B�܂�(6)(9)�͍H���Ȃǂ̑傫�ȍ�Ƃ��K�v�Ȃ��߁A�����ɂ͎�������낤�B
����Ď����\�Ȃ��̂�(1)(2)(3)(5)(7)�ł��낤�B���̓_�����P���邱�Ƃ́A���܂ł̖�s�̖��͂��������ƂȂ���s�̔��W�ɂȂ���Ǝv���B����A��s�����S�Ɋό��������̂ł͖����A�n���̐l�X�̗��p���]���ʂ萷��ŁA�ό��q�ɂƂ��Ă���ɗ��p���₷���Ȃ�悤�ɔ��W���邱�Ƃ�]��ł���B
�ӎ�
�{�_�����쐬����ɂ�����A���X�̂��w���E�������������������w�������̐^�����搶�Ɋ��Ӑ\���グ��B���v�ɂ��ċ����Ă����������{�w���̋{��͕v�搶�A�A���P�[�g�쐬���ɒ�����̃A�h�o�C�X��������������p����������w�̗эG���搶�ɂ����Ӑ\���グ��B�A���P�[�g�����J�n���ɋ��͂����Ă�����������p����������w�̒��A������w���w���̗��}�����ɂ���\���グ��B��s�Ɋւ��鎑��������������������Ɛ}���فi��k�j���ؕ��{�����S���̗ш��h���A�ό��Ɋւ��鎑������Ă�����������p�ό�����̊F�l�ɂ��ӈӂ�\����B�Ō�ɁA�����̏ꏊ����Ă������ꂽ�m�і�s�̉���o�c�҂̊F�l�A�����ɋ��͂��Ă������������{�l�ό��q�E��p�l�̊F�l�ɂ�����\���グ��B
���p�����ƒ�
[1]�������A�u��k�s�����逛��s���@�^�w���s�הV�����v�A����������w��ƊǗ��������m�_���A1995�N
[2]��ƎŁE�юq���Eḉ����E緜}���E���u�m�A�u��s����s�הV��r�^�T���\�Ȍi���A�m�сA�ؐ��X�O��s�ח�v�A�w�����w��x5(2)�A39�Ł`56�ŁA1998�N12��
[3]��ƎŁA�u�R���̌��I�p�x�T����s�����^���e�����f�v�A�w�ˊO�V�e�����x15(4)�A1�Ł`25�ŁA2002�N12��
[4]����E�����E���i��A�u�����O�V�q�Ίό���s�V�����f�d�v���F�m�y���ӓx�V�����\�ȍ��Y�s�Z���ό���s�ח�A�w���Y���p�ȑ�w�w��x191�Ł`212�ŁA2002�N12��
[5]�s�ۗρA�u���̖�s��ԑ����Ύg�p�ҏ���ԔV�e�������\�ȑ�p�䒆�s���b�������ؖ�s�^���{��B�����s���V���X�X�ח�v�A���b��w���z�y�s�s�v��m�_���A2003�N1��
[6]�s�×ρA�u�m�і�s�@�o�c�Ǘ��V�����v�A�w�����n�������x32�Ł`56�ŁA2003�N4��
[7]�s�×ρA�u�m�і�s�ڋq�����x���́\�Ȓ���������w�w������s�ח�v�A����������w�s��暨���K��w�n�m�_���A2004�N
[8]�]�r�P�A�u�����ЗV�q�Ζ�s�V��Nj��^�s����V�����v�A����������w�ό����ƌ������m�_���A2004�N
[9]����綦�A�u�T����k�s���̈��H�����y�����֑��^���\�V�����v�A������k�ȋZ��w�n�V�ݐv�������m�_���A2005�N6��
[10]�ؔ@�A�u��s�����Ί��m�o�V�e�� �\�Ȏm�сE�Ս]�X�E�t���s�ח�v�A���V��w�ό��w�n�m�w�ʘ_���A2005�N7��
[11]�����_���A�u�ό���s���W�V�ۑ�^���T���\�ȍ��Y�Z���ό���s�ח�v�A�w�y�n��茤���G���x�A2002�N12���A64�Ł`66��
[12] ��ʕ��ό��ǁA�w���ؖ���94�N�@���䗷�q����y���������@2005
Annual Survey Report on Visitors Expenditure and Trends in Taiwan�x�A2006�N7���A65��
[13]�ьb�A�u�������͋@���^�p���s�s�X�V�����V�����F�m�і�s�V�Ė͋[�v�A����������w�����s���w�n�m�_���A2002�N7���A67�Ł`68��
[14] ��ƎŁA�u�R���̌��I�p�x�T����s�����^���e�����f�v�A�w�ˊO�V�e�����x15(4)�A
2002�N12���A6�Ł`7��
[15]���ԁA�w�|�P�b�g�K�C�h��p�x�A2006�N1���A�����A43�ŁA69��
[16] ��ʕ��ό��ǁA�w���ؖ���94�N�@���䗷�q����y���������@2005
Annual Survey Report on Visitors Expenditure and Trends in Taiwan�x�A2006�N7���A66��
[17] �ؔ@�A�u��s�����Ί��m�o�V�e�� �\�Ȏm�сE�Ս]�X�E�t���s�ח�v�A���V��w�ό��w�n�m�w�ʘ_���A2005�N7���A38�Ł`47��
[18] ��ƎŁA�u�R���̌��I�p�x�T����s�����^���e�����f�v�A�w�ˊO�V�e�����x15(4)�A1�Ł`25�ŁA2002�N12��
[19] �s�×ρA�u�m�і�s�ڋq�����x���́\�Ȓ���������w�w������s�ח�v�A����������w�s��暨���K��w�n�m�_���A2004�N�A28��
[20] ��ʕ��ό��ǁA�w���ؖ���94�N�@���䗷�q����y���������@2005
Annual Survey Report on Visitors Expenditure and Trends in Taiwan�x�A2006�N7���A139�Ł`140�ŁA167�Ł`168��
[21]Beerli, & Martίn�A�uFactors Influencing Destination Image�v�A�wAnnals of Tourism Research�x31 (3)�A2004�N�A660�Ł`664��
[22] �ؔ@�A�u��s�����Ί��m�o�V�e�� �\�Ȏm�сE�Ս]�X�E�t���s�ח�v�A���V��w�ό��w�n�m�w�ʘ_���A2005�N7���A22�Ł`24��
[23] ���؏T��ЁA�u�o�ϓ���v�A�w��k�T��x2057���A2002�N6���A�ihttp://www.roc-taiwan.or.jp/news/week/2057/113.html�ɂ��j
�Q�l����
1. �k�����A�����s�������n�i�V�n�搫������A������k�ȋZ��w���z�^�s�s�v�挤�����A2003�N
2. �ĖP���A�u��s���k�v�A�w��k���������x��148���A257�Ł`274�ŁA2004�N6��
3. �X���Y�A�w�₳���������̃R�c�x�A�匎���X�A2005�N3���A����
4. �����^�i�A�wSPSS��Amos �ɂ��S���E�����f�[�^��́\���q���́E�����U�\�����͂܂Łx�A�����}���A2005�N12���A����
5. �╣�疾�A�w���Ȃ����ł���f�[�^�̏����Ɖ�́x�A�����o�ŁA2006�N3���A����
6. �w�g���x���X�g�[���[13 ��k�x�����ЁA2004�N9���A����
7. �ɓ��ꓙ�A�u��Δ�r�@��p�����ό��q�̊��ғx�Ɋւ��钲���ƕ��́\��p�l�ό��q��
����\�v�A�w���{�o�c�H�w��_�����x274�Ł`282�ŁA2004�N
8. �ɓ��N�i�E�\�q�����E�c�����q�A�u�����Ȃ��环��A�ւ��Ȃ���l����v�A�i�J�j�V�o�ŁA2005�N3���A����
9. ����N�A�u��p�̉��䎖��v�A�w�Ɛ��o�ϊw�_�p�x29�A95�Ł`114�ŁA1993�N
10. �]���{�A�u��p�l�͎��ƁE�|�Y���Ă�����������ď�������Ċ撣���Ă���v�A�wSapio�x14(3)�A103��~105�ŁA2002�N2��
11. �h�Ôn�A�u��s�ɖ��ł��h�����v�A�w���Ԃ��ɂ��x13(13)�A56�Ł`59�ŁA2002�N12��