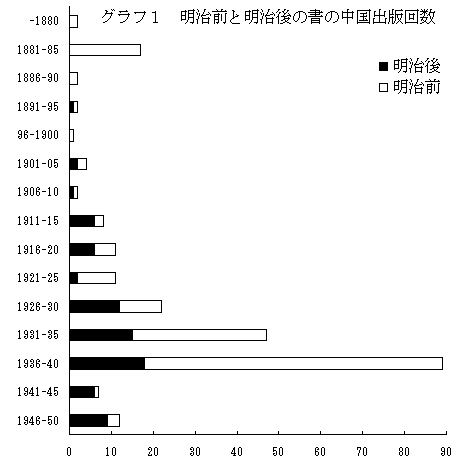 表1のように、日本医書は清末に相当する一九一〇年以前の約五〇年間(15)に三〇回、ほぼ民国時代に相当する一九一一〜五〇年の四〇年間に二〇七回の出版があり、圧倒的に民国時代に多い。同一書の再版を除いた書目数を拙報(11)でみても、日本の伝統医学関連書は清末までに二六書が新刊されていたが、民国間に新たに出版されたのは一三九書(16,17)にのぼっていた。
表1のように、日本医書は清末に相当する一九一〇年以前の約五〇年間(15)に三〇回、ほぼ民国時代に相当する一九一一〜五〇年の四〇年間に二〇七回の出版があり、圧倒的に民国時代に多い。同一書の再版を除いた書目数を拙報(11)でみても、日本の伝統医学関連書は清末までに二六書が新刊されていたが、民国間に新たに出版されたのは一三九書(16,17)にのぼっていた。The translation and publication of traditional Japanese medical works began to take off in China from 1911. There was a sharp increase from 1929, and because of the ratification that year of the "Plan to Abolish Chinese Medicine" and because of the need to respond to the attacks of the abolishers, modernization and scientification became important tasks. Japanese medical texts became popular as useful models. The main force of the publishing boom were pre-Meiji works; in particular, works by Edo-period textual medical scholars were published in increasing numbers, including commentaries on them. Meiji and post-Meiji works were increasingly published from 1929; most popular were texts, which were "scientified" by authors pursuing modern pharmacology. However, the Huitong group felt that this "scientification"was the wrong direction to be moving in, making this but a superficial popularity. Thus, the heart of the boom in traditional Japanese medical texts and their reception in China from 1929 were works by Edo-period textual medical scholars. This boom peaked in 1936, filling eight calendar years all told, and from 1937 came to an end with the commencement of the Sino-Japanese War.
一 緒言
中国周縁の民族文化は、中国古代からの伝統医療と医学(以下、中国医学と略す)の影響を少なからず受け続けてきた。日本の伝統医学も例外ではない。その一方、中国医学自身も周縁民族や非中国文化圏の医療・医学を歴代受容してきた。とりわけ実験科学を基盤とする近現代医学からの影響は相当に大きく、それが現在にいたるも続いている(1)。
他方、日本では明治から近代欧米式を唯一の正式医学とし、これを修めた者のみを医師とした。そして明治二十八年(一八九五)、漢方医提出の医師免許改正法案が議会で否決され、伝統医師の存続可能性一切が失われてしまう(2)。しかしながら、明治四十三年(一九一〇)初版の和田啓十郎『医界の鉄椎』を嚆矢に、近代医学を修めた医師のなかから伝統医療を行う者がわずかながら輩出してきた。また近代薬学には当初から生薬学があり、いわゆる和漢薬が主要な研究対象とされている。ケミカルな薬理物質の探求も、生薬などの天然資源が今なお対象である。さらに民衆の医療に定着していた生薬製剤の製造・販売は原則的に禁止されず、針灸治療は近代医学教育を受けた針灸師の形で存続しえた。以上の背景があって、明治後期からは近代医学・薬学を基盤としたり、その修飾を受けた伝統医薬学の復権が徐々に始まり、戦後に急速な発展をとげて現代の隆盛にいたる(3)。
この反面、幕末までに中国を凌駕する数々の業績を築いてきた考証医学派を中心とする純粋な伝統医学研究は、別の運命をたどった。近代医学とまったく学問体系を異にするため、明治以降は研究者層の払底を余儀なくされたのである。その結果、彼らの著述や研究資料であった厖大な医薬古典籍は無用の長物と化し、あるいは死蔵され、あるいは巷間に流出していった。これら書物、ときには版木などが当時来日していた中国の学者や官僚に注目され、さまざまな経過をたどり清末の中国に伝入した様子はすでに紹介した(4,5)。
さて明代に始まるヨーロッパ医学の中国伝来にともない、中国医学界には中体西用とも一脈通じる匯通学派(6)と呼ばれる折衷的流派が徐々に出現しており、これについての研究は少なくない(7,8,9)。その一人に清末から民国にかけて活躍した丁福保(一八七四〜一九五二)がいる。彼が明治以降の医薬書を精力的に翻訳・出版した経緯はすでに報告した(4,10)。また清末から一九九一年までに中国で復刻された日本の伝統医書のリストも報告した(11,12)。
この調査過程で、中国での日本伝統医書の出版には何度かの流行があること。その盛衰には、中国と日本の政治状況が影を落としていること。さらに清末以降の匯通学派を含む伝統医学界全般に、日本医書の影響が見え隠れすることに気づいた。しかし、これら諸点については従来ほとんど注目されていない。そこで本稿では民国時代に焦点をあて、日本医書との関連を考察することにした。
二 中国版日本医書の年代推移
前述のように、清末では来日した中国の学者・官僚が日本の伝統医学研究を紹介している。これが本格的な日本医学との最初の接触だった。しかし当時の「中国漢医の実際治療面にどれほどの影響をおよぼしたかという点は甚だ疑問で、…一部の読書人を喜ばせたに止まり、大多数の漢医はそのような書物の存在さえも知らなかったと思われる」(13)、と岡西は判断する。
ただし導火線となったのは間違いなく、続く民国間には日本伝統医学関係書のブームが訪れた。その情況は、かつて筆者が報告した「中国において出版された日本の漢方関係書籍の年代別目録」(11)に見ることができる。当拙報には補足の余地もままあるが、まずはこれに基づきカウントしてみた。すなわち、明治前・明治後の伝統医学関係書が清末と民国時代に出版された回数を、再版も含めて五年単位で集計するのである。この結果を表1に示した。
| 出版 年代 | 明治前の書 | 明治後の書 | 総計 | ||||||||||
| 考証派 | その他 | 古方派 | 針灸 | 評注 | 小計 | 漢方 | 生薬 | 針灸 | 通俗 | 医史 | 小計 | ||
| -1880 81-85 86-95 91-95 96-1900 01-05 06-10 | 1 12 1 2 | 1 3 1 1 1
| 1 1 | 1
|
| 2 17 2 1 1 2 1 |
| 1 |
| 1 2 |
| 1 2 | 2 17 2 2 1 4 2 |
| 小計 | 16 | 7 | 2 | 1 | 26 | 1 | 3 | 4 | 30 | ||||
| 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 44-50 | 1 3 5 23 23
| 3 3 5 4 22 1 | 1 3 2 1 | 3
| 2 1 2 | 2 5 9 10 32 71 1 3 | 1 2 7 | 3 1 1 2 6 7 2 4 | 1 1 2 | 1 3 1
| 1 4 | 6 6 2 12 15 18 6 9 | 8 11 11 22 47 89 7 12 |
| 小計 | 55 | 37 | 25 | 10 | 5 | 133 | 27 | 26 | 9 | 5 | 7 | 74 | 207 |
| 総計 | 71 | 44 | 27 | 11 | 5 | 159 | 27 | 27 | 9 | 8 | 7 | 78 | 237 |
なお本表の明治前の書で「考証派」は江戸医学館を主宰した多紀氏ら一門の著述、「古方派」は吉益東洞に代表される古方派関連の著述をいう。また考証派・古方派・針灸に入らない著述を「その他」とし、こうした明治前の著述を基に中国で評や注を加えた著述を「評注」とした。明治後の書で「漢方」としたのは漢薬治療を主とする著述、「生薬」は和漢薬を中心とした生薬学に相当する書、「通俗」は一般人対象の健康法・養生法などの書、「医史」は医学史関連書(14)をいう。
さらに明治前と明治後の書が中国で出版された年代変化をグラフ1に表した。
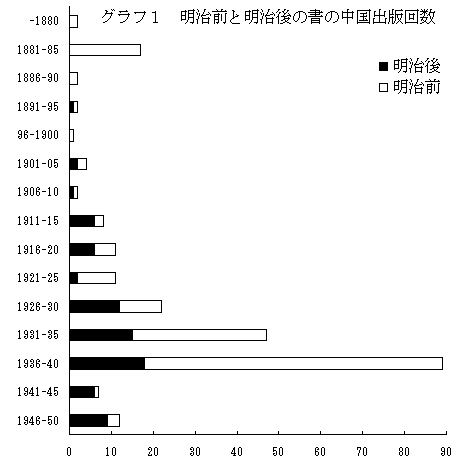 表1のように、日本医書は清末に相当する一九一〇年以前の約五〇年間(15)に三〇回、ほぼ民国時代に相当する一九一一〜五〇年の四〇年間に二〇七回の出版があり、圧倒的に民国時代に多い。同一書の再版を除いた書目数を拙報(11)でみても、日本の伝統医学関連書は清末までに二六書が新刊されていたが、民国間に新たに出版されたのは一三九書(16,17)にのぼっていた。
表1のように、日本医書は清末に相当する一九一〇年以前の約五〇年間(15)に三〇回、ほぼ民国時代に相当する一九一一〜五〇年の四〇年間に二〇七回の出版があり、圧倒的に民国時代に多い。同一書の再版を除いた書目数を拙報(11)でみても、日本の伝統医学関連書は清末までに二六書が新刊されていたが、民国間に新たに出版されたのは一三九書(16,17)にのぼっていた。
そこで表1で一九一〇年以前を見ると、明治後の書は四回の出版があるが、うち三回は通俗医書である。一方、明治前の書は二六回出版されており、うち一七回までが一八八一〜八五年に集中していた。その大多数は楊守敬が来日時に多紀氏ら著述の版木一三種を購入し、帰国後の一八八四年に一括して『聿修堂医学叢書』と名付けて重印出版(4,11)したことによる。この楊守敬による考証医学派の紹介を除くなら、明治時代すでに新たな伝統医薬研究書が出版されてはいたが(18)、それらはまだ中国で注目されなかったらしい。
ところで中国人の日本留学ブームは、日清戦争(一八九四)と日露戦争(一九〇四〜〇五)をひとつの契機に、一九〇五年ごろ最初のピークを迎えた(19)。(2011, 1,14追記:一〇九四年には北京大学前身の京師大学堂から清政府の第一回官費留学生三一名が一高に留学、翌年に東大と京大に入学し、うち三名は医学科に進学した。彼らは一九〇八年に北京大学留学生編訳社を創設し、教科書の中国語訳や北京大学学生の初創刊学術誌も出版した。薩日娜「旧制第一高等学校に学んだ初期京師大学堂派遣の清国留学生について」『科学史研究』四九巻〔二五六号〕二一六〜二二六頁、二〇一〇)一九〇七年には京師大学堂から医科が廃止され、その学生全員が日本留学に送り出されている(20)。彼らが帰国して活躍し始めるは、それより四、五年は後のことだろう。するとグラフ1のように一九一一年から出版数の増加が始まるのは、彼ら帰国留学生の活動とどこかで通底しているに相違ない。
当時日本は近代医薬学を採用しつつも、その長を取った新たな伝統医薬学の胎動が始まっていた。同文の中国人がこれに注目するのはなかば当然で、一九〇九年に医学調査で来日した丁福保もそうだった(10)。中国で日本伝統医書の出版が増加し始めた一九一一年から二〇年までの期間、出版の過半が明治後の書であるのは当情勢の反映であろう。
さて出版は一九一一年から微増傾向だったが、二一〜二五年の一一回から二六〜三〇年の二二回へと急増し、さらに三一〜三五年の四七回、三六〜四〇年の八九回と倍々に増加していく。再版を除いた新刊書数でみても(11)、二一〜二五年は八書だが、二六〜三〇年の一八書、三一〜三五年の二一書、三六〜四〇年の六六書と、やはり急増している。かくもの増加が一定期間持続したのなら、何かの事情が中国で一九二六〜三〇年の間に発生したと推定すべきだろう。
この間の出版を毎年の回数と(新刊書数)で逐一みると、一九二六年は〇(〇)、二七年も〇(〇)、二八年は二(一)なのに、二九年から八(七)、三〇年は一二(一〇)と急変していた(11)。これは一九二九年かその前年に、原因となる何かの事件が発生したことを強く示唆している。さらに問題の解決に日本の伝統医書が有用だったらしいことも。
ちょうど該当する事件が起きていた(21)。一九二八年五月一五日に開かれた民国政府の第一次全国教育会議にて、大阪医科大学卒の汪企張(?〜一九五五)が中医廃止案を提起したのである。そして翌二九年二月二四日、大阪医科大学卒の余岩(字を雲岫、一八七九〜一九五四)を筆頭とする中医廃止派の提出したいわゆる「廃止中医案」が、政府の第一次中央衛生委員会で批准されたのだった。これは約半世紀前に明治政府が開始した漢医廃止策に倣ったものだったが、日本の前例に学んだ中医側のねばり強い存続運動のため、けっきょく実施にはいっていない。すなわち二九年三月一七〜一九日に上海で開催された第一次全国医薬団体代表大会を皮切りに迅速な対応がなされ、ついに三六年一月二二日発布の中医条例で合法地位を獲得、三七年三月一一日には政府衛生署に中医委員会を設立させることに成功している。
こうした対応のひとつが伝統医学教育の体系化と新教材の編纂だったが、中医廃止派による五行説などへの批判に応え、世論や政治家の理解を得られるものでなければならない。他方、日本では江戸中期以降の古方派以来、後期の考証派を含め五行説を医療に利用するのを否定している。また楊守敬が紹介した考証派の著述は幕府江戸医学館の教材に相当し、高度な学術性と体系性を備えている。さらに明治後の伝統医書は近代医学の洗礼を受けている。そうした特徴を持つ日本医書は当時の中国医学体系化と近代化に、かなり有用なモデルだったに違いない。一九二九年から日本医書の出版が急増し始めたのは、上述の背景のためと判断していいだろう。
しかし出版数は一九三六〜四〇年の八九回を絶頂期とし、四一〜四五年には七回にまで激減してしまう。この絶頂期にいたる過程を年ごとにみると(11)、三四年に八回、三五年に二一回、三六年に八三回と加速度的な勢いだった。ところが三七年には三回、三八年には一回、三九年には〇回と急減してしまい、あとは一九五〇年まで毎年数回程度の出版にとどまる。実藤恵秀らの調査(22)でも、近代医薬書を含めた日本医薬書全体の中訳本はまったく同傾向を示す。すると三七年にブームが終息したことと、同年に中医存続運動が一応成功を収めたことは無関係とみていいだろう。ならば理由はいうまでもない。第二次上海事変(一九三七年)からの日中全面戦争による反日と戦乱の結果である。けっきょく民国時代の日本伝統医書のブームは、一九二七年から三六年までの足かけ八年で終焉したのだった。
ところで表1・グラフ1を明治前・明治後の書ごとにみると、一九三六〜四〇年間まではともに上昇するが、とりわけ明治前の書は出版数が急速に増える傾向がうかがえる。これを検討するため、民国時代の刊行について表1から明治前医書のグラフ2と、明治後医書のグラフ3を同一尺度で作製してみた。
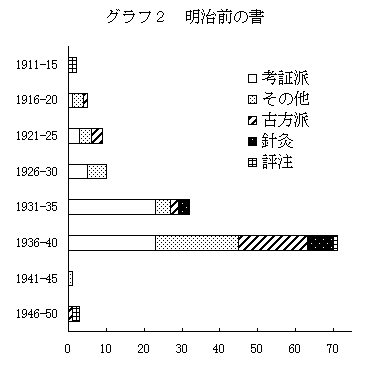
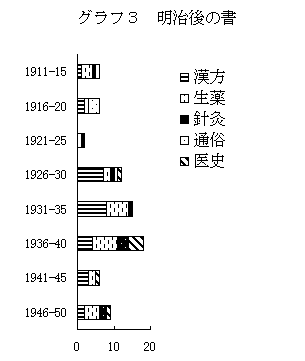
さらにグラフ2で、考証派の書はブームの終了まで徐々に増加しているが、その他と古方派の書は三六〜四〇年(前述のように実際は一九三六年)に急伸している。他方、明治後の書はグラフ3のごとく、ブームが過ぎた四一〜四五年も極端に急落せず、四六年以降は増加傾向に転じている。以上については、いかなる書に需要があり出版されたかを具体的に検証する必要があろう。
三 明治前医書の中国版
明治前の医書を初めて中国で本格的に紹介したのは一八八四年の『聿修堂医学叢書』だった。これ以降、少なからぬ医学叢書がきそって明治前の書を収載し、それゆえ明治前の書の中国版は事実上、叢書本が大多数を占めている。一度に各書を刊行する叢書には、翻訳の手間がかからず容易に出版できる明治前の書が適していたからに違いない。それら叢書に収められた日本医書を、拙報(11)から表2に整理してみた。
| 刊年 | 叢書名 | 収書数 | 日本医書の分類:書数 |
| 1913 1915 1923 1928 1931 1931 1936 1936 1937 | 六訳館医学叢書 医薬叢書 三三医書 薬庵医学叢書 国医小叢書 何氏医学叢書 皇漢医学叢書 珍本医書集成 古本医学叢刊 | 22 56 99 22 34 4 72 90 2 | 考証派への評注:2 (生薬:1) 考証派:2 その他:1 古方派:5 考証派への評注:1 その他:2 古方派:1 考証派:2 考証派への評注:1 考証派:16 その他:26 古方派:16 針灸:3(漢方:2 生薬:5 針灸:1 医史:3) その他:1 考証派:1 考証派への評注:1 その他:1 古方派:2 医史:1 針灸:1 |
表2のごとく、たしかに叢書収載本の多くは明治前の書で、明治後の書は( )内に記したものにとどまる。また前述のように、出版数のピークは一九三六年の八三回だったが、本表でその七九回までが叢書本だったことが分かる。しかも日本書七二種(24)のみからなる、若き陳存仁(一九〇八〜九〇)(25)編纂の『皇漢医学叢書』が大多数を占めていた。もし当叢書がなければブームのピークは前年の三五年だったろうし、グラフ2で「その他」と「古方派」の書が三六〜四〇年に急伸していたのも当叢書の存在による。当叢書は現在も中国で復刻され続けており、日本医書の紹介に巨大な役割をはたしたと評さねばならない。
一九三六年にはトピック的な書も出版されていた。多紀元胤の『医籍考』八〇巻で、弟の多紀元堅手校本を一九三三〜三五年に富士川游が影印出版しており、これを上海の中西医薬研究社がそのまま縮印、さらに書名・人名索引を付して出版している。本書の価値は今なお高いが、この中国縮印本に載る王吉民・宋大仁・范行準ら当時の医史学者の文より、彼らが本書の存在を伝え聞き、いかに入手を渇望していたかがよく分かる。本書の出版と索引作成に尽力したのは若き范行準(一九〇六〜九八)(26)で、題字を中医廃止派の筆頭たる余岩が記しているのは興味深い人間関係をうかがわせる。
前述した同年刊の『皇漢医学叢書』も、本書を『中国医籍考』の名で活字版として収めている。それ以前に出版された考証派の書は、ほぼすべて『聿修堂医学叢書』本を活字で再版したに過ぎなかった。したがって、これら『(中国)医籍考』の出版で考証派の医書誌研究も広く中国に知られたことになる。なお同年には岡西為人らの『宋以前医籍考』一〜三集が満洲医科大学東亜医学研究所より出版されており、日本人による中国医書誌の研究書が集中的に刊行された年でもあった。
さて考証派の著述は、日本書ブームの終了する一九三六年まで徐々に増加し、着実な評価のたかまりを示していた。彼らの書は現在まで中国で出版が重ねられ、多紀元堅の著述のみで五七版におよび、日本の三一版よりはるかに多い(27)。それゆえ、単なる再版にとどまらない書も叢書中に出現した。表2からも分かるが、彼らの書に評注を加えた書である。
すなわち廖平(一八五二〜一九三二)(28)による一九一三年の『六訳館医学叢書』には『脈学輯要評』と『薬治通義輯要』があり、両書は多紀元簡の『脈学輯要』と『薬治通義』に基づく。廖平の『脈学輯要評』は曹炳章(一八七七〜一九五六)(29)による一九三六年の『中国医学大成』にも転載された。酴鉄樵(一八七八〜一九三五)(30)による一九二八年の『薬庵医学叢書』には『傷寒論輯義按』があり、これは元簡の『傷寒論輯義』に基づく。何廉臣(一八六一〜一九二九)(31)による一九三一年の『何氏医学叢書』には『新増傷寒広要』があり、これは元堅の『傷寒広要』に基づくほか、元堅の『傷寒論述義』と浅田宗伯の『傷寒論識』もそのまま収載する。
以上の廖平・酴鉄樵・何廉臣による評注活動は多紀元簡・元堅の著述についてのみで、計四書と数も多くない。しかし酴鉄樵や曹炳章・何廉臣は民国中医界の指導勢力を占めた匯通学派の代表人物であり、酴は一九二二年の『群経見智録』で余岩が中医を批判した『霊素商兌』(一九一七)に正面から論争を挑んでいる(32)。当時の日本では多紀氏ら考証派の研究を医史学者が注目するのみだったのに(33)、中国では対立する中医廃止派と匯通学派の双方が評価していたのだった。
日本人が意図的に元堅の書を中国に紹介した例もある(34)。元堅の腹診書『診病奇{イ+亥}』がそれで、本書は大部分が和文であり、未刊のまま明治を迎えていた。元堅の子・雲従の弟子だった松井操は、駐日清国公使館員より腹診が中国にないことを知り、腹診を普及させるために本書を漢訳。また明治初期に来日して東京で書店等を経営、浅田宗伯らの診療を受けて腹診を知り、かつ『聿修堂医学叢書』に感服していた王仁乾が松井の希望をうけ、日本で漢訳本を印刷して光緒十四年(一八八八)に中国で頒布したのである。
さらに王仁乾本を浙江中医専門学校の王慎軒が教材用に校訂し、一九三一年に『診断学講義』の名で蘇州国医書社から出版している。一方、日本統治下にあった台湾では伝統医廃止策がとられていた。そこで復活運動の一環だった講義の教材として、昭和十年(一九三五)に蘇錦全が『診腹学講義』の名で王慎軒校訂本を台湾漢医薬研究室から再版したのである。『診病奇{イ+亥}』が日本で最初に出版されたのは、その九か月後だった。
以上のように民国一九三六年までの日本医書ブームにおいて、明治前医書では多紀氏を中心とした考証派の著述が清末以来、一定して出版数を増やしていた。それは評価のたかまりを反映していようし、中医廃止派にも匯通学派にも影響を与えていたらしい。また三六年に出版数が急伸したのは『皇漢医学叢書』のためであり、本叢書により考証派以外にも明治前の書が数多く中国に紹介された。明治前の書は多く、こうした叢書本として中国で出版されていたのである。
四 明治後医書の中国版
明治以降の医書では、どのようなものが好まれ紹介されたのだろう。そこで一九一一年から新中国成立前後までに、二回以上出版された漢方治療書・針灸書・生薬書を調査したところ計一七書があった。これを分野ごとに、中国の初版年順で刊年・中国名(著者・原書名)を列記すると以下のようである(35)。
〔漢方治療書〕
①一九一一・一七・二〇・三〇年刊『医界之鉄椎』(和田啓十郎『医界の鉄椎』)
②一九一六・二九・三四・四三年刊『漢法医典』(野津猛男『臨床漢法医典』)
③一九二九・三〇・三一・三四・三五・三九・五二・五六年刊『皇漢医学』、一九三〇年刊別訳本『皇漢医学』(ともに湯本求真『皇漢医学』)
④一九二九年刊『臨床応用漢方医学解説』、一九三〇年刊『古方新医学解説』、一九四六年刊『日医応用漢方釈義』(ともに湯本求真『臨床応用漢方医学解説』)
⑤一九二九・三五年刊『漢薬神功方』(石原保秀『皇漢名医和漢薬処方』)
⑥一九三一・三四・四三年刊『和漢医学真髄(和漢処方学津梁・東洋和漢医学実験集ともいう)』、一九三三年刊『漢方処方学歌訣』(ともに渡辺煕『現代医学改造の烽火 東洋和漢医学実験集』)
⑦一九三三・三五年刊『類証鑑別皇漢医学要訣』、一九三六年刊『類証鑑別漢医要訣』(ともに大塚敬節『類証鑑別皇漢医学要訣』)
⑧一九四七・五四・五五・五六年刊『中医診療』(矢数道明・木村長久ら『拓大漢方講座教材』)〔針灸書〕
⑨一九一五・一七・二三・二四・三二年刊『最新実習西法針灸』(岡本愛雄『実習針灸科全書』)
⑩一九三〇・三三・三五・四〇年刊『灸法医学研究』(原志免太郎『灸法の医学的研究』)
⑪一九三〇・三一・三二・三三・三六・三七・四一年刊『高等針灸学講義』(延命山針灸学院『高等針灸学講座』)
⑫一九三六・四八・四九・五一・五二・五四・五五・五六年刊『針灸秘開』(玉森貞助『針灸経穴医典』)
⑬一九四九・五一・五四年刊『針灸処方集』(代田文志『臨床治療要穴』・松元四郎平『針灸臨床治方録』)〔生薬書〕
⑭一九一〇・一一・一四・三四年刊『化学実験新本草』(日本の生薬学書から編集)
⑮一九一四・一八・二六年刊『漢薬実験談』(小泉栄次郎『漢薬実験談』)
⑯一九三〇・三三年刊『新本草綱目』(小泉栄次郎『和漢薬考』)
⑰一九四六・四七・四九年刊『実用中薬大綱』(宮前武雄『図説和漢薬応用の実際』)さて以上の著者は、漢方治療書の全員が医師、生薬書は薬剤師か薬学者、針灸書は針灸師・針灸学校・医学者で、みな近代医薬学を修めている。当然ながら各書ともに近代医薬学の用語や表現がみえる。明治以降でもこれらに該当しない内容や著者の漢方・針灸・生薬関係書は少なくないが、そうした書は以上一七書以外の中国版でも数えるほどしかない。つまり近代科学の修飾を受け、いわゆる「科学化」された書が総じて好まれたのだった。
一七書が民国期の一九一一〜四九年に出版された回数をみると、漢方治療は八書で二七回、針灸は五書で二〇回、生薬は四書で一二回だった。刊行が重ねられた書ほど需要があったはずなので、本数字は当時好まれた分野と書の反映とみていいだろう。
図1 中国訳『皇漢医学』掲載の
湯本求真自筆の祝辞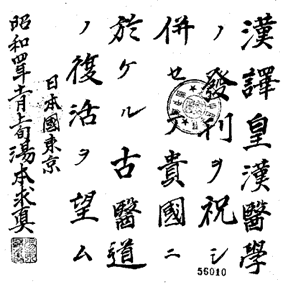 刊行数の多い書をみると、湯本求真の『皇漢医学』に二種の訳本があり計七回、新中国以後も含めると九回におよび、もっとも版を重ねた明治後の医書だった。湯本の書では『臨床応用漢方医学解説』も訳本が三種出ており、彼はよほど注目されていたらしい。『皇漢医学』の周子叙訳本には湯本求真自身の祝辞(図1)が載り、周序には「…凡湯本所言、皆余所欲言而不能言者也。中医垂絶之緒、庶幾可以復振矣。夫資科学之実験、則不偏尚懸解、明古方之妙用、則不徒重機械、是誠医林之準縄、民生之根本也…」(36)という。
刊行数の多い書をみると、湯本求真の『皇漢医学』に二種の訳本があり計七回、新中国以後も含めると九回におよび、もっとも版を重ねた明治後の医書だった。湯本の書では『臨床応用漢方医学解説』も訳本が三種出ており、彼はよほど注目されていたらしい。『皇漢医学』の周子叙訳本には湯本求真自身の祝辞(図1)が載り、周序には「…凡湯本所言、皆余所欲言而不能言者也。中医垂絶之緒、庶幾可以復振矣。夫資科学之実験、則不偏尚懸解、明古方之妙用、則不徒重機械、是誠医林之準縄、民生之根本也…」(36)という。
この初版は一九二九年の年末に出たが、同年二月には前述の「廃止中医案」が批准されており、その切迫感と本書への期待感を当序文にみることができよう。事実、一七書のうち六書は二九年と三〇年に初版が集中しており、それらが同案への対抗策としての近代化や科学化のモデルとされていたことを物語っている。各訳書名でみても、「高等」「最新」「西法」「医学研究」「化学実験」などの語があり、みな同じ雰囲気を伝えている。
四回刊行された『医界の鉄椎』は近代医学を修めた医師・和田啓十郎がその不足を指摘し、伝統医学の優位性を主張した日本最初の書として名高い。そうした性格は以上のいずれの書にも大なり小なりある。前述したが、中医廃止を唱えた余岩にしても汪企張にしても日本で近代医学を修めていた。したがって、これらの書は彼らへの反論にも代用可能であり、当時の中医界にとって近代化を含めた恰好の援軍だったに相違ない。
ところで明治前の書は一九三七年以後、出版が数点にまで激減していた。しかし明治後の書にそれほどの急変が見られなかったのはなぜだろう。中医側は存続運動の結果、三六年の中医条例と三七年の中医委員会設立で一応の成功をみたが、実際それらは戦乱のため実施どころではなかった。また中医廃止派との対立が消えたわけでもなく、一九四五年の戦争終結で再燃している(37)。こうした期間、明治後の書が翻訳出版され続けているのは、やはり上述と同様の価値が認められてのことと推定できる。
五 影響
前述した民国代の医学叢書には、考証派の多紀元簡・元堅の著述に評注を加えた計四書が収載されていたが、うち二書は『傷寒論』の研究書だった。またそれらの評注者には匯通学派の人物が目立った。表2の『日本漢医傷寒名著合刻』も浅田宗伯の『傷寒弁要』と『傷寒翼方』からなり、編者は匯通学派の立場もとった秦伯未(一九〇一〜七〇)(38)である。このように考証派の傷寒研究が匯通学派に注目・評価されていたし、彼らの『傷寒論』関係著述にも影響を与えていた。
その顕著な例として、匯通学派の陸淵雷(一八九四〜一九五五)(39)の『傷寒論今釈』をまず見てみたい(40)。本書は一九三一年の初版から五六年まで七版を重ね、民国代の『傷寒論』研究書では出版回数が最多で(41)、影響力も大きかったと思われるからである。また一九三〇年の自序に、「此書…首巻成于上海中医専門学校、次両巻成于(上海)中国医学院、後数巻成于上海国医学院」とあるように、彼の講義録でもあったらしい。
さて彼の師であり、上海中国医学院の校長も任じた民族革命思想家の章炳麟(号を太炎、一八六九〜一九三六)は、本書に寄せた一九三一年の序に「…陸子(淵雷)総合我国諸師説、参以日本所証明、有所疑滞、又与遠西新術校焉。而為今釈八巻…」という。実際、本書が利用する日本書は間接引用も含め四五種(42)におよび、中国書の三四種より多い。日本文献の引用は人名のみの場合もあるが、大多数は明治前の文献で、明治後は『皇漢医学』と藤田謙造の『温知堂雑著』程度だった。その理由は本書に明記されないが、彼の先輩で『傷寒論輯義按』を著した匯通学派の酴鉄樵は、「…如但求科学化、則非驢非馬、必有大害。又不可効法東洋(日本)、彼国現在医学…表面是科学化、裏面仍是用中国旧方薬、可謂中医同化于西医…。我国若効法日本、本談不到改良中医、廃除可矣」(43)と、明治後の「科学化」された伝統医学に倣うのは危険という。陸淵雷も同様の見解だったかも知れない。
一方、彼が引用した明治前の書は、考証派・古方派・その他がほぼ同数だった。引用回数の最多は山田正珍『傷寒論集成』で、次いで多紀元簡『傷寒論輯義』、多紀元堅『傷寒論述義』、浅田宗伯『勿誤薬室方函口訣』、吉益東洞『方機』『方極』、尾台榕堂『類聚方広義』などで、やはり考証派からの引用量の多さが目立つ。一方、これら引用書には中国版になっていない書がきわめて多い。間接引用の可能性を除去しても、中国に伝来していた江戸刊本・写本を相当熱心に博捜し、利用していたことが分かる。
『傷寒論』と同じ張仲景著の『金匱要略』についても、陸淵雷は『金匱要略今釈』を著した(44)。本書は一九三五年の初版から五五〜五七年まで少なくとも八版を重ね、民国代の『金匱要略』研究書では出版回数が最多である(45)。本書の引用文献は間接引用も含め日本書・日本人が五一種(46)で、中国書の一九種よりはるかに多い。また日本書のうち明治後は四種のみで、他は明治前の書だった。引用された明治前の書数ではその他の書が多く、次いで考証派と古方派がほぼ同数だが、引用回数では考証派の書からが多い。
一方、陸淵雷は本書一八四頁で、中国の歴代注釈と日本の古方派が外台烏頭湯を誤認しているのは、『外台秘要方』の確認を怠ったためと厳しく批判する。あるいは一九三四年の自序で「…予則宗師仲景、又不同日本古方派之篤守成方…」ともいう。古方派の主張と一線を画していたのは疑いない。
以上のように、陸淵雷は仲景医書の解釈に中国歴代の書や明治後と古方派の書も参照はするが、かなりの部分を考証派の所説に依拠していた。それが時流に合致していたためもあろう、彼の二書は民国代もっとも版を重ねている。彼以外でも匯通学派の中心人物らが考証派の仲景研究を評価していたし、日本の注釈を採用した黄竹斎(一八八六〜一九六〇)の『傷寒論集注』や、閻徳潤(一八九八〜?)の『傷寒論評釈』もある(39)。
当時の匯通学派は伝統医学の実践において五行説を否定しつつ、近代医学の実験主義に基づこうとした。その際、恰好の古典が五行説による記述の少ない『傷寒論』であり、最適のモデルが五行説を捨象して解釈する日本の書だったといえよう。しかし明治後の書は近代医学の修飾があるにしても、古典研究は質量ともに明治前の書におよばない。そこで選択されたのが考証派の書だった。当時の中医界で指導勢力を占めた匯通学派は、実践のための一古典として『傷寒論』を選択し、考証派の研究を採用しつつ近代医学との匯通を目指していたのである。
六 総括
中国では日本留学ブームからの帰国者増加と並行し、一九一一年から日本伝統医書の翻訳と出版が増加し始めている。それが急増するのは二九年からで、直接要因は明治政府に倣った「廃止中医案」が同年に批准されたことだった。中医界は廃止派の批判に応えるためにも、近代化・科学化を焦眉の課題とさせられたのである。この中国医学革新に有用なモデルとして日本医書が流行したのだった。
需要の増加に応えたのは翻訳の手間が少ない明治前の書で、それゆえ多くは叢書本として刊行されている。とりわけ多紀氏を中心とした考証派の著述は一定して出版数を増やしていたのみならず、それらへの評注書まで出現している。彼らの『傷寒論』研究は匯通学派の著述に少なからぬ影響を与え、医書誌研究は中医廃止派にも評価されていた形跡があった。他方、古方派の書は一九三六年の『皇漢医学叢書』をピークに一時の流行はあったが、さほどの影響は遺さなかった。
明治後の書も二九年から増加に転じたが、和文を中国訳しなければならない要因もあり、急増はしていない。一九一一年から二回以上出版された書をみると、いずれも著者は近代医薬学を修めており、いわゆる「科学化」された書が好まれていた。そうした日本人が近代医療の不足をいい、伝統医療の優位性を大なり小なり主張する書ゆえ、主唱者が日本で近代医学を修めた中医廃止派への反論も兼ねていたのである。ただし匯通学派はその「科学化」を近代医学への同化とも感じており、けっきょく表面的な流行にとどまった。
そして明治前の書を主とした二九年からの日本伝統医書ブームは、足かけ八年後の三六年に絶頂期を迎えたのち、あっけなく終焉してしまう。一九三七年からの日中戦争が原因だった。「もし」が歴史に無意味とはいえ、戦争がなければ現在の両国伝統医学にかくもの懸隔はなかっただろうなどと、いささか夢想せざるを得ない。
*本稿は京都大学人文科学研究所創立七〇周年記念国際シンポジウム「西洋近代文明と中国の近代」での講演(一九九九年十一月十九日)に補訂を加えたものである。
文献と注
(1)中国で一九五六年から設置された伝統医科大学の履修科目はたびたび改変されているが、中国医学以外に現代医学をおよそ五〇%以内の割合で教育している(真柳誠「現代中国医療事情・その2 医学教育とその制度」『現代東洋医学』五巻一号一〇五〜一一一頁、一九八四年)。
(2)この間の熾烈な存続運動は、深川晨堂『漢洋医学闘争史 政治闘争篇』(復刻版、東京・医聖社、一九八一年)に詳しい。
(3)漢方復権の歴史は矢数道明『漢方略史年表』『同続編』『同続々編』(東京・春陽堂書店、一九七九・八六・九一年)に詳しい。
(4)真柳誠「清国末期における日本漢方医学書籍の伝入とその変遷について」『矢数道明先生喜寿記念文集』六四三〜六六一頁、東京・温知会、一九八三年。
(5)真柳誠「江戸期渡来の中国医書とその和刻」、山田慶兒・栗山茂久編『歴史のなかの病と医学』三〇一〜三四〇頁、京都・思文閣出版、一九九七年。
(6)任応秋『中医各家学説』一五四〜一八〇頁「第八章 匯通学派」、上海科学技術出版社、一九八〇年。
(7)劉伯驥『中国医学史』六二四〜六三五頁、台湾陽明山・華岡出版部、一九七四年。
(8)程之范主編『中外医学史』一三六〜一三九頁、北京医科大学中国協和医科大学聯合出版社、一九九七年。
(9)石田秀実「中国伝統医学はなぜ解剖学を早期に受容・展開させなかったのか」、田中淡編『中国技術史の研究』七一五〜七三八頁、京都大学人文科学研究所、一九九八年。
(10)高毓秋・真柳誠「丁福保与中日伝統医学交流」『中華医史雑誌』二二巻三号一七五〜一八〇頁、一九九二年。
(11)真柳誠「中国において出版された日本の漢方関係書籍の年代別目録 第一報」『漢方の臨床』三〇巻九号四七〜五一頁、一九八三年。「同 第二報」同三〇巻一〇号三二〜四一頁、一九八三年。「同 第三報」同三一巻二号六四〜七五頁、一九八四年。
(12)蕭衍初・真柳誠「中国新刊の日本関連古医籍」『漢方の臨床』三九巻一一号一四三一〜四四頁、一九九二年。
(13)岡西為人「中国に渡った日本の漢方医学」『日本東洋医学会誌』三巻一号六四〜六六頁、一九五三年。
(14)この「医史」に分類された計七書のうち六書は、日本が運営した満洲医科大学と上海自然科学研究所による出版である。
(15)文献(11)によれば、中国における年代のはっきりした日本伝統医学書の出版は清・咸豊九年(一八五九)に始まる。
(16)この一三九書のうち一六書は満洲医科大学・上海自然科学研究所など、日本ないし日本人が運営した機関・書店による出版である。
(17)ちなみに不完全とは思われるが、同仁会の調査(同仁会調査部「華訳日本医書」『同仁会報』第四冊一九〜三八頁、一九四一年)によれば、清末から一九四一年までに翻訳出版された日本医書は一五〇書で、うち日本の伝統医学書は一三書ある。
(18)たとえば一八九〇年初版の下山忠典『生薬学』、のち中国訳版が出た一八九三年初版の小泉栄次郎『和漢薬考』など。
(19)実藤恵秀『中国人日本留学史』五五〜六二頁、東京・くろしお出版、一九六〇年。
(20)趙洪鈞『近代中西医論争史』一五四頁、合肥・安徽科学技術出版社、一九八九年。
(21)文献(20)、一〇九・一一四〜一一七・一二二〜一二七・一四二〜一四九・二七八頁。
(22)日本医薬書全体の中訳本は、一八九六〜一九一一年の四六書から一九一二〜三七年は一一九書まで急増するが、一九三八〜四五年には一三書にまで激減する(実藤恵秀監修「4.応用科学類訳書明細表」『中国訳日本書総合目録』四七頁、香港・中文大学出版社、一九八〇年)。
(23)江戸時代までの医学著作は一万書を越える(真柳誠「江戸以前全医学著作のインターネット検索」『日本医史学雑誌』四五巻二号二九二〜二九三頁、一九九九年)。
(24)陳存仁『中国医学史』一二〇頁(香港・中国医学研究所、一九六九年)によれば、陳氏は中央国医館から派遣されて日本で漢方書を蒐集し、九三種を当叢書に収めたという。この集計が何に基づくか不詳だが、当叢書の第七二書は「中国医薬論文集」で、明治から昭和の論文三四篇を翻訳・収載している。
(25)楊杏林「医林怪傑陳存仁」『中医文献雑誌』四一期二八〜三〇頁、一九九五年。
(26)伊広謙「范行準伝略」『中華医史雑誌』二八巻四期二四四〜二四五頁、一九九八年。
(27)真柳誠・郭秀梅「多紀元堅の著述」『日本医史学雑誌』四二巻一号一一一〜一一三頁、一九九六年。
(28)丸山敏秋「廖平と楊注『太素』」『東洋医学善本叢書』第八冊九三〜一一〇頁、大阪・東洋医学研究会、一九八一年。
(29)文献(20)、九三頁。
(30)呉雲波「酴鉄樵生平和学術思想」『中華医史雑誌』二一巻二期八八〜九三頁、一九九一年。
(31)柴中元ら「何廉臣生平及対祖国医学之貢献」『中華医史雑誌』一四巻二期八七〜八九頁、一九八四年。
(32)文献(20)、一八一〜一八六頁。
(33)たとえば富士川游による『医籍考』の出版、森鴎外による『伊沢蘭軒』ほかの史伝、森潤三郎による『多紀氏の事蹟』など。
(34)真柳誠・矢数道明「清・中華民国時代に受容された日本の腹診学」、日本東洋医学会第四三回学術総会(一九九二年五月一六日)にて口演。
(35)当部分の書誌は主に文献(11)によったが、中国版については『全国中医図書聯合目録』(薛清録主編、北京・中医古籍出版社、一九九一年)で補訂し、日本版の原本については筆者所蔵本・矢数道明氏所蔵本・学術情報センター総合目録データベースWWW検索サービス(http://webcat.nacsis.ac.jp/)で補訂した。
(36)一九二九年の上海中華書局版による。
(37)文献(20)、一二七〜一三一頁。
(38)秦伯未『秦伯未医文集』一〜一〇頁、長沙・湖南科学技術出版社、一九八三年。
(39)文献(20)、二二〇〜二三一頁。
(40)陸淵雷『傷寒論今釈』の人民衛生出版社版(一九五六年)による。
(41)注(35)所引『全国中医図書聯合目録』、六一頁。
(42)引用された日本書・日本人を列記すると以下のようである。傷寒論集成、内藤希哲、東洞家配剤鈔、傷寒論輯義、方機、皇漢医学、勿誤薬室方函口訣、病因備考、類聚方広義、生生堂治験、生生堂医談、傷寒論述義、方極、方伎雑志、傷寒論疏義、建殊録、続建殊録、非薬選、漫遊日(雑)記、成積(蹟)録、古方便覧、叢桂亭医事小言、方輿{車+兒}、橘窗書影、傷寒論弁正、薬徴、続薬徴、医方口訣集、腹証奇覧、時還読我書続録、松川世徳治験、伊沢信恬、傷寒雑病弁証、蕉窗雑話、青州治譚、温知堂雑著、山田業広、松原家蔵方、医事或問、永富独嘯庵、餐英館治療(療治)雑話、青嚢瑣探、名医方考、清川玄道、先哲医話。
(43)文献(6)、一六八〜一六九頁。
(44)陸淵雷『金匱要略今釈』の人民衛生出版社版(一九五六年)による。
(45)注(35)所引『全国中医図書聯合目録』、九八頁。
(46)引用された日本書・日本人を列記すると以下のようである。金匱要略述義、薬徴、続薬徴、金匱要略輯義、方機、方極、清川玄道、類聚方広義、方輿{車+兒}、皇漢医学、勿誤薬室方函口訣、生生堂治験、成積(蹟)録、険症百問、橘窗書影、蕉窗雑話、続建殊録、建殊録、黴瘡治方論、方伎雑志、古方便覧、導水瑣言、華岡青州医談、和久田寅(叔虎)、雑病弁要、蘭軒医談、静険堂治験、牛山活套、松原家蔵方、医心方、類聚方集覧、叢桂亭医事小言、漫遊雑記、稲葉克(文礼)、(多紀)元胤、療難指示録、生生堂医談、漢法医典、内科秘録、医方口訣集、先哲医話、工藤球卿、藤田謙造、伊沢信恬、東郭医談、洛医彙講、東洋医学処方各論、医{(勝−力)+貝}、砦草、医余、春林軒丸散便覧。