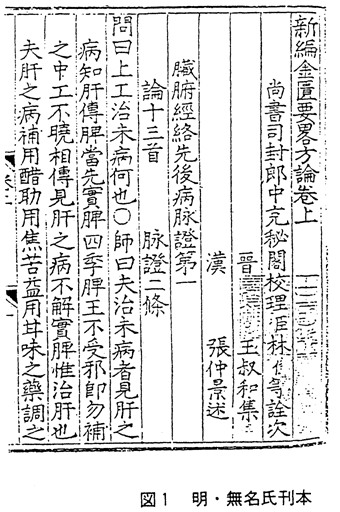
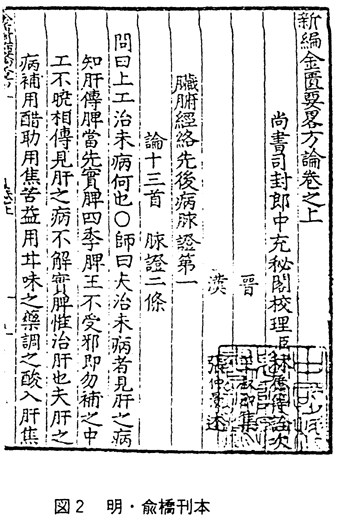 A¾E³¼§{i}Pj
A¾E³¼§{i}Pj^ö@½
êA¬§
@êÊÉwàºvªxÍA»sw¦_xÌÉL³êéw¦Gi²ja_x\ZªÌGaªªP£µ½àÌA é¢Í»êÉR·éAÈÇÆÊà³êÄ¢éB»µÄ¡Ìw¦_xÍ\ªÈÌÅA±êðZªªGaªÅ èA»swàºvªxOªÍ»êð¼ªÉߪµ½àÌAÆླêé±Æà éBµ©µ{̬§ÉÖ·é¿Íw¦_xÈãÉÈA»êðOqÌæ¤ÉP»·éÌÍɳª éB
@»à»àw¦_xÌ£i©Æ³êé¶ÉuGavÌåÍ éªAuàºvÈÇÌåÍDZÉàÈ¢BܽA»±ÉL·w¦Ga_x\ZªÍu¦vÆuGavÌ_ªÒ³ê½àÌƵÄàAeXªôªÅ Á½©Ís¾Å éB¨ÌªÍ`ÊßöÅXɸ·éÌÅA¡Ìw¦_x\ªªà\ªÅ Á½ÆÍfèÅ«È¢BܵÄâ»êç̱ÆÍAu£i©vÌLqðMpµ½ãÅÌc_Å éBâÍè{̬§E¬àAܸjÀÉÆçµÄl@³êËÎÈéÜ¢B
@³Äwàºvªx̼ª³jÉL^³ê½ÌÍA³ãÉÒ[Ìwvjx|¶uÉuàºvªûOªA£iïA¤faWvÆ é̪ÅÅA»êÈOÌwä@xâ¼wxÉÍ©¦È¢BÞëñwvjxÉL^̪AãqÌkv{Z³ãÇÉæéZ§AÂÜè¢íäéuvüvðo½àÌÅ é±Æ;¤ÜÅàÈ¢Bµ½ªÁÄ{̬Íà¿ëñA¬§à³mÈÓ¡ÅÍuvüvÈOÉkè¦È¢Bµ©µ»ÌàeÌ£¹Æ`³ÍA éöxÌǪÂ\Å éB
ñA£¹ÆvÈOÌ`³@
@»¶Ì¿AO¢Iã¼É¬§Ìw¬ox檪Æwb³ox浪ÉA»ê¼ê»wàºvªxÆη鶪©çêéB½¾µ»êçÍããÌtÁÆàl¦çêAK¸µàÌàÌÆÍfèµï¢Êª éB
@ÅàMÅ«éúÌLÚÍìk©Ì«vãA¼ïlÜl`lµONÌÔɬ§µ½w¬iûxÉ©çêé[1]BÍú{ÉxÆàÞÇãÉÍ`µA»ÌÊ{ªÌ¸ot¶ÉÉ»¶·éB»¶ÌªêO¼ÍàeIÉ©ÄàããÌ¥¶ÍܸÈA´{ÌÔðÛ¶µÄ¢éÆvíêéB»±ÉÍ»wàºvªxÚƯêAàµÍµ½û¼E\¬òEå¡ð¶ª©¦éΩè©Aªª¶ÉÍøpƵÄu£iÙ¦óûLãªA£iGûLªªvƾL³êÄ¢éBw¬iûx{¶Ì»wàºvªxÆÌÞ¶ÈǪA»ÌÉL·iÌñ©çÌøpÅ é©Í¢Ú¾ªAÈÆàÜ¢Iã¼ ÉÍ»wàºvªxÌàeÌ éªª¬zµÄ¢½±ÆͱêæèmسêéB
@µ¢IÅÍAä@ãÌwa¹ó_xÌwlGaÌÑÉAui£ji]vÈÇƵĻwàºvªxÌÞ¶ªL³êÄ¢éBwä@xoÐuÉàu£iÃwlûñªvÌL^ª éÌÅAÍiÌwlaÉÖ·éàPs³êÄ¢½±ÆªM¦éB¢Åµ¢I ÅÍAÌwçàûxª\E¦ûºÉAøpoT±»L³È¢ªuSavuÏfavu©átavÈÇA»wàºvªxÆÙÚêv·éѼÉÞʳê½Îð¶âûªLÚ³êÄ¢éB³çɯ̪ñ\ZEH¡ÉÍAiïuÜ¡¹vH¡ÑvÌƨڵ«¶âA»wàºvªxÌæñ\lEñ\ÜÑÆÙڤʷéuHÖviH{ãÌÓEÖõjÌ_ª©çêé[2]B
@wçàûxæèñSNãÌúiµÜñjA¤ûZªÒ[µ½wOäévûxÉÍAwi£ji¦_x\ªª©çÌøp¶ª½ûÚ³êÄ¢éB°çÍAwïvxÉL·£³ONiµZZjÉãt³ê½ã¯Ì±¿ÚÉAu£i¦_ñ¹iâjvÆwè³êéƯêÆvíêéB»Ì\¬ðwOäévûxÌøp¶æè²×éÆAwi£ji¦_x\ªªÌàAªñ`ªE\ª»w¦_xÆÎBª\êE\l`\ªªA»wàºvªxÆεĢéBªêEãE\ñE\OÍA»ÌªðLµ½øp¶ªÈ¢ÌÅÎÖWÍs¾¾ªA¨æ»O¼\ªª»w¦_xA㼪ªª»wàºvªxÆηéàeÆèÅ«éB
@É»wàºvªxÆÌÎÖWðA»ÌSñ\ÜÑeXÉ¢ĸ¸·éÆAv\êÑÆÌζª éBwOäévûxÉÍwi£ji¦_xÌS¶ªøp³ê½í¯ÅÍÈA±êðl¶·êÎAÌwi£ji¦_xÉÍ»wàºvªxÆ©ÈèßÌàeªÜÜêÄ¢½Æè³êéBµ©µ¼ÒÍÑÌɨ¢ÄwÇêv¹¸Aµ½ªÁļÚÌ`³ÖWÍFßï¢B¼ûA»wàºvªxââÁÙÈàeÌæñ\O`ñ\ÜÑAÂÜèuGÃûvÆuHÖvÌζÍwi£ji¦_x©çêØøp³êĢȢBãíèÉÊÌwiiûjxâA»êðøpµ½w£¶iûjx©çÌÝwOäévûxÉøp³êÄ¢éB±Ì±Æ©çàA»wàºvªxÍãÌwi£ji¦_xɼÚR·éàÌÅÍÈ¢±ÆªTسêæ¤B
@Èãðv·éÉAã¿ Éiªµ½Æ³êéw¦Ga_x\ZªÌGaªÉA»wàºvªxªR·éÆ¢¤ðßܾ͢¼àÉ·¬¸A»ÝÌƱëÉêÌàeªw¬iûxÌ«vãÜÅkê龯ŠéBܽÝÌ`³ÖWð¾ç©Éµ¦È¢ªAwa¹ó_xwçàûxwOäévûxÈÇÉø©ê½Ã¶æèAZ©©çúÉ©¯ÄiÌGaÉÖ·é_âû̪AøpâP£EÈÇÌ¡GÈ`³ðèԵȪçAXÉ»wàºvªxÌ´`ÉߢpÆÈÁÄ«½±Æªª³êæ¤Bµ©µ±êÆÄí¸©È»¶¿©ç̪Ìæðo¸AmèIÈàÌÅÍ è¦È¢B
OAkv{ÉæéZù
@æÉwàºvªxÌàeÌ£¹ªÜ¢I ÜÅÍÙÚÇÂ\ȱÆðq×½ªA»Ì¬§Í½iKÉí½èAsÚƹ´éð¦È©Á½Bµ©µàe̬§úÅÍÈA»wàºvªx̬ƷéÈçÎA»êÍuvüvÉæèßÄwàºvªxƵħs³ê½kvúÆmèÅ«éBÉ[È\»ð·éÆAwàºvªxÈéÍuvüvÉæèa¶µ½³AƾÁÄàß¾ÅÍÈ¢BuvüvÌoÜÍ»wàºvªxÉOtÌAkv{Z³ãÇÌòbÅ éÛtE·ïEÑ̶ɾL³êÄ¢éB»ÌÖAªÍX·¢ªAȺɻãêóµÄÝæ¤B
@£iÍw¦EGa_xv\Zªðµ½Bµ©µ¡Ì¢ikvjÉͽ¾w¦_x\ªª`¶·éÌÝÅAwGa_x͢ɩ¦¸A»ÌêEñªÆÌûÉøp³êÄ¢éÉ·¬È¢BƱëªËÑwm̤ªÍ éúAÆÌ}ÙŹðó¯½ÃÉAiwàºÊvªûxOªð©µ½BÍãªÉ¦AªÉGaAºªÉûÆwlaªL³ê½àÌÅ Á½B»±Å]ʵÄlÌw¯ÒÉÌÝ`¦AÉûÆ»Ìå¡Øª®õµÄ¢éàÌðgpµÄݽƱëAøÊÍ_Ì@Å Á½Bµ©µÌ éªÍaØÌLÚÌÝÅ·éûªµÄ¢½èAtÉûÌÝÅ»Ìå¡ØªÈ¢ÈÇA¡ÃÉgp·éÉÍs®SÈÅ éB@ ÈãÌLqæèÌÀªmçêæ¤B@ÆÍíêíêòbÉãÌZùð½¶A·ÅÉw¦_xAÉwàºÊoxðZ§µA¡Ü½ÌZùª®¬µ½BÌZùÅÍAºªÉ Á½ûðeXÌ·éØó¶ÌÉzuµÈ¨µA~}ÌÛÉÖXðÍ©Á½BܽÆÌûÉUÝ·éiÌGaÉÖ·é_àÆûÌöðÌæAeÑÉuûvƵÄââµAÌ¡Ã@ðL°½Bµ©µãªÌ¦ªÍiw¦_xÆärµÄjߪª½¢ÌÅíµA»Ì¼ÌGaæèùHÖõÜÅÍcµASñ\ÜÑƵ½BûÍd¡ð«ñSZ\ñûA±êðãºÌOª{ÉÄÒ¬µ½B¼Íi¤ª©ÌjÌð¥PµÄwàºû_xÆ·é
@»wàºvªxÌê{ÍA¤ªª{}ÙÅ©µ½iwàºÊvªûxOªÅ éB¤ªÍwvjxñ`Ü\OÌ`ÉæêÎAkv{}Ù Ú^Ìw¶ÚxÌÒ[iêZOlNɺ½AêZlêN®¬jÉQÁµÄ¢éB±ÌÍ°ç»ÌÛÉ©³ê½àÌÅ ë¤BÀAw¶ÚSßxÉÍuàºÊvªOªA£iïvÆL^³êÄ¢éB
A±ÌÉͦâGaEùHÖõÌ_ÆûªL³êÄ¢½ªAߪEEE¹ª éΩè©AûÆå¡ð¶ªooA é¢Íêûª¯ÄgpɵsÖÆÈÁÄ¢½B
B»±ÅÛtçͱÌðZù·éÉ ½èAãªÌ¦ªÍ·ÅÉw¦_xðZ§¸ÝÈÌÅíBºñªðÄÒAEªðãÉøp³êÄ¢½iÌöðWßÄâUA é¢ÍuûvƵ½B±ÌuûvÍ»wàºvªxð©éÆv\ÑÉãt³êAwOäévûxwçàûxwçàûxwIãûxwÁûxwßøûxwá^±ûxÈÇAZ©Eä@EÌãûæèAvñ\ñûªââ³êÄ¢éB
C±ÌSÃEÄÒEZ³ÉæèASOªñ\ÜÑEvñSZ\ñûÌƵÄV½Éa¶µ½Ìªwàºû_xÅ éB
@³Ä»sÌwàºvªxÍAܳµ±ÌÉL·wàºû_xƯêÌ`ÔÆÈÁÄ¢éBÂÜè»wàºvªxÍAãqÌ@ÛtçÉæéåüùÌÉAiÌGa¡ÃƵÄÄÒ³ê½êíÌSó{ÈÌÅ éBµ½ªÁÄÂXÌàeͳĨ«A¡íêíꪩéƱëÌwàºvªx̬ÍA³mÉͱÌuvüvƳêËÎÈçÈ¢B
@Ȩ»wàºvªxɱÌæ¤È¡GȬ§E¬Ìoܪ é±ÆÍA{¶ÌðßÅàíɯӳêé׫ŠéBá¦Îå¡ð¶Ì¶ÌE\»@ªââããIÅ Á½èAòÊPÊÉuªvÈǪgíêÄ¢é±ÆÈÇÅA»êçð£iÈãÌ¥¶EtÁÈÇƵÄðßÌÎÛOÆ·é±ÆªXÉ©¤¯çêéBµ©µ»êçÍAi̶ª{ÈOÌiKÅeÔÉ·øEзø³ê½ÊAKRIɶ¶½Ï»É·¬¸A{¿IÉÍâÍè£i̶ÈÌÅ éBÉÍAuÁª¡ÛvÆL³êÄ¢é±ÆæèAª¡Ûð£iÈãÌûƵ½èA£iªÁ̪¡Ûðøpµ½©Ì@öo·élà¢éB±êàAª¡ÛªwÁi[vjûxÉiÌûƵÄÚÁÄ¢½ÌÅAuvüvÌÛÉuÁvƾLµÄûÌÉ]ÚµA¤ªª©µ½Ìðâ[µ½±Æ̳ðÉæéÈàƾíËÎÈçÈ¢B
lAvÈãÌ`³ÆÅ{
@¤ªªkv{Ì}ÙÉ©µ½iwàºÊvªûxÍà¿ëñ»¶¹¸A±êðîÉuvüvðo½wàºvªxnÌݪ»ÝÉ`íÁÄ¢éB±êçÌcÅÅ ékvZ³ãǧEå{wàºvªx̧sNÍA»wàºvªxÉL³êĢȢB½¾»ÌZùɽ¸³íÁ½ò¯Ì¼Æ¯E¼æèAª¼×lÍ¡½ONiêZZZj̧sÆèµÄ¢é[3]B»ÌãAй³NiêZãlj©çNÈàÉA¢íäé¬{wàºvªxªqÄæè§s³ê½±ÆÍw¬oxãtÌ«¶©çmçêéBµ©µ±êçkv{̧{ÍA¢¸ê໶µÈ¢Bܽ»¶Å̶æèAÌìvãÉàV{Ì Á½±Æªª³êéªA»êà`¶µÈ¢B
@MÒ̱êÜÅ̲¸ÉæêÎAwàºvªxÌ»¶Å{ÍdüEeóâSû{ðÜßñZ\íÉàãéªA·×Ī³ãÈ~E¾ãÜÅÌÜÅ{æèh¶µÄ¢éB»±Å»êçÜÅ{ÌREÖWÉ¢ÄÈPÉྵĨ±¤B
@³Eû¹¿§{[4]
@¡ñA{Éeóµ½Ìª»¶ÅÃÌÅÅ éB»Ì»¶ÆÝÍ©ÂÄzEÉmçêĢȩÁ½ªAMÒç̲¸Éæèkåw}ÙÉBêË ³êÄ¢é̪©³ê½BÅÉOtÌû¹¿ÉæêÎAÞÍvµÊsµÄ¢È©Á½wàºvªxðüèµA±êð§s·é½ß³Ìã³ZNiêOlZjɶðµÄ¢éB½¾Å̪ãæOElt¾¯Í§s¨æÑ̪¼tÆÙÈèA¾úÌâÆ»f³êéB±êÍYÌÅتj¹Ì½ß¤èȨ³ê½½ßÈÌÅAkåw{ÌóüN;úÆÈë¤BȨ{̪ãtÌ]ÉÍAȺÌkçhiêªOã`êãêÜjÉæé©M¯êªn³êÄ¢éB
àºvªAȾæâJü{C{û}v{×ÅÀA¥`´{ARF¬`âBã{¥Eë½B³§{^æâ{»AÞ×óLVÐBõÑOA¾©°ãCñÏtAöLBXskçh@ ±êæèkåw{ÍA´Ì¼È ÆEwÒÌkçh ÅAÞªãCÅüèµ½±ÆªðéBÞÍ{ð³§{ÆÓè·éàÌÌA»êª¾ÌCóÅ é±ÆͩƵĢéBµ©àãqÌæâJü{ð{C{û}v{ÆëFµ½½ßAÅÆÌÖWð®SÉðµÄ¢È©Á½çµ¢BöÝÉ{ÌeÉÍvñ\ñíÌ óª³êA»êæè{ÍåÍìE·]YEñÏtEkçhE·öEïÈÇÌèðññS\NÉí½è¬]µ½ãAkåw}ÙÌ ÉAµ½oܪmçêéB
@³Ä±Ìû¹¿§{ÉÍA»ÝÊsÌÅÉÍ©¦È¢vÅÌÔª½Û³êÄ¢éBá¦Î¼ÌªÉuVÒvÌñð¥·é±ÆBÛtç̶ÅAuÆvuåãvu¾qvÌOåÉεhØÌ®ª©çêé±ÆB»Ì¶ãÉláÅïÒ³L̬ªt³êÄ¢é±ÆB{¶eªªÉAïÒ¼ðÑE¤faE£iÌÉzµAÊsÅƳ½ÎÅ é±ÆB{¶Ì®ÉæèAwàºÊvªûxÌ´¶ÆuvüvÉæéâU¶ÌæʪM¦é±ÆAÈÇÅ éBÈãÌÁ¥Íû¹¿{Ì{¶©ÌÉàvÅÌÔª½Û½êÄ¢é±Æ𦴵A©Â»Ìê{Íìv§{A é¢ÍàE³ÔÌ{C{û}ìv§{Å Á½±Æ𪳹éB
@µ©µÅ̼ÉuvªvÌñð_ÍAkvÌå{E¬{¨æÑàÌÊs{̼L^ɱÌñðà̪Ȣ½ßAû¹¿àµÍ»êÉéÔÌüÆvíêéBêûA{©ÌÍû¹¿§ÌÅØðp¢½ããÌCó{̽ßAÅØÌÅâÐÑêÅóüÌsN¾È¶ª½¢B é¢ÍªâàeÉgp³êÄ¢éBÆÍ¢¦AëEE¶ÍããÌÅæèÍé©ÉÈAËÄãqÌ_ðl¶·éÈçA»¶Å{ÌÅÊÉ éP{ÆFßçêéB
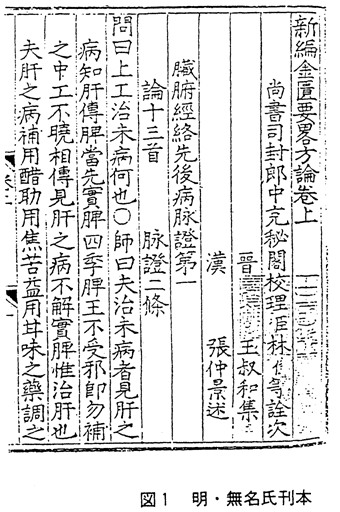
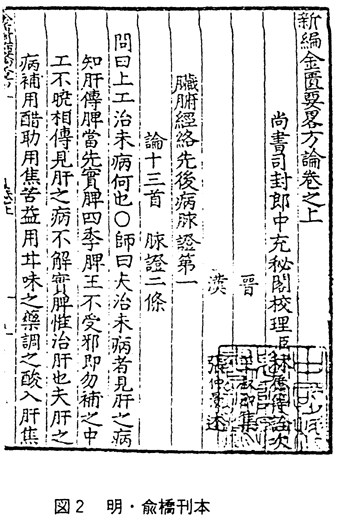 A¾E³¼§{i}Pj
A¾E³¼§{i}Pj
@±ÌÅ{à³Eû¹¿§{¯lAð¡ÜÅ»¶ªëÔÜêÄ¢½ªAMÒçÉæèkÌÈw@}ÙÉ{ªê{AäkÌÌ{¨@ɾ¡ ÌeÊ{ªê{iºªj©³ê½[5]BÅÉàÊsÅÉÍÈ¢vÅÌÔªAÅ®ãÉFZÛ½êÄ¢éBµ©µ»êÆTƵÄÌgpÉϦ¤é©ÍÊâèÅ éBÅÍ̱»¢íäévÅÌ»êÉéªA{¶ÌëEE¶EÌìµ³ÍÅÌŽéàÌÅ éBµ½ªÁÄA ÜÅwàºvªx̤ÆZ¨É¨¢ÄÌÝA¿lÌFßçêéÅ{Æ¢¦æ¤B
B¾E`´§{i}Qj
@Å;ÌÃõNÔiêÜññ`ZZjÉ`´ªðtµÄ§sµ½àÌÅ éBÅ»ê©ÌÌÝÍ»ÝmF³êÈ¢ªAêãñãNÉwlp§kÒlxæñÅÉeóû^³êA©ÂÄú{Åàδ¾ÌðèÅ»êªÄeó³êÄ¢½Bܽ]Ëú ÉŪ|³êvlíÌdü{ª éªA»¶ÍÉßÄÈ¢B
@`´{ÍOf̾E³¼§{Æ_ŤʷéªAá_à½X©çêéBµ½ªÁļÅÍ°ç¤ÊÌcÆ·éà`¾Ô̧{ܽÍÊ{ª èA»êæèh¶µ½Æz³êéªA³mÈƱëÍs¾Å éBܽÅà¾E³¼{ÙÇÅÍÈ¢ªëEE¶ÍÉ¢ÆܪÈAâÍèEZ¨ÈOÌÚIÉÍK³È¢B
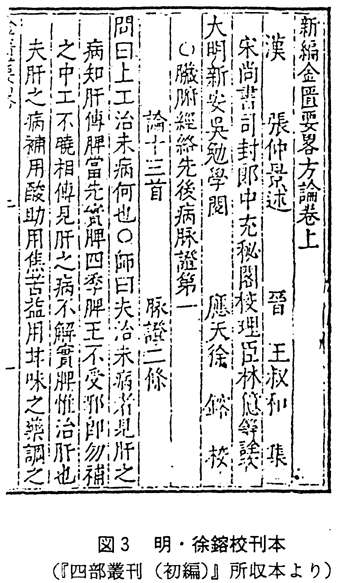
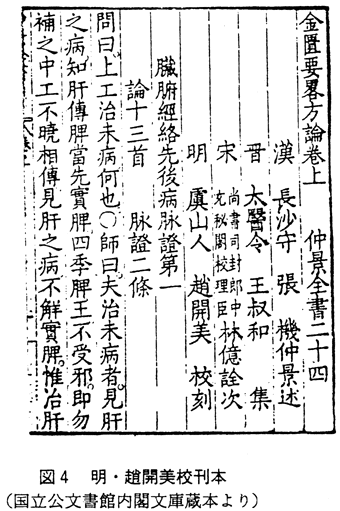 C¾EèOZ§{i}Rj
C¾EèOZ§{i}Rj
@Å;Ìï\ONiêܪÜjÉAèOªÃ{EV{ÆÌ·éÈÆàñíÌwàºvªxðZµAïñ\ãNiêZZêjÉà×wSÌwá㳬SxÉÒü§s³ê½àÌÅ éBæÁÄÅÍã{ÆàÄÎêA©Èè¬zµ½çµú¼É½»¶µÄ¢éBßãÉÍ»Ìeó{ªêãêãNÉwlp§kÒlxæêÅÉûßçê½Ù©A±êÉîÃíÌeó{ª»ÝàâäpæèoųêAÅàyµÄ¢éB
@ÅÌÅ®Eå𸸵ÄÝéÆAèOªZÌê{Ƶ½ÌͳEû¹¿{ÌnÆA¾E³¼{¨æÑ`´{ÌnÅ é±ÆªðéB»µÄê©·éƶÓÌs¾ÈåÍÈA®àvÅ̪۽êÄ¢éª@Å éBƱëªOOÅÆär·éÆAÂXÌåÉÍÓðÊèâ·µ½èAvÅð¤½ßÓIÈüÏEȪÈǪȳê½AƵ©v¦È¢ªªµÎµÎ©çêéBܽëརBµ½ªÁÄÅÌnÍL¬zµÄ¢éªAàe¤ÌeLXgÉàZ¨Ìê{Éàr¾â誽¢Æ¢¦æ¤B
D¾EæâJüZ§{i}Sj
@Å;ÌæâJüªAïñ\µNiêÜããjɧsµ½wiSxÉÒü³êÄ¢éB»êÅiS{ÆàÄÎêéB±ÌæâJüÅÍEäpÉvܪ»¶µA»Ìeó{ªÅkóoųêÄ¢éBú{É;´ÌŪ èAßNÉú{¿û¦ïæè´¡åÅoųêÄeÕÉüèÅ«éB±Ì¼A]ËúÈã¨æÑ´E¯ÔÉÍÒ¬ðêÙÉ·éÊ{ÌwiSxÉÒü³êA½Éjè§s³êÄ¢½[6]B
@ÅÉÍOq̳Eû¹¿Ì¶ªOt³êé±ÆæèAû¹¿{ðê{É|µ½±ÆªmçêéBܽe×É©éÆAÌå;E³¼{ÆêvµÄ¢éBµ©µèO{Ì@«°üÍwÇÈAÙÚÀɼÅÌ媥P³êAëàȢ٤ŠéBÆÍ¢¦¼ÅÉ©çêévÅÌÔÍ®SɸíêĨèAnÌÙÈé¼ÅÌ媬ݷé_©çàAÅÌP{«Íû¹¿{æèÍé©ÉòéB
ÜAàeTª
@»wàºvªxÍSOªñ\ÜÑæè¬èAñSZ\ñûÆñSã\êÌò¨ªLÚ³êÄ¢éB±ÌªÍw¦_xÌ\ªæèÍé©ÉÈ¢ªA{¶ÌÍââÈ¢öxÅ éB
@æêÑÌäDoæãa¬ØÍAwìxtÑÉ੦éuãH¡¢avÌåæènÜèAȺÜsàðpµ½ffÉÖ·é_ÆÈÁÄ¢éB±±ÅÌ_ÍuàovnãÌ_ÆߢB½¾Èöðo½`Õà éªA±êÍÑÌÝÉÀçÈ¢BÑÅÍaöðàöEOöEsàOöɪ¯é`ªq×çêĨèAãÌvãÉwOöûxªq³êéàÆÆÈÁÄ¢éB
@æñÑæèæ\ãÑÍeí¾aÊÌ_àÆ¡ûÅA±ÌÒ¬ðuovÆ·éÈçÎAw¦_xÌOAOzÉæéÒ¬ÍuÜvÌÖWÉ éB¼É¤ÊÌûÍÈÈ¢ªA»ÌpÍÍÍÙÈé±Æª½¢Ba¼EÇó¡ÃÆ¢¤_Aܽ«aªÔ ³êÄ¢é_ÈÇ©çAwàºvªxÌp¿lÍÞµëw¦_xðãñÁÄ¢éBÀA¡úpp³êéiṳ̂¿Ad¡ðE·éÆwàºvªxoTÌûªæè½¢B
@æñ\`ñ\ñÑÉÍAwlȾ³Ì_ÆûªLq³êÄ¢éBwä@xoÐuÉL^Ìu£iÃwlûñªvÍA»Ì¼ÆªæèA é¢ÍYÑÌOgæèPs³ê½àÌ©àµêÈ¢B½¾æñ\ñÑÌÉÍí¸©êûAu¬ápIûvÈé¬Èûª éB±êÉÍu^ñiûvÆ׶ªt³êÄ¢éªAw¬oxªãÉͬGaÌÑà éÌÅAiÌÉÍ{æè½Ì¬aÉÖ·é_âûª Á½Ì©àµêÈ¢B
@æñ\OÑÍ~}¡ÃAæñ\lEñ\ÜÑÍùHÖõÆHÅÌ¡@ªq×çêÄ¢éB±êçOÑÍ»êÈOÌÑÆÉï«ðÙÉ·éÌÅAàÆÍw¦_xwàºvªxÌ{¶ÆÊnÉ Á½àeÅAÌ¿ÉÒ³ê½Æl¦çêéB
@±Ìæ¤ÈR©çOÑÍiÌ{¶ÅÍȢƵÄAXɵÄðßÌÎÛOƳêéªA»Ìàeð£iÈ~ÌàÌÆ·éÌͰ糵ȢBÆèí¯æñ\lEñ\ÜÌñÑÍwçàûxÉL·iïuÜ¡¹vH¡ÑvÆÌÖWªl¦çêAêàÉÍw¿x|¶uªL^Ìw__©éHÖxÜÅ£¹ªª³êéÙÇA»±ÉÍ©ÈèâãÌ`³ªc³êÄ¢éÆvíêé[2]B
k¶£l
[1]¬]Ëmuw¬iûxà|»¶µ½Ãªq{vAwú{ãjwGxOñªêAêãªZB
[2]^ö½uwãSûxøÌw__oxw__HoxÉ¢ÄvAwú{ãjwGxOêªñAêãªÜB
[3]ª¼×lwã{lxêãñ`êããÅAìåãóüZ^[AåãAêãµlB
[4]^ö½çuwàºvªx̶£wI¤iæêñj|³Eû¹¿§wVÒàºû_xvAwú{ãjwGxOlªOAê㪪B
[5]^ö½çuwàºvªxÌÃÅ{ñíÉ¢ÄÌVm©vAwú{ãjwGxOZªñAêãªlB
[6]^ö½uÊ{wiSxÌÆ\¬ÚvAwú{ãjwGxOlªêAê㪪B