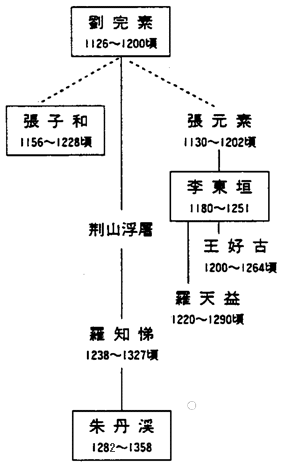 当解題の二書ほかの著書で知られる朱丹渓は、金元四大家の最後の一人であり、中国のみならず日本においても、四人の内で最も後世に歓迎された医家である。これは丹渓の医説が、前三者つまり劉完素・張子和・李東垣らの長を採り短を補い、独自の域へと完成させたからといえよう。あえて大雑把にいうと、丹渓はいわゆる金元医学の集成者なのである。丹渓に至る金元の主要な医家の師弟関係を左のように図示してみると、彼がそれらを折衷しうる時代にあったことが理解されよう(□内は四大家)。
当解題の二書ほかの著書で知られる朱丹渓は、金元四大家の最後の一人であり、中国のみならず日本においても、四人の内で最も後世に歓迎された医家である。これは丹渓の医説が、前三者つまり劉完素・張子和・李東垣らの長を採り短を補い、独自の域へと完成させたからといえよう。あえて大雑把にいうと、丹渓はいわゆる金元医学の集成者なのである。丹渓に至る金元の主要な医家の師弟関係を左のように図示してみると、彼がそれらを折衷しうる時代にあったことが理解されよう(□内は四大家)。真柳 誠
一、朱丹渓
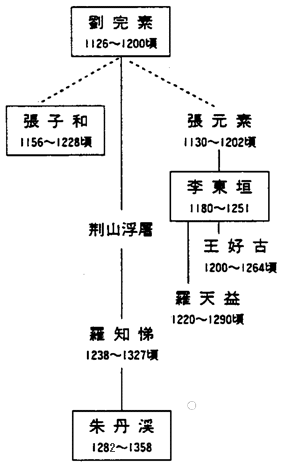 当解題の二書ほかの著書で知られる朱丹渓は、金元四大家の最後の一人であり、中国のみならず日本においても、四人の内で最も後世に歓迎された医家である。これは丹渓の医説が、前三者つまり劉完素・張子和・李東垣らの長を採り短を補い、独自の域へと完成させたからといえよう。あえて大雑把にいうと、丹渓はいわゆる金元医学の集成者なのである。丹渓に至る金元の主要な医家の師弟関係を左のように図示してみると、彼がそれらを折衷しうる時代にあったことが理解されよう(□内は四大家)。
当解題の二書ほかの著書で知られる朱丹渓は、金元四大家の最後の一人であり、中国のみならず日本においても、四人の内で最も後世に歓迎された医家である。これは丹渓の医説が、前三者つまり劉完素・張子和・李東垣らの長を採り短を補い、独自の域へと完成させたからといえよう。あえて大雑把にいうと、丹渓はいわゆる金元医学の集成者なのである。丹渓に至る金元の主要な医家の師弟関係を左のように図示してみると、彼がそれらを折衷しうる時代にあったことが理解されよう(□内は四大家)。
さて朱丹渓の事跡に関する史料は多い。主なものを挙げると、『格致余論』自序と宋濂序(一三四七)、宋濂「故丹渓先生朱公石表辞」[1](以下「石表辞」と略)、載良「丹渓翁伝」[2](「翁伝」と略)などがある[3]。いずれも本人や面識のあった者によるもので、『元史』や『新元史』の朱震亨伝よりはるかに詳しい。各々には齟齬する点も少しあるが、以下に大筋を摘録しておこう。
朱丹渓は{矛+攵+女}州義烏(浙江省金華県)の出身。姓は朱、名を震亨、字を彦修という。住居が丹渓と呼ばれる赤い渓流の傍にあったので、門人は字を避け、丹渓(先生・老人・翁)の号で尊称した。元の前至元十八年一一月二八日(西暦で一二八二年一月九日)の生れ、至正十八年(一三五八)六月二四日の卒。享年七八。*07,10,11付記:西暦による丹渓の生年月日は、長谷部ら『朱震亨『格致余論』訳注』(横浜国立大学長谷部英一研究室、2007年9月)iii頁のご指摘により、1281年11月28日から1282年1月9日に改めた。
丹渓は幼い時に父を亡くしたが、学を好み、進士を志していた。三〇歳の時に母の腹痛を衆医が治せなかったことから、『素問』を三年間学習した。その二年後には、母の病を丹渓自ら治療したという。しかしその以前、すでに弟や伯父・叔父などを庸医の手で失っていた。
三六歳の時、東陽の八華山にて許謙(文懿)に就き、道徳性命の説など朱子四伝の学を数年修めた。久病に臥していた許謙は丹渓の非凡な才を認め、ある日、医道に進まないかと助言した。大いに悟るところがあった丹渓は、これより挙人の道から医の道へ四〇歳にして転じた。
当時は『和剤局方』流の医学がまだ南方で主流を占めており、丹渓も一心にこれを学んだ。しかしそれら古い処方では今の病に対応できず、医学は『素問』『難経』の諸経に基づかねばならないことを痛感した。そこで中国各地に師を求める旅に出、武林(杭州)にてその郡に羅氏がいることを知った。
羅の名は知悌、字を子敬、世間は太無先生と称し、南宋の理宗時代(一二二五~六四)に(「石表辞」は宝祐中[一二五三~五八]という)僧侶であった。医を劉完素の弟子である荊山浮屠(荊山の僧侶)に授けられ、完素以外にも張子和・李杲の説に通じていた。が性格はひどく偏狭で、その学を人に伝えないことで知られていた。
丹渓は幾度(「石表辞」は一〇回)も訪問をくり返し断られた末、ついに門前に立ちつくして面会を許された。その際、知悌は「子は朱彦修ではないか」と問い、すでに丹渓の医名を知っていたという。この時、丹渓は四四歳。そこで初めて劉完素・張子和・李東垣・王好古らの書に接し、知悌に師弟の礼を尽し数年間学び、その学を伝えられた。
帰郷した当初、丹渓の医説は『局方』医学にまだ拘泥していた当地の医家に潮笑され、排斥された。しかし師の許謙の久疾を治療以来、数年にして医名が高まり、諸医も丹渓に心服するようになった。医名が四方に鳴り響いてより、患者のない日はなかったが、雨や雪の日でも往診を断ることがなかった。また貧者といえども往診し、無償で薬を与えた。
丹渓は粗衣・粗食につとめ、七〇を過ぎても顔色衰えず、精気に満ちていたという。晩年、弟子の張翼らに請われ、ようやく『格致余論』『局方発揮』『傷寒(論)弁(疑)』『本草衍義補遺』『外科精要新論(発揮)』などの書(他に「石表辞」は『宋論』『風水問答』の二書を挙げる)を著した。
臨終に際し丹渓は甥の朱嗣氾を呼び、「医学亦難矣。汝謹識之」とだけ言い、端坐して卒した。
丹渓の父の諱は元、母は某氏。妻は戚氏・道一書院山長象祖の女で、丹渓に先立つ三五年前に卒。嗣衍と玉汝の二男があり、嗣衍は先立つ三年前に卒。また四女があり、それぞれ傅似翁・蒋長源・呂文忠・張思忠に娶いだ。孫は男が一人。女は二人あり、一人は丁楡に娶ぎ、一人はまだ幼い。
丹渓は没した五か月後の一一月、某山の原(義鳥より東八里の朱村鷹嘴岩山麓)に葬られた。
二、朱丹渓の著作
現在に伝わる医書で、丹渓の名を冠したり、丹渓撰とされるものは三〇を下らない。もちろん丹渓がそれだけの書を著すはずはなく、大部分は弟子や私淑者の撰、あるいは末裔が秘蔵していたと称するものである。これらの撰述や刊行はおよそ明初から始まり、清代に至る。その風潮は一面、丹渓がいかにもてはやされたかを物語ろう。しかし同じもてはやすのでも、日本では後述のように当解題の二書のみが幾度も復刻されており、両国の受容の差を示すものとして誠に輿味深い。
したがってここでは、解題の二書を除き、丹渓の自撰の可能性が高い書についてのみ、以下に略述しておこう。
『傷寒弁疑』
戴良の「翁伝」が丹渓の著として挙げるもので、宋濂の「石表辞」が『傷寒論弁』若干巻と記す書と同一であろう。これ以外の記録や該当する現存書は見当らず、早くに佚伝したと思われる。
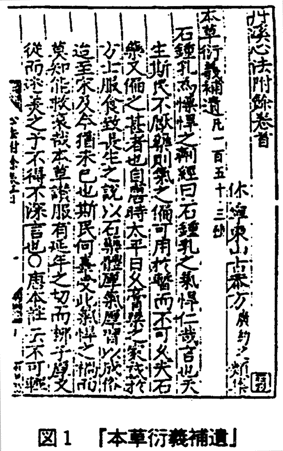 『本草衍義補遺』
『本草衍義補遺』
「翁伝」「石表辞」ともに本書を丹渓の著として挙げ、後者は若干巻と記す。現伝するものでは、方広の『丹渓心法付余』(一五三六序刊)の巻首に一巻本(図1)が載せられているが、丹渓の序などはない。これには石鐘乳以下の一五三種と、新増補として防已以下の四三種、計一九六種の薬物が収載されている。
『本草綱目』巻一「歴代諸家本草」は本書について、「二百種近くを載せる。発明する所が多いが、蘭草を蘭花としたり、胡粉を錫粉とするなど、旧説の誤りを踏襲している。また諸薬を五行に分配している点は牽強に失する」と論評する。
『本草衍義』は宋の政和六年(一一一六)に、寇宗{大+百+百}が『嘉祐本草』『図経本草』(一〇六一)の不備を補う目的で編撰した書。計五〇二種の薬物を載せ、各薬の解説の所々には、いわゆる金元薬理の萌芽といえる論が見える。丹渓が本書を扶翼したのも、故なしとはしないだろう。
『外科精要発揮』
「翁伝」「丹渓」ともに丹渓の著として挙げ、後者は若干巻と記す。書名からみて、陳自明の『外科精要』(一二六三)に関する書と思われるが、現存等の記録はなく不詳。
『宋論』『風水問答』
「石表辞」は丹渓の著として、前者一巻と後者若干巻を挙げる。しかしいずれも他の記録や該当する現存書がなく、早くに散佚したものと思われる。
以上の五書、および後述の二書以外は、いずれも丹渓没後に世に出たもので、およそ丹渓自撰とは認め難い。そのいくつかについては、岡西為人の解題がある[5]。なお丹渓の後裔および門下については、方春陽が近年報告している[6]。○
三、『格致余論』
〔成立年代〕
本書には丹渓の自序と、宋濂の序がある。前者は年代を記さない。至正七年(一三四七)に記された後者によると、丹渓は高齢にもかかわらず精気にあふれ、前人未発の論を多くなしている。そこで門人の張翼らに請われ、本書にまとめた。これに『格致余論』と名づけ、宋濂に示して序を求めた、という。すると本書の成立は、宋濂序の一三四七年、丹渓が六七歳の時となる。
なお宋濂序は、丹渓のこの書は民を益すること甚だ大きいので、三家(劉完素.張子和・李東垣)の書と、世に並び伝えられるべきだ、と記す。これを以て本書の初刊を、一三四七年の少し後と考えられなくもないが、可能性は低い。というのも、もし丹渓の書が生前に刊行されていたなら、前述の伝などにその旨の記載があってよかろう。しかしいずれも自著として、本書を含めた五書ないし七書の名を挙げるのみである。ならば初刊は丹渓が没した一三五八年以降かと疑われ、あるいは『東垣十書』の第一版(一三九九~一四二四、拙著「『東垣十書』解題」参照)に収められたのが、本書の最初の刊本かも知れない。
ちなみに本書の丹渓自序では、書名の所以を「古人以医為吾儒格物致知一事。故目其篇曰格致余論」と述べている。「格物致知」は『大学』に「致知在格物」とあることに基づく儒学の認識論であるが、許謙に朱子学を学んだ丹渓らしい命名である。そして本書中にも、儒学を背景とした医論が多見される。
〔構成と内容〕
本書の諸版本には、校訂者が違ったりなかったり、一巻本や二巻本などの相違がある。ただいずれも全四六篇(論四〇、箴・章句各二、箴序・章句弁各一)よりなり、個々の字句の異同等以外は、内容に大差はない。全篇は丹渓の医学認識を論説したいわゆる医論書で、各篇中にはその論拠として丹渓の治験も多く記されている。
それらの医説は、諸典籍・医書などを引用しながらも、極めて独創的な論となっており、多く後代の議論の対象となった。そこで以下に代表的な議論を訳出し、紹介しておこう。
兪弁『続医説』[7](一五二二成)
丹渓は医の聖者であり、『格致余論』は古今を超えており、軽々しく論ぜられない。しかし反復して熟読すると、疑わしき点も少しはある。永{王+容}ら『四庫全書総目』[8](一七八九成)第一は「左大順男右大順女論」である。丹渓は脈位の陰陽を言わず、ただ気血の陰陽のみを取りあげ、手の左右の論を立てている。これは経旨に背く。
第二は「醇酒宜冷飲論」である。私が見るところ、世の人は熱い燗酒を飲んでも問題ないが、暑い盛りでも冷酒を飲むと病になることがある。これはおかしい。
第三は「倒倉論」である。丹渓はこの方法を西域の異人から得たという。近頃、私は数人の士大夫がこれを信じて行い、相ついで死ぬのを目撃した。これもおかしい(以下略)。
丹渓は陽が動きやすく、陰が欠けやすいといい、「滋陰降火」を重視し、「陽は常に有余、陰は常に不足」の論を立てた。張介賓(『景岳全書』伝忠録)らは、これを攻撃している。しかし丹渓の主意は補益にあり、それでくどくどと飲食や色欲をいましめているのである。また丹渓の補陰諸丸も奇効が多い。なお本書の諸篇中で、しばしば話題に挙げられるのが末篇の「張子和攻撃注論」である。劉完素の瀉火説を発展させた、張子和流の攻撃的な瀉下剤の乱用は人を多く殺している、と李東垣も『内外傷弁惑論』の冒頭などで間接的に批判していた。しかし丹渓は当篇で、「子和之法。不能不致疑於其間」と子和を名指しで非難している。と同時に、『和剤局方』流も強く批判する。このようなことから、医家が門戸を分かって攻撃しあうのは丹渓に始まる、と後世しばしば評されるのであろう。ちなみに、当篇は丹渓の自撰ではない、という説も最近あり[9]、ますます興味はつきない。孫一奎の『医旨緒余』は次のように述べている。丹渓の時代は平穏で、人々は欲望に任せて精を涸らし、内火を盛んにしていた。加うるに剛剤を用い、死に至らしめていたので、丹渓の説ができたのである。これを解らない後人が寒凉剤で人を殺しているのは、丹渓の学習が足りないのである、と。以上の説は、当を得たものといえよう。(以下略)。
〔版本〕
本書の現存版本、とりわけ和刻本は他の『東垣十書』所収本より多い。そこで『十書』所収の本書については刊年を記すにとどめ、所蔵等は省略する。拙稿「『東垣十書』解題」を参照されたい。また清以降の版本も煩を避け、割愛した。
元刊本
鎮江市図書館所蔵。『局方発揮』との合刊本。未見につき詳細は不詳。あるいは明初の刊本か。
明刊本
①明刊小字本 南京図書館所蔵。未見につき不詳だが、あるいは『十書』の遼藩本、ないしは熊氏本か。
②正徳三年(一五〇八)熊氏梅隠堂刊『十書』本。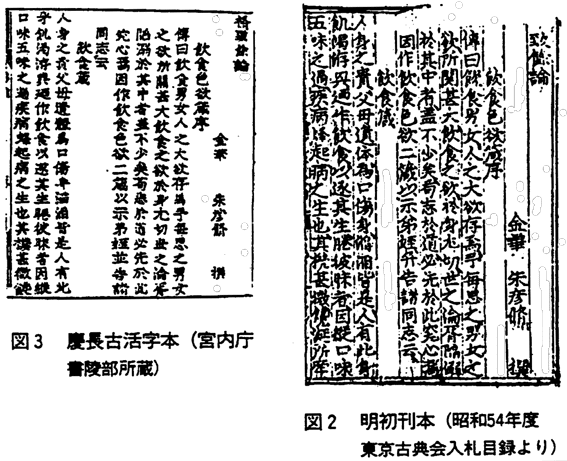 ③明初刊本(図2)昭五十四年度の東京古典会入札目録に掲載された。同目録は元刊本と記すが、目録頭を「新刊東垣十書格致余論」に作る点、版式・字様の特徴より、前掲熊氏本の翻刻と思われる。ただ『十書』全体が復刻されていたかは、同版の他書が現存せず不詳。
③明初刊本(図2)昭五十四年度の東京古典会入札目録に掲載された。同目録は元刊本と記すが、目録頭を「新刊東垣十書格致余論」に作る点、版式・字様の特徴より、前掲熊氏本の翻刻と思われる。ただ『十書』全体が復刻されていたかは、同版の他書が現存せず不詳。
④嘉靖八年(一五二九)遼藩刊第三版『十書』本。
⑤万暦十一年(一五八三)周氏刊『十書』本。
⑥万暦二十九年(一六〇一)序刊『医統正脈全書・十書』本。
⑦万暦末(一六十一~一三)頃王肯堂校訂『十書』本。
⑧明末頃『十書(十二種)』本。
朝鮮刊本
①中宗後半(一五二九?四四)頃内医院刊『十書』本。
②英祖四十一年(一七六四)恵民署鉄活字刊『十書』本。
日本刊本
①慶長二年(一五九七)小瀬甫庵刊古活字『十書』本。
②慶長間(一五九六~一六一四)古活字一二行一九字本 宮内庁書陵部所蔵(図3)。
③元和間(一六一五~二三)古活字本 大阪府立図書館・天理図書館・久原文庫所蔵。未見。あるいは④と同版か。
④元和(一六一五~二三)頃古活字『十書』本。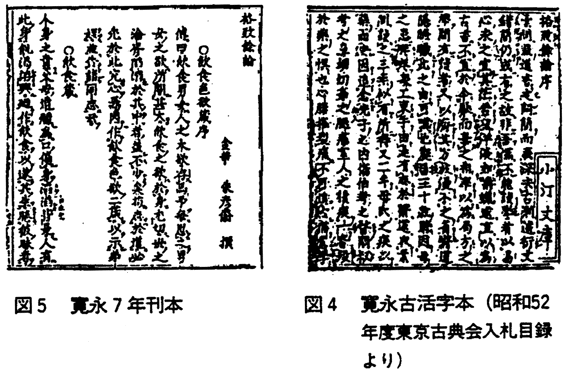 ⑤寛永間(一六二四?四三)古活字一二行一七字本 昭和五十二年度東京古典会入札目録に掲載された(図4)。
⑤寛永間(一六二四?四三)古活字一二行一七字本 昭和五十二年度東京古典会入札目録に掲載された(図4)。
⑥江戸初古活字本 大東急記念文庫所蔵。
⑦寛永(一六二四~四三)頃刊『十書』本。
⑧寛永七年(一六三〇)敦賀屋久兵衛刊本 個人蔵(図5)。古活字本の覆刻だろう。
⑨寛永十八年(一六四一)風月宗知刊本 武田科学振興財団杏雨書屋所蔵。
⑩正保二年(一六四五)刊本 武田科学振興財団杏雨書屋所蔵。⑨本の翻刻。
⑪慶安元年(一六四八)林甚右衛門刊本 東京大学総合図書館・都立日比谷図書館・国立国会図書館・金沢大学図書館所蔵。⑩本の重印本。
⑫慶安二年(一六四九)刊本 田中新吾氏所蔵。⑩本の重印本。
⑬万治元年(一六五八)武村新兵衛刊『十書』本。
⑭万治三年(一六六〇)敦賀屋久兵衛刊本 北京・中医研究院図書館所蔵。⑧と同版か。
⑮寛文五年(一六六五)村上勘兵衛刊頭注本 研医会図書館・沈陽医学院ほか所蔵。
⑯寛文九年(一六六九)刊本 神宮文庫・坂上義和氏所蔵。
⑰寛文間(一六六一~七二)中村五兵衛開版本 大久保諶一氏所蔵。
⑱延宝九年(一六八一)橋本屋長兵衛刊本 柏瀬茂氏所蔵。
⑲元禄元年(一六八八)前、山本長兵衛重印⑬『十書』本。
⑳元禄二年(一六八九)吉(芳)野屋徳兵衛刊『医家七部書』所収重印⑲本 国立国会図書館所蔵。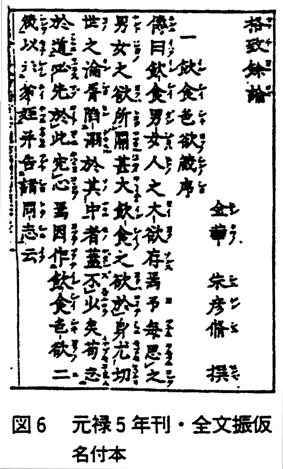 21元禄五年(一六九二)秋田屋清兵衛開版・全文振仮名付本 研医会図書館東北大学附属図書館ほか所蔵。
21元禄五年(一六九二)秋田屋清兵衛開版・全文振仮名付本 研医会図書館東北大学附属図書館ほか所蔵。
22元禄五年(一六九二)井筒屋六兵衛刊21本 個人蔵(図6)。
23元禄七年(一六九四)後刊、『医家七部書』所収重印⑲本 北里東医研書庫所蔵。
24宝暦十年(一七六〇)大田又右衛門刊本 北京・中医研究図書館所蔵。
25江戸・川勝又兵衛重印⑱本 北京大学図書館・慶応大学医学情報センターほか所蔵。
○以上、現存する『格致余論』は、およそ元明刊本が八種、朝鮮刊本二種、日本刊本二五種を数えることができた。中国・朝鮮版のほとんどが『十書』本であるのに対し、日本では江戸初期から単行本として幾度も復刻や重印が行なわれている。これは中国で朱丹渓撰と称する書が、数多く明清間に出版されたのと全く異なる形で、日本では丹渓の医論が流行したことの如実な証左といえよう。
特異な例では、全文に振仮名が付けられた図6本がある。このような例は、他に『傷寒論』『金匱要略』にもあり、その意図は言うまでもない。反対に極めて詳細な頭注を施した鼇頭注本の⑮は注目に価する。匡郭内にまで注が刻入されているが、残念なことに注者を知る手掛りをまだ発見できない。しかし先人の遺した貴重な業績なので、今回の影印では個人蔵の⑲本と⑮本を底本に選択し、一括して復刻することにした。
なお江戸初期における本書の研究は、⑮の頭注本に限らない。筆者の管見では、以下の三書が刊行されている。これらも本邦における丹渓の流行を物語るものといえよう。
『格致余論鈔』五巻 撰者不詳。寛永十三年(一六三六)および同二十一年(一六四四)敦賀屋久兵衛刊。『格致余論疏鈔』八巻 広田玄伯撰。延宝七年(一六七九)序、西村市郎右衛門刊。
『格致余論諺解』七巻 岡本一抱撰。元禄九年(一六九六)序、西村市郎右衛門刊。
四、『局方発揮』
〔成立年代〕
本書には序跋等がなく、成立年をそれから知ることはできない。ただ『格致余論』の宋濂序、また同人の「翁伝」の記載から見ると、『格致余論』に次いで書き上げたと思われる。するとおよそ一三四七年より、少し後の成立となろう。
また初刊年も前書にて考察したごとく、丹渓が没した一三五八年以降かと思われる。あるいはやはり、『東垣十書』の第一版が本書の初刊本かも知れない。
〔構成と内容〕
本書の全版本は一巻本で、いずれも計三一条からなる。各条は「或曰」で始まる一字落ちの文と、「予曰」で始まる文が対になった、問答形式の医論である。それらの論点はかなり多岐にわたっているが、『格致余論』が医学概論とするならば、本書は臨床に則した医論集といえよう。
個々の論述では所々に治験例を交えながら、徐々に丹渓の主張する滋陰降火の具体的運用法を解説している。同時にそれは、『局方』の処方は燥剤が多く、内火を盛んにしてしまう、という批判であり、『局方』の没理論の指摘でもある。これが本書名の所以となっていることは、巻頭の序に相当する文に強い口調で述べられている。
もちろん『局方』に対する批判は『格致余論』にも多く、この点からすると両者はまさしく同工異曲といえよう。また『局方』流への反発は金元の諸大家に共通するが、それを単に処方の固定的運用の非難にとどめず、滋陰という治療方針から論及する点では、李東垣などより徹底している。張元素から承け、李東垣でほぼ完成された理詰による処方の組み方を、丹渓は上手に導入している。が温補ではなく、滋陰による火熱証の治療を主張する点では、劉完素や張子和の所説の発展が見られる。
丹渓も自から述べているが、この相違の背景には気候風土の差を無視できない。つまり東垣らは北方人で、丹渓は南方人なのである。中国南方と気候が似ている日本にて、東垣らより丹渓の書が格段に歓迎された理由の一つは、この点にあるかも知れない。とまれ前述のごとく、本書を含めた丹渓の説は歓迎の反面、また強い反論も張景岳などから受けたことは事実である。四大家随一の理論家ではあるが、師承関係からであろうか、丹渓は時にいささか強引な論理を展開させている。これに立腹するのは、景岳一人でもなかろう。
〔版本〕
本書は以下の諸版本が現存している。なお清以降の中国刊本は割愛し、前書で掲げた叢書本は「格①」本のように記述を省略した。それらの書誌については、拙稿「『東垣十書』解題」を参照されたい。
元刊本
上海中医学院図書館(黒口本)および鎮江市図書館(『格致余論』と合刊)所蔵。未見。あるいは明初刊本か。
明刊本
①「格②」本。
②成化二十年(一四八四)遼藩刊第二版『十書』本。
③「格④」本。
④「格⑤」本。
⑤「格⑥」本。
⑥「格⑦」本。
⑦「格⑧」本。
朝鮮刊本
①「格①」本。
②「格②」本。
日本刊本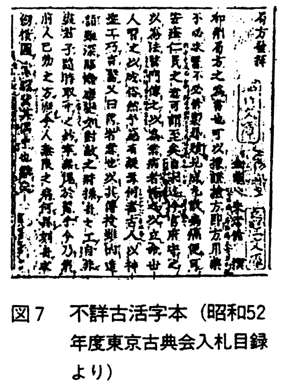 ①「格①」本。
①「格①」本。
②慶長十三年(一六〇八)?古活字一二行一八字本 武田科学振興財団杏雨書屋所蔵。
③元和間(一六一五~二三)古活字一二行一七字本 同右書屋所蔵。「格⑤」と同版。
④寛永間(一六二四~四三)古活字一二行一七字本 研医会図書館所蔵。
⑤不詳古活字一〇行一七字本 武田科学振翼財団杏雨書屋所蔵。
⑥不詳古活字九行一六字本 同右書屋所蔵。
⑦不詳古活字一二行一八字本 昭和五十二年東京古典会入札目録に掲載(図7)。②本と似るが別版。
⑧「格⑦」本。
⑨寛永十八年(一六四一)刊本 神宮文庫・日本大学図書館富士川文庫ほか所蔵。
⑩慶安元年(一六四八)刊本 静嘉堂文庫・慶応大学医学情報センター所蔵。⑨の翻刻本。
⑪「格⑬」本。
⑫万治二年(一六五九)村上勘兵衛刊頭注本 個人蔵。
⑬寛文間(一六六一~七二)耆屋甚助刊本 研医会図書館所蔵。
⑭「格⑲」本。
⑮「格⑳」本。
⑯「格22」本。
○以上のように『格致余論』同様、『局方発揮』も本邦で幾度も刊行されていたことがわかる。さらに本書の解説本も、左の二書が刊行されている。
『局方発揮抄』三巻 撰者不詳。寛永五年(一六二八)古活字本。研医会図書館所蔵。巻頭に「丹渓翁伝」を付す。仮名混りの「ナリ」「ゾ」式文体なので、あるいは曲直瀬塾あたりのテキストか。これらの検討より・今回の影印復刻には、個人蔵の⑭本と⑫本を底本に選択した。ただ残念なことに、⑫本の鼇頭注が誰の手になるか、いまだ確証しうる史料は発見しえていない。『(和剤)局方発揮諺解』六巻 岡本一抱撰。宝永五年(一七〇八)大塚屋権兵衛等刊。京都大学図書館・武田科学振興財団杏雨書屋所蔵。
文献と注
[1]宋濂『宋文憲公全集』巻五十(『四部備要』所収、中華書局)。
[2]戴良『九霊山房集』巻五(『叢書集成初編』所収、商務印書館、一九三六)。
[3]「石表辞」と「翁伝」は、隆慶六年山東布政使施篤臣刊『丹渓心法付余』(台北・新文豊出版公司影印、一九八二)の末尾にも付録されている。
[4]真柳誠「『本草衍義』に見られる宋代薬理説の発展」、『第一〇五回日本薬学会口演要旨集』三六四頁、一九八四。
[5]岡西為人『中国医書本草考』一六五頁、南大阪印刷センター、一九七四。
[6]方春陽「朱丹渓弟子考略」、『中華医史雑誌』一四巻四期、一九八四。
[7]兪弁『続医説』巻一「格致余論」、上海科学技術出版社、一九八四。
[8]永{王+容}ら『四庫全書総目』八七一頁、北京・中華書局、一九八一。
[9]丁光迪ら『中医各家学説・金元医学』三五〇頁、南京・江蘇科学技術出版社、一九八七。