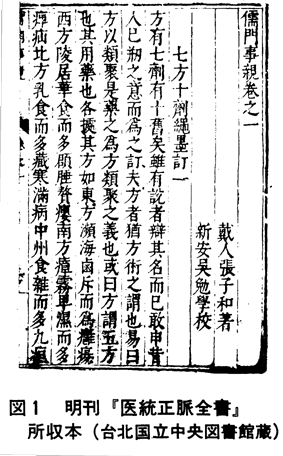 (6)明・万暦二十九年(一六〇一)呉勉学刊『医統正脈全書』所収、『儒門事親』全十五巻(図1)、同全書中「劉河間医学六書」所収、『張子和心鏡』一巻、現存多数。
(6)明・万暦二十九年(一六〇一)呉勉学刊『医統正脈全書』所収、『儒門事親』全十五巻(図1)、同全書中「劉河間医学六書」所収、『張子和心鏡』一巻、現存多数。真柳 誠
一、張子和について
いわゆる攻下派の始祖とされ、『儒門事親』の著者である張子和は、劉完素(河間)・朱震亨(丹渓)・李杲(東垣)らと共に金元の四大家に並び称されている。その伝は『金史』本伝や元・劉祁の『帰潜志』、明・李濂の『医史』などに見え、また元版『儒門事親』の張頤斎序や『四庫全書提要』にも関連の記述がある[1][2]。相互に齟齬する点もあるが、いまそれらを整理すると以下のようである。
張子和の初名は従正、字を戴人(一説に号)、子和は後の名である[3]。出身は{目+隹}州の考城(今の河南省蘭考県)で、戴人と称したのは考城が春秋時代の戴国であることに因む。後に陳州の宛丘(今の河南省{目+隹}陽県)に移り住み、晩年までここで生活していたと思われ、それで宛丘と称されることもある。さて以上の伝と記述には、子和の具体的生没年や活躍年が記されていない。ただし『儒門事親』や彼の遺した「七言絶句四首」(嘉靖版の末尾に附)等の記載により、太医を任じた期間はおよそ一二一九年の前後。『儒門事親』の内容が記されたのは約一二一〇〜一二二八年の間[3]。生年は金の貞元四年(一一五六)頃。没年は金の正大五年(一二二八)頃で、享年は約七十二と推定されている[4]。彼の性格は放胆で威儀がなく、頗る書を読み、詩を作り、酒を嗜んだ。医術は十数歳頃より父に就いて学び、劉従益(『帰潜志』に子和の伝を記した劉祁の父)の門に遊学の後、金の興定年間(一二一七〜一二二一)に召されて太医を任じた。しかしその攻撃的治療と性格のためか太医院内外で誹謗に遇い、間もなく太医を辞して宛丘の蔡河付近に住み、麻知幾(徴君、九疇)や常仲明(用晦)と交遊を結ぶこととなる。
そして彼らと日々医術の奥義を論議し、これを当時すでに文名のあった麻知幾が協力して一書となし、『儒門事親』と名付けた。その謂は、儒のみが医理を明弁し、医を以て親に事(仕)えることである。他方、常仲明は子和の遺論を集めて『治法心要』を作った、という。
張子和の医名は太医を辞任した後も東州(東都の{抃−才+サンズイ}京、今の河南省開封)に鳴りわたったとされるが、晩年の生活は恵まれなかったらしい。それは彼の「七言絶句四首」中に、「而今憔悴西山下。更比文章不値銭」や「歯豁頭童六十三。迩来衰病百無堪。旧游馬上行人老。不是当初過汝南(今の河南省汝南県)」などの句が見え、病と貧しさの中で過去の栄耀を追憶する心情を赤裸々に吐露していることより窺える。
張子和の医説は『素問』や『傷寒論』などの記載を根拠に、劉完素の所説を発展させ、寒凉剤を応用することにある。そして汗・吐・下の三法で、邪を攻撃する治療を特徴とする。例えば『儒門事親』巻一の立諸時気解利禁忌式に、彼は劉完素流の辛凉剤を四十余年用いた結果、傷寒・温熱・中暑・伏熱などを数えきれぬほど治したと豪語するなど、その運用によほどたけていたらしい。
その一方、巻二の推原補法利害非軽説に「養生当論食補。治病当論薬攻」と主張するごとく、いわゆる温補剤による補法の弊害も強く唱えた。これは当時広く流行した『和剤局方』の影響に対する反発であり、彼が私淑する劉完素の医説にも同様の背景がある。そして薬補を否定する代わりに、邪を攻めて駆逐されると元気は自ずから回復する、という見解を提起している。
これらの医説は後代に強い影響を与えた。例えば温病学派の一人で、『温疫論』(一六四二)を著した呉有性(又可)が、治療の急務は去邪にあり汗・吐・下の三法を主とすること。『血証論』(一八八四)の著者・唐宗海(容川)が、{ヤマイダレ+於}血を攻下すると新血は生じ、血虚を補えると主張して多くの駆{ヤマイダレ+於}血剤を創方したことなどは、いずれも張子和の医説の発展といよう。
他方わが国では、曲直瀬玄朔門下の饗庭東庵(一六一五〜一六七三)やその門下の味岡三伯などが劉完素・張子和の医説を奉じ、ために劉張派[5]・後世家別派[6]などと呼ばれている。また吉益東洞が温補剤を多用する当時の後世方派に反対し、駆梅療法もあって攻撃的治療を提唱した背景には、張子和の影響が十分に考えられる。ただし子和が『儒門事親』巻二の凡在下者皆可下式に、「鳴呼。人之死者。豈為命乎。…如此死者。医殺之耳」と述べて当時の天命論に反対したのに対し、東洞は『医断』などで「死生は命なり、天より之を作す。医も之を救うこと能わず」と天命論を唱えた点で大いに異なる。
しかしながら張子和の攻下の主張は過激で、度を過ごした論も多々見え、これへの反論も少なくない。例えば朱丹渓は『格致余論』巻二の張子和攻撃注論で、子和の論理的矛盾と短絡を厳しく指摘する。また呂元膺は「張子和の医術は老将の敵に対するが如く、或いは背水の陣を布き、或いは河を済って舟を焚き、死地に活路を求めるもの、効なきときは即ち潰滅するのみ」、とまで評している[7]。
二、『儒門事親』について
張子和の著書では『儒門事親』三巻が代表的であるが、「儒門事親」の名は明刊本以降、子和に関連する著作を一括した叢書名に転用され、現在に至っている。それらの現存版本を列記すると以下のようである。
〔中国刊本〕
(1)金刊(「三消論」の跋(一二四四)より、実際は蒙古の一二四四年刊)『張子和医書』全十二巻、静嘉堂文庫所蔵。
(2)南宋刊『張子和医書』存二巻二十一葉、静嘉堂文庫所蔵。(1)本に後付。
(3)元・中統三年(一二六二)刊『(太医張子和先生)儒門事親』三巻『直言治病百法』二巻『十形三療』三巻、北京大学図書館所蔵。
(4)元・皇慶二年(一三一三)妃山陳氏書堂刊『(新刊)劉河間傷寒直格』所収、常仲明編『(新刊)(太医)張子和心鏡』一巻、静嘉堂文庫所蔵。当本のみは倣元写本である。
(5)明・嘉靖二十年(一五四一)邵輔刊『儒門事親』全十五巻、武田科学振興財団杏雨書屋ほか所蔵。
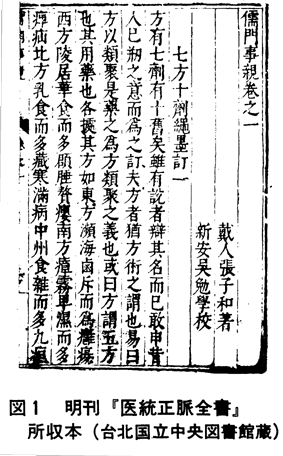 (6)明・万暦二十九年(一六〇一)呉勉学刊『医統正脈全書』所収、『儒門事親』全十五巻(図1)、同全書中「劉河間医学六書」所収、『張子和心鏡』一巻、現存多数。
(6)明・万暦二十九年(一六〇一)呉勉学刊『医統正脈全書』所収、『儒門事親』全十五巻(図1)、同全書中「劉河間医学六書」所収、『張子和心鏡』一巻、現存多数。
(7)明・万暦年間懐徳堂刊『劉河間傷寒三、六書』所収、『張子和心鏡』一巻、上海中医学院図書館所蔵。
(8)清・敦化堂刊『儒門事親』全十五巻、浙江図書館所蔵。
(9)清・同徳堂刊『劉河間医学六書』所収、『張子和心鏡』一巻、上海中医学院図書館ほか所蔵。
(10)清・光緒三十三年(一九〇七)京師医局補刊『医統正脈全書』所収、『儒門事親』全十五巻、同全書中「劉河間医学六書」所収、『張子和心鏡』一巻、現存多数。
(11)清・宣統元年(一九〇九)刊『豫医双璧』所収、『儒門事親』全十五巻、現存多数。
(12)清・宣統元年(一九〇九)千頃堂書局石印『劉河間医学六書』所収、『張子和心鏡』一巻、現存多数。
(13)清・宣統二年(一九一〇)寧波汲{糸+更}斎書局石印『儒門事親』全十五巻、中国中医研究院図書館ほか所蔵。
(14)清・宣統二年(一九一〇)上海国学扶論社石印『儒門事親』全十五巻、北京中医学院図書館・雲南省図書館所蔵。
(15)清・宣統二年(一九一○)千頃堂書局石印『儒門事親』全十五巻、現存多数。
(16)中華民国二年(一九一三)上海江左書林石印『劉河間医学六書』所収、『張子和心鏡』一巻、南京中医学院図書館ほか所蔵。
(17)中華民国二十五年(一九三六)刊『中国医学大成』所収、『儒門事親』全十五巻、北京図書館ほか所蔵。
(18)一九五八年上海衛生出版社重印(17)本。現存多数。
(19)一九五九年上海科学技術出版社鉛印『儒門事親』全十五巻、中国中医研究院図書館所蔵。
(20)一九七二年台北旋風出版社鉛印(17)本。
(21)一九八四年河南科学技術出版社鉛印『儒門事親校注』全十五巻。
〔日本刊本〕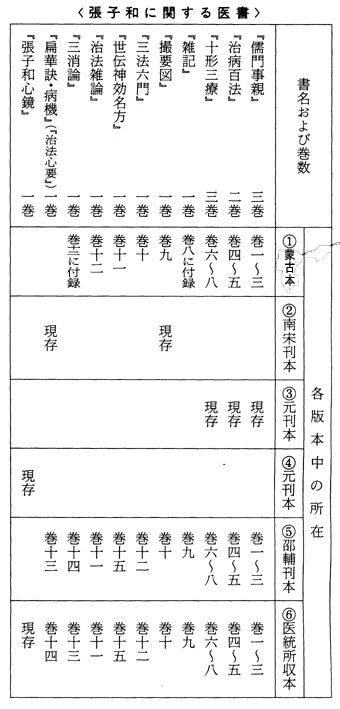
(22)正徳元年(一七一一)渡辺元安序刊『儒門事親』全十五巻、研医会図書館・東京大学総合図書館ほか所蔵。
(23)浪華書肆田縁叔平重刷(22)本、矢数道明氏・大阪府立図書館・北京首都図書館所蔵。
以上、『張子和医書』を二版種、『儒門事親』三巻本を一版種、『儒門事親』十五巻本(叢書)を十三版種、『張子和心鏡』を七版種数えることができた。これらの内、(6)本は(4)本および編成を変えた(5)本を底本に翻刻したもの。(7)〜(16)(22)(23)本は全て(6)本に基づき、(17)〜(21)本は和刻の(22)本または(23)本の系統を底本としている。また(1)本と(2)本の重複部分は別版であるが版式・字体ともに酷似するので、(2)本は(1)本を覆刻したもの。かつ(2)本には(1)本にない部分もあるので、(1)本は残欠本で本来は十二巻以上あったと推測される。したがって張子和に関連する医書群は、いずれも(1)〜(6)本までを基に派生していることになる。いま(1)〜(6)本に収められる医書群を整理し、次表に作成してみた。
この表から理解されるように、張子和に関係の書は金刊本(恐らく初刊本)の段階で少なくとも九種が一括して刊行され、南宋の覆刻本も同様であったと思われる。ところがそれらは(3)の元刊本に寄せた張頤頤斎の序に、「惜其真本、徴君(麻知幾)蔵于名山中、不可復見。今之板行者、尚多錯乱簸闕多」と記すように、問題の多いものだったらしい。しかし張頤斎は続けて「異時有好事、購得真本、重刊而行之」と記しているので、(3)本は麻知幾が山中に秘蔵したという真本の系統に基づくと思われる。この(3)本中の『(太医張子和先生)儒門事親』三巻のみは、江戸末頃まで京都の伊良子氏に所蔵されていたことを『経籍訪古志』の記録より知れるが、現在は北京大学図書館に別の完本が架蔵されるだけである。当(3)本は三書の合刊で、(1)本とは編成が違う。他方、(5)本はその編成より明らかに(1)本の系統にあり、(6)本も(5)本の邵輔序を転載するので同系統と判断し得る。
さて現在通行している『儒門事親』は、全て(6)本を翻刻ないし翻印した計十五巻の叢書本であり、そこには前表のごとく全十書が収載されている。これら十書の内には劉河間の『三消論』のごとく、明らかに張子和と直接の関係がない書もあり、全てが張子和本人の著述とは到底みなし得ない。これについては、多紀元簡が目黒道琢の説を引き『医{謄−言+貝}』の中で考証している。
さらに山田業広(一八〇八〜八一)は晩年の著『医学管錐』の内集巻十一にて、「儒門事親綜概」と題する詳細な考証を遺している。慶応大学医学情報センター富士川文庫にはその自筆写本(図2、いまネット画像に省略)があるが、漢文で記されているので、いまその全文を現代語に意訳して以下に転載しようと思う。なお原文の細字双行注は〔 〕内に入れ、筆者の訳注は( )内に記して両者を区別した。
儒門事親綜概(山田業広著『医学管錐』内集巻十一より、真柳誠訳注)
私(山田業広)は二十五、六歳の時に本書を読み、劉君(多紀元簡)の『医{謄−言+貝}』に所載の驪恕公(目黒道琢)の説により「綜概」を作した。これは今(明治八年、一八七五)を去ること四十余年前であり、再検討すると十中の六、七は満足のゆくものではない。しかしこれを補訂する暇もないので、そのまま記して他日の考察資料に備えたいと思う。
(一)呉勉学が校刻した『儒門事親』全十五巻は、「張子和著」と題している。しかし今、全篇を査考したところ、前の三巻が本来の『儒門事親』であり、その文章の峻逸たること後の数篇とは大いに異なる。この前三巻の「補論」の頁には「得遇太医張子和先生」といい、「水解」の頁には「九疇聞之」などという文があることからみると、これは子和が親験したことを口授し、麻九疇がそれを筆写したことは明白である〔『四庫全書提要』に「劉祁帰潜志称、麻知幾九疇与之善、使子和論説其術、困為文之」というので、この書はまぎれなく九疇が記している〕。現存の元刊本が三巻までしかないことも考えると、本書が元々後半の十二巻と一書でないことは一層明らかであろう。
そこで今、後半の十二巻を分析し、その大略を明らかにしてみたい。もちろん不明瞭なところもあるが、なんとか玉石の混交なきようしたいと思う。
(二)巻四・五の二巻は『治病百法』で、巻十一の『治法雑論』と大同小異である。ただし前者は後者に比べ、厥・諸積・喀血・衂血・嗽血・瘡{ヤマイダレ+節}瘤腫丹毒・誤呑銅鉄魚刺麦芒・禁蝎・夜啼・噂・身痩肌熱・拗哭不止・瘡疥風癬・自禿瘡・瘧疾不愈の計十四条が多い。なお『治病百法』の初めの「風一」から「寒六」までは、それ以下の条でいうことと記述形式が大いに違うので、巻十中の風暑湿火乾寒の治法が敷衍されたものである疑いもある。
要するにこの『治病百法』の二巻は、まじないの方法があって逆に薬方が少ない点、各条に項目を掲げて妄りに煩雑している点もあり、戴人(張子和)の面目ではないと疑われる。
(三)巻六・七・八の三巻は『十形三療』、巻九は『雑記』の九門である。それらの論中では、子和を「戴人」、九疇を「先生」、自分を「余」と称しているので、あるいは麻九疇の門人が記したものかもしれない。〔「戴人」の称は毎条にある。「麻先生」と「余」の称は、巻六の「中風十七」「代指痛二十二」「滑泄二十九」「疱後嘔吐五十五」「病発黄七十三」、巻八の「痔百三十九」、巻九の「謗峻薬」条、「同類相嫉」条などに散見される〕。
ところで、この二書は麻九疇が筆写し、常仲明が補足したという説もある〔李濂の『医史』や『四庫全書総目提要』など〕。しかしこの二書計四巻は、決して九疇の所筆でも仲明の著でもあり得ない。なぜなら常仲明の名は徳(これは『四庫全書総目』の誤認。常仲明の名は用晦で、徳はその子の名である)[8]、仲明はその字であるのに〔『四庫全書総目』の『傷寒心鏡』提要による〕、巻八の「腹脹水気」条には「常仲明曰」の文がある。もし仲明が補足したのなら、自分の字を記す道理はない。また九疇を「先生」と称すからには、仲明の補足でないことも明白である。そもそも子和の直門として、全篇を通して記載のあるのは四人しかいない。すなわち麻九疇、常仲明〔巻六の「遇挙手熱」条、巻八の「水気」条)、景先〔巻六の「牙痛」条、巻九の「臨変不惑」条〕、趙君玉〔巻六の「病発黄」条、巻九の「痔」条〕である。そして景先にしても君玉にしても字のようであるから、『十形三療』『雑記』の二書はますます子和の直門が書いたとは思えない。
(四)巻十は『撮要図』、巻十一は『治法雑論』、巻十二は『三法六門』、巻十三は『三消論』、巻十四は『治法心要』〔『医方類聚』は巻十四からとして『治病百法』を引く〕、巻十五は『世伝神効名方』である。いま巻十の末を見ると、「戴人張子和述已上之図、校改為篇法」と記されている。また巻十三の『三消論』は劉河間の著で、全く子和とは関連がない。しかるに十三巻の末に、『三消論』の巻首には六位蔵象の二図があると記すので、巻十と巻十三の二巻は一人の作と知れよう。かつその巻首に子和の名はないので、つまりそれらは錦渓野老の所輯である〔巻十三末に見える〕。錦渓野老が何人かは未詳であるが、子和を「張先生」と称し、九疇を「微君」と呼ぶので、あるいは常仲明あたりかもしれない。錦渓はもちろん号である。巻十四に至っては甚だしく体裁がとれていない。あるいは『脈経』の文を挙げ〔「扁鵲華陀察声色定死生訣要」および「珍百病死生訣第七」など〕、あるいは巻の前後で所説が重出する〔当巻の「四因」説と巻十所載の論はほぼ同じ。また「五苦六辛」も巻二の「攻裡発表箋」の所載に同じ〕などの例がある。
これを要するに、『撮要図』『三消論』『治法心要』の三書にはまるで発明するところがなく、また張子和の真本ではない。
(五)巻十一〔『治法雑論』〕と巻四、五〔『治病百法』〕は大同小異。恐らく一書が異伝した結果であろう。ただしこの巻十一は項目を分かたず、まじないも載せず、殆ど古色たるものがある。とはいえ両者の字句は互いに得失があり、異本の疑いを否定できない。
(六)巻十二は『三法六門』、巻十五は『世伝神効名方』である。いま前者の「六門」を見ると子和の常用方法を収めている。しかし後者は必ずしもそうではなく、それは一、二方にすぎず〔歯痛に巴豆を用いたり、不臥散・酒{ヤマイダレ+徴}丸の類〕、あたかも付録のようである。また両書には重出する処方〔当帰散・蓮穀散・治諸風疥癬など〕があるので、恐らく著者は別であろう。
(七)舟車丸と濬川散の二方は、巻六以下にしばしばその目があるが、巻十二の『三法六門』と巻十五の『世伝神効名方』には記述がない。いま各巻を相互に検討すると、巻一〜五巻では導水丸・禹攻散を用いる条が数十あるが、一つとして舟車丸・濬川散に言及する条がない。逆に巻六以下では舟車丸・濬川散を用いる条が数十あるが、導水丸・禹攻散には一条も言及していない。例えば巻六の「湿痺七十七」には、張子和が日常使用する峻剤として舟車丸・濬川散・通経散・神祐丸・益腎散を挙げるが、導水丸・禹攻散には言及しない。そもそも導水・禹攻の二方は子和の日用方剤にもかかわらず、巻六の『十形三療』などはなぜ用いないのだろうか。
そこで思うに舟車丸は導水丸・濬川散は禹攻散と同じであろう。そして著者が同一でないため、その名を異にしたのであろう。しかるに『玉機微義』(一三九六頃、徐用誠撰)や『医方集解』(一六八二頃、汪昴撰)には舟車・濬川の二方を載せるが、何を出典としているか不詳である。
(八)前三巻の『儒門事親』には「汗吐下」を並び称す例はないが、後巻ではこれがしばしばである。また禁酒・{ヤマイダレ+徴}・進食や巴豆・烏頭・附子なども一つとして見えないが、『三法六門』や『世伝神効名方』にはそれらがある。巻六の「日赤三十五」の条には黍粘子退翳方を挙げて「別集中にあり」というが、今本(医統正脈全書本)に「別集」はない。巻十一にも通解丸・越桃飲子・消湿散の項目があるが、そのものの記載はない。およそこの類は枚挙にいとまがない。
以上を要するに『儒門事親』計十五巻の全篇が張子和の自著でないのはもちろんのこと、また一人の手に成るものでないことも明白である〔朱彦修(丹渓)の『格致余論』にも同説がある。参考すべし〕。以上のようなことは麻九疇らが張子和の言を受けた際、その精意を審らかにせず、いたずらに誇張した表現で衆目を引かんとした結果であり、決して子和の本意ではない。読者はよろしく本書の甚だしき点やおごりを去り、その精意のある部分のみを味わうべきであろう。
本書の大略は例えるならば、『素問』『霊枢』を臓腑、劉完素を骨子、汗吐下を四肢としている。そして本書の小児説・汗吐下論・可吐式・補法説・補論・水解などは、当時の無知への警笛ばかりでなく、そもそも医家の模範とすべきであろう。すなわち巻二の「可下式十六」を見ると、「随証不必下奪、在良工消息之也。余所以言此者、矯世俗語」と述べるように、彼はただ当時の旧弊を打破せんとしたにすぎないことがわかる。したがって読者はその長所に最も着眼すべきだが、その短所も知っておくべきだろう。
前三巻の『儒門事親』は元刊本で校訂可能であるが、巻四以下にも誤謬は少なくない。これを読みながら加えた愚考を別に書き出し、ここに述して綜概とした。以て後日の校勘に備えたい。
以上、山田業広の論考を紹介したが、これにより『儒門事親』計十五巻に収められる諸医書の性格が、ほぼ明らかとなったであろう。そこでこれを医統正脈全書本に基づく現行『儒門事親』全十五巻の順に、筆者の知見も補足して整理してみると左記のようになる。
巻一〜三、『儒門事親』三巻、張子和口授、麻九疇撰文。以上の他に『張子和(傷寒)心鏡』一巻があり、これは劉完素およびその門人らの書を集めた元刊の『劉河間傷寒直格』に付刻されて以来、『医統正脈全書』などにも収録されている。当書は元刊本の題記および内容から見て、張子和の遺論を常仲明が編輯し、補足したものと思われる。巻四〜五、『治病百法』二巻、張子和述、後代敷衍。巻十一『治法雑論』の別伝本。
巻六〜八、『十形三療』三巻、麻九疇門人の撰。
巻九、『雑記』一巻、麻九疇門人の撰。
巻十、『撮要図』一巻、劉完素後裔の撰、錦渓野老(常仲明か)の輯。
巻十一、『治法雑論』一巻、張子和述。巻四・五『治病百法』の別伝本。
巻十二、『三法六門』一巻、麻九疇の輯か。
巻十三、『三消論』一巻、劉完素撰、錦渓野老輯。
巻十四、『治法心要』一巻、常仲明輯。当書は巻首などの篇名より、『扁華訣・病機論』と呼ばれることもある[9]。
巻十五、『世伝神効名(諸)方』一巻、張子和直門輯。ただしこの門人は麻九疇と別人。あるいは常仲明か。
なお上述の諸書以外に記録には、『三復指迷』一巻(李湯卿『心印紺珠経』)、『子和心法』一冊(『文淵閣書目』等)、『張氏経験法』二巻(『国史経籍志』等)、『秘伝奇方』二巻(『千頃堂書目』等)、『汗吐下方』(『補三史芸文志』等)の書が張子和の著とされているが、上述書との関係やその真偽は未詳である。
三、和刻『儒門事親』について
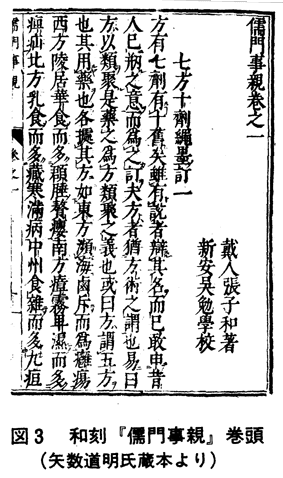 先に掲げたごとく、当版は渡辺元安が正徳元年(一七一一)に序を付して刊行。その後、浪華の田縁叔平という書店に版木が流れ、そこでもう一度印刷されている。したがっていずれも同版であるが、前者の欄上に付刻の眉注を、後者は削除して印刷した形跡が各所に見える。この作為は、恐らく前者を刊行した書店の者が眉注を作成していたため、その出版権などの問題があり、田縁叔平はその部分のみを版木から削り、印行したものと思われる。
先に掲げたごとく、当版は渡辺元安が正徳元年(一七一一)に序を付して刊行。その後、浪華の田縁叔平という書店に版木が流れ、そこでもう一度印刷されている。したがっていずれも同版であるが、前者の欄上に付刻の眉注を、後者は削除して印刷した形跡が各所に見える。この作為は、恐らく前者を刊行した書店の者が眉注を作成していたため、その出版権などの問題があり、田縁叔平はその部分のみを版木から削り、印行したものと思われる。
さて当版は毎巻首(図3)に「新安呉勉学校」と記すように、呉勉学が校刊(一六〇一)の『医統正脈全書』所収本を底本としている。図1と図3の比較で明らかだが、両者の行数・字詰めは一致し、字体も酷似している。したがって和刻版は中国板の罫線を除き、訓点を加えた以外は、ほぼ忠実に翻刻されたものといえよう。ただしこの訓点が誰の手になるかは不明である。あるいは、当和刻版に序文を草した渡辺元安かもしれない。
その「新鐫儒門事親叙」によると、元安は瀉下派の代表に張子和を、補養派の代表に薛立斎(薛己)を挙げている。そして治療には仲景のごとく虚実に応じ、補瀉の双方を使い分けることが必須であるのに、今の世は補を好んで瀉をにくみ、大黄・芒消をまるで蛇か蠍のようにおそれている。それゆえ補に偏向した書ばかり出版されており、張子和の書は殆んど知られていない。これでは初学者が実を瀉すことを知らず、実を実してしまう恐れもある。そこで本書を出版して世に広め、薛己の書と併用されるようにしたい、という。
宇津木昆台の『日本医譜』によれば、渡辺元安は日向延岡藩の儒医・渡辺正庵の子。名を栄、字を元安、通真と号した。父に医術を受けた後、若くして京都に上り、儒を伊藤仁斎に、医を有馬存庵に学んだ。その後は京都に住み、数療年あって法眼に叙せられたが、すでに痼疾があって享保七年(一七二二)二月二日に没した。享年は五十九。妻は尾崎氏の女で、二子があったがいずれも夭逝し、弟の渡辺玄隆が日向で家業を継いだ、という。これより『儒門事親』の刊行は、元安が四十八歳の時とわかる。また序文の末記によれば、院号は松下睡鶴軒と称したらしい。
以上より、今回の影印後刻には矢数道明氏所蔵の田縁叔平刊本を底本に選択し、眉注については研医会図書館所蔵本より補うことにした。
文献および注
[1]多紀元胤(中国)医籍考』六五五〜六六〇頁、北京・人民衛生出版社翻印、一九八三。
[2]岡西為人ら『宋以前医籍考』九六九〜九八八頁、台北・古亭書屋、一九六九。
[3]方春陽「張子和考」『上海中医薬雑誌』一九八五年第二期、四三〜四五頁。
[4]李聡甫ら『金元四大家学術思想之研究』六四〜六六頁、北京・人民衛生出版社、一九八三。
[5]矢数道明『近世漢方医学史−曲直瀬道三とその学統−』三○頁、東京・名著出版、一九八二。
[6]富士川游『日本医学史』二八九頁、東京・形成社復刊、一九八二。
[7]前掲[5]、所引文献、二四頁。
[8]核堂「医史巵言」『(中華)医史雑誌』第二巻第一・二期、一九四八。
[9]岡西為人(「張従正」『漢方の臨床』一四巻一○号、一九六七)は、『儒門事親』の邵輔刊本を実見せず、多紀元胤の『医籍考』の記載のみによったため、『治法心要』と『扁華訣・病機論』は別書で、邵輔本に『三消論』はないと誤解している。このため『治法心要』が医統本になく、それは『三消論』と同一書ではないかと失考している。