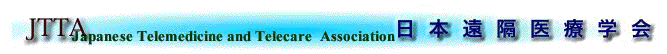分科会
現在活動中の分科会をご紹介いたします。
分科会の設立については、本文下記の案内をご覧下さい。また、以下の分科会への参加希望、お尋ねについては、学会事務局までお知らせ下さい。
「モバイル国際遠隔医療分科会」 平成20年4月設立
分科会長:吉田 晃敏 所属:旭川医科大学、学長、眼科学講座(旭川医科大学遠隔医療センター)
過疎地、僻地、離島地域等の通信インフラ設備の行き届いていない地域にあっても携帯電話は利用可能であり、普及率は国民一人に一台所有といっても過言ではない時代になりました。現在の携帯電話は多彩な機能と通信速度の飛躍的向上により音声通話のみならず大量データの送受信が可能になっております。その世界最高水準の機能を医療領域で活用し、いつでも、どこでも医師、看護師、コメディカルと繋がっている安心感と利便性を日本から世界へ普及、推進することを目的といたします。
「遠隔診療・遠隔ケアシステム技術分科会」平成19年11月設立
分科会長名 乾 貴宏 所属 北海道情報大学 医療情報学科(公認情報システム監査人)
遠隔医療の質は、通信インフラである通信網・運用を行うソフトウェアならびにシステムの質により左右され、保健・医療・福祉分野での運用においては、人 的・物的・金銭的資源および情報セキュリティが課題となる。また、構築に関してSI(システムインテグレータ)等の専門家との連携は必要不可欠であるが、
SIの提案が適切であるか否かを評価する為に、一定の知識を習得する必要がある。本分科会では勉強会・事例研究を通じ、遠隔医療・地域医療の普及および遠 隔診療・遠隔ケアシステムの構築に必要な技術についての研究を行う。
「Web医療研究分科会」平成18年11月設立
分科会長 武蔵国弘 所属:NPO法人MVCメディカルベンチャー会議
通信技術の進歩は著しく、医療分野へのさらなる応用が待たれている。インターネットを通じた情報交換が企業-個人間から個人-個人間へと大きく パラダイムシフトした近年の現象はWeb2.0と呼ばれている。本研究会はWeb2.0の医療現場への応用を研究し、社会貢献性の高い、より利便性の高い 遠隔医療の実現を目指す。
「地域がん対策ネットワーク推進分科会」 平成18年8月設立
分科会長:神谷 誠 所属:群馬大学大学院医学系研究科病態病理学分野
本分科会は、地域社会と地域医療を担う一次・二次医療機関が、インターネットを通じて連携する地域がん対策ネットワーク構築の推進を目的とす る。目的を達成する為に、がん情報共有ネットワークサーバの構築を行い、地域の一次・二次医療機関に対してネットワークへの参加を促す。また,地域社会に 対しては、がん患者の遠隔在宅療法・遠隔終末医療を支援するネットワーク作りを促進するために、講演活動等を通じて積極的な知識の普及を行う。
「健康セルフチェック・テクノロジー分科会」 平成18年6月設立
分科会長:長谷川高志 所属:国際医療福祉大学
健康状態について患者・利用者が自分で記録し、自己評価できる質問項目群を開発し、健康の自己管理に役立つ身体情報記録・管理方式の確立と普及 を目的とする。患者・利用者が体調を自己記入できるネットワーク型電子式健康記録や、健保組合等での保健指導に活用できるパラメータであり、ネットワーク 上で利用者・保険者・医療者・コンタクトセンターなどが共通に活用することで、テレケアから健康管理まで幅広い健康情報の共有化が可能となる。 当分科会 では、パラメータ開発と改良、普及、これを用いた健康情報の記録・自己評価の実証プロジェクトの支援、健康記録データの収集と分析、効果の実証を行う。
「診療連携分科会」平成18年5月設立
分科会長:柏木賢治 所属:山梨大学医学部眼科学講座
今日、診療の高度化や分化化が急速に進行するとともに医療資源の偏在が顕著となっている。患者に適切な診療を普遍的に提供するためには、高度専 門病院と地域診療機関との有機的かつ有効的連携が益々重要になっている。高度情報通信社会が到来しているにも関わらず、医療においては必ずしも十分な診療 連携体制が整えられてはいない。本分科会ではこのような現状を踏まえ効率的かつ有機的な診療連携体制確立のための研究を行う。
「運動施設の医療連携分科会」平成18年3月設立
分科会長:木村 穣 所属:関西医科大学心臓血管病センター・健康科学センター
遠隔管理により医療機関とフィットネスクラブ、健康増進施設との連携をより強化し、医療的介入、評価を遠隔で行うことを目的とする。具体的行動 として、フィットネスクラブや健康増進施設での心電図検査や、運動負荷試験時の心電図監視などの循環器的管理、テレケアとしての栄養、メンタルなど生活習 慣の予防、治療手法の開発、効果の検証を目的とする。
「市民参加の遠隔医療分科会」平成17年9月設立
分科会長:瀧澤 清美 所属:NPO法人地域診療情報連携協議会
今日、インターネット等の情報通信技術が急速に普及する中で、これらの新規技術を医療、保健、福祉に活用しようという動きが進んできています。 こうした中で、これまで情報が及びにくかった消費者に容易に安価に情報を提供できる利点は高く、医療機関その他の組織・団体から利用価値の高い情報やサー ビスを提供利用できるような情報化社会の実現が期待されています。
しかしながら、こうした利便性の一方では、情報やサービスの内容が十分評価吟味されないまま提供されることがあり、今後、利用者側での不利益やトラブルの発生が懸 念されています。また、個人の医療や健康に係る情報は、プライバシー性が高く、インターネットのようなオープンなネットワークの中で知らないうちに個人情報が漏洩したり、不正利用されたりするリスクが高まってきています。
こうした状況の下、様々な立場の関係者がこの分野でのインターネット利用に伴う問題について協議し、情報やサービスに対する一定の信頼性が確 保される方法を創意工夫していくなどして、患者や市民が情報やサービスを安全、有効に利用できるよう環境づくりを推進していくことにより、もって遠隔医療 学会の増進に寄与したいと考えています。
「救急医療分科会」平成17年9月設立
分科会長:大林俊彦 所属:東京大学医学部附属病院 材料管理部
昨今、救急出動回数の増加とともに救急車の有料化なども議論されてきています。また、IT化の波に押される形で、日本全国でこれまで様々な形で 救急車、救急医療へのITの応用した実証実験、そして一部は実用化が進んできてはいますが、まだまだ先端技術の進歩が、安全安心な社会、一刻を争って展開 される人命を守る救急医療に、いつでもどこでも活用されている状況とは言いがたい。そこで、遠隔医療学会を核として、幅広く、これらの分野で、志ある多く の方々の参加をいただければと思います。そして、将来的には日本救急医学会等との連携も目指し、研究・実用化を強力に推進していくためにも力を結集させよ うではありませんか。よろしくご参加の程お願いいたします。
「ケアマネジメント分科会」 平成17年9月設立
分科会長: 別宮 圭一 所属:株式会社インターネットインフィニティー
(居宅介護支援センターひまわり)(クローバーケアステーション)
高齢者介護のケアマネジメントにおいて、さまざまなニーズにあった遠隔介護をIT利活用などを進めることで具現化し、業務の効率化を図るとともにケアマネジメントの質を高度化することを目的とします。
「過疎地・離島医療ネットワーク分科会」 平成17年9月設立
分科会長:吉田 晃敏 所属:旭川医科大学眼科学講座(旭川医科大学遠隔医療センター)
医療過疎が進む過疎地・離島では、高度な医療を受けるのは容易ではなく、医療格差の是正、医療の質向上の手段として、遠隔医療の普及・推進が 期待されている。本分科会は、医療関係者、行政機関、産業界の英知を結集し、過疎地・離島に対する遠隔医療を推進するため、その課題と推進策を検討するこ とを目的とする。
「遠隔栄養サポート分科会」平成17年8月設立
e-Nutrition research and development project [ENRDP]
分科会長:郡 隆之 所属:利根中央病院 外科
インターネットの普及により,多くの人々がホームページにアクセスし,情報を得ることができるようになってきた.栄養に関する情報も同様に多くの人が知るところとなっている.しかし,個人レベルでの栄養状態の把握およびその管理に関しては十分な情報がない.
本分科会の目的は,
1)インターネットを介して個人の栄養状態を把握するためのインターネット上のソフトウェアを構築する
2)インターネットを介して,栄養に関する質問を受け付けられるQ&Aを構築する
3)インターネットを介して,個人に必要な「食」および「栄養補助食品」を知ることのできるシステムを構築することである
「地域IT政策分科会」平成17年8月設立
分科会長:安江 輝 所属:長野県伊那中央病院
遠隔医療はすべての地域であまねく享受できるサービスであることが求められるが、我が国におけるブロードバンドをはじめとする情報通信基盤や運 用手法が地域実情等により各様であるだけなく、医療関係者以外の遠隔医療の理解が乏しく地域政策として進んでいない現状にある。本分科会では学会への行 政・自治体、技術、NPO等の地域情報化推進関係者の参加を促進し、遠隔医療を地域情報化政策等に反映させるための調査、情報共有、各方面への提言などを 積極的に推進する。
「在宅医療支援分科会」平成17年8月設立
分科会長:太田隆正 所属 :太田病院 内科
これからの医療では寝たきり老人を含めた在宅医療の再検討が行われている。その中で医療と介護の連携がより重要となってくる。IPTV電話を利用し、視覚的に患者家庭や介護現場と医療機関を結ぶ試みには多くの有用性がある。
目的:
IPTV電話で訪問看護師を介して患者家庭と医療機関と通信。
IPTV電話通信実験により機器の改良を行う。
IPTV電話通信により可能な利用方法を検討していく。URL http://niimi-ma.no-ip.com/~ishikai/
分科会制度について 平成17年7月1日
日本遠隔医療学会には、多様な分野に関わる方々が参加されています。それぞれの分野での活動を支援することで、その内容を深め、学会での交流を図る ことで、ひいては、学会活動全体を活性化することができると考えます。そこで、支援策として分科会制度を試行的に発足させ、学術大会での分科会セッション の設置、学会誌への活動報告掲載等を進めます。
ぜひ、分科会を設立していただき、より積極的に学会活動を応援していただくようお願いします。
- 3名以上の会員で分科会を組織できます。以下の分科会設立願い書式に従い、会員名を記載して、学会事務局までメールをお送り下さい。
- ご希望により、学術大会に分科会主催のセッションを設置できます。以下の分科会セッション設置願い書式に従い、セッション名を記載して、学会事務局(大会事務局ではありません)までメールをお送り下さい。
- ご希望により、学会誌へ報告を掲載します。
書式送付先 jtelemed@hsp.md.shinshu-u.ac.jp
信州大学医学部附属病院医療情報部内 日本遠隔医療学会事務局 TEL 0263-37-3016
既設分科会への参加希望、お尋ねも事務局へご相談下さい。
1 分科会
日本遠隔医療学会に分科会を置く
目的
多様な分野それぞれの活動を支援することで、日本遠隔医療学会の活動を活性化する。
申請・審査
会員3名以上の申請をもって分科会の設立を申請できる。
役員会で申請の審査上、承認する。
期間・継続
分科会の設置は2年間とするが、継続の申請も可能である。
学術大会セッション・シンポジウム
学術大会長への申請およびその許諾により、分科会として学術大会にセッション・シンポジウムをもつことができる。
学会誌
分科会長は、日本遠隔医療学会誌(学術大会論文集)に活動報告を掲載することができる。
2 分科会設立願い書式
日本遠隔医療学会会長殿
分科会の設立を申請します。
名称「 」
分科会長名
所属
会員名(2名以上)
活動の目的・内容(100-200字)
3 分科会セッション設置願い書式
日本遠隔医療学会 学術大会会長殿
分科会セッションの設置を希望します。
希望セッション名
(3-5演題程度)
予定演題名 1
予定演題名 2
予定演題名 3
予定演題名 4
予定演題名 5
分科会名
分科会長名
所属