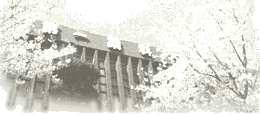 研究内容
研究内容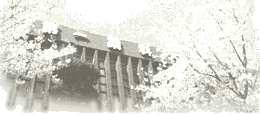 研究内容
研究内容
FFRPたんぱく質群によるDNA・リガンド識別機構の解明
微生物の環境変化への応答、代謝、増殖、さらには細胞間情報伝達を制御する重要な転写因子グループであるFFRPたんぱく質群を研究対象とします。具体的にはFFRPのNドメインが塩基配列を系統的に識別する機構やCドメインが多様なリガンドを識別する機構の解明、FFRPを標的として、その種特異性に基づき細菌種ごとに対処する新しい創薬戦略の開発、少数の転写因子により多数の遺伝子群の環境的制御を可能とする機構の全体像の解明を行ないます。本研究室では、現在問題となっている多剤耐性Pseudomonas aeruginosaに対する新たな抗菌薬の開発を目標としている。Pseudomonas aeruginosaのゲノム配列から8種のFFRPたんぱく質を検索し、その中の6種はこの菌に特異的であることが明らかとなった。現在、それらの結晶化、構造解析を行っている。さらに、これらの蛋白質のDNA結合部位を決定し、Pseudomonas aeruginosaでのFFRPたんぱく質群の転写様式を解明する。本研究は鈴木 理 博士 (産業技術総合研究所 脳神経情報研究部門 DNA情報科学研究グループ長)との共同研究である。
緑膿菌は、多様な環境下(水中、土壌、植物、動物組織)に生育するが、深刻な院内感染を引き起こすが如く、その適応能力を発展させている場合もある。一方、あたかも多細胞真核生物のように、シグナルを介して菌集団全体での協調した遺伝子発現制御機構が存在する。これは、細菌細胞間の低分子物質を介した情報伝達機構を利用したものであり、その一部はクロラムセンシングシステム(QS system)として知られている。QS systemは、その病原因子エステラーゼ遺伝子lasBの発現制御の研究の中で発見され、その発現に必須な転写因子LasRが報告されたことによる。その後、QS system に関与する転写因子RhlRが発見され、緑膿菌にはLas系およびRhl系のQS system が存在すると言われている。この様な緑膿菌の「異常さ」は、共通して、その高度な転写調節機構に起因すると考えられている。 我々は、上述のような緑膿菌の「異常さ」、環境の変化への応答、増殖ならびに細胞間情報伝達の転写機構を解明する目的で、ひとつの転写因子グループFFRPタンパク質群(Feast/Famine Regulatory Proteins)をダーゲットに研究を進めている。FFRPという区分は、大腸菌のLrp(Leucine-Responsive Regulatory Protein)の機能を総括する饗宴―飢餓制御(Feast/Famine Regulation)という言葉を引用している。その役割は大腸菌Lrpで示されているように広範な遺伝子群を多様に制御していることである(Calvo, J.M., and Matthews, R. G. Microbiol. Rev. 58, 466-490 (1994))。このような多くの遺伝子群を支配するFFRPを、我々は公開されている緑膿菌PAO1のゲノム塩基配列をもとに8種類突き止めた。この数は、真正細菌中では最多で(ちなみに、大腸菌3種、結核菌3種)、緑膿菌の「異常さ」によく対応する(Suzuki M., Aramaki H., and Koike H. Proc. Japan Acad. 79B, 242-247 (2003))。最近、我々は、緑膿菌systemの発現制御に関連していることを緑膿菌PAO1のDNAチップをFFRP群が病原因子の産生を制御しているQS 用いて、初めて見い出した。すなわち、Las系のlasI, rpaL, mvaT, lasA, toxA, aprA遺伝子、ならびにRhl系のFFRP群が、QS systemおけるrhlR, dksA, lasB, aprA, toxA示唆した。これらLas系およびRhl系のQS systemに関して、分子生物遺伝子の転写量を増減させていることを学的な解析が進んでいるにも関らず、剤の開発はなされていない。その理由のひとつに、LasRやRhlRの立Las系およびRhl系に対する阻害体構造の解明が不可欠であるが、それらのていない現状がある。また、毎年のように起きる大学病院でのタンパク質の精製ができ多剤耐性緑膿菌究アプローチが求められている。(MDRP)の出現とも併せて、感染症対策に関する新たな研究が求められている。本研究では、病原菌対策の一環として、まず、DNAチップより得られたQS systemの発現制御に関与している転写因子FFRP群について、Las系およびRhl系の遺伝子群に対する新たな転写制御機構を解明することを目的とする。また、FFRPが代謝経路を調節する転写因子でもあることから、代謝中間産物をはじめとする低分子性リガンド(特にアミノ酸類に注目)の特定を目指す。幸運にも、FFRPの立体構造の解明の研究が始まっており、本研究での成果が創薬のためのリード化合物とのドッキングスタディへの知見として提供され、緑膿菌感染対策の一環としての薬剤開発への道を拓くことが可能になると確信する。
緑膿菌の外毒素ピオシアニン産生に関与する因子の構造生物学的解析
緑膿菌はそれ自体では病原性は低くが、気管支肺炎などで好中球による攻撃が十分に望めない患者で感染することが多い。特に、呼吸器の緑膿菌感染は産生される毒素により肺組織が破壊され重篤化しやすい。この毒素ピオシアニンは、特に、嚢胞性線維症における肺への感染中に、多く産生される。したがって、ピオシアニンの発現調節を解明することは、宿主への感染メカニズムを理解する上で重要である。本研究では、ピオシアニンの発現に関与する因子PhzM, PhzSおよび PhzHを構造生物学的に解明することを目的とする。その結果は、緑膿菌の病原性発現機構の理解の基礎を与えるとともに、新規の抗緑膿菌薬に対する創薬の基盤を与えるものと期待される。
糖尿病腎症の原因解明(SNP解析)
現在、日本では20万人以上の患者さんが腎不全のために透析治療を受けていて、さらに毎年3万人以上が新たに透析治療を導入されています。糖尿病性腎症は、この新たに透析導入される患者さんの中で最も多い原因で、有効な治療法や予防法が確立していないために、その患者数は急激に増加しています。残念ながら今までのところその正確な発症メカニズムは解明されていません。一方、今までの研究結果から、糖尿病になっても腎症になりやすい人とそうでない人がいることが分かってきました。そこでこの違いがどのようにして起こるのかを、新しい研究手法であるSNP解析により調べることが、糖尿病性腎症の治療法および予防法開発の突破口になると期待されています。私たちは、糖尿病性腎症の患者さんと、糖尿病でありながら腎症になっていない患者さんのデータを解析することで、糖尿病性腎症の発症メカニズムを解明し、新たな治療法や予防法の開発につなげることを目指しています。本研究は福岡大学医学部第一内科教室・眼科学教室および九州大学大学院薬学研究院医療薬科学専攻臨床薬学講座薬剤学分野との共同研究である。